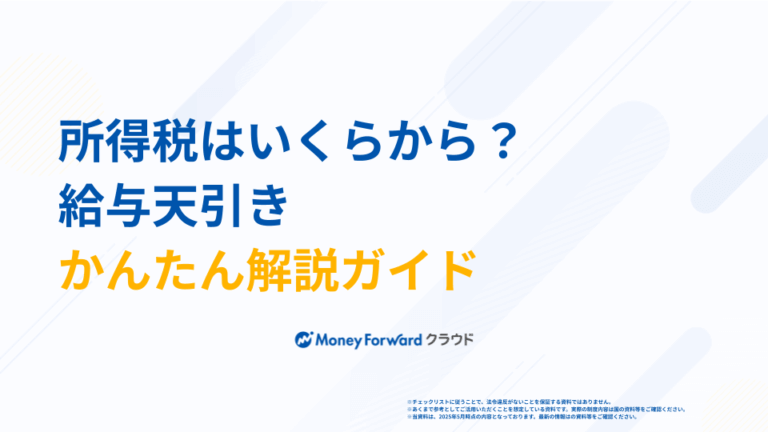- 更新日 : 2025年11月6日
所得税はいくらから給与天引きされるか?仕組みや変動時の確認方法を解説
給与明細を確認すれば、社会保険料などが天引きされていることがわかります。働いている以上、天引きは当たり前と考えがちですが、一定以上の収入から行われます。当記事では、所得税の天引きについて、その仕組みや対象となる種類、計算方法など、様々な角度から解説します。
目次
所得税はいくらから給与天引きされるか?
従業員の給与が一定以上でなければ、所得税は天引きされません。給与が一定以上の額でなければ、天引きすべき所得税自体が発生しないからです。そして、その境目となる金額が「103万円」です。
所得税には、控除制度が存在し、該当する控除があれば、納めるべき所得税額が減額されます。そのような控除のなかでも、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)については、給与所得者であれば誰でも適用されます。そのため、2つの控除の合計額である103万円までは、原則として所得税が発生しません。つまり、給与から所得税が天引きされるのは「103万円を超える」場合です。
ただし、年収103万円以下であっても、月収が8.8万円を超える場合には、天引きの対象となってしまいます。正社員であれば、基本的に年収103万円を超えているため、あまり問題となりませんが、パートやアルバイトの場合には注意が必要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
所得税・住民税の課税・非課税ルール
所得税や住民税の課税・非課税の判断は、正確な給与計算の根幹となる重要な要素です。
本資料では、給与担当者が実務で迷いやすい項目を中心に、課税・非課税のルールを体系的に整理し、業務上の注意点についても解説します。
定額減税の実務対応で間違えやすい10のポイント
2024年6月から実施された所得税・住民税の定額減税は、手順が細かく定められており、企業の労務担当者にはイレギュラーな対応が多く求められます。
本資料では定額減税の実務対応で間違えやすいポイントと正しい対応方法を解説します。
年末調整でよくある質問&回答集
年末調整で従業員から寄せられやすい19の質問と回答例、担当者として業務を進めるうえで知っておきたいポイントをまとめました。
資料で紹介した内容を従業員に事前周知するなど、年調業務の負担軽減にお役立てください。
所得税の給与天引きの仕組みとは?
所得税を給与から天引きする仕組みを「源泉徴収」と呼びます。原則として、企業は源泉徴収義務者であるため、従業員に給与を支払う都度、源泉徴収を行うことが必要です。通常であれば、発生した所得税は従業員自らが納めるはずですが、企業が源泉徴収を行うことで、代わって国に納付しています。源泉徴収の対象は、従業員への給与や賞与だけでなく、弁護士等への報酬や原稿料等も対象であるため、企業がこれらの報酬を支払う際には、支払額から源泉徴収が行われています。
企業に勤める会社員は、所得税の過不足を調整するための手続きである「年末調整」の対象でもあります。そのため、自分で所得税に関する手続きを行うことなく、正しい額の納税が可能です。しかし、自営業者等は年末調整の対象ではないため、自分で所得税を申告しなければなりません、この手続きが「確定申告」です。
会社員は、原則として確定申告の対象ではありません。しかし、会社員であっても、寄附金控除や雑損控除、医療費控除といった年末調整では控除されない控除の適用を希望する場合には、確定申告を行うことになります。これらの控除は、年末調整では適用できないためです。また、会社員でも、アフィリエイトなどの副業で得た収入が20万円を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。
給与天引きされる各種税金・保険料
所得税のほかに、住民税も年間税額を12等分した額が、毎月の給与から天引きされ、企業が従業員に代わって市区町村に納付しています。このような住民税の仕組みを「特別徴収」と呼びます。
天引きは、税金だけでなく、社会保険料や雇用保険料も対象です。毎月の給与からは、従業員負担分の健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料が天引きされています。なお、労災保険料は企業のみが負担し、従業員負担分はないため、天引きの対象とはなりません。
天引きは原則違法
給与からの天引きは、原則として違法です。労働基準法では「賃金の全額払い」を定めており、給与から一定額を控除する天引きは、この原則に触れるため違法となります。税金や社会保険料等が天引きされている理由は、法令に特別の定めがあるためです。
所得税や住民税については、所得税法や地方税法で天引きを認めているため、企業が天引きを行っても違法とはなりません。社会保険料等も各法令で認められているため同様です。また、労使協定を締結することで、社宅費や労働組合の組合費などを天引きすることも認められています。これらの例外的な処理を除いて、原則として天引きは許されないと覚えておきましょう。
所得税が給与天引きされているか給与明細で確認しよう
給与明細の項目は、「勤怠」「支給」「控除」の3つに大別可能です。勤怠では、就業日数や労働時間、有休取得日数などの項目が設けられており、これらの情報を基に支給される給与額が計算されます。支給では、基本給や残業手当、通勤手当など、従業員に支給される給与の情報が記載されています。控除には、給与から控除される項目が記載されており、この項目を確認することで、自分がどの税金や保険料の天引き対象となっているか確認可能です。また、控除されている額も同時に確認できます。
控除には、通常以下のような項目が設けられています。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
- 住民税
上記のほかに、社宅費や組合費を控除すると定めている企業であれば、その項目が設けられているでしょう。自分が何をどの程度、天引きされているか確認したければ、給与明細を確認してください。
所得税の給与天引き額が変動した場合のチェックポイント
給与から天引きされる所得税は、毎月一定額というわけではなく、変動する場合もあります。天引きされる所得税が変動した際に、確認すべきポイントについて解説します。
所得税が変動する原因
所得税が変動する原因は様々ですが、たとえば、扶養人数に変更があった場合が例に挙げられます。所得税は、従業員が扶養する親族等の数に応じて減額される仕組みです。そのため、配偶者と離婚した場合や子どもが独立した場合などは、所得税の額が上がってしまいます。
残業代や休日出勤手当は、所得税の課税対象です。繁忙期で残業を多く行った月の給与からは、平常時よりも多くの所得税が天引きされることになります。基本給に変動があった場合も同様です。
所得税は、社会保険料を控除した後の金額に課されるため、社会保険料の額に変更があれば、給与から天引きされる額も変動することになります、社会保険料は、報酬額を一定ごとに区分した「標準報酬月額」を基に計算されます。
標準報酬月額は、原則として1年を通して変わることはありません。しかし、大幅な賃金の変動があった場合や、育休・産休から復職したような場合などには、年度の途中でも標準報酬月額が変更されます。
ほかにも、税制度そのものが変更されたような場合が考えられます。税率や控除制度等に変更があれば、当然所得税の額にも影響を及ぼすでしょう。また、給与計算自体が誤っている場合も考えられます。天引きされる所得税が変動した場合には、これらのポイントをチェックしてみましょう。
所得税が適正か確認する方法
自分が納めた所得税を確認する方法としては、「源泉徴収票」の利用が挙げられます。源泉徴収票には、以下のような情報が記載されています。
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除の合計額
- 源泉徴収税額
- 控除対象配偶者の有無
- 控除対象扶養親族の有無
- 社会保険料等の金額
- 生命保険料の控除額
- 地震保険料の控除額
- 住宅借入金等特別控除の金額
所得税は、社会保険料等の控除額を差し引いた課税所得に課されます。源泉徴収票には、源泉徴収された税額が記載されているだけでなく、上記のような情報が記載されているため、課税対象となる金額を知ることが可能です。源泉徴収票は、年末調整後に発行されるため、記載された情報を基に、所得税が適正かどうか確認してみましょう。
給与天引きされる所得税の計算方法
毎月の給与から天引きされる所得税は「源泉所得税」と呼ばれます。源泉所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いることで計算可能です。たとえば、社会保険料等が控除された後の給与等が月40万円である場合には、扶養人数ごとに以下の金額が給与から天引きされます。
| 扶養する人数 | 源泉所得税(月) | 源泉所得税(年間) |
|---|---|---|
| 0人 | 16,510円 | 198,120円 |
| 1人 | 13,270円 | 159,240円 |
| 2人 | 10,040円 | 120,480円 |
| 3人 | 7,560円 | 90,720円 |
| 4人 | 5,930円 | 71,160円 |
| 5人 | 4,320円 | 52,840円 |
| 6人 | 2,710円 | 32,520円 |
| 7人 | 1,080円 | 12,960円 |
なお、上記の額は甲欄が適用された場合となります。甲欄が適用されるのは「扶養控除等申告書」を提出した従業員であり、未提出の場合には、税率の高い乙欄が適用されることになるため注意してください。
定額減税により所得税が3万円の減税に
国民の負担軽減を目的とする制度である「定額減税」が、2024年6月から実施されています。定額減税は、令和6年度の税制改正に盛り込まれたもので、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円の減税をその内容とする制度です。つまり、定額減税によって、所得税が3万円減額されることになります。
2024年6月以降に支払われる給与や賞与を対象とする源泉徴収税額から、その時点における定額減税額の控除が行われる事務を「月次減税事務」と呼びます。月次減税事務においては、6月以降に最初に支払われる給与等から減税額を控除し、控除し切れない部分があれば、2024年の間に支払われる給与等から順次控除していきます。
月々行う処理である月次減税事務に対し、年末調整を行う時点における定額減税額に基づき、清算が行われる処理は「年調減税事務」と呼ばれます。定額減税の事務においては、月次減税事務と、年調減税事務の2つの処理を行うことが必要です。
所得税における定額減税の対象者は、次の通りです。
- 2024年度おける納税義務者(所得税)のうち、2024年度の合計所得金額が、1,805万円以下(給与による収入のみである場合は、2,000万円以下※)の方
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合であれば、2,015万円以下
定額減税においては、同一生計配偶者や扶養する親族等の数に応じて、減税額が変動します。たとえば、本人のほかに同一生計配偶者と扶養する子どもがひとりいる場合には、3万円×3=9万円の所得税が減額されます。ただし、本人および配偶者等のいずれも居住者※に限定されることに注意してください。
※国内において、住所を有する個人または、現在まで引き続き1年間以上、居所を有している個人
天引きの仕組みを理解して正しく源泉徴収を行おう
給与からは所得税をはじめ、様々なものが天引きされています。ただし、全ての従業員が天引きの対象となるわけではなく、一定以上の収入が要件です。この点については、天引きを行う企業だけでなく、従業員もよく理解する必要があります。また、所得税などは、法律の定めがあるため天引きが許されているだけあり、原則として天引きは違法です。天引きできるものとできないものなど、天引きのルールを理解するために、ぜひ当記事をご活用ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
特定退職金共済制度とは?中退共との違いやメリット・デメリットを徹底解説【退職金規定テンプレ付】
特定退職金共済制度(特退共)は、国の認可を受けた商工会議所などが運営する、信頼性の高い退職金制度です。事業主が毎月掛金を支払うことで、従業員の退職金を計画的に準備できます。 本記事では、特定退職金共済制度の仕組みやメリット・デメリット、混同…
詳しくみる給与計算における住民税とは?市町村によって計算方法が異なる?
「自分が住んでいる町は隣の町より住民税が高い」という話を耳にしたことはありませんか? 住民税は、全国のどの都道府県市区町村に住んでいても同じだというのが原則です。ただし、自治体が税率を変更する権限をもっていますので、場合によっては例外も出て…
詳しくみる就業規則の退職金規定のポイントは?支給条件から計算方法、トラブル対処法まで解説
退職金は、長年勤続した従業員にとって将来の生活を支える大切な資金であり、企業にとっては従業員のモチベーションや定着率に関わる重要な人事制度の一つです。しかし、「自分の退職金はどうなっているのか?」「就業規則のどこを見ればいいのかわからない」…
詳しくみるエクセルで15分単位の給与計算をするには?関数や無料テンプレートを紹介
表計算ソフトのエクセルは、給与計算にも活用できます。関数の使用により、15分単位の勤怠管理や日をまたぐ勤務時間なども迅速な計算が可能です。しかしエクセルでの給与計算には注意点もあります。本記事では、エクセルを使った給与計算シートの作り方、よ…
詳しくみる【テンプレ付】源泉徴収税の納付期限はいつ?所得税・住民税の手続きや納付方法
給与から天引きされているのは、社会保険料や雇用保険料だけではありません。所得税や住民税などの税金も源泉徴収や特別徴収され、給与から天引きされています。 当記事では、源泉徴収(特別徴収)税について、納付期限や納付手続き、利用可能な特例など、多…
詳しくみる給与袋(給料袋)に適した封筒とは?書き方や印刷する方法も解説!【無料テンプレ付き】
給与袋(給料袋)に適した封筒選びは、給与の受け渡しをスムーズに行うために重要です。本記事では、給与袋の選び方のポイントや、手書き・印刷それぞれの作成方法について解説します。サイズや色、紙質などを考慮し、用途に合った封筒を選びましょう。手書き…
詳しくみる