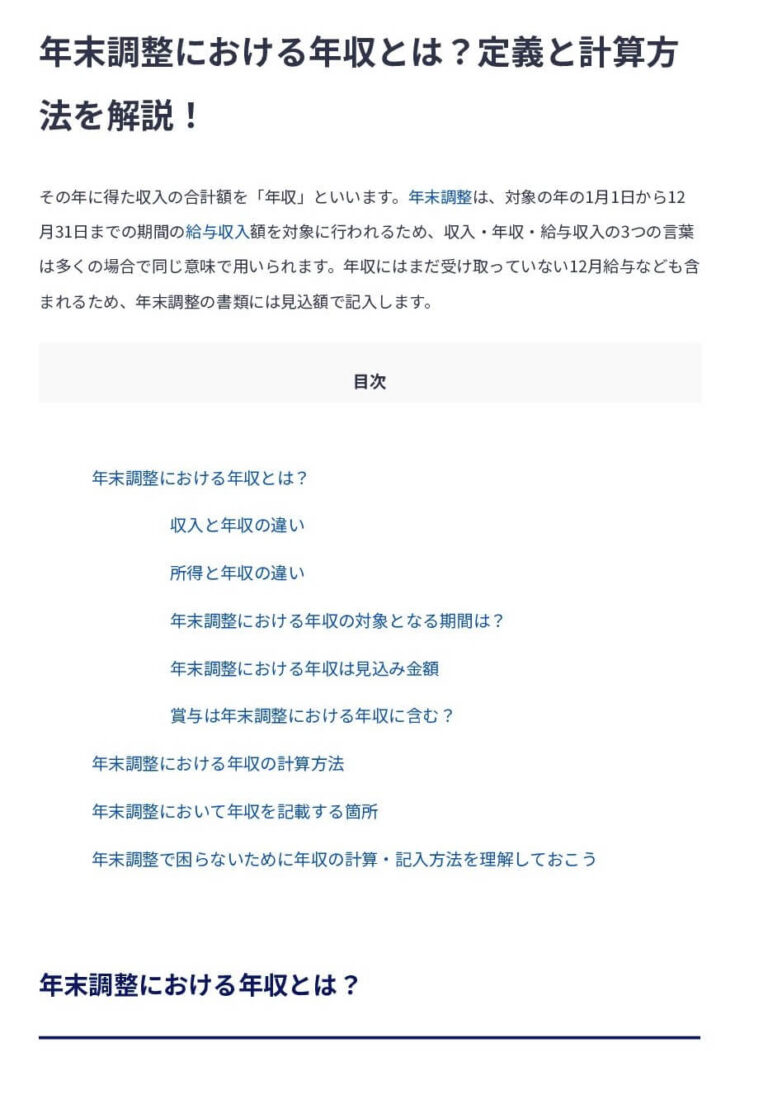- 更新日 : 2024年11月22日
年末調整における年収とは?定義と計算方法を解説!
その年に得た収入の合計額を「年収」といいます。年末調整は、対象の年の1月1日から12月31日までの期間の給与収入額を対象に行われるため、収入・年収・給与収入の3つの言葉は多くの場合で同じ意味で用いられます。年収にはまだ受け取っていない12月給与なども含まれるため、年末調整の書類には見込額で記入します。
目次
年末調整における年収とは?
年末調整では、日常生活では馴染みのない言葉や、理解できない言葉がよく登場します。「年収」や「収入」、「所得」なども、難しい言葉ではありませんが、具体的になにを指しているのかはわからないという方も多いのではないでしょうか。
年末調整における年収・収入・所得の言葉には、以下のような違いがあります。
収入と年収の違い
収入は金銭を得ることや、得られた金銭を指して使われる言葉です。労働の対価として支払われる給与については、「給与収入」が用いられます。
年収は、その年1年間の収入の合計額です。年末調整は1年を単位として行われるため、収入と年収は同じものとして取り扱われます。
所得と年収の違い
収入から、その収入を得るためにかかった費用を差し引くと所得になります。
例えば、土地などを売った場合、譲渡収入から購入代金や書類作成費といった取得・譲渡にかかった費用を差し引いたものが、譲渡所得になります。しかし、給与の場合は必要経費を差し引くことができません。このため必要経費に代わるものとして給与所得控除額を定め、給与収入から差し引いて給与所得を求めます。2020年以降の給与所得控除額は以下の通りです。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| ~1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001~1,800,000円 | 給与収入額×40%-100,000円 |
| 1,800,001~3,600,000円 | 給与収入額×30%+80,000円 |
| 3,600,001~6,600,000円 | 給与収入額×20%+440,000円 |
| 6,600,001~8,500,000円 | 給与収入額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円~ | 1,950,000円 |
年末調整では給与収入が年収として取り扱われるため、給与収入から上の表の給与所得額を差し引いた金額が給与所得額になります。
年末調整における年収の対象となる期間は?
年末調整で年収として計算に含むのは、その年の1月1日から12月31日までの期間の収入です。
年末調整における年収は見込み金額
年末調整は、その年の最後の給与支払時に行われ、申告書はそれより前、11月下旬から12月中旬にかけての期間に記入して提出しなければなりません。年末調整における年収は、1月1日から12月31日までの給与・賞与であるため、申告書の記入・提出後に受け取る12月賞与や12月給与も含める必要があります。
およその金額を想定しての記入となるため、年末調整での年収は、見込額になります。
賞与は年末調整における年収に含む?
年末調整では、賞与も毎月の給与と同じように年収に含まれます。
年末調整における年収の計算方法
年末調整では、その年1年間に支払いを受けた給与・賞与の金額を合計して年収を計算します。年末調整における年収の計算では、以下の点に気をつける必要があります。
- 合計するのは手取り額ではなく、支給額です。
- まだ受け取っていない分も含める必要があります。
- 支給時期が先の12月賞与や12月給料は見込額を求めて計算に使用します。
- 転職して前職の給与収入がある場合も、計算に含めます。
年末調整において年収を記載する箇所
年末調整で年収などを書く欄は、以下のように基礎控除申告書に設けられています。

参考:令和5年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
書き方は次の通りです。
①計算した年収を記入します。
②①の年収から給与所得控除額を差し引くことで求められる、給与所得額を記入します。次の速算表を用いると、簡略に計算できます。
■給与所得額速算表
| 年収(①の金額) | 給与所得額(②に記入する金額) |
|---|---|
| ~550,999円 | 0円 |
| 551,000~1,618,999円 | 年収(①)-550,000円 |
| 1,619,000~1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 1,620,000~1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 1,622,000~1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 1,624,000~1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 1,628,000~1,799,999円 | 年収(①)/4(千円未満切捨)→×2.4+100,000円 |
| 1,800,000~3,599,999円 | 年収(①)/4(千円未満切捨)→×2.8-80,000円 |
| 3,600,000~6,599,999円 | 年収(①)/4(千円未満切捨)→×3.2-440,000円 |
| 6,600,000~8,499,999円 | 年収(①)×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円~ | 所得金額調整控除なし→年収(①)-1,950,000円 |
| 所得金額調整控除あり→年収(①)-所得金額調整控除 |
③給与所得以外の所得がある場合に記入します。
④給与所得(②)と給与所得以外の所得(③)の合計額を記入します。
年末調整で困らないために年収の計算・記入方法を理解しておこう
年末調整は、毎月の給料から差し引かれた源泉徴収の合計を、所得税と同じ金額にする手続きです。1年を単位として行われるため、年末調整での収入は年収と同じ意味になります。12月給与といった支払いがまだの給与・賞与も含まれるため、年末調整で年収を書く際は見込額を想定して記入する必要があります。
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額です。簡略に計算できるよう速算表が準備され、記入する場所は基礎控除申告書にあります。年収の計算・記入方法を理解して、正確に年末調整をスムーズに行えるようになりましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末調整で火災保険は控除されるか?
火災保険は、火災や自然災害(台風による被害、落雷による被害など)によって建物や家財に損害が生じた場合に補償される保険です。以前は年末調整や確定申告の際に、支払った火災保険料に対して適用される「損害保険料控除」がありましたが、現在は廃止されて…
詳しくみる所得税が戻る?押さえておきたい年末調整の基本的な手順
会社など役員や従業員を雇用している事業主は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行ったのち、役員や従業員に給与を支払っています。 その1年間に源泉徴収された所得税や復興特別所得税の合計額と、納めるべき税額は一致しなければならないのですが、…
詳しくみるiDeCoは年末調整で申告できる?年末調整や確定申告の書き方や手順を解説!
自分で将来の年金を積み立てていくiDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛け金に応じて、所得税や住民税の控除を受けることができます。個人払込で掛け金を支払っている場合には、年末調整の際に支払額の申告が必要です。 iDeCoの申告が必要になるケー…
詳しくみる契約社員は年末調整の対象?確定申告をしたほうがいいケースも解説
契約社員も年末調整の対象です。ただし、契約社員が自分で確定申告をしなければならないケース、確定申告をしなければ受けられない控除があって所得税還付のためにも自分で確定申告をしたほうがいいケースがあります。 ここでは、どのような働き方が契約社員…
詳しくみる年末調整と転職者の関係
会社で働く場合に受け取る給与や報酬は、源泉徴収として所得税が前もって天引きされています。 しかし、各納税者の最終的な所得税額が決定すると、払いすぎた分や不足分を調整しなければなりません。 ここでは、年末調整の対象者に加え、転職者や退職者の年…
詳しくみる傷病手当金は年末調整の対象?
「傷病手当金」に所得税はかからず、年末調整の対象にはなりません。給料の代わりに休職中に受け取っていたとしても、年末調整での申告は不要です。扶養控除の申告での基準にも関係しませんが、社会保険の扶養家族の収入基準には関係します。傷病手当金受給者…
詳しくみる