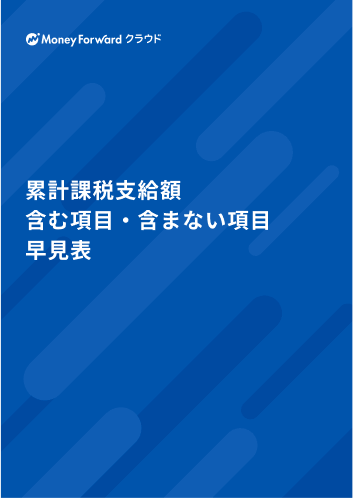- 更新日 : 2025年5月27日
累計課税支給額とは?103万の意味や含まれない金額、年収との違いを解説
従業員が給与を受け取る際には、給与明細が発行されます。給与明細には、勤務日数や控除された保険料などをはじめ、様々な情報が記載されていますが、その中に「累計課税支給額」という項目が存在します。当記事では、累計課税支給額の意味や計算方法、年収との違いなどについて解説します。
目次
累計課税支給額とは?
「累計課税支給額」とは、給与明細が発行された時点における年度内の「課税支給額」の累計となる額です。一方、課税支給額は、従業員に支給された給与のうち、所得税等の課税対象となる金額を指しています。累計課税支給額に誤りがあれば、正しく所得税等を計算できません。過誤納の問題が生じる恐れもあり、年末調整にも大きな影響を及ぼします。
なお、累計課税支給額は、「課税支給額累計」や「課税支給累計」、「課税累計額」などと表記される場合もあります。意味合いは異ならないため、累計課税支給額と同様の意味を持つ金額が表示されていると判断してください。
累計課税支給額はどこで確認できる?
累計課税支給額は、給与明細の該当項目で確認することが可能です。給与明細に設けられた累計課税支給額の項目に記載されている金額が、その年の1月から発行時点までの課税支給額の累計です。
なお、累計課税支給額を独立した項目として給与明細に設けていない企業もあります。その場合には、通常欄外に累計課税支給額の印字とともに、金額が記載されているため、そちらで確認が可能です。
累計課税支給額に含まれる、含まれない金額
課税支給額の累計額である累計課税支給額には、従業員に支給された金銭の全てが含まれているわけではありません。たとえば、所得税等の課税対象とならない手当は、課税支給額には含まれないため、累計課税支給額にも含まれないことになります。累計課税支給額に含まれる金額と含まれない金額について、項目を分けて解説します。
累計課税支給額に含まれる金額
累計課税支給額に含まれる金額には、基本給をはじめとして残業手当や休日出勤手当など、様々な種類が存在します。累計課税支給額に含まれない金額に該当しない手当などは、全て累計課税支給額に含まれることになります。また、賞与も所得として課税対象となるため、支給された場合には累計課税支給額に含まれる金額です。
累計課税支給額に含まれる金額のうち、主なものは以下の通りです。
- 基本給
- 残業手当
- 休日出勤手当
- 職務手当
- 役職手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 賞与
従業員に支給される手当等のほとんどが該当することになりますが、一定の手当等は課税対象から外れるため注意が必要です。
累計課税支給額に含まれない金額
一定金額までの通勤手当などは、課税の対象から外されるため、累計課税支給額に含まれません。累計課税支給額に含まれない主な手当を、以下の表にまとめます。
| 累計課税支給額に含まれない手当 | |
|---|---|
| 通勤手当 | 通勤手当は、1か月当たり15万円を限度として非課税となります。そのため、限度内の支給であれば、累計課税支給額に含まれません。なお、自転車や自動車で通勤する場合には、距離に応じて非課税となる額が変動します。 |
| 出張手当 | 出張手当は、業務に本来必要な範囲内の支給であれば、非課税です。そのため、累計課税支給額にも含まれないことになります。ただし、日帰りが可能であるのに宿泊した場合などは、課税対象となります。 |
| 宿日直手当 | 宿日直手当は、1回当たり4,000円までが非課税です。範囲内であれば累計課税支給額に含まれませんが、超えた部分は課税対象となります。 |
| 在宅勤務手当 | 在宅勤務手当は、実費相当額が非課税となります。そのため、立て替え払いを行った従業員に実費精算したような場合、その支給額は累計課税支給額に含まれません。 |
| 資格取得手当 | 従業員が担当業務に関連する資格を取得するための費用を手当として支給する場合は非課税となり、累計課税支給額に含まれません。ただし、システムエンジニアが簿記の資格を取得するなど、業務に関連しない場合には、課税対象となります。 |
| 食事手当 | 食事手当は、以下の条件を満たせば、非課税となるため、累計課税支給額に含まれません。
|
累計課税支給額103万の意味とは?
所得税においては、「103万円の壁」と呼ばれる基準が存在します。これは、所得税の計算における基礎控除額が48万円、給与所得控除額が55万円として設定されており、両者の合計額が103万円となることが由来です。
103万円の壁を超えた部分に所得税が発生するため、課税支給額の合計である累計課税支給額が103万円以内であれば、所得税は非課税です。つまり、給与明細の累計課税支給額の表示が103万円以内であるかどうかで、自分が所得税を課されるか否かを判断できます。また、103万円を超えた場合には、配偶者控除が受けられなくなるため、配偶者の所得税も高くなります。
所得税の103万円の壁のほかにも、社会保険における「130万円の壁」と呼ばれる基準が存在します。130万円を超えると、親や配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する義務が生じるため、このように呼ばれています。
ただし、こちらは累計課税支給額から判断することはできません。所得税の103万円の壁と異なり、130万円の壁は通勤手当等を含めた総支給額で判断されるからです。給与明細の累計課税支給額に130万円以内と表示されていても、扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならない場合があることに注意しましょう。
累計課税支給額の計算方法
累計課税支給額を計算するためには、まず課税支給額を計算しなければなりません。課税支給額の計算は、以下のように行います。
たとえば、支給総額が30万円、通勤手当等の非課税となる支給額が5万円の場合には、以下のように計算できます。
25万円が1か月当たりの課税支給額となるため、毎月の支給額に変動がないと仮定すれば、25万円に1月から給与明細発行月までの月数を乗じることで、累計課税支給額を算出できます。1月発行であれば25万円、6月発行であれば150万円、12月発行であれば300万円が累計課税支給額です。
より具体的なケースを挙げて、再度計算してみましょう。下記のような給与が支払われた場合の3月間における累計課税支給額を計算します。
| 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
| 通勤手当 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
| 残業手当 | 2万円 | ー | 3万円 |
| 休日出勤手当 | ー | ー | 1万円 |
| 出張手当 | ー | 2万円 | ー |
| 総支給額 | 25万円 | 25万円 | 27万円 |
| 課税支給額 | 22万円 | 20万円 | 24万円 |
1月は、総支給額25万円のうち、非課税となる通勤手当3万円を控除して課税支給額を計算します。2月は1月と総支給額自体は同様ですが、内訳が異なります。残業手当が支給されない代わりに、非課税である出張手当が支給されているため、通勤手当同様に控除が必要です。その結果、1月よりも低い20万円が課税支給額として計算されました。
3月は残業手当も休日出勤手当も課税の対象であるため、累計課税支給額に含まれ、非課税である通勤手当を控除した24万円が課税支給額となります。
今回のケースにおける3月間の累計課税支給額は、以下のとおりです。
累計課税支給額と年収との違い
年収をどのように定義するかは、自由です。しかし、健康保険料といった社会保険料や、源泉所得税などが引かれる前の総支給額の年間における合計額を表すのが一般的です。累計課税支給額は、課税の対象となる課税支給額の合計であるため、両者は異なった金額であるといえるでしょう。
たとえば、1か月における支給額が以下のようになるケースで、両者の違いを見てみましょう。
|
総支給額35万円には、非課税となる通勤手当が含まれているため、これを控除した33万円が課税支給額となります。総支給額と課税支給額のふたつを用いると、年収と1月から12月までの累計課税支給額を計算可能です。
年収:35万円(総支給額)×12月=420万円
年間における累計課税支給額:33万円(課税支給額)×12月=396万円
誤った理解はトラブルのもと
正確な税額を計算するためには、前提となる正しい累計課税支給額の計算が必要です。累計課税支給額の計算が誤っていれば、過納や未納の問題が生じてしまいます。また、年収との混同も避けなければなりません。
累計課税支給額の計算においては、課税の対象となる手当等の理解も欠かせません。当記事を参考に、累計課税支給額に対する理解を深め、過納や未納を未然に防いでください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
産休中はボーナスの査定期間に入る?賞与が減る、もらえない原因も解説
産休期間もボーナス(賞与)の査定期間に含まれることが一般的です。しかし、査定期間中に産休を取得した場合、ボーナスの金額に影響が出る可能性はあります。この記事では、産休中のボーナスの扱いや、査定期間の考え方、支給額の計算方法、社会保険料との関…
詳しくみる定額減税はいつから・いつまで減税される?
近年の企業の賃上げが物価上昇に追いついていない現状や家計負担の増加もあって、政府の経済対策として2024年6月から所得税と住民税の定額減税が実施されています。 定額減税がはじまると、労務担当者は月次の給与計算事務だけでなく、年末調整にも対応…
詳しくみる所得税徴収高計算書の記入方式
給与や報酬を支払う事業者にとって、源泉徴収業務は避けて通れない重要な税務手続きです。しかし、いざ「所得税徴収高計算書」を目の前にすると、どの欄に何を記入すればよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。 所得税徴収高計算書は、源泉徴収…
詳しくみる茨城県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
茨城県は工業が発展しており、特に自動車や電子部品の製造が盛んです。また、農業や観光業も重要な産業として位置づけられており、多様なビジネスが展開されています。こうした多岐にわたる業種では、給与計算の正確性と効率化が求められますが、中小企業にと…
詳しくみる有給休暇を付与したら通知は義務?通知する項目を例文つきで解説
原則、有給休暇を付与した際の通知は義務ではありません。労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者には、年次有給休暇を付与する必要があります。しかし、付与時に通知する義務があるかについては、意外と知られていないポイントです。 本記…
詳しくみる山梨県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
山梨県は豊かな自然を背景に、ワインや果物の生産が盛んであり、観光業も急成長しています。また、精密機器や自動車部品の製造業も地域経済を支える重要な産業です。こうした多岐にわたるビジネス環境では、給与計算の正確性と効率化が企業運営において不可欠…
詳しくみる