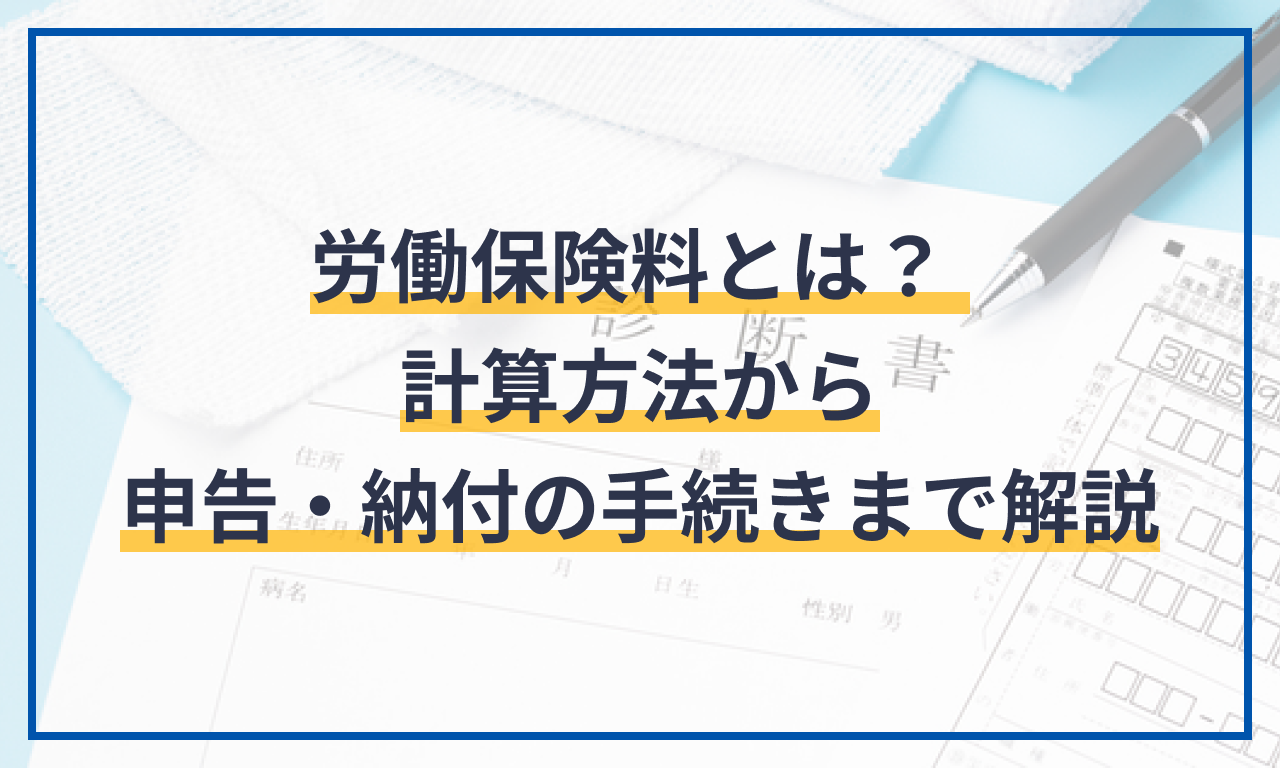- 更新日 : 2023年11月30日
ツァイガルニク効果とは?意味や例、起きる原因を解説!
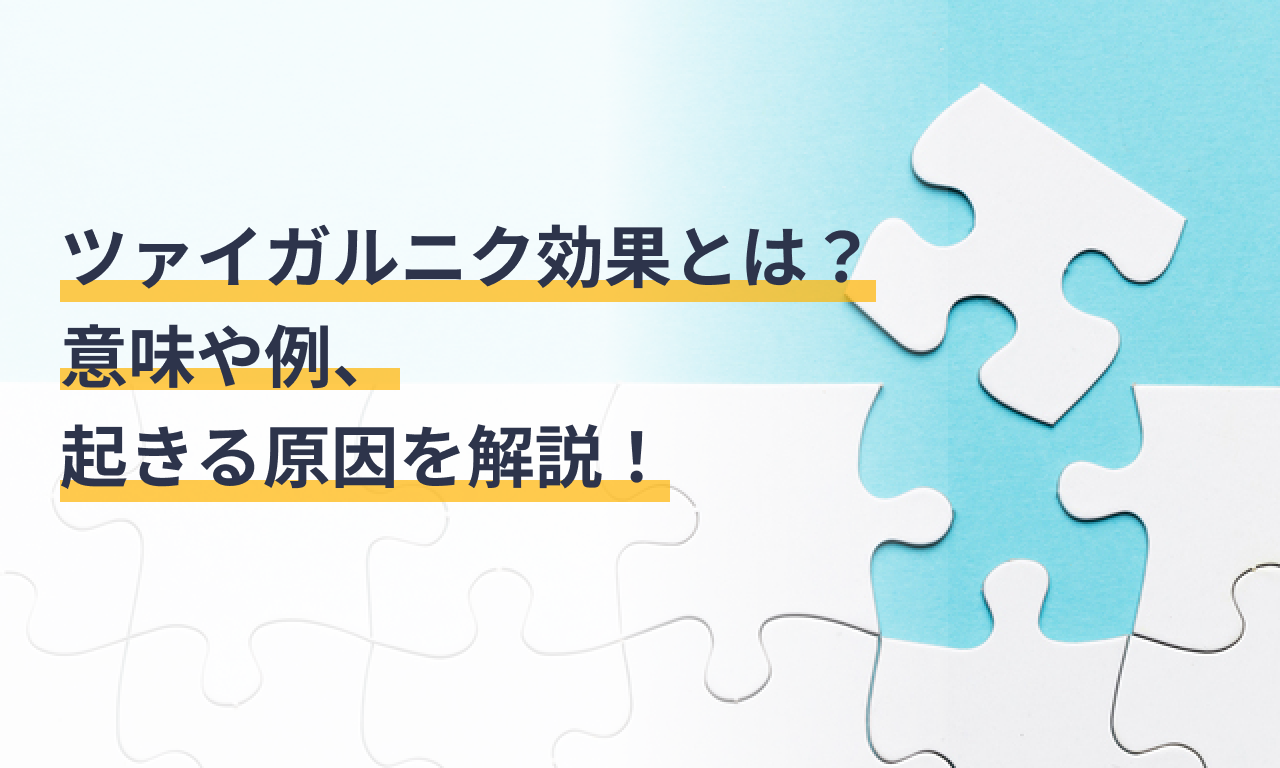
「ツァイガルニク効果」という心理学的な現象をご存知でしょうか?未完了の課題や目標に対する特別な関心やモチベーションを生む現象です。この効果を理解し、仕事やプロジェクトに活用することは、成果を上げる秘訣といえるかもしれません。今回の記事では、ツァイガルニク効果の意味から、仕事での活用方法まで、詳しく解説します。
目次
心理学:ツァイガルニク効果とは?
ツァイガルニク効果とは、達成できた事柄よりも、達成できなかった事柄や中断している事柄の方をよく覚えている現象のことを指します。これは、人間が何らかの欲求が未完了の場合は緊張感が持続しやすく、それが達成されることで緊張感が解消するという仮説に基づいた心理学実験で実証されました。
例えば、テレビのクイズ番組では、正解を出す前にCMを挟むことで視聴者の興味を引きつけます。これは、「途中で終わると気持ち悪い」という人間の心理を逆手に取ったものです。
ツァイガルニク効果の由来
ツァイガルニク効果は、1920年代、旧ソビエト連邦(現ロシア)の女性心理学者であるブルーマ・ツァイガルニク(Bluma Zeigarnik)によって発見されました。彼女は、ウィーンのカフェでウェイターが客の未払いの注文を正確に覚えていながら、支払済みの注文はすぐに忘れてしまうことに気づきました。
この発見が起因となり、実験を行い、「目標が達成されない行為に関する未完了課題についての記憶は、完了課題についての記憶に比べて想起されやすい」という事実を見出しました。この効果は彼女の名前を取ってツァイガルニク効果と呼ばれています。
ツァイガルニク効果の例
ツァイガルニク効果は人々の注意を引き、行動を促進するための有用な心理現象です。ビジネス、勉強、マーケティングにおけるツァイガルニク効果の具体例を解説していきましょう。
ビジネス・仕事
ビジネスや仕事の場面では、ツァイガルニク効果を活用して効率的に仕事を進められます。例えば、1つの作業を長時間続けるのではなく、中断を挟みながら行うことで、こまめな休憩を取ることができ、より集中して取り組めます。
また、営業においては最初に自社製品のメリットなど、顧客の興味を引き寄せる情報を伝え、詳細な情報を控えるようにすることで、顧客の関心を引き寄せた状態を維持して営業を行えます。
勉強・試験
ツァイガルニク効果は勉強にも応用できます。例えば、決まった時間で強制的に勉強をストップすると、「勉強の続きがしたい」「やり残したことが気になる」という気持ちになります。これにより、モチベーションが維持しやすくなり、勉強中の集中力をキープしやすくなります。また、暗記しなければいけないものを覚える際には、「中途半端な状態で終わり、続きを再開する」というサイクルで勉強すると効果的です。
広告・マーケティング
マーケティングでは、あえて中途半端な情報を与えることでユーザーの興味を引くことが可能です。例えば、広告の途中で「続きはWebで」と表示されると、視聴者はその続きが気になってインターネットで検索することもあります。このような広告では、あえて全ての情報を明かさずに視聴者の記憶に強く残すというツァイガルニク効果が働いています。
ツァイガルニク効果が起きる原因
ツァイガルニク効果が起きる原因は、未完了のタスクや課題が人の脳内に残り、それに対する関心や不安が高まることに関連しています。以下の要因が複合的に働き、ツァイガルニク効果が起きる原因となります。未完了の課題や目標は、人の注意と行動に影響を与え、その解決を求める心理的なプロセスを引き起こします。
心理的な不確実性
未完了の課題やタスクは、脳内に不確実性を生み出します。人は未知の結末や答えに対して興味を抱き、それを知ることで不安や好奇心が解消されるため、未完了の状態に関心を寄せる傾向があります。
脳の認知プロセス
未完了のタスクは脳の「オープンループ」を形成します。これは、タスクが開かれた状態で終わらずに残っている状態を指し、脳はこれを閉じることを欲します。そのため、未完了の課題に対する注意が高まり、それを解決しようとする動機が生まれるのです。
ゴール達成の欲求
人は目標やタスクを完了することで達成感や満足感を得ます。未完了のタスクがあると、成し遂げた達成感を得る機会に巡り合うので、最後まで取り組もうという気持ちになるのです。
ツァイガルニク効果のメリット
ツァイガルニク効果を活用することで、従業員のモチベーション醸成と業務生産性の向上を図れるので、組織にとって大きなメリットをもたらします。ここでは2つのメリットを紹介します。
課題達成のモチベーションに寄与する
ツァイガルニク効果は、達成していない事柄や中断された物事が強く記憶に残って気になる心理的現象です。この効果を活用すると、物事に取り組むモチベーションの維持や向上につながるメリットが得られます。中途半端な状態になった事柄があると気になる心理が生まれますが、「早く終わらせたい」「解決したい」といった強い思いを上手にコントロールすることで、高いモチベーションを維持したまま物事を解決へと導けるようになるでしょう。
生産性の向上につながる
ツァイガルニク効果は仕事などの生産性を高めるメリットがあります。仕事中に新規で仕事の依頼を引き受けた場合、これまでやっていた仕事は中途半端になることもあるでしょう。中途半端な仕事が気になる心理状態が生まれると、再開したときにはツァイガルニク効果によって高い集中力を維持でき、効率的に業務を遂行できるようになります。
また、「これまで行っていた仕事を早く終わらせたい」との欲求も高まるため、結果として新規で引き受けた仕事も効率的に行えるようになり、業務全体の生産性を高められます。
ツァイガルニク効果のデメリット
ツァイガルニク効果にはデメリットもあります。デメリットにも留意しつつ、慎重に効果を活用することが重要です。
ストレスにつながる
ツァイガルニク効果は、達成できなかった事柄や中断してしまった事柄が強く記憶に残る心理現象です。しかし、この効果を狙って仕事をあえて中断する場合、緊張感が残ると同時に仕事が未完になるためストレスを抱えます。特にストレスへの耐性が低い方や、仕事に対する意識が高い方は、こういった中断した仕事が多いほど、大きなストレスがかかります。また、未完の仕事がとどまることによって、ストレスを感じてしまう恐れがあります。
未達成が多いとモチベーション低下のリスクも
ツァイガルニク効果は、達成できなかったり、中断してしまったりした事柄が強く記憶に残るという特性を持っています。しかし、これが逆効果となり、仕事が完結できない状況が続くと、仕事に対するモチベーションの低下につながります。また、未完の仕事が増えれば増えるほどストレスが蓄積される可能性があり、これもモチベーションの低下につながる恐れもあります。したがって、ツァイガルニク効果を活用する際はバランスを保つことが重要です。
ツァイガルニク効果を仕事で活用するには?
ツァイガルニク効果をうまく活用することで、業務のモチベーションアップに活かせます。ここでは、3つのポイントを紹介します。
あえてキリの悪いところで終わらせる
ツァイガルニク効果を活用するためには、仕事をあえてキリの悪いところで終わらせることが有効です。これは、中断された仕事が記憶に残りやすく、作業を再開したときに集中力を維持したまま取りかかることができるからです。また、作業を先延ばしにしてしまう傾向のある方は、少しでも手をつけておくことでツァイガルニク効果が働き、作業を終わらせようと取りかかるきっかけになります。
タスク管理を徹底する
ツァイガルニク効果をモチベーションや生産性のアップに活かすためには、「適切な負荷量を保つ=タスク管理」の徹底が欠かせません。タスク管理を適切に行うことで、必要な課題を絞り込み、効率的に業務を進めることが可能になります。
適切に仕事が終わらせられるよう管理する
ツァイガルニク効果を活用するためとはいえ、大した理由もないのに仕事を中断するのは良くありません。中断された仕事がたまっていくとタスク管理が難しくなり、無駄な業務が増えてしまう恐れがあります。無駄な業務が増加すると、作業効率が下がるといった問題が生じてきます。仕事を中断したとしても、作業時間を記録して、目標の時間で終わらせられるようにタスク管理しましょう。
ツァイガルニク効果を理解し、仕事の生産性向上に活用しよう!
ツァイガルニク効果は、未完了の課題に関する特別な心理的プロセスを起こし、モチベーションを高めることを期待して活用できます。とはいえ、過度なストレスを引き起こすこともあるため、適切なバランスの維持とタスク管理が必要です。仕事での成果を向上させるために、ツァイガルニク効果を上手に活かしてみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。