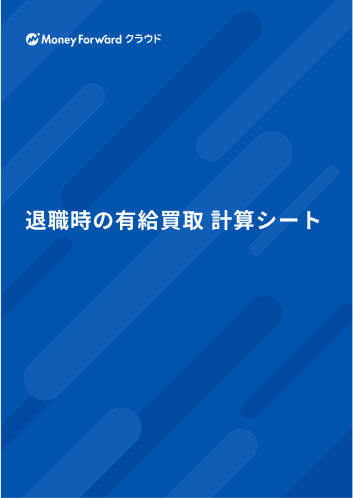- 更新日 : 2025年5月27日
有給休暇の買取ができるパターンと計算方法を解説
有給休暇の買取は原則違法です。しかし、例外的に認められるケースもあり、適切に運用すれば法的リスクを回避できます。
本記事では、有給休暇の買取が認められる具体的な条件や計算方法について解説し、買取時に発生しやすいトラブルや注意点も紹介します。企業の適切な労務管理のためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次
有給休暇の買取は原則違法である
有給休暇の買取は原則として違法です。
有給休暇の本来の目的は、休暇を取得することで労働者の心身の疲労をリフレッシュさせ、ゆとりのある生活を保つことです。有給休暇を取得することで、生産性の向上も期待できます。
企業が有給休暇を買い取れるようになると、企業側が積極的に有給を買い上げ、従業員に有給を取得させない事態も起こりかねません。上記の状態では、何のために有給休暇についての法律を定めたのかわかりません。
そのため、従業員からの申し出であっても、有給休暇の買取は違法とされていますが、例外として、企業が有給休暇の買取をしてもよい場合もあります。
有給休暇の規定については下記の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
有給休暇の買取が認められるケース
有給休暇の買取は原則として禁止されていますが、例外的に認められるケースもあります。違法な取引と適法な買取には明確な違いがあり、誤ると法的リスクを伴う可能性があるため注意が必要です。以下では、有給休暇の買取が認められるケースを解説します。
退職時に未消化で残っている有給休暇
退職時に未消化の有給休暇がある場合は、例外的に買取が認められます。
定年退職や自己都合退職かにかかわらず、退職後は労働者の権利を失うため、有給休暇の取得ができません。そのため、有給休暇を買い取っても従業員の不利益にはならないことにより、違法にはなりません。
ただし、有給休暇を使用せずに買い取った場合、社会保険の加入期間が変動する可能性があります。たとえば、退職日が3月25日で10日分の有給を買い取った場合、資格喪失日は3月26日となり、資格喪失月の前月である2月までが社会保険の加入期間となります。
一方で、3月25日が最終出勤日で、退職日までを10日間の有給休暇取得で処理した場合には、資格喪失月は4月となり、3月までが社会保険の加入期間です。
時効により権利が消滅した有給休暇
有給休暇は付与から2年で時効により権利が消滅します。権利が消滅すると、労働者は有給休暇を自由に取得できなくなるため、買取が認められます。
上記は、消滅した有給休暇を買い取っても労働基準法違反にならないためです。
労働基準法第115条では、賃金請求権の時効は5年、災害補償や有給休暇の請求権の時効は2年と定められています。そのため、付与から2年が経過した有給休暇は、法的に取得する権利を失います。
ただし、買取制度がない場合は、有給休暇の消滅を防ぐために企業が取得を促すことが重要です。
法定日数を超える有給休暇
労働基準法で定められた有給休暇の日数を超える部分は、会社独自の制度であるため、買取が認められます。法定外の有給休暇は、企業が特典として設けたものであり、労使間の合意により買取条件を自由に決めることが可能です。
法定外の有給休暇には、就業規則で定められた特別休暇が含まれます。特別休暇があることで、労働者は体調不良に備えて年次有給休暇の取得を控える必要がなくなり、有給休暇の取得促進にもつながります。
有給休暇買取のメリット
有給休暇の買取は、従業員だけでなく企業側にもメリットがあります。主なメリットは、以下の2つです。
社会保険料の負担軽減
退職する予定の従業員が、残っている有給休暇を消化するまで退職せず休暇を取ることがよくあります。この間、まだ従業員は企業に在籍しているため、社会保険料の負担をしなければなりません。
有給休暇を買い取って退職日を前倒ししてもらえば、社会保険料の負担が減少する可能性があります。
退職する従業員とのトラブル回避
有給休暇消化中の退職予定者は、出社はしませんが企業の従業員であることに変わりはありません。そのため、労働者としての権利を企業に求めることができ、場合によってはトラブルの原因となる可能性があります。有給休暇の買取をして有給消化期間を無くすことにより、リスクを回避できます。
また、一般的に有給休暇の上限は40日ですが、業務の状況や退職理由などによっては消化しきれない場合もあるでしょう。残った有給休暇は退職と同時に消滅するため、退職する従業員とトラブルになる可能性があります。この場合、残った有給休暇を買い取ることにより、円満に解決できるでしょう。
有給休暇の買取で起こりやすいトラブル事例
有給休暇の買取は例外的に認められていますが、トラブルが発生する可能性があります。違法な取引や手続きの不備があると、企業・労働者双方にとって不利益を招くこともあります。
適切に対応するためには、どのような問題が起こり得るのかを把握しておくことが重要です。以下では、有給休暇の買取で起こりやすいトラブル事例を紹介します。
買取できるかに関する労使間でのトラブル
有給休暇の買取では、「会社都合で取得できなかった有給を買い取ってもらえない」「買取制度があることを知らなかった」といったトラブルが発生しやすい傾向にあります。
とくに、就業規則に買取規定がない場合、口約束だけでは「言った・言わない」の問題に発展しやすくなります。
対策として、買取制度の有無や条件を明確に記載した書面を作成し、労働者と取り交わすことが重要です。したがって、就業規則には買取の対象や有給休暇の買取金額、支払い日、支払い方法などを明記しておきましょう。
買取金額に関するトラブル
有給休暇の買取において「通常の賃金で計算されると思っていたが、実際の買取額が低かった」といったトラブルが発生することもあります。
有給休暇の買取金額は法律で定められておらず、企業が自由に設定できるため、計算方法の説明不足や労使間の認識の違いが原因でトラブルが発生します。
トラブルを避けるためには、買取金額の計算方法を事前に明確にし、労使間で合意を得ることが重要です。
有給休暇の買取の回避方法
有給休暇の買取は例外的に認められるものの、本来は従業員が取得する必要があります。買取が常態化すると、労働者の休息機会が失われるだけでなく、企業の負担も増える可能性があります。
そのため、適切な対策を講じ、有給休暇の買取を回避することが重要です。以下では、有給休暇を適切に取得してもらうための具体的な方法を紹介します。
有給休暇を取りやすい環境を整える
有給休暇の買取を防ぐには、取得しやすい環境を整えることが重要です。具体的には、業務の進行状況を週次ミーティングで共有し、同僚が業務を把握できる体制を築くことで、休暇中でも仕事が円滑に進みます。
また、「個人で完結させる」という意識を改め、チームで業務を分担することで、休みやすい職場環境をつくります。取得を促す声かけや取得状況の確認制度を導入することで、有給休暇を積極的に利用する環境が整えられるでしょう。
下記の記事では、有給休暇を適切に取得するための方法について解説しているため、あわせてご覧ください。
有給休暇を計画的に管理する
有給休暇の買取を回避するには、計画的な管理が有効です。年次有給休暇の計画的付与制度を導入すれば、付与日数のうち5日を除いた残りの日数を労使協定のもとで割り振れます。
たとえば、10日付与される場合は5日、20日なら15日を計画的に付与可能です。計画的に付与する制度を導入すると、有給休暇の取得率が向上し、未消化分の買取を防げます。さらに、労働者が遠慮せずに休暇を取得しやすくなり、企業全体の働きやすさも向上します。
有給休暇を買取してもらう場合の適切な計算方法
有給休暇の買取では、事前に適切な計算方法を定めることが重要です。労働基準法第39条第9項では、買取金額の計算方法として「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬日額」の3つが規定されています。
以下では、各計算方法について解説します。
通常賃金で計算する場合
通常賃金とは、所定の労働時間を働いた際に支払われる賃金のことです。
有給休暇を買い取る際、通常賃金で計算する方法は給与形態によって異なります。
- 月給制:「月給 ÷ 労働した月の所定労働日数」
- 週休制:「週給 ÷ 労働した週の所定労働日数」
- 日給制:「所定の出勤日数分そのまま」
期間が設定されている場合は、「期間の賃金額 ÷ 所定労働日数」で計算されることが一般的です。
平均賃金で計算する場合
平均賃金とは、労働基準法で定められた手当や補償の算定基準となる金額で、有給休暇の買取時にも適用されます。計算方法は以下のとおりです。
| 計算式 | 備考 | |
|---|---|---|
| 平均賃金 | 直近3ヶ月の総賃金 ÷ 期間の総日数(暦日数) | 例) 4月から6月の総賃金が90万円の場合、「90万円 ÷ 91日 = 9,890円」 |
| 最低補償額 | 総賃金 ÷ 直近3ヶ月の労働日数 × 60% | 日給制・時間給制・出来高給制の場合に適用 |
最低補償額が平均賃金を上回る場合は、最低補償額が適用されます。
標準報酬月額で計算する場合
標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険で用いられる報酬の基準で、一定の等級に分類されています。有給休暇を取得する際、標準報酬月額をもとに日割り計算を行い、1日あたりの賃金を算出します。
計算方法は「標準報酬月額 ÷ 30日 × 休暇日数」です。
標準報酬月額が30万円(厚生年金19等級)の場合、5日分の買取額は「30万円 ÷ 30日 × 5日 = 5万円」となります。
定額の場合
定額方式では、企業が事前に定めた金額を1日あたりの有給休暇賃金として支払います。有給休暇の買取額に関する法律はなく、企業が任意で設定可能です。シンプルで管理しやすい反面、実際の賃金と差が生じることがあります。
とくに、勤務時間や日数が不定期なパートタイマーやアルバイトに適用されることが一般的です。企業は、公平で適切な買取額を設定することが重要です。
有給休暇の買取に関する注意点
有給休暇を買い取る際には、法律違反にならないよう注意が必要です。労働基準法では、年5日分の有給休暇取得が義務付けられており、未消化分の買取は限定的な場合にのみ認められます。
適切な手続きを踏まずに取引すると、法令違反となる可能性があるため事前にルールを確認することが重要です。以下では、有給休暇の買取に関する注意点を解説します。
買取は義務ではない
有給休暇の買取は法律で義務付けられていません。従業員が買取を当然の権利と誤解すると、企業が拒否した際にトラブルになる可能性があります。
法律上、有給休暇は労働者の疲労回復と生活の質向上を目的としており、自由に売買できるものではありません。そのため、企業は買取を拒否できます。ただし、トラブルを防ぐため、就業規則に取引の可否を明記しておくことが重要です。
下記記事では、年次有給休暇の取得が義務化されたことについて解説しているため、知識を深めるためにもあわせてご覧ください。
買取の予約は違法である
有給休暇の買取予約とは、未消化の年次有給休暇を企業が事前に買い取ることを約束する行為です。しかし、労働基準法に違反するため注意が必要です。
買取を予約すると、労働者が本来取得できる有給休暇が実質的に減少し、休暇が付与されないのと同じ状態になります。
上記は、労働基準法第39条に定められた最低付与日数を満たさず、違法です。企業は有給休暇を適切に管理し、労働者が取得しやすい環境を整えることが重要です。
買取は「賞与」として計上する
従業員にとって有給休暇とは、休暇を取っても給料が発生する日のことです。
つまり、企業側は従業員が有給休暇を取得した場合、通常通り給料が発生したとして処理します。しかし、企業が従業員の有給休暇を買い取りした場合には、買い取った金額を給料として扱うことはできません。
有給休暇の買取で従業員に支払った金額は「賞与」として扱われます。
したがって、賞与を支払った場合と同様の手続きが必要です。まず、支払い後5日以内に「被保険者賞与支払届」を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。
従業員には本来の賞与と同様に社会保険料を控除された金額が支払われますので、給与明細ではなく、賞与明細を発行します。
有給休暇の買取ルールを確認して法違反を回避しよう
有給休暇の買取は、原則として違法ですが、退職時や法定日数を超えた分など、例外的に認められるケースもあります。
誤った運用をすると労使間でのトラブルや法的リスクにつながるため、ルールを正しく理解し、適切に対応することが重要です。従業員が有給を取得しやすい環境を整備し、必要に応じて買取のルールを確認して違法リスクを回避しましょう。
よくある質問
有給休暇は買取できる?
原則として違法ですが、条件によっては買取できるケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
有給の買取ができるケースは?
法定日数より多く有給休暇が与えられている場合の多い分、失効した有給休暇、退職時に未消化の有給休暇など、従業員を休ませるという有給休暇の趣旨を損なわないケースのみ買取できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
有給休暇の関連記事
新着記事
再雇用制度の就業規則の記載例!ルールの決め方や変更手続きも解説
高年齢者の雇用確保が求められる中、再雇用制度の整備は企業にとって重要な課題です。就業規則において再雇用制度を明確に定めることで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、円滑な人事運営が可能となります。本記事では、再雇用制度の就業規則への記載方法や注…
詳しくみる60歳再雇用は何歳まで?更新や拒否、無期転換、給与や規則の決め方まとめ!
60歳で定年を迎えた後も働きたいと考える人が増えていますが、再雇用の給与や契約更新、就業規則など不安や疑問も多いものです。本記事では、再雇用制度の基本から、給与の決まり方、更新や拒否のルールまで、企業と働く側の両視点でわかりやすく解説します…
詳しくみる60歳以上の高齢者雇用の助成金や給付金、支援、手続きまとめ
人手不足が深刻化する中、60歳以上の高齢者を積極的に雇用する企業が増えています。こうした取り組みに対して、国や自治体は助成金を支給し企業を支援しています。高齢者雇用助成金は、60歳以上の雇用に対して一定の条件を満たすことで受け取ることができ…
詳しくみる退職者への源泉徴収票の発行はどうする?再発行の対応や注意点を解説
退職者への源泉徴収票の発行は、企業が必ず対応すべき重要な法定業務のひとつです。これは退職者が確定申告や転職先での年末調整を行う際に必要不可欠な書類であり、正確かつ期限内に交付しなければなりません。発行手続きには給与情報の集計や送付方法の確認…
詳しくみる再雇用で活用できる助成金や給付金とは?シニアの支援、手続きまとめ
60歳以上の再雇用や継続雇用を支援するため、企業や個人が活用できる助成金や給付金制度があります。人手不足が深刻化する今、高齢者の雇用を促進するための支援策を知り、適切に活用していきましょう。この記事では、助成金の種類、条件、手続き、金額、注…
詳しくみる給与計算における日割りの端数処理のやり方!欠勤・遅刻・早退時の計算例まとめ
給与計算では、日割り計算や端数処理が必要になる場面が多くあります。例えば、入社日や退職日が月の途中、欠勤や時給制社員の勤務日数が変動する場合などです。基本給や手当の一部に小数点以下の金額が生じた際、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のどれ…
詳しくみる