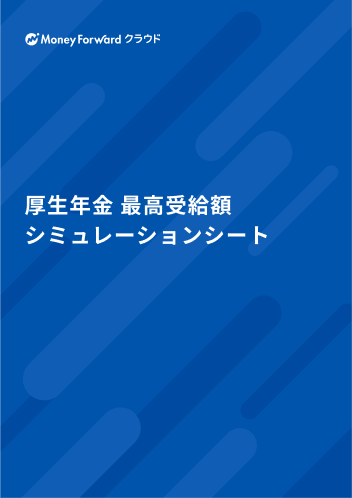- 更新日 : 2025年3月27日
厚生年金の最高額は?いくらもらえる?
老齢厚生年金の受給額は支払ってきた保険料に応じて決まるため、基本的には現役時代の年収が多い人ほど、また加入期間が長いほど多くの年金を受け取れます。
ただし、保険料の計算の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額には上限があることに注意しましょう。今回は厚生年金の最高額や、最高額を受給するための条件などを解説します。
目次
厚生年金の最高額は?
老後に受け取れる、厚生年金の理論上の最高額は月額でおよそ30万3,000円です。厚生年金は国民年金と異なり、年収が高く、加入期間が長いほど受給額が増える仕組みのため、受給額に関して「満額」は存在しません。ただし、給与や賞与を保険料に反映する際の上限が決まっているほか、加入期間も70歳までという区切りがあることを押さえておきましょう。
また、後述しますが、老後に受給できる老齢年金には、基本的に厚生年金と国民年金の2つがあります。国民年金の満額は、40年間保険料を納めた場合に約6万5,000円となるため、厚生年金と国民年金を合わせると36万8,000円程度になります。
なお、日本年金機構が公表している、夫婦2人分の平均的な厚生年金と国民年金の合計金額は約22万円です。
厚生年金についておさらい
厚生年金は日本の公的年金制度の2階部分にあたり、1階部分の国民年金に上乗せして支払われる年金のことを指します。厚生年金として受け取れる金額は、保険料を納めていた現役時代の月収や賞与の金額によって変わります。納めてきた保険料が多い人の方が、受け取れる年金の金額も多くなる仕組みです。
国民年金は20歳以上60歳未満の国民すべてに加入義務があるのに対し、厚生年金は会社員や公務員が加入します。つまり、自営業やフリーランスの方は厚生年金には加入していません。
また、国民年金は年収に関わらず、40年間すべての月において保険料の全額を納めていれば同じ金額の年金を受け取れるため、両者の違いに注意しましょう。
なお、国民年金の老齢基礎年金は、従来は保険料を25年以上支払うと受給資格を得られましたが、現在は10年に短縮されています。ただし、国民年金の老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間保険料を払い続ける必要があります。
標準報酬月額と標準賞与額を元に計算する
厚生年金の保険料を計算する際の元になるのが「標準報酬月額」と「標準賞与額」です。厚生年金や健康保険などの社会保険料は、実際の給与や賞与の金額をそのまま使って計算するわけではありません。
給与や手当などに関しては、社会保険料の計算をしやすくするために、金額を一定の範囲で区切った「月額等級」に当てはめます。標準報酬月額とは、月額等級によって設定されている、保険料の計算用の金額のことです。
標準報酬月額は「32等級の65万円」が上限として設定されています。月額等級の32等級には標準報酬月額63万5,000円以上が当てはまるため、給与や手当といった報酬額が63万5,000円以上の場合、保険料は同じです。
また、賞与は税引前の金額から1,000円未満の端数を切り捨てます。支給1ヶ月あたり150万円が上限となるため、1回の賞与額が150万円を超える場合は150万円となります。
厚生年金の最高額をもらえるための条件
次に、厚生年金の理論上の最高額をもらえるための条件を確認していきましょう。老齢厚生年金の受給額は、前述のとおり上限があるものの、年収によって異なります。さらに加入期間が長いほど、受給できる金額が増える点もポイントです。
理論上の最高額の老齢年金を受け取るには、次の条件を満たしている必要があります。
- 厚生年金への加入期間中、常に標準報酬月額の上限である63万5,000円以上の給与を受け取る
- 厚生年金への加入期間中、賞与を常に年3回、標準賞与額の上限である150万円以上受け取る
- 中学を卒業後すぐに就職し、70歳まで上記の条件で継続して働く
ちなみに給与が63万5,000円、150万円の賞与が3回支給される方の年収は1,212万円です。
ただし、15歳の若さで会社員として1,200万円以上の金額を稼ぐことも、70歳までその年収を維持し続けることもかなりのレアケースといえます。あくまでも最高額の目安として捉えましょう。
厚生年金額を算出する計算式
老齢厚生年金の最高額を計算するプロセスを知っておきたいという方もいるでしょう。
老齢厚生年金の金額の原則の計算式は、次のとおりです。
なお、2003年4月より前は、賞与が厚生年金の保険料の対象ではなかったため、計算式が異なることに注意しましょう。
今回の計算では、わかりやすくするため、被保険者として加入していたのはすべて2003年4月1日以降の時期とします。
標準報酬額は、標準報酬月額と標準賞与額の合わせたものです。賞与が150万円ずつ年3回支払われている場合、それを12で割ると37万5,000円となるため、標準報酬額は「65万円+37万5,000円」で102万5,000円です。
そのため、15歳から70歳まで働いていた場合の老齢厚生年金の金額は以下のように計算できます。
ここから、厚生年金の月額は30万3,000円になることがわかるでしょう。このケースでは、実際には国民年金の老齢基礎年金も合わせて合計36万8,000円程度の受給額となります。
現役時代の生活水準やお金に対する価値観によって、この金額を高いとするか否かの判断はわかれるといえるでしょう。
厚生年金の受給額早見表
将来自分がもらえる年金がいくらぐらいなのか、気になっている方も多いかもしれません。年金受給額の計算は非常に複雑であるため、詳しくは毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」を確認することをおすすめします。ねんきん定期便には、これまでの年金の保険料の納付状況と、受給できる年金の見込額が記載されています。
ここでは、おおよその年金受給額を知りたいという方に向けて、年収・加入年数別のおおよその厚生年金の受給額早見表をご紹介します。
| 年収 | 厚生年金の加入年数(保険料納付期間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
| 300万円 | 1.5万円 | 2.2万円 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.5万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
| 400万円 | 1.9万円 | 2.9万円 | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.8万円 | 7.8万円 |
| 500万円 | 2.3万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 7.0万円 | 8.2万円 | 9.4万円 |
| 600万円 | 3.2万円 | 4.8万円 | 6.4万円 | 8.0万円 | 9.6万円 | 11.3万円 | 12.9万円 |
※2003年の制度改正以降の「平均標準報酬額✕5,769/1,000✕加入月数」によって計算
※百の位以下は切り捨て
参考:大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています|日本年金機構
厚生年金の最高額の目安を知ろう
老齢厚生年金の理論上の最高額は、月額でおよそ30万3,000円です。国民年金の老齢基礎年金は、保険料が一律であるため、40年間保険料を納付していれば満額を受給できます。一方で老齢基礎年金は、保険料を算定する際に給与や賞与に上限が設けられるものの、基本的には年収が高く加入期間が長いほど受給額が増える仕組みです。
ただし月額30万円程度の厚生年金を受給するには、中学卒業後すぐに働き始め、年収1,200万円程度をキープし続けることが必要であり、あまり現実的な状況とはいえません。
厚生年金の最高額を受給することは難しいかもしれませんが、この機会に、将来自分が受け取れる厚生年金の見込み額を確認してみてはいかがでしょうか。
よくある質問
厚生年金の最高額は?
理論上の概算額は、月額で30万3,000円程度です。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金の最高額をもらえるための条件は?
中学卒業後から70歳まで厚生年金に加入し、その間継続して毎月63万円5,000円以上の給与と年3回150万円以上の賞与が支給されている必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金の第3号被保険者とは?扶養との関係は?
厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者に該当します。第3号被保険者は、国民年金保険料も厚生年金保険料も納付する必要がありません。第3号被保険者に該当する旨の手続きを行うことで、国民年金保険料を納めなくても、年金額…
詳しくみる産前産後休業期間中は厚生年金保険料は免除される?育児休業等期間中も解説
経済的な理由で従業員が休業取得をためらうようなことがないように、産前産後休業期間中や育児休業期間中にはさまざまな経済的支援制度が用意されています。 産前産後休業や育児休業期間中に健康保険、厚生年金保険の保険料の免除を受けるには、企業からの申…
詳しくみる入社手続き中の従業員が退職したら社会保険はどうなる?退職後の手続きも解説!
従業員は、入社日に社会保険の被保険者資格を取得します。そのため、すぐに退職した場合でも被保険者資格取得日・被保険者資格喪失日に応じて必要な社会保険料を納めなければなりません。従業員負担分を給与から控除できない場合は、別に徴収する必要がありま…
詳しくみる介護保険サービスの自己負担額は?負担割合や計算方法も解説
介護保険サービスを利用することになった際に、気になる点の一つとして「いくらかかるのか?」ということがあります。サービスを安心して受けられるようにするためにも、かかる費用についての目安を知っておくことが必要でしょう。 今回は、介護保険サービス…
詳しくみる雇用保険における再就職手当とは
失業や休業の場合にはもちろん、労働者が能力開発のため教育を受ける場合にも利用できる雇用保険。一般的には失業保険と言われる、自己による都合や会社側の都合によって離職した際に支給される基本手当がよく知られていますが、さらに、知っておくと得する意…
詳しくみる社会保険の随時改定を行う3つの条件!月額変更届の書き方や残業の影響を解説
昇格などで賃金に大幅な変動があれば、それに伴い社会保険の保険料も改定が必要になります。この手続きを社会保険の随時改定といいます。ただし、臨時手当により1ヶ月だけ賃金が増加したり、残業代によって給与が増えたりする場合は随時改定の対象外です。 …
詳しくみる