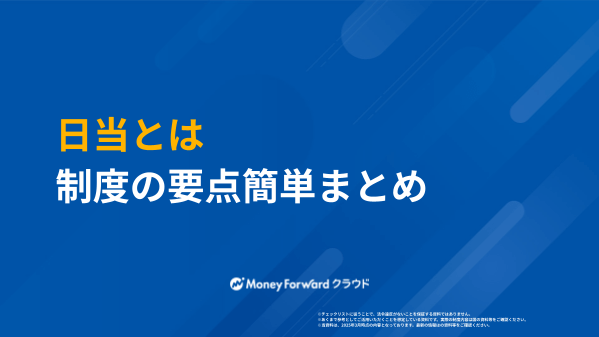- 更新日 : 2025年3月26日
日当とは?意味や決め方、課税対象かを解説
日当と日給は同じものだと思われるかもしれませんが、1日単位で支給される賃金を指す日給とは意味や性質が異なります。日当は1日単位で支給される手当であり、会社経営上発生するのは、主に出張時に支給する「出張手当」や「旅費手当」などが代表的です。ここでは、日当の意味や決め方、税法上の取り扱い、導入方法などについて解説します。
日当とは
日当とは、出張手当や旅費手当のように、1日単位で支給される手当を指し、労働の対価として企業が従業員に支払う賃金とは異なります。日給は労働の対価として支払う賃金、つまり1日働いたことによる給与そのものを指し、月給であれば基本給に相当する金額です。日当は基本給以外に支払う手当であり、労働の対価とはいえないものの、手当の一種といえます。
企業経営上発生する日当には、代表的なものに出張時に発生する「出張手当」や「旅費手当」などがあります。最初に、日当の目的や交通費や出張費との違いについて確認しましょう。
日当の目的
日当の目的は、出張先で従業員が立て替えた経費や、生活費、雑費などの負担分を補填することにあります。そのため、労働の対価として企業が従業員に支払う賃金・給与・手当などとは目的も性質も異なります。
日当の金額や支払い方法については、法的な決まりはありません。日当のルールは、就業規則の出張旅費規程などで定めるのが一般的です。出張先までの距離、宿泊の有無、出張期間、役職の種類などによって金額を決めることが多いでしょう。
交通費や出張費との違い
交通費や出張費は、実費精算が原則です。出張先への往復の交通費、宿泊費は領収書などで実際にかかった費用を確認できるため、経費としてそのかかった費用を精算し、従業員に支給します。
一方、日当を手当として定められた金額で支給すれば、出張先で生じた実費を領収書で確認し、後日精算する必要なくなります。日当を支給することで経費精算の作業負担を減らすことが可能となり、業務効率化にもつながります。
日当は出張時に必要となる費用全体の補填を目的とすることも、交通費や宿泊費以外の生活費や雑費の支払いを目的とすることも可能です。そのため、以下の2つの支給方法が考えられます。
- 出張時に必要となる交通費や宿泊費を含めた費用全体を経費として支給する
- 出張時に必要となる交通費や宿泊費は実費精算し、それ以外の生活費・雑費にあたる費用を経費として支給する
日当を設けるメリット
企業が出張時に発生する経費を日当としてを設けることは、多くのメリットがあります。
社員からの不満防止に繋がる
出張時には、出張先で食事をすることもあれば、飲み物、歯ブラシ、タオルなどの生活必需品を購入することもあります。出張命令がなければかからなかったはずの費用を従業員が全額負担すれば、出張をすることに対する不満につながります。日当には、従業員へのねぎらいや不満の抑制の効果もあるのです。
想定外の出費を補填できる
長期出張であれば、洗濯やクリーニング代が必要となることもあります。また、緊急時に思わぬ出費が発生することもあります。出張時の想定外の費用について補填できることもメリットといえるでしょう。
日当の決め方 – 目的別に解説
日当の金額の決め方や支給方法については、特に法的な決まりはありません。また、日当の支払いを法律で義務付けられているわけでもありません。したがって、日当は企業で自由に設定することが可能です。日当の決め方について、目的別に見ていきましょう。
外食費用の補填の場合
朝食や夕食は、宿泊先のホテルや旅館の料金に含まれることが多いでしょう。しかし、ビジネスホテルなど、宿泊プランや宿泊先によっては食事が含まれていないことがあります。また、新幹線で移動中に食事代を自分で負担することもあれば、出張先で自分で店を探して昼食を取ることもあります。
出張先での外食は普段よりも費用がかかることが多く、長期間出張する場合には大きな出費になることがあります。食費を日当で補填することも検討したほうがよいでしょう。
残業代カバーの場合
出張先で残業をすれば、残業代の支払いが必要です。日当を残業代の支払いを目的として支給することも可能ですが、この場合、実態として残業代に当たれば賃金・給与に該当し、給与所得になります。実際の時間外手当や休日・深夜労働の手当が日当を上回る場合には、別途、追加で残業代の不足分を支払わなければなりません。
また、出張時には、事業場外のみなし労働時間制を適用して、残業代を支払わないケースもあるでしょう。しかし、実際に残業をしたにもかかわらず残業代がないと、従業員が不満を持つことになるため、日当でカバーするというケースもあります。この場合は、日当は残業代とはいえません。
出張による時間拘束の補填の場合
出張は、普段会社に出勤するときよりも通勤や移動時間が増えます。そのため、増加した拘束時間分を日当で補填する場合があります。出張先や支給目的、役職によっても金額は異なるでしょう。役職者の日当を4,000〜5,000円前後で設定し、役員はそれよりも多くし、一般社員はそれよりも少なくしている企業もあります。
日当の支払い金額 – 目安はある?
日当の支払い金額には目安はあるのでしょうか。所得税法の決まりや支給額の目安について解説します。
法律上の決まり – 所得税法
日当は、適正なルールで運用されていれば、所得税法上非課税の取り扱いとなります。 所得税法基本通達9-3では以下のように記載されています。
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
つまり、適正なバランスが保たれた基準となるように出張旅費に関する規定を整備し、通常必要とされる範囲内の支出として規定に沿った支払いを行います。同業種・同規模の企業と比べてその日当が高額ではなければ、日当は非課税になるのです。
支給額の目安
日当は、適正なルールで運用することが何よりも重要です。支給額の目安は、以下の点がポイントとなります。
- 通常必要とされると認められる範囲内の支出であること
- 同業種・同規模の企業と比べて日当が高額ではないこと
日当の金額は、出張先が日帰りか宿泊を伴うものか、出張先が国内か海外か、出張するのが一般社員か役職者・役員であるかによって異なります。産労総合研究所では、 国内・海外出張旅費に関する調査を実施しているので、支給額の目安として参考にするとよいでしょう。
参考:2023年度 国内・海外出張旅費に関する調査結果 | 産労総合研究所
日当と課税の関係
日当と課税の関係を簡単にまとめて見てみましょう。
基本的には課税対象にならない
先に説明したように、日当は通常必要と認められる範囲内で適正なルールで運用していれば、原則として非課税です。経費として認められるものであり、所得税の対象とはなりません。したがって、源泉徴収する必要もありません。
高額な日当は課税対象に
日当が基準に合致しない場合や高すぎる場合、税務署から否認されると給与所得として課税対象になります。否認された部分については所得税や住民税が従業員に課税されることになるため、注意しなければなりません。役員の場合には役員賞与となり、会社の経費に算入できないこともあります。
日当の消費税はどうなる?
出張先が国内で、出張のために支給した日当が通常必要な支出と認められる金額の範囲内ならば、課税仕入れの対象になります。課税仕入れの対象となる金額については、仕入税額控除が可能です。
勘定項目は?消費税や法人税の経費など
日当は旅費交通費の勘定科目で計上し、経費として落とすことが可能です。法人であれば経費に算入することで、法人税の節税につながります。ただし、個人事業主の場合、従業員に対して支払う日当は経費として計上できますが、本人の出張手当を経費に計上することはできません。
消費税は商品購入やサービスなどの消費を対象に課税するものであり、日当とは性質の異なるものであるため課税対象外です。
日当の導入方法
日当を支払うルールがない企業の場合、日当を支給することで節税につながります。そのためには、就業規則に出張旅費規程などを設け、適正なルールで運用することが重要です。日当を導入する手順を見ていきましょう。
1.日当の目的を決める
出張をすることがある企業の場合には、日当を設定する目的や必要性を考え、出張する際の手続き、基準などを、出張旅費規程を作成する前に決めておく必要があります。
2.日当の適用範囲を決める
日当を就業規則の出張旅費規程などで定める際には、その適用範囲を決める必要があります。対象は役員と従業員とするのが一般的です。役員と正社員のみに支給するのか、パートやアルバイトが出張するケースもあるのかを、よく検討してから導入するのがよいでしょう。
3.出張の定義を決める
出張の定義を定めることも必要です。どれくらいの移動距離なら出張といえるかは、特段決まりはありません。そのため、「勤務地から出張先までの距離が片道200km以上」などと、出張の定義として妥当な距離や地域の範囲を企業独自に決めておく必要があります。出張の定義を決める際、日帰りとする距離や地域の範囲、宿泊を認める距離や地域の範囲を決めておくことも大切です。
4.費用項目を設ける
出張費用の項目を設ける必要があります。出張費といっても、「交通費」「宿泊代」「食事代」「日当」などと項目を就業規則の出張旅費規程などに明確に定めておかなければなりません。その際、交通費や宿泊費を含めた費用全体を「交通費や宿泊費を含む日当10,000円」などと定めることも、交通費や宿泊代は実費精算し、食事代や雑費を「日当3,000円」などと定めることも可能です。
5.就業規則を作成する
会社のルールは就業規則に定める必要があります。たとえば社員に出張を命じるのであれば、就業規則に「業務上必要な場合には、会社は従業員に出張を命じることができる」などといった業務として命じる根拠がなければなりません。日当の支払いも同じです。臨時の賃金に関する事項や従業員のすべてに適用される事項を定める場合には、就業規則に必ず定めなければなりません。
6.出張旅費規程を作成する
就業規則に委任規定を設ければ、出張旅費規程を就業規則とは別規程で定めることも可能です。出張旅費規程も就業規則の一部です。就業規則の本則に出張旅費に関するルールを規定することも、別規程として本則から独立させて設けることも可能です。
日当の目的、適用範囲、出張の定義、費用項目、精算方法などのほかに、領収書や清算書の提出、出張報告書の作成などについてもルールを定めておく必要があります。出張旅費に関するルールは多岐に及ぶため、別規程で定めておくと便利です。
日当の支給における注意点
日当を支給するルールを設けることは、従業員だけではなく企業にもメリットをもたらします。しかし、日当を設ける場合には、就業規則にルールが定められていなければなりません。ここでは、正社員以外の従業員を対象とする場合の注意点について解説します。
パートやアルバイトも対象?
日当を支給する対象には、パートやアルバイトも含めることが可能です。
ただし、多くの企業で、正社員に適用される就業規則と非正規社員の就業規則を分けて作成しています。パートやアルバイトなどの従業員にも日当を支給する場合には、パートやアルバイトに適用される就業規則にも出張旅費に関する規定を定めることを忘れないように注意しましょう。
派遣社員や契約社員も対象?
契約社員についても、パートやアルバイトと同じように、契約社員に適用される就業規則にルールを設ければ、日当支給の対象とすることが可能です。
しかし、派遣社員は自社の従業員ではないため、主張時に日当が支給されるかは、派遣社員と派遣元企業との労働条件によって決まります。
派遣社員を出張させることができるかどうかは、派遣元企業に確認して調整する必要があります。派遣社員と派遣企業との雇用契約や派遣元企業の就業規則の内容によっては、出張させることができないケースもあるため注意が必要です。
日当は適正なルールで運用することが重要
日当は、出張先で従業員が立て替えた経費や、生活費、雑費などの負担分を補填するためのものです。出張旅費に関する規定を整備し、適切な金額で支給すれば所得税の対象には含まれず非課税になります。また、支払った費用は経費として計上できるため、企業としても節税につながります。
日当を正しく理解して支給することは、企業にも従業員個人にもメリットをもたらします。そのためには、就業規則に出張旅費規程などを設け、適正なルールで運用することがなによりも大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
福島県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
福島県は農業や製造業が盛んで、特に米や自動車部品の生産が有名です。また、再生可能エネルギーや観光業も急速に発展しており、多様なビジネスが展開されています。こうした多岐にわたる業種では、給与計算の正確性と効率化が企業運営において重要ですが、中…
詳しくみる有給休暇の基準日を統一することはできる?方法や注意点を解説
有給休暇の基準日を、全社で統一することは可能です。ただし、運用の仕方を間違えると、従業員に不利益が生じたり、法律違反に該当したりする可能性があります。 2019年4月1日に労働基準法が改正されて以降、有給休暇の管理方法についてお困りの人事労…
詳しくみる管理職だと残業代は出ない?管理監督者との違いから解説!
管理職などの役職に就くと、残業代を受け取れない場合があります。一般に「管理職は残業代が出ない」と言われますが、労働基準法に則ると「管理監督者は残業代が出ない」と表現するのが正確です。この記事では管理職と管理監督者の違いと定義、36協定との関…
詳しくみる源泉所得税が0円の所得税徴収高計算書の書き方は?税務署への提出は必要か
所得税徴収高計算書を0円で提出する場合、本税の欄に「0」と記入するだけで対応可能です。本記事では所得税徴収高計算書の書き方の中でも、源泉所得税の納付額が0円になる場合とその具体例、書き間違えた場合の訂正方法、0円でも提出する理由も解説します…
詳しくみる給与査定表とは?作り方や注意点を解説
給与査定表は、従業員の給与を決定する際に必要な情報を整理し、評価基準に基づいて公平かつ透明性のある査定を行うために必要なものです。 本記事では、給与査定表の基本的な知識から作成方法、注意点までを詳しく解説します。 そもそも給与査定とは 給与…
詳しくみる香川県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
香川県でビジネスを展開する企業にとって、給与計算は従業員の満足度と企業の信頼性を左右する重要な業務です。しかし、税務や社会保険の複雑な手続きを自社で管理するのは大きな負担となります。 この記事では、香川地域における給与計算代行サービスの料金…
詳しくみる