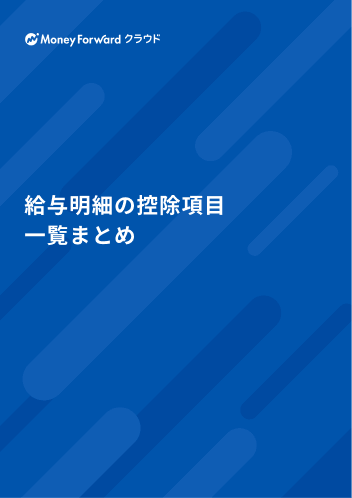- 更新日 : 2025年5月27日
給与明細の控除項目とは?計算から記載方法まで解説
給与明細にはさまざまな支給項目や控除項目があります。支給項目は、雇用契約書や労働条件通知書に記載の賃金や手当ですので分かりやすいと思います。しかし、控除項目は、「どうしてこの金額が控除されるのか?」と疑問を持つことがあるのではないでしょうか?
今回は、給与明細の控除項目の概要と計算方法、注意点について解説します。
目次
給与明細の控除項目とは
給与明細に控除項目として主に表示される項目には、「法定控除」と「法定外控除」があります。
法定控除は、給与から控除することが法律で定められている項目で、法定外控除は、会社と労働者の代表との間で「労使協定」という協定を締結することによって初めて給与から控除できるようになる控除項目です。
法定控除は、以下のものが該当します。
法定外控除は、以下のものが該当します。
- 社宅・寮費
- 財形貯蓄
- 社内預金
- 労働組合費
など
法定控除以外の控除項目は、会社によって控除項目の名称や内容が異なります。
給与明細に記載される控除額の計算方法
ここからは、給与明細の控除項目毎に、控除額の計算方法について見ていきましょう。
健康保険料の計算方法
健康保険は、従業員やその家族が病気やケガにより医療機関で治療を受ける際の医療費の負担軽減をしてくれる保険です。
健康保険の被保険者は、それぞれの被保険者期間の月毎に健康保険料を納付します。
健康保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額、または、標準賞与額に健康保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担します。
【給与の場合】
【賞与の場合】
(計算例)
会社員Aさんの場合
- 東京都内の会社に勤務
- 年齢45歳
- 全国健康保険協会の健康保険加入
- 給与額:417,500円、賞与額:417,500円
給与額から標準報酬月額は410千円に、賞与額から標準賞与額は417千円になります。
よって、以下の通りとなります。
=410,000円×9.84%(東京都の健康保険料率)÷2
=20,172円
=417,000円×9.84%(東京都の健康保険料率)÷2
=20,516.40円
≒20,516円(50銭以下の場合は切り捨てによる)
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険は、働くことや収入を得ることが困難になった場合に、従業員やその家族の生活を守ってくれる老齢年金、障害年金、遺族年金などの制度がある保険です。
被保険者はそれぞれの被保険者期間の月毎に厚生年金保険料を納付します。
厚生年金保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額、または、標準賞与額に厚生年金保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担します。
【給与の場合】
【賞与の場合】
(計算例)
会社員Aさんの場合
- 東京都内の会社に勤務
- 年齢45歳
- 全国健康保険協会の健康保険加入
- 給与額:417,500円、賞与額:417,500円
給与額から標準報酬月額は410千円に、賞与額から標準賞与額は417千円になります。
よって、以下の通りとなります。
=410,000円×18.3%÷2
=37,515円
=417,000円×18.3%÷2
=38,155.50円
≒38,155円(50銭以下の場合は切り捨てによる)
雇用保険料の計算方法
雇用保険は従業員の失業、育児休業、教育訓練を受ける際など、雇用の安定、就職の促進のための失業等給付や教育訓練給付などの給付を受けることができます。
雇用保険料の額は、下記の計算式で求められます。
雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。また、労働者負担分と事業主負担分の雇用保険料率も異なりますので注意が必要です。詳細は下記の雇用保険料率表を参考にして下さい。

(計算例)
会社員Aさんの場合
- 東京都内の会社(小売業)に勤務
- 年齢45歳
- 賃金総額:417,500円
事業の種類が小売業の場合、雇用保険料率は、労働者負担:3/1,000、事業主負担:6/1,000になります。
よって、以下の通りとなります。
=417,500円×3/1,000
=1,252.50円
≒1,252円(50銭以下の場合は切り捨てによる)
=417,500円×6/1,000
=2,505円
介護保険料の計算方法
介護保険は、介護が必要な人に、必要な費用を給付してくれる保険です。
従業員は40歳から介護保険の被保険者になり介護保険料を支払います。
介護保険料の額は、各被保険者の標準報酬月額、または、標準賞与額に介護保険料率を乗じた金額を事業主と被保険者が半額ずつ負担します。
【給与の場合】
【賞与の場合】
(計算例)
会社員Aさんの場合
- 東京都内の会社に勤務
- 年齢45歳
- 全国健康保険協会の健康保険加入
- 給与額:417,500円、賞与額:417,500円
給与額から標準報酬月額は410千円に、賞与額から標準賞与額は417千円になります。
よって、以下の通りとなります。
=410,000円×1.8%÷2
=3,690円
=417,000円×1.8%÷2
=3,753円
所得税の計算方法
所得税は、給与から所得控除を差し引いた金額に一定の税率を乗じて算出される税金のことです。
所得税は各従業員が納付する税金ですが、会社が給与から控除する形で代わりに納付手続きを行っています。
所得税の額は次のように求めます。
- 給与の総支給額から通勤手当などの非課税の手当を差し引きます。
- 1.で求めた金額から社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)を差し引きます。
- この社会保険料等控除後の給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」で求めます。その際に、扶養控除等申告書の提出がある従業員は「甲欄」の該当扶養親族の人数の欄で、提出がない従業員は「乙欄」で税額を参照することになります。
(計算例)
給与の総支給額が417,500円、総支給額のうち通勤手当が16,000円、社会保険料合計が62,629円、扶養人数が1人の甲欄適用者の場合
- 総支給額-通勤手当=417,500円-16,000円=401,500円
- 1.の金額-社会保険料=401,500円-62,629円=338,871円
- 社会保険料当控除後の給与等の金額が338,871円、給与扶養親族の人数が1人なので、「給与所得の源泉徴収税額表」を参照すると、所得税は8,370円になります。

出典:令和3年分 源泉徴収税額表|国税庁
給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)|国税庁から加工して作成
住民税の計算方法
住民税は、各従業員の前年度の所得を基に計算され、居住地の市(区)役所などから通知されます。会社は通知を受けた住民税額を各従業員の給与から控除します。
ですので、会社は住民税の計算を行う必要はありません。
(計算例)
会社員Aさんの場合
- 東京都千代田区に居住
- 千代田区からの通知額:13,000円/月
よって、住民税=13,000円になります。
その他控除の計算方法
会社により、社宅・寮費、財形貯蓄、社内預金、労働組合費など、法定控除以外の控除については、労使協定を締結することによって初めて給与控除が可能になります。
これらの項目は、会社によって協定内容が異なりますので確認が必要です。
- 社宅・寮費・・・会社から説明された家賃、通信費、光熱費などを支払います。
- 財形貯蓄 ・・・銀行などと契約を取り交わした金額を毎月控除します。
- 社内預金 ・・・会社との取り決めの中で、毎月の預金額を申請して給与から控除します。
- 労働組合費・・・労働組合が決めた組合費を給与から控除します。
給与明細の控除における注意点
給与計算での控除に関しては、給与明細に見慣れない「マイナス控除額」が発生することがあります。
ここからは、マイナス控除がどのような場合に発生するのかについて見ていきます。
マイナス控除が発生した場合
給与明細の控除項目は通常支給額から差し引きますが、年末調整で還付金が発生したり、給与計算を間違えたことによる返金があったりした場合にマイナス控除が発生することがあります。
年末調整では、計算結果により所得税が還付されることが多くあります。その際、例えばその他の控除項目の合計額よりも還付額が大きいと総控除額がマイナスになり、従業員に還付金が支給されることになります。
給与計算を間違えたことによる影響に関しては、法律上の問題もありますので次で説明します。
給与明細にマイナス控除が発生した場合、人事労務担当者は、その原因を確認して従業員からの問い合わせに対して説明できるようにしておく必要があります。
給与明細の計算を間違ってしまった場合
給与計算を間違えてしまい、例えば給与未払いになってしまった場合、それが給与計算ミスであったとしても労働基準法違反になります。
通常は、発覚した後に追加で給与の支払いを行いますが、当該従業員への謝罪と十分な説明を行ったうえで、速やかに支払う手続きを進めるように準備しましょう。
その際に、社会保険料や所得税など、発覚した時期によっては行政機関への届出事務等が発生する場合がありますので、注意して再計算手続きを行います。
逆に、給与が過払いになった場合は、それが給与計算上のミスであっても会社には返還請求する権利がありますので、従業員に過払い分の返還を求めることができます。その場合も従業員には十分な説明を行って理解を得てください。
給与明細の控除項目について正しく理解しておこう!
給与明細に表示されている控除項目について、どのような項目があり、その各項目の計算方法について確認してきました。
また、控除項目の給与明細への記載方法や給与明細にマイナス控除が出る場合、給与計算を間違えてしまった場合の対応についても見てきました。
給与は従業員の生活に直結するお金になります。人事労務担当者として普段から給与計算に誤りがないよう細心の注意をはらい、また、従業員に配布した給与明細に関する質問には迅速に、また正確に回答できるように普段から正しく理解しておきましょう。
よくある質問
給与明細の控除項目には何がありますか?
給与明細に記載される控除項目には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税、給与から控除することがある項目に、生命保険料、損害保険料、財形貯蓄、社内預金等があります。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナス控除が発生した場合の対応について教えてください。
マイナス控除が年末調整の還付金が原因であるときは問題ありません。給与計算の誤りによる返金でのマイナス控除の場合は、返金までの過程で従業員への十分の説明と謝罪、早急な差額精算の手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定額減税で手取りが増える?いくら増えるかを解説
近年物価の上昇が続いており、国民の生活は厳しいものとなっています。賃上げを行う企業も多く見られますが、それでも物価の上昇は大きな負担となっており、対策が必要です。 当記事では、物価上昇に伴い増加した国民負担の軽減を目的とする定額減税について…
詳しくみる源泉徴収の対象期間とは?源泉徴収票の発行・保管期間を解説
源泉徴収とは、1年に支払われた給与の額や、控除額、保険料などが記載されているものです。源泉徴収の対象期間とは、1月から12月までの12ヶ月のことを指し、年度の扱い(4月から3月)ではないことに注意しましょう。また、源泉徴収票は、転職する際に…
詳しくみる実質賃金とは?名目賃金との違いやマイナスになる原因をわかりやすく解説
実質賃金とは、単なる給与額面ではなく、労働者の購買力を正確に示す重要な指標です。近年、日本では実質賃金の低下が問題となっており、多くの企業や労働者に影響を与えています。 本記事では、実質賃金の概念や名目賃金との違い、マイナスになる原因につい…
詳しくみる定額減税の給与計算やシミュレーション例をわかりやすく解説
政府の経済政策の一環として、定額減税が導入されることになりました。この制度は、従業員の税負担を軽減し、経済活性化を図るための取り組みです。給与計算の現場では、この定額減税の適用に際し、さまざまな対応が求められることになります。 本稿では、定…
詳しくみる愛媛県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
愛媛県内で企業活動を行う際、給与計算の正確性と効率性は成功の鍵を握ります。しかし、日々の業務に追われる中で給与管理に十分な時間を割くのは難しいものです。この記事では、愛媛における給与計算代行サービスの料金相場を詳しく解説し、コストを抑えつつ…
詳しくみる退職金制度はどうやってつくる・廃止するのか 制度比較や注意点を詳細解説
昨今の企業では、退職金の制度は廃止される、または設置されない傾向にあります。 かつての終身雇用が当たり前だった世の中では、退職金は給与の一部として、後払いされるものという認識がありましたが、最近では認識が変わってきています。 一部では、労働…
詳しくみる