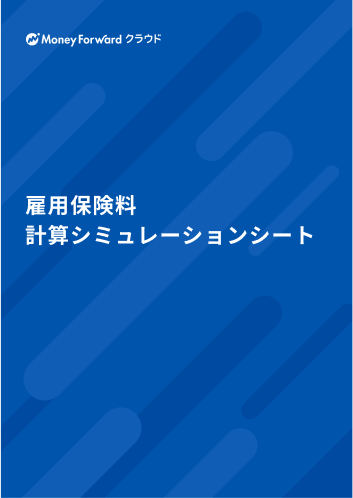- 更新日 : 2025年4月24日
雇用保険の計算方法は?賃金月額・交通費・パートの場合について
雇用保険とは、失業した従業員への給付や、転職者の雇い入れ従業員のスキルアップを行う事業所(会社)の支援を行うための保険です。支払う賃金総額に応じて雇用保険料は計算されますが、雇用保険料率は事業の種類ごとに異なっているなど、いくつか注意点があります。
また、賃金総額に手当が含まれている場合は、その内容によって雇用保険料の計算から除く場合もあります。
当記事では、雇用保険の計算方法について、具体例をあげて説明します。
目次
雇用保険とは
雇用保険とは、失業した方の生活保障などのための保険です。それ以外では、教育訓練や育児休業中の方への給付なども、この雇用保険によってなされます。
従業員を一人でも雇い入れた事業所は、雇用保険の適用事業です。また適用事業の従業員は、以下の条件を満たす場合、雇用保険に加入する(被保険者になる)ことが法律で義務付けられています。
| 雇用保険の加入条件 |
|---|
|
なお、上記の要件を満たしていても、経営者と同居する親族や、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される季節労働者などは、例外として雇用保険に加入となりません。
\雇用保険料の計算をラクに/
雇用保険料とは
雇用保険料とは、雇用保険の掛け金のことです。前述の雇用保険加入者(被保険者)の賃金が計算対象です。
雇用保険料の支払いは事業所と従業員の双方の負担となります。なお、雇用保険料率は事業所と従業員で別々に定められており、従業員が負担する金額よりも、事業所が支払う金額のほうが高額です。
また、従業員が雇用保険料を支払うときは、原則として支払われる給料の中からあらかじめ控除(天引き)する形で徴収されます。
雇用保険の支払い者とは
雇用保険料の支払い者は、前述の通り事業所と労働者です。事業所は雇用保険料を多く支払うことになっていますが、これは雇用保険二事業に関する負担が上乗せされるためです。
雇用保険二事業とは、名前から分かる通り「雇用安定事業」と「能力開発事業」によって構成されています。つまり、従業員のスキルアップや転職者の受け入れ支援等についての事業ですが、これらの給付は従業員ではなく事業所向けのものです。そのため、二事業に関わる負担は事業所が負います。
雇用保険料を給与から天引きする者について
前述の通り、適用事業に雇用される従業員は、条件に該当すれば雇用保険加入が義務となっており、その保険料は給与から天引きされます。
一方、役員については事業所との雇用契約ではなく委任契約となるため、雇用保険に加入はできず(被保険者となれず)、雇用保険料は天引きされません。ただし、兼務役員の場合は雇用保険に加入することが可能です。
兼務役員とは、役員であると同時に労働者性が強く従業員としての身分を有する者のことです。労働者性が強く兼務役員に該当するかは、管轄のハローワークにより「賃金と役員報酬の比率」など複数の要素から総合的に判断されます。
65歳以上の従業員について
2017年の雇用保険法の改正により、65歳以上の従業員についても「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」場合は、雇用保険に加入することが義務付けられました(保険料徴収は2020年4月から開始)。要件を満たしている場合、基本的には勤め続ける限りは雇用保険料を給与する必要があります。
なお、65歳以上の従業員が退職し失業状態となった場合は、通常の失業給付(基本手当)ではなく、高年齢求職者給付金を受給することになります。
日雇い労働者について
日雇い労働者とは、文字通り日毎に雇用される労働者(従業員)のことです。前述した雇用保険に加入義務のない方の中でも、以下のいずれかの要件を満たした状態で適用事業所である職場に勤務すると、その従業員は日雇労働被保険者という区分で雇用保険に加入することになります。
・日々雇用される者である
・30日以内の期間を定めて雇用される者である
なお、日雇労働被保険者に対しては直接給与からの雇用保険料天引きを行いません。給与を支払う都度、日雇労働被保険者手帳という手帳に雇用保険印紙を事業所で貼り付けます(雇用保険印紙はあらかじめ購入する必要があります)。
事業の種別により異なる雇用保険料率
雇用保険料の料率は事業の種別により異なります。具体的には、次の3つの区分の内どれに当てはまるかで料率が変化します。
| 3つの区分 |
|---|
|
詳しくは後述しますが、一般の事業は他の2つの事業に比べて保険料率が低く設定されています。事業の構造の違いが理由です。
農林水産業、清酒製造業は季節によって仕事量が増減することが一般的です。そのため、季節によっては失業者が増大することも多く、その分、給付を受ける失業者の割合が多い傾向があります。
また、建設業も1つのプロジェクトごと従業員を雇い入れているケースが多く、プロジェクトが完了すると失業者が発生します。加えて、建設の事業には助成金の種類が多いことも特徴です。
これらの背景から、一般の事業以外の2つの事業では、雇用保険料率を上げることで公平性を保っています。
雇用保険料の計算方法と2024年の雇用保険料率
雇用保険料は、雇用保険料率×賃金総額で求められます。
「賃金総額」とは毎月貰う賃金の総額を指し、通勤手当や深夜手当などの各種手当や賞与も含まれます。
雇用保険料の計算では、厚生年金保険や健康保険の計算に用いる「標準報酬月額」とは異なり、「賃金総額」であるため注意が必要です。なお、雇用保険料率を決定する際は、以下の雇用保険料率表を用います。
2024年4月からの雇用保険料率は、2023年度の雇用保険料率から据え置きとなっています。なお、雇用保険料率は2023年に引き上げとなりましたが、背景にあるのは、コロナ禍を契機とする助成金支出の増大などです。
\法令に準拠した雇用保険料計算/
雇用保険料は賞与からも天引きする
前述の通り、毎月支払われる給与だけではなく、賞与(ボーナス)も雇用保険料徴収の対象となります。計算方法は基本的には給与から天引きするときと同じです。
・雇用保険料率 × 賞与総額
なお、退職後に賞与が支払われた場合は、その賞与からも雇用保険料を天引きする必要があるため注意しましょう。
労働者の負担分の計算方法
はじめに、雇用保険料率表で自社の保険料率を調べます。「労働者負担」欄の料率から確認可能です。「該当する事業の種類」の「労働者負担」欄を確認し、保険料率を調べます。
次に、労働者の賃金総額に上記で確認した保険料率をかけて雇用保険料を算出しましょう。このときに1円未満の端数が生じた場合は、50銭以下であればを切り捨てし、50銭を超える金額であればを切り上げにします。
賃金総額には通勤手当などの各種手当を含めて計算しますが、手当の性質によっては賃金総額に含めない(雇用保険料の計算対象とならない)ものもあるため、注意が必要です。以下で、例を挙げていきますのでご参照ください。
| <賃金総額に含める手当> |
|---|
|
| <賃金総額に含めない手当> |
|---|
|
なお、上記の区分はあくまで見本であり、名称に関わらず労働の対償として支払われるか否かで賃金総額に含めるかが決まります。判断に迷った場合は、管轄のハローワークに相談してみましょう。
事業主の負担分の計算方法
基本的には労働者の負担分の計算方法と同様です。
最初に、雇用保険料率表で自社が該当する事業の種類を確認し、事業主負担分の保険料率を確認します。その上で、労働者の賃金総額に保険料率をかけて雇用保険料を算出します。手当等の扱いも同様です。
端数が生じた場合の計算方法
雇用保険料の計算を行った際は、1円未満の端数が生じる場合があります。このとき、従業員の給与から天引きすべき金額については、厚生労働省の案内に従い、以下のルールで処理を行います。
- 1円未満の端数が50銭以下の金額であれば切り捨て処理とする
- 1円未満の端数が50銭を超える金額であれば切り上げとする
例えば、一般の事業に勤務する従業員の給料が、200,333円(賃金総額)であったとしましょう。この場合、雇用保険料率をかけた金額は(1,201.998円)です。1円未満の端数は998銭で50銭を超えるため、切り上げ処理を行い給与から天引きする雇用保険料は1,202円となります。
雇用保険の計算に「交通費」は含める?
雇用保険法における「賃金」の定義には、出社のために必要な交通費(通勤手当)も含まれています。つまり、企業が従業員に毎月支払う交通費は、賃金の一部とみなされ、雇用保険の保険料計算に利用されます。
具体的には、社会保険(健康保険や厚生年金保険)の保険料を計算する際、基本給に加えて通勤手当や家族手当などの固定的な給付も考慮されます。これらの給付は「標準報酬月額」を定める際の計算基礎になり、この月額に対して各種保険料率が適用されて保険料が算出されます。
労働保険(労災保険と雇用保険)においても同様で、通勤手当を含む総賃金に保険料率を掛け合わせて、必要な保険料を計算します。したがって、雇用保険を適切に管理するためには、交通費を賃金の一部として適正に扱い、保険料の計算に含める必要があります。
雇用保険の計算方法の具体例
ここで、上記で説明した雇用保険の計算方法について、具体例を数例説明します。
一般の事業に従事した場合の計算方法
以下の前提で計算します。
| 前提 |
|---|
|
住宅手当と通勤定期代は労働の対償と見なされるため、賃金総額に含めます。実際の計算は以下の通りです。
<労働者負担分>
300,000(円)× 1000分の6 = 1,800(円)
<事業主負担分>
300,000(円)× 1000分の9.5 = 2,850(円)
建設業に従事した場合の計算方法
以下の前提で計算します。
| 前提 |
|---|
|
技能手当は労働の対償と見なされますが、出張旅費は見なされず賃金総額に含めません。そのため、賃金総額は380,000円として計算します。
<労働者負担分>
380,000(円)× 1000分の7 = 2,660(円)
<事業主負担分>
380,000(円)× 1000分の11.5 = 4,370(円)
農業に従事した場合の計算方法
以下の前提で計算します。
| 前提 |
|---|
|
この場合、結婚祝い金は労働の対償は見なされず、賃金総額に含めません。そのため、賃金総額は180,000円として計算します。
<労働者負担分>
180,000(円)× 1,000分の7 = 1,260(円)
<事業主負担分>
180,000(円)× 1,000分の10.5 = 1,890(円)
雇用保険の賃金月額と計算方法について
雇用保険被保険者資格取得届には多くの項目がありますが、賃金欄には、従業員の給与形態と月額賃金が記載されます。
給与形態(賃金支払いの態様)では、従業員に支払われる給与の形式を指定します。例えば、「月給制」は固定の月額給与を意味し、「時間給」は時給制を指します。フォームには「月給」「週給」「日給」「時間給」「その他」という選択肢があり、適切なものを選んで番号を記入します。
次に、賃金月額の記入では、従業員が受け取る1ヶ月の総賃金を記載します。これは月給制の場合はそのままですが、週給や日給の場合も月額換算して記入します。金額は1,000円単位での記入が求められ、例として23万7,000円の場合は「237」と記入します。
計算方法(月給/日給/時給)
雇用保険被保険者資格取得届での賃金月額計算は、月給制、日給制、時給制によって異なる方法で行います。ここではそれぞれの計算方法を分かりやすく解説します。
月給制の場合
基本給と各種手当を合計します。例えば、基本給が21万円、通勤手当が5,000円、住宅手当が2万円の場合、合計は23万5,000円になります。
この金額を賃金月額として「1−235」と記入します(「1」は月給制を示す)。
日給制の場合
日給を所定労働日数で乗じて、手当を加算します。
例えば、日給が10,00円、所定労働日数が21日、通勤手当と住宅手当がそれぞれ1.2万円の場合、計算は、以下の通りです。
- 10,000円×21日=210,000円
- 210,000円+24,000円=234,000円
これを「3−234」と記入します(「3」は日給制を示す)。
時給制の場合
時給に1か月の総労働時間を乗じて、手当を足します。
時給1,200円で月100時間の労働時間、通勤手当が5,000円の場合、計算は、以下の通りです。
- 1,200円×100時間=120,000円
- 120,000円+5,000円=125,000円
「4−125」と記入します(「4」は時給制を示す)。
パートの雇用保険の計算方法について
前述の通り、雇用保険の加入条件は以下の2つを満たすことです。
| 雇用保険の加入条件 |
|---|
|
この条件を満たせば、原則パートであっても被保険者となります。
時給制のパートの場合、先ほど紹介したように、時給と月の労働時間をかけた金額に、各種手当の金額をプラスして賃金を計算します。
その後、求めた賃金の総額に対して、雇用保険料率をかけて、雇用保険料を算出できます。
雇用保険料を抑える方法について
今まで見てきたように、雇用保険料は事業主負担があり、その料率も労働者負担より大きい点が特徴です。雇用保険料の負担を抑えたい場合は、雇用保険の加入義務が発生しない従業員を増やすことがあげられます。
例えばアルバイトの従業員を雇用する場合は、1週間の所定労働時間を20時間未満とすることで、雇用保険の加入義務を発生させないことが可能です。また、雇用契約ではなく業務委託等で働いてもらう場合も雇用保険の加入義務は生じないため、雇用保険料の抑制には繋がります。
ただし、上記はいずれも雇用保険料にのみ着目した方法です。対策を考える際は、その他の費用や優秀な人材確保など、総合的に判断しましょう。
今回の記事では、雇用保険の計算方法についてまとめました。事業の種類や、賃金総額に含めるべき手当の判別など、意外と多くのことに注意が必要です。その他には、雇用保険料率が変更となる場合には事前に把握しておく必要があります。計算方法自体は比較的シンプルですが、定期的な点検等を通じて、正しい計算を心がけましょう。
よくある質問
雇用保険の支払い者は誰ですか?
事業主と労働者の両者です。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険料はどのように求めますか?
労働者の賃金総額に雇用保険料率をかけて求めます。詳しくはこちらをご覧ください。
雇用保険料率はどこで調べられますか?
厚生労働省が公表している雇用保険料率表から求めます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年金手帳とは?廃止済み! 厚生年金と国民年金で変わること
2022年3月まで、厚生年金や国民年金に加入すると「年金手帳」が交付されていました。 厚生年金手帳・国民年金手帳のような区別はなく、どちらも共通の手帳です。年金関連情報の管理に必ず用いられていましたが、4月に廃止されて新規交付をされなくなり…
詳しくみる健康保険組合とは
日本で健康保険と呼ばれているのは、健康保険法に基づく雇用者を対象とした医療保険です。この被用者医療保険事業を国に代わって行っているのが、健康保険組合です。 つまり、健康保険組合は被用者医療保険事業である健康保険を代理で行っているひとつの組織…
詳しくみる外国人の厚生年金加入について – 脱退一時金などの制度を解説
外国人であっても、日本に居住していて20歳以上・60歳未満であれば厚生年金には強制加入が必要です。要件に該当する場合には、「脱退一時金」というお金を請求することが可能です。 この記事では、外国人の厚生年金の加入義務や、受給可能な年金の種類、…
詳しくみる医療保険とは?社会保険との違いはある?
「医療保険」や「社会保険」という言葉をよく耳にしますが、その違いについて意識して考えたことがない方は多いのではないでしょうか。 医療保険は保険制度の名称ですが、社会保険は医療保険を含めた公的保険制度の総称です。ここでは、医療保険の基本を解説…
詳しくみる厚生年金の住所変更 – 手続きについて解説!
厚生年金において、引っ越しをした際の住所変更手続きや結婚などによる氏名変更手続きは必要なのでしょうか。従来は住所変更届・氏名変更届を提出する必要がありましたが、マイナンバー制度の導入に伴い、自分での変更手続きは原則不要です。この記事では、厚…
詳しくみる退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介
退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退職者の算定基礎届について解説します。基本的な記入例や対象者別…
詳しくみる