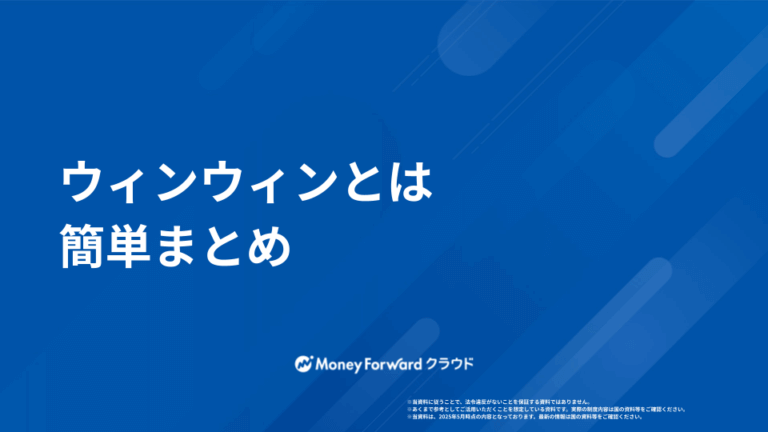- 更新日 : 2025年6月23日
ウィンウィンの言い換えは?意味や例文、ビジネスで良好な関係を築く方法
会社は営利を目的としているため、ビジネスにおける自社の利益追求は、ごく自然なことです。しかし、自社の利益のみを追求していては、取引相手が不満を抱き、良好な関係を構築できません。
当記事では、取引相手と良好な関係を構築するために重要なウィンウィンについて解説します。使い方や例文も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
ウィンウィンとは?
「ウィンウィン」とは、自分と相手の双方が利益を得ることが可能な状態を指す言葉です。主にビジネス上の取引や契約における当事者の関係性を指して使われます。「勝つ」を意味する英単語である「Win」を重ねることで、自分と相手の双方が勝つ、つまり互いに利益があることを表しています。
ウィンウィンの関係
自分のみや相手のみといった当事者一方のみが利益を上げるのではなく、当事者双方が利益を上げ得る関係性は、「ウィンウィンの関係」と呼ばれます。自社の利益のみを追求するのではなく、ウィンウィンの関係を目指した取引であれば、相手も条件交渉に臨みやすくなるでしょう。
ウィンウィンの言い換え
ウィンウィンは、お互いが利益を上げることや、お互いに損がないことを意味しています。このような意味を持つ言葉は多く存在するため、例文とともに紹介します。
相互利益
「相互利益」とは、お互いに利益があることを意味する言葉です。意味として、ほぼ異なることがないため、ウィンウィンの言い換えが必要な場合に良く使用されます。
相互利益は、以下のように使用されます。
「今回は、自社と取引先双方にとって、相互利益のある契約が締結できた」
三方良し
「三方良し」とは、商売において売り手と買い手、さらに世間が満足するという意味を表す言葉です。商人としての心得を表した言葉であり、売り手と買い手の満足は当然、世間(社会)に貢献することが商売において大切であると説いています。自分の利益だけを重視しないという点において、ウィンウィンと近しい関係にある言葉です。
三方良しの例文は、以下の通りです。
「今回のプロジェクトが成功すれば、地域貢献も果たせるため、まさに三方良しだ」
持ちつ持たれつ
「持ちつ持たれつ」とは、お互いに助け合うことを意味します。自分が苦しいときに相手から助けられることもあれば、逆に苦境の相手を助ける場合もあるでしょう。一方的な利益供与ではなく、お互いが助け合う関係であるため、ウィンウィンに近い言葉といえます。
持ちつ持たれつは、以下のように使用されます。
「取引先とは、お互いに融通を効かせた持ちつ持たれつの関係が構築されている」
共存共栄
「共存共栄」とは、ふたつ以上のものが相対立することなく、助け合い、発展していくことを意味します。共存共栄の関係性であれば、仮に利害が相反していたとしても、手を取り合って助け合うことで、ともに成長を続けられます。自分だけでなく、相手の成長や発展にもつながるという点において、ウィンウィンの意味にも近く、言い換えとして使用可能です。
共存共栄の例文は、以下のようになります。
「縮小傾向にある市場で生き残るためには、業界内の対立を止め、共存共栄の関係を築かなければならない」
ギブアンドテイク
「ギブアンドテイク」とは、何かを得るためには、まず自分から相手に与えなければならないことを意味しています。英語の成句である「give and take」から来ている言葉であり、お互いの譲歩や、協力を表します。一方的な利益の供与ではなく、相手からも利益を受け取るという点で、ウィンウィンに近い意味を持つ言葉です。
ギブアンドテイクの例文は、以下の通りです。
「取引相手とは、こちらが有利な条件で取引を続けているため、今後は自社が便宜を図る必要がある。ビジネスにはギブアンドテイクが重要だ」
ウィンウィンの使い方と例文
ウィンウィンは、ビジネスシーンや契約の場面で使われることが多いですが、日常生活で使われる場合もあります。シーンごとに使い方を見ていきましょう。
ビジネスシーン
ウィンウィンが最も使われるのは、ビジネスシーンにおいてです。得意分野の異なる会社同士がお互いの不得意分野を補う形で、共同プロジェクトを開始するような場面が想定できるでしょう。自社のみでは、進出不可能な分野であっても、共同の形を取れば、進出可能です。このような形のプロジェクトは、両社にとって新規市場での顧客獲得につながり、ウィンウィンの関係であるといえます。
また、ビジネスにおける取引関係を指しても、ウィンウィンは頻繁に使用されます。たとえば、商品を大量に購入することで、単価を下げるような場合です。この取引は、購入単価の下がる買い手にとってメリットがあるだけでなく、売り手にとっても在庫を抱えるリスクからの解放を意味します。このような取引は、売り手と買い手の双方にとって利益のあるウィンウィンの取引といえるでしょう。
以下にビジネスシーンにおける例文を紹介します。
「我が社の持つ販売ネットワークと、A社の高い技術力を合わせれば、新たな顧客の獲得が可能となる。このプロジェクトは、新規市場における両社の競争優位性構築につながるウィンウィンのものだ」
「我が社にA社の商品が納入されれば、コスト削減につながる。これは、我が社にとってのメリットとなるだけでなく、A社にとっても商品PRのチャンスとなり、ウィンウィンの取引といえるだろう」
契約
契約シーンにおいても、ウィンウィンはよく使用される言葉です。たとえば、契約において納品を早める代わりに、価格に上乗せするようなケースが想定できます。この契約は、一見高い価格で販売する側にのみ有利に見え、ウィンウィンと思えないかもしれません。しかし、早急な納品が必要であった場合には、渡りに船の提案となり、価格上昇によるデメリットを上回るメリットが享受できるでしょう。つまり、販売側は高価格で販売でき、購入側は早期の納品が可能となるウィンウィンの契約となります。
早期の納品を必要とする相手の足元を見るような契約であれば、ウィンウィンの関係とはいえません。あくまでも双方にとってメリットのある契約であることが必要です。また、長期の継続契約を前提として、価格を下げるような場合も双方にとって、メリットのあるウィンウィンの契約となります。このような契約であれば、一方は安く仕入れることが可能となり、もう一方は安定した販売先を確保することが可能となります。
契約におけるウィンウィンの使用例は、以下のようになります。
「交渉の結果、販売価格の引き上げを条件に、納品期日を早めることが決定した。これは、両者にとってメリットのあるウィンウィンの契約だ」
「単発の契約ではなく、継続という形であれば、価格を抑えることも可能と提案された。双方にとって、利益のあるウィンウィンの提案のため、一考の価値がある」
日常生活
ウィンウィンは、ビジネスシーンや契約締結の場だけでなく、日常生活でも使用される言葉です。お互いにとって利益となる状況は、取引を伴うビジネスシーンなどに限定されるものではないからです。
日常の買い物であっても、ウィンウィンな関係となる場合があります。たとえば、ある商品について、より安く購入できる店舗を知っていれば、相手に対して、その情報を提供する代わりに自分の分も商品を購入してきてもらうよう持ち掛けることも可能です。その結果、相手は安く商品を購入することが可能となり、自分は買い物に行く手間を省けるウィンウィンな関係になるといえるでしょう。また、複数人での施設利用による団体割引が適用されるような場合もあります。このような場合に、暇を持て余している相手を誘うことは、一方は安価での施設利用、もう一方は暇の解消と、双方にとってウィンウィンな関係になっているといえます。
日常生活におけるウィンウィンは、以下のように使用されます。
「Aから最安値の店舗を教えてもらった。代わりにAの分も買ってくることになったが、お互いにとってメリットのあるウィンウィンの情報提供だった」
「団体割引があるからとAからプールに誘われた。暇を持て余していたため、ウィンウィンの誘いだった」
ビジネスでウィンウィンが重要な理由
ビジネスにおいては、どうしても自社の利益を優先しがちです。しかし、自社の利益のみを押し通そうとする契約では、相手も首を縦に振らないでしょう。ある程度の譲歩を行い、ウィンウィンの関係となるような契約とすれば、相手も受け入れやすくなります。また、自社の利益のみを追求していては、相手からの譲歩や協力も望めません。ビジネスは自社のみで行うことはできないため、ウィンウィンの関係性構築が必要です。
取引を継続するためにもウィンウィンの関係性構築は重要です。相手側のみに利益があるような一方的な取引では、とても継続して行いたいとは思えないでしょう。また、ウィンウィンの関係性構築は、営業活動にも関わってきます。自社の利益のみではなく、相手の利益も考えたうえで、営業を行えば、信頼できる取引相手だと判断されることになるでしょう。信頼は営業をはじめとしたビジネス活動において、極めて重要な要素であるため、ウィンウィンを意識することが大切です。
ウィンウィンの関係を築くには?
相手とウィンウィンの関係を築くためには、譲歩や協力の姿勢を示すことが必要です。自社の利益を頑として譲らず、交渉の余地もないようであれば、とてもウィンウィンの関係を構築することは叶わないでしょう。ただし、あまりにも譲歩してしまうと、自社にとって利益のない取引となってしまいます。譲ることのできないラインを定めたうえで交渉を行いましょう。
ウィンウィンの関係を構築するためには、相手の視点で取引や契約を考えることも重要です。自分にとっては、ウィンウィンとなる提案を行ったつもりでも、相手にとっては足元を見られたと感じるような場合もあり得ます。自分の譲歩や協力が、相手のそれと釣り合っているかよく考えなくてはなりません。双方にとって満足できる利益が上がらないようであれば、ウィンウィンの関係とは呼べないことを忘れないようにしましょう。
ウィンウィンの反対語
ウィンウィンには、反対となる意味を持った言葉も多く存在します。これらの言葉を理解し、反面教師とすることによって、ウィンウィンな関係構築の助けとすることも可能です。
ゼロサム
「ゼロサム」とは、誰かが得をすれば誰かが損をする関係を表した言葉です。利益と損失の合計(サム)がゼロとなることから、このように呼ばれています。また、このような思考は「ゼロサム思考」と呼ばれます。
lose-win
「lose-win」は、自分が負け、相手が勝っている状態を指して使われます。値引きだけを迫られるような、自社にとって損しかない取引は、lose-winな取引であるといえるでしょう。
win-lose
「win-lose」は、lose-winとは逆に自分が勝ち、相手が負けている状態を指します。相手にのみ譲歩を迫るような取引は、ウィンウィンな取引とはならず、win-loseな取引となります。
no deal
「no deal」は、取引が不成立であることを意味する言葉です。ビジネスシーンでは、ウィンウィンな状態でなければ取引を行わない「win-win or no deal」として使用されることが多くなっています。
lose-lose
「lose-lose」とは、自分も相手も負けている状態を意味しています。ウィンウィンとは真逆であり、誰の利益にもなっていませんが、相手の妨害を意図してこのような状態となる場合もあります。
ビジネスではウィンウィンな関係構築を
会社は営利を目的として設立されているため、自社の利益追求を行うこと自体は問題ありません。しかし、ビジネスは自社のみで行うものではなく、必ず取引の相手方が存在します。取引相手のことを考慮せず、自社の利益のみを追求すれば、反発を招き、協力を得ることや取引を継続することは困難となるでしょう。
そのような事態を避けるためには、自社のみではなく、相手にとっても利益となるウィンウィンな関係の構築が必要です。当記事で紹介した事例などを参考として、良好な関係構築に努めてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
入社手続きの服装は?働き方や季節別の選び方、注意点などを解説
入社手続きは、企業の担当者や上司からの印象を左右する大切な場面です。この記事では、入社手続きの服装で迷う方へ、新卒・転職・パートなどの働き方や季節ごとの選び方をわかりやすくまとめました。人事担当者が押さえておくべきポイントも解説していますの…
詳しくみる労働者派遣法とは?改正の歴史や禁止事項、違反した場合の罰則などを解説!
労働者派遣法とは、派遣労働者を保護することなどを目的に定められた法律。 1986年の制定依頼、規制の緩和や強化など、当時の社会的背景に応じて改正が行われてきた。 守るべきルールも多く、違反すると罰則を受けるものもあるため、派遣事業を行う場合…
詳しくみるオンライン研修(Web研修)とは?開催方法・メリット・注意点やおすすめサービスを解説!
オンライン研修(Web研修)とは、インターネットを通じてパソコン、スマホ、タブレットなどがあればどこでも参加することができる研修のことです。オンライン研修は、オフラインでの研修と異なり研修会場が不要です。本記事では、オンライン研修の概要、開…
詳しくみる役員名簿とは?役員の範囲はどこまで?ひな形を基に書き方や注意点を解説
企業の経営陣を一覧にした役員名簿は、株主総会や取引先などのステークホルダーに対する公開など、さまざまな場面で必要となります。この記事では、役員名簿の概要や範囲、書き方のポイント、そして更新時の注意点について解説します。 役員名簿とは? まず…
詳しくみる男女雇用機会均等法とは?禁止事項や差別・違反の具体例、企業が行うべき対策
1985年に成立(翌1986年に施行)した男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等な取扱いや待遇等を規定した法律です。この法律では、性別を理由とする差別の禁止や、不利益取扱いの禁止等が定義されています。 本記事では、男女雇用機会均等法の…
詳しくみるパワハラ防止法とは?法改正の内容や対策法を解説!
パワハラ防止法の対策方法を検討する企業が増えています。2022年4月には法改正が行われ、中小企業もパワハラ防止法の対象となりました。パワハラ防止法に違反すると職場環境が悪化するだけでなく、企業名公表といった罰則を受けるリスクも高まります。そ…
詳しくみる