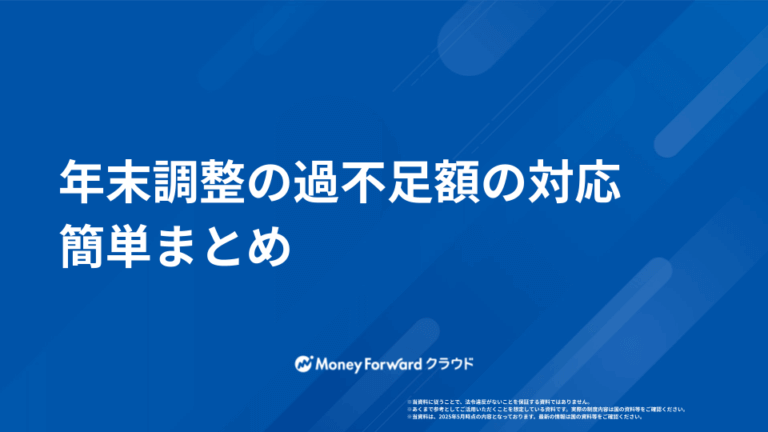- 更新日 : 2025年6月23日
過不足税額とは?確認手段と計算方法について解説
年末が近づいてくると、会社員・公務員の方はその年の給与所得に対して年末調整を行って1年間の税額の精算をしなければなりません。
今回は、年末調整において生じる「過不足税額」(還付額や徴収額)を従業員はどのように確認すればよいのか、また、会社が過不足税額を算出する方法や還付・徴収する手続きについて解説します。
目次
過不足税額とは?
毎年11月下旬から12月上旬にかけて、毎月の給与・賞与から源泉徴収された源泉徴収税の合計額と、本来納付すべき給与所得の年調年税額の過不足税額の調整をするために年末調整が行われます。
過不足税額とは、上記の源泉徴収税額の合計額と年調年税額を比較して出てきた超過金額、あるいは不足金額であると定義されています。
年末調整の結果、源泉徴収税を多く納付していた場合は過不足税額はマイナスになるので還付され、納付した税額が少なければプラスの金額になるので追加で源泉徴収税を徴収されるという意味です。
過不足税額はどうやって確認する?
過不足税額は簡単に言うと「1年間の給与・賞与から徴収された源泉所得税と、同じ1年間で実際に納付すべき本来の年税額の差額」になります。
過不足税額の確認方法としては、実際に納付すべき所得税額の計算方法を国税庁HPの「令和3年分 年末調整のしかた」の『Ⅲ 年末調整のしかた』を参照しながら計算し、1年間の給与・賞与の源泉所得税の合計額と比較するしかありません。
通常は会社で年末調整を行い、過不足額を調整してくれますので、給与明細等でその金額を見て確認することになります。
給与明細のマイナス表記を確認する
年末調整の結果で給与明細に過不足税額がマイナス表記される場合を確認していきましょう。
過不足税額がマイナス表記される原因として、まず、「給与・賞与に対して源泉徴収された税額が少ないケース」が考えられます。
最近の給与計算ソフトを使用している場合は、国税庁HP「令和3年分 源泉徴収税額表」の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」を利用しているので、それほど誤差が出ることはありません。ただし、支給する毎に算出している税額と年間の給与所得を基に算出している税額で計算の基になる金額が異なりますので、差額の発生も起こると考えられます。
他には、「年の途中で扶養家族が減ったケース」が考えられます。
よくあるのは、扶養の範囲内で働いていた配偶者の年収が103万円を超えてしまったために扶養から外れることになってしまい、配偶者控除が受けられなくなってしまったというケースです。
ほかにも、子供が大学卒業して扶養を外さないといけなかったのに外すのを忘れていた、などで差額が発生するケースもあります。
扶養家族の扶養状況が変わった際には、なるべく早く申し出を行ってもらい、正しい徴収税額の計算をすることが必要になります。
過不足税額の計算方法
過不足税額の計算方法ですが、まず、1年分の毎月の給与・賞与から徴収した徴収税額を合計します。
次に、1年分を合算した給与所得から年調年税額を計算します。
この2つの税額を比較して、徴収税額の合計額よりも年調年税額の方が多い場合は、その差額分だけ納める税額が多かったということになりますので、その差額を還付します。
逆に、徴収税額の合計額よりも年調年税額の方が少ない場合は、その差額分だけ納める税額が少なかったと言うことになりますので、その差額を追加で徴収します。
過不足税額の計算方法は、国税庁から出ている「年末調整のしかた」で解説されていますので、そちらも参照してみてください。
参考:
令和3年分 年末調整のしかた|国税庁
過不足額の精算|国税庁
過不足税額が生じた時の手続き
年末調整の実施により過不足税額が生じた際には、徴収税額の還付、または、追加徴収の手続きが発生します。
ここからは、還付や追加徴収の方法について見ていきます。
過納額・超過額の還付を行う
それでは、具体的に過不足税額をどのように手続きしていくかを見ていきましょう。
毎月の給与・賞与から徴収した1年間の源泉徴収税の合計額が、1年間で本来納付すべき年調年税額より多い場合には、源泉徴収税の超過額が発生していますので、差額の源泉徴収税額を還付する手続きを行います。
還付方法については、年末調整を行う月(通常は12月)の給与で計算された源泉徴収額から差し引くことで本人に還付を行います。
会社は、年末調整を行う月の給与で本来納付すべきである源泉徴収税額から差額の源泉徴収税を差し引いて税務署に納付することになります。
年末調整を行った月の源泉徴収税額だけでは還付しきれなかった場合や、会社の廃業、従業員側の徴収税額がなくなり差し引きできなくなった場合は、税務署から直接還付を受けることもできます。
年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書の作成
「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」は、年末調整で過不足税額を計算した結果、還付額が発生し、その還付額が年末調整を実施した月分の源泉徴収額だけでは還付しきれず、下記のような事象により還付できなくなる場合に作成が必要になる書類です。
- 会社の解散、廃業により会社が還付できなくなった場合
- 従業員から徴収する税額がなくなり還付できなくなった場合
- 過納額が多額で、還付する月の翌月からさらに2カ月還付したとしても還付しきれない場合
作成方法は、様式「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の裏面の記載要領等や次のURLを参考にしてください。
参考:[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求|国税庁
従業員が直接還付を受ける場合には、様式「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を各従業員別に作成する必要がありますので注意してください。
年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書の作成ができましたら、下記の書類を添付して会社を所轄する税務署に提出してください。
- 受給者各人の「源泉徴収簿」の写し
- 過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)
- 過納額を翌年に繰り越して還付しているときは、翌年分の「源泉徴収簿」の写し
最後に提出期限ですが、還付できなくなった事由が発生してから5年間で時効になりますので注意が必要です。
不足額を徴収する
これまでは過不足税額のうちの還付について解説しましたが、ここからは、毎月の給与・賞与から徴収した1年間の源泉徴収税の合計額が、1年間で本来納付すべき年調年税額より少ない場合について見ていきます。
毎月の給与・賞与から徴収した1年間の源泉徴収税の合計額が年調年税額より少ない場合は、会社はその過不足金額(今回の場合は不足金額)を年末調整を行う月分の給与から徴収します。
それでもなお不足額が残ってしまった場合には、その後に支払う給与から徴収することになります。
年末調整時の過不足税額について理解しておこう!
年末調整では、1年間に支給された毎月の給与・賞与からの徴収税額と、1年分の本来の徴収税額を比較して、その過不足税額を精算する手続きが必要だということを見てきました。
また、過不足税額が生じた場合には、納付し過ぎた場合には本人に還付し、納付不足の場合には追加徴収すること、その際の還付方法、徴収方法についても解説しました。
年末調整により過不足税額を計算して正しく納税することは会社にとっても大事な手続きになります。国税庁のHPなども参照しながら過不足税額への理解を深めていきましょう。
よくある質問
過不足税額とはなんですか?
過不足税額とは、給与・賞与から1年間に徴収した源泉徴収税額と、同じ1年間で本来納めるべきはずの源泉徴収税額の差額を求めた際に発生した超過金額、あるいは不足金額のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
過不足税額はどうやって確認しますか?
過不足税額は自分で計算して算出することはできますが、専門知識が必要なため難しいと思います。通常は会社で年末調整を行ってもらい、算出された過不足税額を確認することになります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
2021年の年末調整の変更点は?令和3年度税制改正のポイントを徹底解説!
年末調整は毎年のように税制改正の影響を受け、改正されていきます。2021年についても令和3年度税制改正により、さまざまな変更がありました。 ここでは、令和3年度税制改正における2021年の年末調整の変更点について解説します。 2021年の年…
詳しくみる年末調整手続きの電子化とは?方法やメリットについてわかりやすく解説!
年末調整といえば、従業員から紙で書類や控除証明書を受け取る必要があるなど、多くの労力がかかるものでした。しかし、今は、年末調整も電子化がされており、年末調整にかかる手間が削減できます。 ここでは、年末調整の電子化や「そのメリットとは何か?」…
詳しくみる年末調整で申請できない控除は?確定申告が必要なケースを解説
年末調整で所得税が還付になり、12月の給料が楽しみという方も多いのではないでしょうか。1年間に生じた収入や支出によって、「控除」を受けられると聞いたことがあるかもしれません。控除には様々なものがあり、年末調整で申請できないケースや、確定申告…
詳しくみる源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく解説(事例付き)
源泉控除対象配偶者には、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、所得金額が95万円以下の生計を一にする配偶者が該当します。多くの場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象になり、納税者本人の所得税を少なくできます。 これらの控除を受…
詳しくみる死亡退職した従業員の年末調整はどうしたらよい?
会社は従業員に対して、毎年最後の給与を支給する際に年末調整を行う義務があります。しかし、年度中に死亡した従業員がいる場合、その者に対する年末調整は年度途中に行わなければなりません。相続手続きに必要なことから早い時期での対応・処理が求められ、…
詳しくみる国民年金保険料は年末調整で控除できる?書き方や会社員でも必要なケースを解説
年末調整の控除では、生命保険料をはじめ、給与から天引きされる社会保険料も所得税控除の対象になります。では、この社会保険料に国民年金保険料は含まれているのでしょうか。 「会社員だから国民年金保険料は払っていない」「自分は厚生年金だから関係ない…
詳しくみる