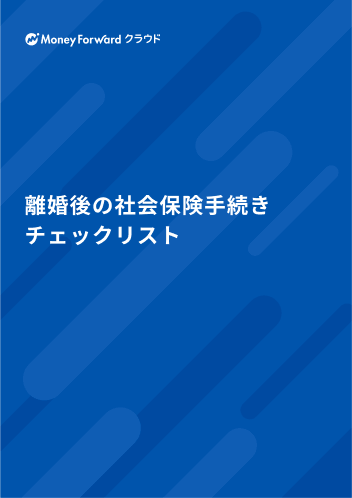- 更新日 : 2025年5月26日
離婚をしたら社会保険はどうなる?会社が行う手続き
従業員が離婚したら、会社は健康保険喪失証明書を発行するといった被扶養者関連の手続きをします。配偶者が離婚後すぐに就職しない場合、資格喪失日から14日以内に社会保険から国民健康保険への切り替えが必要なこともおさえておくと、問い合わせにスムーズに対応できるでしょう。今回は、離婚時に必要な社会保険の手続きに関して解説します。
目次
離婚をしたら社会保険はどうなる?
離婚をすると婚姻関係だけでなく、扶養関係も消滅します。そのため、妻が夫の扶養家族として健康保険や厚生年金といった社会保険に加入していた場合は、自分で変更の手続きをしなければなりません。
ここでは主に健康保険に焦点を当て、離婚した際に扶養の扱いがどうなるのか、また国民健康保険への切り替え手続きの方法などについて解説します。
離婚した場合の社会保険の扶養
前述のとおり離婚をすると、妻が健康保険や厚生年金などの社会保険において会社員の元夫の扶養に入っていたケースでは、元夫の健康保険や厚生年金からは外れます。
離婚した妻が、元夫の社会保険から外れた後の各ケースごとの健康保険に関する主な対応は、以下のとおりです。
| 妻の離婚前の状況 | 離婚後の働き方など | 求められる対応 |
|---|---|---|
| 専業主婦だった | すぐには働かない (親などの扶養や世帯にも入らない) | 国民健康保険に加入する |
| 自営業を営む | ||
| 就職する | 勤務先の健康保険に加入する | |
| 扶養内で働いていた | 継続して働く |
このように、元夫の会社の健康保険から外れた後も働かないようなケースでも、国民皆保険制度によって国民健康保険に加入できます。無保険になってしまうと、医療機関にかかった際に自費で高額な医療費を支払わなければなりません。しかし、国民健康保険に加入できるため、病気やけがをしたときにも一部負担金のみの支払いで済みます。
なお、元夫が会社員ではなく自営業を営んでいた場合には、夫も妻もそれぞれ国民健康保険に加入しているのが一般的です。その場合、離婚後はそのまま国民健康保険に加入し続けるか、新たに就職する場合には勤務先の健康保険に加入する選択肢があります。また要件によっては、親などの扶養に加入する方法もあります。
社会保険と国民健康保険の違い
社会保険とは、以下の5つの総称をあらわす言葉です。
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
これらは公的な費用負担によって、被保険者や被扶養者が病気やけが、介護や失業などのリスクに備えるための保険です。その中でも、狭義では下記の2つを社会保険と呼ぶことが一般的です。
- 健康保険(医療保険)
- 厚生年金保険(年金保険)
一方で国民健康保険は、勤務先の健康保険や全国健康保険協会、後期高齢者医療制度などに加入している方などを除くすべての方が加入する保険です。
社会保険の1つである健康保険と国民健康保険の主な違いは、以下の3つです。
- 加入者
- 扶養の有無
- 保険料の負担割合
加入者の違いについては、すでにお伝えしたとおりです。
そのほか社会保険である健康保険は、一定の条件を満たしていれば配偶者や親族を扶養に入れることが可能です。そのため、扶養されている方は保険料を支払う必要はありません。しかし国民健康保険には扶養の概念がなく、同居している家族であっても加入者それぞれ
保険料がかかります。
また、健康保険は基本的に事業者と被保険者が半分ずつ保険料を負担するのに対し、国民健康保険は被保険者が全額負担するといった違いがある点もおさえておきましょう。
社会保険から国民健康保険への切り替え
離婚によって元夫の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に切り替える手続きでは、以下のステップを踏む必要があります。
- 健康保険証を元夫に返す
- 元夫の勤務先で健康保険の資格喪失手続きをおこなう
- 国民健康保険の加入手続きをする
まず、健康保険証を元夫に返しましょう。その後、勤務先で健康保険の資格喪失手続き、つまり扶養から外れるための手続きをしてもらいます。具体的には「健康保険 被扶養者(異動)届」で元配偶者について「非該当」に丸をつけ、その理由を選択し、提出します。
喪失証明書の受け取り
健康保険の異動届が受理されると、会社から「健康保険資格喪失証明書」が発行されるため、これを居住地の役所に持っていき、国民健康保険の加入手続きをしてください。
手続きが離婚後になる場合、元夫からの資格喪失証明書の受け取り方法は、郵送などになるケースが多いでしょう。そのため国民健康保険の加入手続きまでタイムラグが起きますが、無保険期間が生じることはありません。国民健康保険の実務上、資格喪失証明書の取得日に遡って加入日を設定することが可能なためです。
ただし、この間に医療機関などで診察を受けた場合、いったん全額を自己負担で支払う必要があります。その後、国民健康保険の加入手続きが終了したら、役所で還付の手続きをおこなうと自己負担分の3割を差し引いた7割が戻ってくるしくみです。
このように、健康保険資格喪失証明書の取得日から国民健康保険に加入するまでの間も無保険期間にはなりませんが、医療機関にかかった際にはいったん全額自己負担で支払います。さらに還付の手続きも必要になるため、なるべく離婚前に元夫に職場での資格喪失手続きをしてもらうよう頼んでおきましょう。
また、国民健康保険への加入は、健康保険などの資格を喪失した日から14日以内におこなうことになっています。手続きが遅れると、さかのぼって保険料を支払わなければならなくなるため注意が必要です。
子どもの扶養
健康保険の場合、親の離婚によって、すぐに子どもも資格喪失をするわけではありません。そのため何もしなければ、元夫の健康保険をそのまま使うことになります。ただし、通院のたびに保険証を元夫から取り寄せる必要が生じるため、手間がかかります。
妻が子どもを自分の健康保険に入れるときは、自分の健康保険を切り替える際、子どもの健康保険もあわせて切り替えましょう。なお離婚後に妻が国民健康保険に加入する場合、国民健康保険には扶養の概念はないため、子どもの保険料の支払いが発生します。
元夫が国民健康保険の被保険者であったケースで、子どもを自分が引き取る場合には夫と子どもは別世帯になり、それまでの保険は利用できなくなるため注意しましょう。
参考:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
従業員が離婚した場合の社会保険手続き
従業員が離婚した際、会社の人事労務担当者は、社会保険においてさまざまな手続きをおこなう必要があります。具体的には、従業員の氏名や住所の変更、扶養者を削除するための手続きなどです。それぞれの手続きに関して解説します。
氏名変更と住所変更の手続き
離婚で従業員の氏名が変更した場合、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている被保険者であれば、原則届け出は不要です。また離婚によって従業員の住所変更が生じた場合にも、氏名変更と同様です。
健康保険・厚生年金保険・被保険者氏名変更(訂正)届の提出
離婚によって氏名変更や住所変更が生じるケースで、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていない場合もあります。このケースでは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」を年金事務センターや年金事務所などに提出しましょう。氏名変更時には健康保険証の添付も必要です。
たとえば氏名変更の場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」に記載する内容は、主に以下のとおりです。
- 事業所整理記号
- 個人番号(または基礎年金番号)
- 被保険者の性別や生年月日
- 被保険者の変更前および変更後の氏名
被扶養者関連の手続き
離婚によって従業員の配偶者や子どもなどが被扶養者でなくなる場合には、前述のとおり「健康保険被扶養者(異動)届」と、健康保険証をあわせて年金事務所に提出します。被扶養者でなくなった理由に印をつけるのも、忘れないようにしましょう。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き|日本年金機構
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
離婚した場合、社会保険料は変わる?いくらになる?変更のあるケース
元夫の勤務先の健康保険に扶養家族として加入していた場合、離婚後は国民健康保険に加入するか、自身の勤務先の健康保険に加入することになります。
被扶養者であったときには、保険料を負担することなく、保険給付を受けることが可能でした。しかし、たとえば国民健康保険に加入した場合、決められた保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険料は、居住する自治体や収入によって異なります。たとえば、令和3年度の東京都新宿区の国民健康保険料の概算は以下のとおりです。
| 給与収入 | 東京都新宿区における1ヶ月あたりの保険料 (介護分なし、40〜64歳以外) |
|---|---|
| 100万円 | 4,492円 |
| 200万円 | 11,409円 |
| 300万円 | 16,974円 |
| 400万円 | 22,857円 |
| 600万円 | 35,577円 |
| 800万円 | 49,410円 |
なお、震災や勤務先の倒産などによってどうしても国民健康保険料の支払いができない場合は、所得が大幅に減少した世帯への減免制度を受けられる可能性があります。
離婚後に就職し、自身の勤め先の健康保険に加入する場合は、会社が保険料の半分を負担してくれます。会社の健康保険の加入者は比較的若く、収入が安定していている傾向にあり、支払い額も低めであることが多いです。
また夫の厚生年金に扶養加入していた場合、離婚後にしばらくは働かなかったり、親などの扶養に入らないケースでは国民年金にも加入する必要があります。令和4年度の国民年金保険料は、一律で月額16,590円です。
所得が少なくて国民年金の保険料を納められない場合、未納扱いにならない「免除制度」や「納付猶予制度」の申請手続きをすることが可能です。
参考:令和3年度 国民健康保険料 概算早見表(給与・年金)|新宿区
参考:国民年金の保険料はいくらですか。|国民年金機構
参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|国民年金機構
従業員の離婚時の社会保険の手続きをおさえよう
従業員が離婚したら、その配偶者は扶養から外れるため、会社は健康保険や厚生年金などの社会保険においても、被扶養者関連の手続きをする必要があります。また、離婚により従業員の氏名や住所が変更する場合にも、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている被保険者以外については、変更の手続きをしなければなりません。
会社として必要な手続き以外にも、扶養から外れた配偶者が自身でおこなう手続きについてもおさえておくと、従業員からの問い合わせにスムーズに回答できるでしょう。
よくある質問
離婚をしたら社会保険はどうなるか教えてください。
たとえば妻が夫の扶養家族として健康保険や厚生年金といった社会保険に加入していた場合、離婚によって扶養から外れることで、被保険者の資格を喪失します。詳しくはこちらをご覧ください。
従業員が離婚した場合、人事労務担当者はどういった対応が必要ですか?
離婚によって従業員の配偶者や子どもなどが被扶養者でなくなる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。氏名や住所の変更が生じる場合は、それらの変更手続きもしなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
健康保険の被扶養者とは?加入条件や被扶養者(異動)届の書き方も解説!
健康保険に加入する被保険者の親族のうち一定の要件を満たす者は、被扶養者となることができ、収入や同居の条件を満たしている親族が、被扶養者として認められます。被扶養者には、被保険者と同じように健康保険証が交付されます。被扶養者となるには被扶養者…
詳しくみる被保険者整理番号とは?健康保険・厚生年金の確認方法と必要な場合を解説
被保険者整理番号とは社会保険の加入手続きの際に発行され、登録内容を変更する際に必要となる番号です。 本記事では、自分の被保険者整理番号が不明という方や人事部の方へ被保険者整理番号についてわかりやすく解説します。被保険者整理番号が変わる場合や…
詳しくみる労災保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説
労災は企業にとって軽視できない問題です。企業としては職場環境の改善などで労災の発生を抑制するだけでなく、労災発生後にも適切な対応が求められます。従業員の収入を保護するためにも、労災保険の休業補償について正しく理解しなくてはなりません。そこで…
詳しくみるぎっくり腰は労災認定される?仕事で発症した腰痛の認定基準や休業補償の金額などを解説
職場での何気ない動作や急な負荷によって、突然襲ってくるぎっくり腰。想定外の痛みとともに業務が中断されることも多く、「これは労災になるのか?」と悩まれる方も少なくありません。実は、ぎっくり腰も一定の条件を満たせば、労働災害として認定される可能…
詳しくみる会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?労働者性の要件についても解説!
雇用保険は、事業主と雇用関係にあり、働くことで賃金を得る労働者が加入対象です。会社の役員、取締役といった人々は、経営者の立場にあり、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、労働条件などから判断して労働者として雇用保険に加入できる…
詳しくみる労働保険料の納付のしかたをわかりやすく解説
労働保険料は、今年度の保険料を概算で申告・納付すると同時に、昨年度に概算で申告した概算保険料と実際に支払った賃金額から計算した確定保険料との差額の清算を行う「年度更新」と呼ばれる複雑な申告・納付方法を行います。 毎月納付する健康保険料や厚生…
詳しくみる