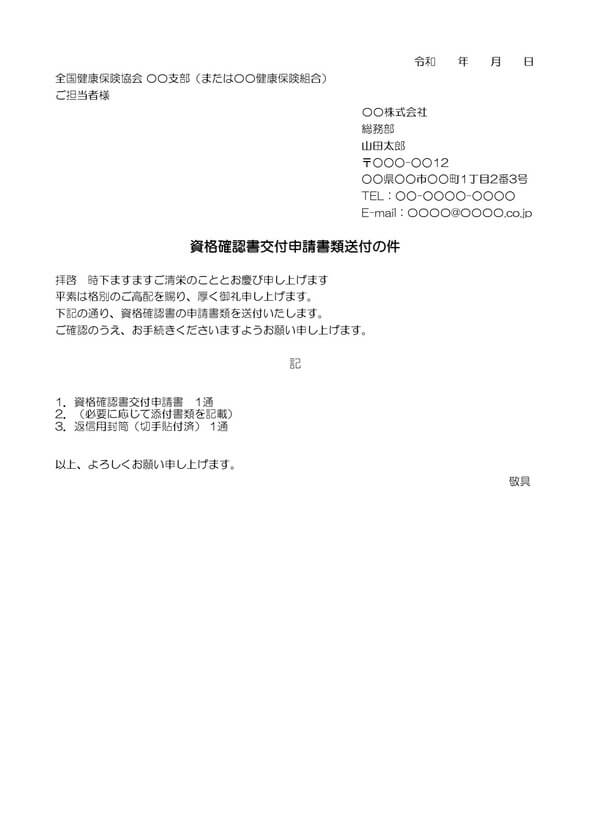- 更新日 : 2025年7月9日
資格確認書とは?どこでもらえる?送付状のテンプレも
2024年12月2日以降、従来の健康保険証が新規発行されなくなる代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となります。
しかし、何らかの事情でマイナンバーカードを取得・利用できない方のために、医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)から無償交付される書類が「資格確認書」です。
目次
資格確認書とは?
マイナ保険証以外の受診方法として利用できる書類
2024年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなるのを受け、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。
一方で、さまざまな事情からマイナ保険証を取得・利用登録していない方や、マイナ保険証による受診が難しい方が保険診療を受けるために、保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市町村など)が無償で交付する書類が「資格確認書」です。
受診時に提示することで保険診療が受けられる
従来の健康保険証と同様に、医療機関や薬局の窓口で提示すると、自己負担割合(例:3割負担)にて保険診療が受けられます。
保険者によって、様式や発行形態(紙のカード型、紙の書面など)は異なります。
資格確認書はどこでもらえる?
「資格確認書」は、ご自身が加入している医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)から無償で交付されます。
- 会社員の方であれば会社が加入している健康保険組合や協会けんぽ、
- 自営業やフリーランスの方、無職の方であれば市区町村の国民健康保険、
- 後期高齢者医療制度に該当する方であれば、各都道府県の後期高齢者医療広域連合、
など、それぞれの保険者が交付主体となります。
交付方法
- 申請不要で交付される場合
マイナンバーカードを取得していない・利用登録していない方は、現行の健康保険証の有効期限が切れるタイミングで自動的に郵送されることが多いです。 - 申請が必要な場合
マイナンバーカードで受診が困難な方や、マイナンバーカードを紛失中・更新中の方は、ご自身で保険者へ申請すると交付されます。
実際の交付時期や手続き手順は保険者ごとに異なります。まずは加入中の保険者からの案内を確認するか、疑問点があれば保険者に直接お問い合わせください。
資格確認書の交付対象
マイナ保険証を使わない場合でも、当面の間は原則として「申請不要」で資格確認書が交付されます。具体的には、下記の方が無償で交付対象となります。
申請不要で交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
- 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度へ加入された方、または転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方
- 令和7年7月末までの暫定措置として、現行の健康保険証が失効する際に申請不要で交付。
申請が必要となる方
- マイナンバーカードを持っていても受診等が困難な方(配慮が必要な方)
- 高齢の方、障害をお持ちの方など。
- 一度申請して資格確認書が交付された場合、更新時には再度申請せずに交付されます。
- マイナンバーカードを紛失・更新手続き中の方
- カードの再発行までに受診の予定がある場合に申請すると資格確認書が交付される。
資格確認書の有効期限や更新について
有効期限は5年以内で、保険者が設定
資格確認書には有効期限があり、保険者によっては2年、3年など異なる場合もあります。更新手続き時、期限切れが近づくと保険者から案内があるケースや、自動的に新しい資格確認書が交付されるケースなど、運用は保険者ごとに異なります。
後期高齢者医療の暫定措置
75歳以上(または一定の障害を有する65歳以上75歳未満)で後期高齢者医療制度の被保険者になられた方は、令和7年7月末までの暫定運用として申請不要で資格確認書が交付されます。
マイナ保険証を使わない場合の受診手順
- 資格確認書の提示
医療機関や薬局に行った際、「資格確認書」を窓口で提示します。 - 自己負担割合での受診
従来どおり3割負担(年齢や収入状況によっては1割や2割負担の場合あり)で診療が受けられます。 - 注意点
- 資格確認書の有効期限切れに注意。
- 氏名や住所など情報の変更がある場合は、必ず保険者や事業主へ届け出し、新しい資格確認書の発行が必要です。
いずれ資格確認書を「返送」する必要があるのか
資格喪失後は使用不可
従業員が退職したり、被扶養者資格を喪失したり、氏名変更により再発行が必要になったりした場合、旧資格確認書は無効となります。
事業主は、従業員から回収した資格確認書を、必要書類(例:被保険者資格喪失届、被保険者氏名変更届)に添付して日本年金機構へ提出し、最終的に保険者へ返納します。
具体的な返納先
- 事業所(会社)
まずは従業員が退職や資格喪失などのタイミングで、資格確認書を事業所の事務担当者へ返却します。 - 日本年金機構へ返送
事業主は、回収した資格確認書等を添付のうえ、被保険者資格喪失届などの手続書類を日本年金機構へ提出します。 - 保険者に最終返納
日本年金機構に届いた書類は、管轄する保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)に返納されます。
事業者が資格確認書を返送する際の注意点
提出書類の確認
- 「被保険者資格喪失届」や「被保険者氏名変更届」など、必要な届書を確認し、不備がないかチェックしましょう。
- 返送先や提出期限は加入している保険者の案内に従います。
個人情報の保護
- 資格確認書には個人情報が含まれます。
- 記入漏れや誤字脱字はもちろん、送付時には封筒をしっかり封緘(ふうかん)し、できれば「重要書類在中」などの表示を行いましょう。
返納漏れを防ぐ
- 本人分だけでなく、家族(被扶養者)分の資格確認書も必ず回収する必要があります。
- 返納漏れがあると手続きが滞る場合があります。
コピーの保管(事業主側)
- 必要に応じて、返送前に資格確認書のコピーを取り、事業所で保管しておくと、万一の確認が必要な際に役立ちます。
- 個人情報の取り扱いには十分注意し、必要がなくなったら速やかにシュレッダー処分等を行います。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
雇用保険と出産
離職の理由が妊娠や出産の場合、そのまま家庭に入って子育てをするためにすぐに就職はしないとみなされ、雇用保険(失業給付)の対象外となります。 しかし現在は、出産後も長くブランクを空けずに再就職活動をする人が増えています。こうした状況にあわせて…
詳しくみる労基署の臨検とは?書類の確認ポイント、是正勧告があった場合の対応
「立ち入り検査で何を見られるのか分からない」 「準備が整っていなかったらどうしよう」 労基署の臨検に対して不安を抱く人事労務担当者もいるでしょう。 臨検は企業の問題点を明らかにし、改善するための機会であり、適切な準備と対応を知れば、不安を軽…
詳しくみる社会保険料(国民年金保険料)の免除制度とは
国民年金保険料は、世代・所得問わず定額です。 しかし、国民年金保険料の納付義務期間に職を失った場合や給料をカットされた場合など、保険料を納めることが厳しくなった場合に備え、「免除制度」が設けられています。 ここで注意していただきたいことです…
詳しくみる厚生年金加入者の配偶者でも国民年金への加入は必要?
会社員や公務員などは、厚生年金に加入するのが一般的です。厚生年金には扶養制度があるため、専業主婦など条件を満たした被扶養配偶者は扶養加入することができます。しかし、収入が一定以上ある場合や、年齢が60歳以上の場合は条件から外れるため注意が必…
詳しくみる雇用保険被保険者離職証明書の書き方は?離職票との違いや提出方法も解説
雇用保険に加入していた労働者が失業した場合、再就職までの生活保障として基本手当を受給することができます。 しかし、給付を受けるためには雇用保険被保険者離職証明書が必要です。 この記事では、雇用保険被保険者離職証明書とはどのような書類なのか、…
詳しくみる一人親方(個人事業主)の労災保険は経費にできる?勘定科目や節税について解説
一人親方(個人事業主)は労災保険に特別加入できますが、保険料を経費に計上することはできません。労災保険は労働者を対象にしたもので、一人親方の加入はあくまで特例であるためです。ただし、確定申告で所得控除の対象になり、節税が可能です。 本記事で…
詳しくみる