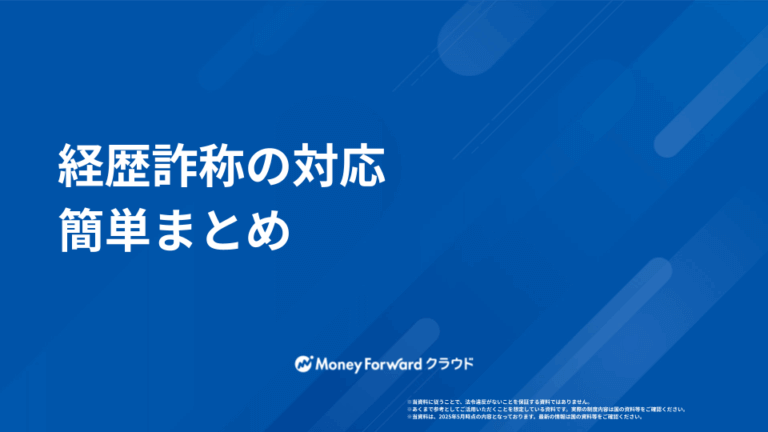- 更新日 : 2025年6月23日
経歴詐称とは?具体例や罰則、企業の対応方法を解説
経歴詐称とは、学歴、職歴、犯罪歴などの経歴を隠したり、虚偽の申告をしたりする行為のことです。経歴詐称が発覚すると企業にとっては大きなリスクになるため、企業の対応が重要になります。本記事では、経歴詐称の具体例や、罰則、企業の対応方法について解説します。
目次
経歴詐称とは?
経歴詐称(けいれきさしょう)とは、本人の経歴を偽ったり隠したりする行為のことです。
経歴詐称には、学歴、職歴、犯罪歴の詐称などがあります。本項では、経歴詐称は罪に問われるかどうかや、詐称と偽証の違いについて解説します。
経歴詐称は罪に問われる?
経歴詐称は罪に問われることはほとんどありませんが、場合によっては罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
例えば、履歴書などの事実、権利、義務などを証明する私文書に、他人の名義を許可なく使用した場合には私文書偽造罪になります。また、金銭目的のために経歴詐称をして、金銭を受け取った場合には詐欺罪になります。
学位などの法令で定められた称号や、資格などを偽った場合には軽犯罪法違反になる可能性があるのです。
詐称と偽証の違い
詐称とは、年齢、職業、経歴などの事実を偽って、現実よりもよく見えるように表現することをいいます。一方、偽証とは、事実を偽って証言することや、事実を捻じ曲げたり、ないことをいかにもあるように言ったりすることです。
経歴詐称の具体例
経歴詐称には、様々な種類があります。経歴詐称を防ぐためには、様々な経歴詐称の具体例を知っておくことが必要です。本項では、経歴詐称の具体例について解説します。
学歴詐称
学歴詐称の大半は、採用時に有利になるために高学歴と詐称するものです。しかし、まれですが、なかには大学卒業を隠すために、高卒と偽る詐称も学歴詐称のひとつです。学歴詐称には、以下のような具体例があります。
- 本当は高卒なのに大卒と最終学歴を詐称する
- 本当に卒業した学部とは異なる学部を卒業したと詐称する
- 浪人や留年を隠すために実際に入学や卒業した年度を詐称する
- 本当は高校や大学を中退したのに卒業したと詐称する
職歴詐称
職歴詐称の多くは、採用時に実際に経験したことのない職歴を経験したことにしたり、不利になる職歴を隠したりすることです。職歴詐称には、以下のような具体例があります。
- 非正規雇用期間を正規雇用期間と詐称する
- 実際には経験のしたことのない業務について経験があると詐称する
- 短期間で退職した企業の職歴を隠す
- 以前の職場で懲戒解雇を受けたことを隠す
免許・資格詐称
免許・資格詐称の多くは、採用時に必要または保有していると有利な免許や資格を保有していると詐称することです。免許・資格詐称には、以下のような具体例があります。
- 社会保険労務士試験が不合格だったのにもかかわらず、履歴書に合格と記載する
- 運転免許を更新していないのに、履歴書に運転免許保有と記載する
- 日商簿記検定2級しか保有していないのに、履歴書に日商簿記検定1級保有と記載する
- TOEICの点数を実際の点数より高く詐称する
年収詐称
年収詐称の多くは、採用後の年収を有利にするために、現在の年収を実際よりも多く詐称することです。年収詐称には、以下のような具体例があります。
- 年収には残業代なども含まれるため、実際の年収よりも多く申告してもバレることはないと思い、年収を実際よりも高く詐称する
- 転職後の年収が有利になるように実際よりも多い年収を詐称する
犯罪詐称
犯罪詐称は、採用や選考に不利にならないために、過去の犯罪歴を隠すことです。犯罪詐称には、以下のような具体例があります。
- 過去に有罪になった犯罪歴を隠して応募する
犯罪詐称とされる犯罪歴は、一般的には有罪になったものに限られます。そのため、不起訴処分、起訴猶予のまま釈放、刑期終了後相当期間の経過の場合は、犯罪歴の申告をしなくても経歴詐称にならない可能性が高いです。
病歴詐称
多くの病歴詐称は、過去にメンタルの疾患がある場合の詐称が多いです。病歴詐称の場合には、以下のような具体例があります。
- 過去にメンタルの不調により長期休んでいたことを詐称する
- 過去に重病を患っていたことを詐称する
病歴の場合は、詐称して入社していたとしても、業務に支障がなければ解雇することは難しいです。
経歴詐称が及ぼすリスク
経歴詐称をした場合、犯罪にはならなかったとしても大きなリスクを及ぼすことになります。本項では、経歴詐称が及ぼすリスクにはどのようなものがあるかについて解説します。
内定の取り消し
経歴詐称した場合に最も多く起こりうるのは、内定の取り消しです。ただし、内定の取り消しは事実上解雇と同様の行為として捉えられるため、労働契約法16条にて客観的に合理的、かつ社会通念上相当である場合のみ認められています。
そのため、経歴詐称した場合であっても、すべて内定の取り消しができるわけではありません。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、懲戒処分の中で最も重い処分であり、労働契約法15条では客観的で合理的な理由があり社会通念上相当である場合のみ認められています。
そのため、経歴詐称した場合であっても、すべてが懲戒解雇にできるわけではありませんが、懲戒解雇相当の経歴詐称をした場合は大きなリスクになります。
懲戒解雇については、下記ページに詳しく記載していますので、あわせてご参考ください。
信用失態
経歴詐称が内定の取り消しや懲戒解雇にならなかったとしても、周りからの信用失態は避けられません。
いくらやる気があっても、仕事を回してもらえなかったり、重要なプロジェクトに参加させてもらえなかったりすることが考えられます。入社できたとしても、大きなリスクは避けられないでしょう。
損害賠償請求
経歴詐称することで企業に損害を与えることになった場合には、企業側が民事で損害賠償請求をする可能性があります。損害賠償が認められれば、賠償金を支払う可能性もあるため、大きなリスクになります。
損害賠償請求については、下記ページに詳しく記載していますので、あわせてご参考ください。
採用後に経歴詐称が発覚した場合の対応
採用後に経歴詐称が発覚した場合は、会社側は解雇を含めた対応策を検討しなければなりません。本項では、採用後に経歴詐称が発覚した場合の対応について解説します。
事実を確認する
経歴詐称が発覚した場合には、まずは事実の確認が必要です。経歴詐称の内容を確認するために、採用時の資料の調査や、本人への聴取などを行います。経歴を詐称したことが、採用や給与に影響を与えたのかなどの事実を確認することが重要です。
業務への影響を評価する
経歴詐称をした従業員の業務への取り組み態度や実績などが、実際の業務に影響を与えたかどうかを評価します。経歴詐称が業務へ影響を与えるものでなく、企業として問題ないものであれば、必ず懲戒解雇をする必要はありません。
対応策を検討する
経歴詐称といえども、業務にまったく影響のない詐称から違法性の高い重大な詐称までそれぞれです。そのため、経歴詐称の内容によって、対応策も変わってきます。
例えば、高卒と大卒と賃金体系が異なる企業において、本当は高卒なのに大卒と偽った経歴詐称は、給与にもかかわる重大な経歴の詐称のため、懲戒解雇の対象です。一方、営業職の従業員が、履歴書に本当は保有していない日商簿記検定3級保有と詐称していても、業務や賃金には関係ないため懲戒解雇をすることはできません。
業務への影響などにより、対応策を決定します。
対応策を実施する
対応策を検討したら、決定された対応策を実施します。対応策が懲戒解雇の場合は、就業規則に懲戒解雇の規定を定めて従業員に周知しておかないと懲戒解雇は有効にならないため注意が必要です。
経歴詐称を防ぐには?
経歴詐称は、将来企業に重大な損害を与える可能性があるため、事前に防ぐことが重要です。本項では、経歴詐称を防ぐためには、どうすればよいかについて解説します。
履歴書の賞罰欄
履歴書の賞罰欄の「賞」とは、受賞した賞や表彰を意味し、「罰」とは犯罪歴や懲役刑などを表す用語です。すなわち、履歴書の賞罰欄には、受賞歴や犯罪歴などを記載します。そのため、実際には犯罪歴があるのに履歴書の賞罰欄へ犯罪歴を記載していなければ、経歴詐称の可能性があります。
経歴詐称の場合は履歴書の賞罰欄と実際の犯罪歴が一致しないため、面接や対話の中で深堀りすることで矛盾が発覚して経歴詐称を防ぐことができるでしょう。また、レファレンスチェックやSNSの情報などを調査することで、履歴書の賞罰欄に犯罪歴を記載していないことが発覚するため、経歴詐称を防ぐことができます。
面接での質問
履歴書や職務経歴書に正しいことを記載しているかは、面接時に深掘りした質問をすることで見抜くことが可能です。例えば、履歴書に記載されている経歴では、当たり前に知っているであろう専門用語で質問をしてみたり、疑問を感じたことに対しては繰り返し質問をしたりします。
経歴詐称をしている場合には、答えが矛盾していたり、つじつまが合わなかったりして必ず回答にボロが出るのです。
証明書の提出
履歴書や職務経歴書に記載されていることが詐称かどうかを見抜くためには、証明書を提出してもらうことが大切です。学歴詐称を防ぐためには卒業証書、資格の詐称を防ぐためには資格取得が証明できる証明書、職歴詐称を防ぐためには退職証明書などを提出してもらいます。
レファレンスチェック
リファレンスチェックとは、採用候補者の現職または前職の上司や同僚などに、人物の特性、業績、経歴などを問い合わせる調査のことです。リファレンスチェックをすることで、履歴書や職務経歴書に記載されていることや、面接の内容が経歴詐称かどうかを見抜くことが可能です。
SNSやインターネットの調査
採用候補者のSNSやインターネットの調査をすることで、投稿内容などから学校、サークル活動、ゼミなどの個人情報がわかります。SNSやインターネットから入手した情報が、履歴書や職務経歴書に記載された内容と異なっていれば経歴詐称の可能性があります。
例えば、SNSには大学を中退したことが投稿されていたのに、履歴書には大学卒業と記載されているケースなどです。
バックグラウンドチェックの外注
採用候補者の履歴書や職務経歴書に記載されている内容など、面接の内容に虚偽がないかを調べることを、バックグラウンドチェックといいます。バックグラウンドチェックは、反社チェックや素行などの専門的な調査が必要なため、専門会社に外注するのが一般的です。バックグラウンドチェックを外注することにより、経歴詐称を防ぐことができます。
経歴詐称が発覚した場合は適切な対応が必要
経歴詐称が採用後に発覚した後にそのまま雇用し続けると、企業の秩序が保てなくなる可能性があります。また、社外からは経歴詐称を許す企業と評価され、取引先と信用問題になる可能性もあるでしょう。
しかし、経歴詐称のすべてのケースで、懲戒解雇にすることはできません。そのため、経歴詐称が発覚した場合には、経歴詐称の重大性、企業や取引先への影響、企業や業務の秩序を考慮し、なるべく影響が少なくなるような適切な対応が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
エンゲージメントとは?なぜビジネスで重要か?高める方法や事例を解説
エンゲージメントとは、誓約・約束・契約などを意味する英単語で、ビジネスにおいては従業員の愛社精神など意味します。エンゲージメントが低いと人材の流出や生産性の低下などさまざまな問題を引き起こすため、エンゲージメントを高める取り組みが重要です。…
詳しくみる再雇用制度とは?導入メリットや定年後の契約の流れ、注意点や助成金を解説!
働き手の確保が企業にとって大きな課題となっています。そこで注目されているのが「再雇用制度」です。定年後も引き続き優秀な人材を活用できるだけでなく、技術やノウハウの継承にも役立つ制度です。 この記事では、導入メリットから運用上の注意点、関連す…
詳しくみる外国人労働者を受け入れた際に起こりうる5つの問題|原因・解決策・事例も紹介
外国人労働者を受け入れると、主に5つの問題やトラブルが発生する可能性があります。 「どのような問題が実際に起こっているの?」「トラブルが発生したときの解決策はある?」など気になっている人もいるでしょう。 そこで本記事では、外国人労働者に関連…
詳しくみる労働協約とは?労使協定との違いや締結プロセスを解説
会社で働くうえでは、給与や休暇をはじめとする様々な取り決めがなされます。労働条件などをあらかじめ当事者間で定めることによって、後のトラブル発生を防止しています。 当記事では、労働協約について解説します。労使協定との違いや適用範囲、注意点など…
詳しくみるクレドとは?語源はなに?会社・企業での使い方や目的を紹介
クレドとはラテン語の「Credo」が語源となっており、ビジネスでは企業全体の従業員が心がける信条や行動指針を指す言葉として使用されます。クレドがあることで従業員のモチベーションが向上したり人材育成を行えたりするメリットがあるのです。この記事…
詳しくみるオンライン研修(Web研修)とは?開催方法・メリット・注意点やおすすめサービスを解説!
オンライン研修(Web研修)とは、インターネットを通じてパソコン、スマホ、タブレットなどがあればどこでも参加することができる研修のことです。オンライン研修は、オフラインでの研修と異なり研修会場が不要です。本記事では、オンライン研修の概要、開…
詳しくみる