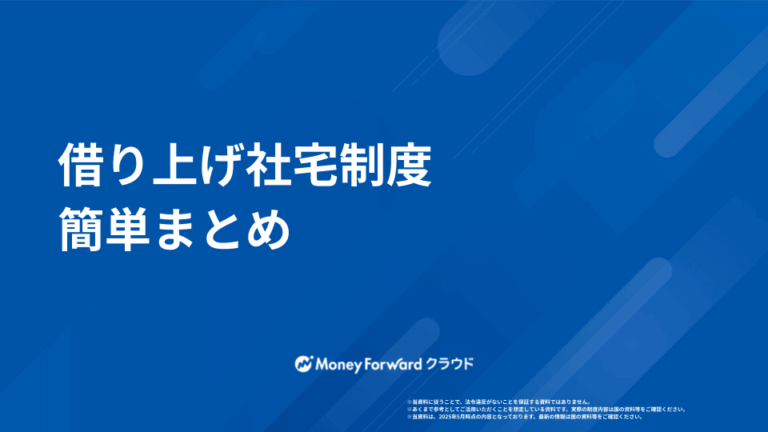- 更新日 : 2025年6月23日
借り上げ社宅制度とは?メリットや税金優遇、導入の流れ、トラブル対応まとめ
借り上げ社宅制度とは、企業が契約した賃貸物件を従業員に貸し出す制度のことです。従業員が負担する家賃が相場よりも低い傾向にあることや、企業によっては従業員が物件を選べる場合があるため、人気の福利厚生制度の1つです。本記事では、借り上げ社宅制度のメリットや注意点、社有社宅制度との違いなどを解説します。
目次
借り上げ社宅制度とは?
借り上げ社宅制度とは、企業が賃貸物件を契約し、従業員に住宅を貸し出す制度のことです。地方に支社や営業所を持つ従業員の転勤が多い企業や、海外事業を展開する企業が、借り上げ社宅制度を導入している傾向があります。
借り上げ社宅制度があると、従業員は慣れない場所で不動産物件を探す必要がありません。地方の場合は、支社や営業所の近くに物件を借りることで、従業員の通勤の負担を減らすメリットもあります。
借り上げ社宅の家賃負担は会社?従業員?
借り上げ社宅制度は法人契約であるため、企業が住居の初期費用を負担するケースが一般的です。初期費用は、家賃の4~5ヶ月分が目安といわれています。ただし、法律で企業の負担が義務付けられているわけではないため、一部を従業員負担にする場合は、社宅管理規程でその旨を定めることも可能です。
家賃は、通常、物件の借主である企業に対して、従業員が企業ごとに決められた金額を支払います。住宅費は家計の中で大きな割合を占めます。そのため、借り上げ社宅制度は、福利厚生制度の中でも従業員の満足度が高い制度といえるでしょう。
一般的な負担については、以下をご覧ください。
| 費用項目 | 費用の目安 | 一般的な負担者 |
|---|---|---|
| 初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など) | 家賃の4~5ヶ月分 | 企業 |
| 引っ越し代 | 時期や荷物量などによる | 企業 |
| 家賃 | ー | 従業員・企業 |
| 更新料 | 家賃の1ヶ月分 | 企業 |
| 生活費 | ー | 従業員 |
借り上げ社宅制度の特徴
借り上げ社宅制度の特徴は、主に以下の3点です。
- 企業側会社が賃貸借契約を行う
- 企業側が家賃の一部を負担する社内管理規程を作成する
- 税金の優遇が受けられる従業員が水光熱費を負担する
それぞれの内容を解説します。
企業側が賃貸借契約を行う
借り上げ社宅を借りる際は、企業側が賃貸借契約を行う必要があります。従業員が個人的に賃貸借契約を結んだ物件は、企業が家賃の一部を負担している場合でも、借り上げ社宅制度とは認められないことがほとんどです。
また、敷金や礼金、火災保険料などの賃貸借契約に付随して発生する費用を従業員が支払っていると、法人の契約とみなされない場合があります。借り上げ社宅と認められない場合、企業が負担する家賃分が給与とみなされ、課税の対象となるため注意が必要です。
企業側が家賃の一部を負担する
借り上げ社宅は従業員への福利厚生制度のひとつのため、企業側が家賃の一部を負担します。
ただし、家賃の全額を企業が負担するのはおすすめできません。全額を企業が負担すると、家賃も給与の一部と判断され、従業員の所得税や社会保険料が増えます。また、企業側も社会保険料の負担が増えます。
税金の優遇が受けられる
社宅制度を導入することで、企業側が負担する家賃を福利厚生費として計上でき、節税効果を得られることがあります。ただし、企業側が負担する家賃が多すぎるときは、優遇を受けられないため注意が必要です。
企業の適切な負担額については、後述する賃料相当額で決定します。節税効果を高めるためにも、企業側の家賃負担額が高額になりすぎないように調整してください。
税制面でお得?借り上げ社宅制度のメリット
借り上げ社宅制度は、従業員にとっても企業にとっても多くのメリットをもたらします。その中でも特に、税制面に関するメリットが大きいことが特徴です。ここでは、税制面における企業側のメリットと従業員側のメリットを解説します。
企業側のメリット
企業側のメリットは以下の通りです。
- 家賃を福利厚生費として計上できる
- 社会保険料の負担を軽減できる
借り上げ社宅の家賃は、福利厚生費として計上することが可能です。福利厚生費とは、従業員に支払う給与や賞与以外の費用のことで、経費として扱われるため原則として非課税の扱いとなります。ただし、従業員から賃料相当額の50%以上を徴収しないと、課税対象になることに注意しましょう。
また、社会保険の計算上、企業に支払う家賃は対象となる収入から差し引けるため、従業員の社会保険料の負担が軽減できます。社会保険料は企業と従業員が折半して負担するため、企業側にとってもメリットです。
従業員側のメリット
従業員側のメリットは、以下の通りです。
- 所得税や住民税の負担を軽減できる
- 社会保険料も軽減されることがある
従業員が借り上げ社宅の家賃の一定額を支払えば、賃料相当額は給与所得として計上しなくてよいため、所得税や住民税の負担額を軽減できます。
加えて、前述のように社会保険の計算上、企業に支払う家賃は対象となる収入から差し引くことが可能なため、社会保険料の負担が少なくて済みます。
参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
借り上げ社宅制度のデメリット
メリットの多い借り上げ社宅制度ですが、デメリットも存在します。企業側のデメリットと従業員側のデメリットは、以下のとおりです。
企業側のデメリット
借り上げ社宅制度における、企業側のデメリットとして挙げられるのは以下の3点です。
- 契約や支払いなどの手続きが発生する
- 借りている部屋が空き部屋の状態でも家賃が発生する
- 解約時に違約金が発生する場合がある
借り上げ社宅制度を導入すると、契約や支払いなどの事務手続きが発生するため、手間がかかります。また、借りている部屋が空き部屋でも家賃が発生する、解約時に違約金を支払うリスクがあるといった点もデメリットです。解約時に違約金を支払うケースとしては、従業員が入居後すぐに退職したり、転勤が決まったりしたような場合が該当します。
従業員側のデメリット
借り上げ社宅制度を利用する従業員のデメリットは、以下のとおりです。
- 自由に物件を選べないことがある
- 社会保障額が減る可能性がある
あらかじめ借り上げ社宅が用意されている場合は、従業員は希望する立地や間取りの物件を選べません。
また、既にお伝えしたように、企業に支払う家賃が収入から差し引かれるため、失業保険や将来受け取れる年金額が減ってしまう点がデメリットといえるでしょう。支払わなければいけない社会保険料が減るのはメリットである一方で、社会保障額も減ってしまうことに注意しましょう。
借り上げ社宅の家賃相場はどのぐらい?
借り上げ社宅の家賃相場は、近隣相場の1~2割程度を目安に設定されることが一般的です。
税制上のメリットを享受するには、借り上げ社宅の賃料を給与所得としてではなく、福利厚生費として計上しなければなりません。そのためには、従業員から賃料相当額の50%以上を徴収する必要があることは既にお伝えしたとおりです。
しかし、ここでの賃料相当額を算出する際の基準になるのは「固定資産税の課税標準額」であり、実際に支払っている賃料とは異なります。ほとんどのケースで、賃貸相当額は実際の家賃よりかなり下回ります。
そのため、従業員が負担する家賃が相場の10~20%程度であっても、賃貸相当額の50%以上を経費として計上できるケースが多いことを押さえておきましょう。
借り上げ社宅の家賃を経費とする条件
社員向けの借り上げ社宅の家賃を経費とするためには、以下の合計額を賃料相当額とし、その50%以上を社員から徴収するようにしてください。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×その建物の総床面積(平米)÷3.3平米
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
役員社宅の場合
役員社宅の場合は、まずは小規模住宅の条件を満たすか確認してください。小規模住宅とは、以下のいずれかの基準を満たす住宅です。
- 法定耐用年数が30年以下かつ床面積が132平米以下
- 法定耐用年数が30年超かつ床面積が99平米以下
小規模住宅の基準を満たす場合は、社員向け社宅と同じ計算式で賃料相当額を求め、その100%以上を役員から受け取っているなら経費として計上できます。
小規模住宅の基準を満たさず、なおかつ会社が所有する社有社宅の場合は、次の合計額の12分の1を賃料相当額としてください。
- 建物の固定資産税の課税標準額×12%(法定耐用年数が30年超のときは10%)
- 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
小規模住宅ではなく、なおかつ借り上げ社宅の場合は、賃料の50%と上記の社有社宅の賃料相当額を比較し、いずれか多いほうの金額を賃料相当額とします。賃料相当額の100%以上を役員から受け取っていれば、経費計上が可能です。
ただし、豪華住宅は賃料相当額の計算方法が異なります。たとえば、床面積が240平米を超える物件やプール付き物件などは豪華住宅と判断されるため、本来支払うべき家賃が賃貸料相当額となります。
借り上げ社宅の家賃負担額を決めるコツ
従業員の福利厚生を充実させるためにも、借り上げ社宅の家賃は相場よりも低めに設定しましょう。同程度の物件の家賃の10~20%程度に設定することが一般的とされています。
しかし、企業が多額を負担しすぎると、かえって従業員の税金や社会保険料の負担を増やしてしまうことがあります。
社員の場合なら上記で紹介した賃料相当額の50%以上、役員なら賃料相当額の100%以上を支払ってもらうようにしましょう。
借り上げ社宅制度を導入する流れ
借り上げ社宅制度は以下の手順で導入します。
- 社内で導入を決定する
- 社内管理規程を作成する
- 賃貸物件を探す
- 賃貸契約を結ぶ
- 従業員に周知し、運用を開始する
順に解説します。
1.社内で導入を決定する
まずは住宅支援制度として社宅制度を導入するか社内で話し合います。社宅制度を導入すると決定した場合は、借り上げ社宅と社有社宅のいずれが適切か決めましょう。
導入の際に弁護士や税理士などから法務・税務のアドバイスを受けておくと安心です。具体的な計画を立てた後、取締役会で審議し、正式に導入を決定します
2.社内管理規程を作成する
借り上げ社宅制度を導入する際は、社内管理規程を作成しましょう。具体的には、以下のような内容を決めておきます。
- 企業と従業員が負担する家賃の割合や金額
- 住居に住むことが可能な人の範囲
- 退去条件
このように、トラブルになりやすい項目についてのルールをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
3.賃貸物件を探す
事業所へのアクセスや設備、管理状態などをチェックし、適切な物件を探します。従業員の世帯構成も考慮し、間取りや広さの選択肢があるとよいでしょう。
4.賃貸契約を結ぶ
設備や管理状態、管理規約などを精査し、問題なければ賃貸契約を締結します。借り上げ社宅では、敷金や礼金、仲介手数料、火災保険料などの初期費用は企業側が負担することが一般的です。
5.従業員へ周知し、運用を開始する
借り上げ社宅の利用条件を従業員に周知し、従業員が利用できるようにします。また、利用中もトラブルや疑問、更新手続きなどが生じることがあるため、運用担当者を決めておくようにしましょう。
借り上げ社宅を運営・管理する方法
借り上げ社宅では、物件の管理会社が普段の管理業務を担当してくれますが、企業側の管理も必要です。借り上げ社宅の運営・管理のポイントについて解説します。
契約内容の確認と更新手続き
賃貸契約を締結するにあたり、契約内容を詳細に確認することが必要です。賃料や敷金、礼金、仲介手数料、原状回復費用などについて細かくチェックしましょう。不動産の専門知識のある方に契約をサポートしてもらうと、見落としを減らせます。
また、物件の更新時期には更新手続きも必要です。物件に暮らす従業員に確認し、更新条件に沿って手続きをしてください。その際、更新料や火災保険料などの費用が発生することがあります。
月次の業務
借り上げ社宅を運営する場合は、毎月、家賃の支払い業務が発生します。社宅ごとに賃料や管理費を確認し、支払額と社宅利用者の負担額に間違いがないか確認しましょう。
なお、社宅利用者からの費用徴収は、現金ではなく給与控除が一般的です。給与控除を処理する担当者と連携をとり、正確に控除を実施してください。
年次の業務
年次業務としては、社宅関連の支払調書の作成が挙げられます。また、作成した支払調書は税務署に提出しなくてはいけません。間違いがないよう、会計・税務の専門家のサポートを受けるようにしましょう。
借り上げ社宅制度でトラブルが起きたら?
借り上げ社宅制度の導入により、次が原因でトラブルが生じることがあります。
- 同居基準が不明瞭
- 原状回復費用・修理費用の負担が大きい
- 物件の管理が十分ではない
社内管理規程を丁寧に作成し、物件を慎重に選ぶなどトラブル対策が重要です。
同居基準が不明瞭なときは、同棲相手や遠い親族は社宅に暮らせるのか判断が難しくなってしまうでしょう。
また、原状回復費用や修理費用のトラブルも想定されます。いずれも物件側のルールに従う必要があるため、賃貸契約を締結する前に確認しておくことが必要です。社宅利用者が独断で修理をすると、立て替えた費用を返還してもらえない恐れがあります。
物件の管理が十分ではなく、建物内の入居者やゴミ捨て、共有部分の清掃などにトラブルが生じるリスクもあります。可能な限りリスクを排除するためにも、慎重に物件を選ぶことが大切です。
「借り上げ社宅」と「社有社宅」の違い
借り上げ社宅制度のほうが社有社宅制度よりも、従業員が物件を選ぶ自由度が高いといえるでしょう。借り上げ社宅制度は、企業が一棟丸ごと借り入れる場合もありますが、従業員が物件を選んで、企業が賃貸手続きをする場合もあります。
それに対して、社有社宅は企業が所有する物件を、従業員に貸し出す仕組みです。そのため、社有社宅制度においては、従業員が立地や間取りなどに関する希望を持っていたとしても、反映されることは難しいといえます。
また、社有社宅では他の住人すべてが同じ企業の従業員であったり、門限やルールなどが設けられたりするため、従業員から敬遠される傾向にあります。さらに、社有社宅は築年数が経過していることも少なくありません。
コストや労力を抑える視点からも、借り上げ社宅のほうがおすすめです。借り上げ社宅は建設費用がかからないことに加え、自社で管理する必要がないため、社有社宅よりも手間がかかりません。
さらに、社有社宅の場合は、従業員への家賃補助は住宅手当、つまり給与扱いになります。そのため、借り上げ社宅と比べて負担する社会保険料の額が大きいこともデメリットといえるでしょう。社有社宅には、固定資産税がかかることも押さえておかなければなりません。
事業所移転の可能性がある場合も、借り上げ社宅のほうが適しています。社有社宅の場合、事業所が社宅から離れた場所に移転してしまうと、従業員の通勤の負担や交通費が増えてしまいます。借り上げ社宅であれば、事業所の移転に応じて近くの物件を新しく探すことが可能です。
借り上げ社宅制度の仕組みやメリットを知ろう
借り上げ社宅制度とは、企業が借りた賃貸物件を従業員に貸し出す制度を指します。相場よりも安い家賃で住居を借りられることや、物件を探す手間が省けることなどから、従業員に人気の福利厚生制度であり、採用活動におけるアピールポイントとなります。また、企業にとっても従業員にとっても、税制面でのメリットが大きいことも魅力です。
一方で、契約や支払いなどの手続きが必要であったり、空き部屋になっても家賃が発生したりといったデメリットも存在します。借り上げ社宅制度の導入は、借り上げ社宅制度のメリットとデメリットの両方をよく理解したうえで検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
外国人労働者が雇用保険で適用除外となるケースと手続きの注意点を解説
外国人労働者の採用において、雇用保険の手続きに悩む担当者は多くいるでしょう。 この記事では、外国人労働者の雇用保険の加入条件や雇用保険適用除外となるケース、手続きの注意点などを解説します。手続きのミスは罰則やトラブルの原因になるため、正確な…
詳しくみるアルバイトをする学生は社会保険に加入するべき?条件を解説
事業者に雇用されて働いている人は社会保険に加入していますが、同じように雇用されていても学生のアルバイトはあまり加入していません。アルバイトとして働く学生は基本的に社会保険への加入義務がありませんが、場合によっては加入しなくてはならないことも…
詳しくみる労基署の臨検とは?書類の確認ポイント、是正勧告があった場合の対応
「立ち入り検査で何を見られるのか分からない」 「準備が整っていなかったらどうしよう」 労基署の臨検に対して不安を抱く人事労務担当者もいるでしょう。 臨検は企業の問題点を明らかにし、改善するための機会であり、適切な準備と対応を知れば、不安を軽…
詳しくみる雇用保険における再就職手当とは
失業や休業の場合にはもちろん、労働者が能力開発のため教育を受ける場合にも利用できる雇用保険。一般的には失業保険と言われる、自己による都合や会社側の都合によって離職した際に支給される基本手当がよく知られていますが、さらに、知っておくと得する意…
詳しくみる厚生年金基金と厚生年金保険の関係について
厚生年金基金は、厚生年金保険に加入している事業所が加入することのできる、一種の企業年金制度です。厚生年金保険に加入している企業やそのグループ企業、また同業種の企業ごとに設立された特別法人によって運営されています。 前者は「単独型」または「連…
詳しくみる一人親方は厚生年金に加入できない?適用除外の理由や加入すべき制度を解説
一人親方は厚生年金には加入できません。老後に受給できる年金は、基本的に国民年金のみです。そのため、国民年金基金やidecoと呼ばれる個人型確定拠出年金への加入を検討しましょう。本記事では一人親方の年金制度を解説します。受け取れる年金額のシミ…
詳しくみる