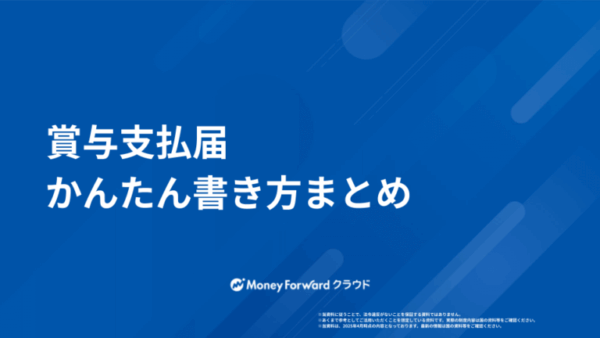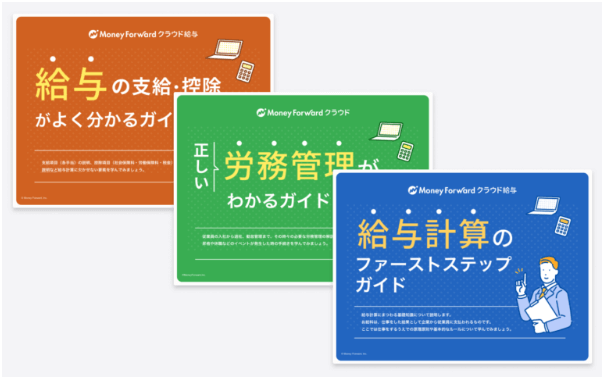- 更新日 : 2025年12月8日
賞与支払届は電子申請できる!e-Govでの手続きの流れやメリットをわかりやすく解説
賞与支払届を提出する際には、電子申請を活用することで業務効率が向上します。
紙での申請に比べて郵送の手間や時間が省けるだけでなく、ミスの防止やコスト削減にもつながります。
しかし、「具体的にどう申請すればいいのか」「どんなメリットがあるのか」といった疑問を抱えている方もいるでしょう。
そこで本記事では、賞与支払届を電子申請する方法や具体的な流れ、メリットについて詳しく解説します。
電子申請のメリットを理解し、効率的な業務運用に役立てましょう。
目次
賞与支払届とは
賞与支払届とは、企業が従業員に賞与を支給した際に、その情報を日本年金機構に報告するための届出書類です。
賞与支払届は、従業員の社会保険料の適正な計算を行うために必要であり、法令で提出が義務付けられています。
次項で、賞与支払届の記入対象者や対象となる賞与、提出先、提出期限について詳しく解説します。
記入の対象者
賞与支払届の記入対象者は、厚生年金保険および健康保険の被保険者と70歳以上の従業員です。
ただし、被扶養配偶者や日雇い労働者、適用除外の従業員は対象外となります。
週所定労働時間または、月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の方は、社会保険に加入しないため対象外です。また、従業員数51人以上の特定適用事業所であっても、以下に該当する場合には社会保険に加入しないため、賞与支払届の記入は不要です。
- 1週間の勤務時間が20時間未満の方
- 給与が月額88,000円に満たない方
- 学生でアルバイトの方
具体的な対象者の範囲は、企業が加入している社会保険制度によって異なる場合があるため、日本年金機構のホームページなどで詳細を確認するのがおすすめです。
対象となる賞与
賞与支払届の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
たとえば、年2回支給されるボーナスや決算賞与などです。
また、下記のような一時金も賞与支払届の対象に含まれます。
- 資格支援手当
- 成果報奨金
- 特別勤務手当
ただし、結婚祝金や退職金など、労働の対価とみなされない一時金は、賞与支払届の対象外です。
提出先
賞与支払届の提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所で、提出方法は、下記の通りです。
- 郵送
- 窓口持参
- 電子申請(e-Gov、マイナポータル)
- 電子媒体申請(CD、DVD)
電子申請や電子媒体申請をすれば、賞与支払届を郵送や持参する手間が省けるのでおすすめです。
賞与支払届を電子申請で提出する方法については、本記事の「賞与支払届は電子申請できる?」で詳しく解説するのでぜひ参考にしてください。
なお、電子媒体申請については、「日本年金機構|電子媒体申請」をご覧ください。
提出期限
賞与支払届の提出期限は、賞与を支給した日から5日以内と定められています。
期限を過ぎても提出は可能ですが、支給日から2年を経過すると受け付けてもらえません。
一方で、支給日より前に提出した場合は書類が返却される可能性があるため、提出が早すぎてもいけません。
そのため、賞与を支給してから速やかに提出するのが良いでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
賞与計算規程(エクセル)
賞与計算に関する取り決めを整備するための、エクセル形式の規程テンプレートです。貴社の規定や運用に合わせて手軽に内容を修正・カスタマイズいただけます。
スムーズな運用開始をサポートする実用的な資料としてご活用ください。
賞与計算(社会保険料計算)シート
賞与支給額の算出および、社会保険料の計算に対応した実務用シートです。
計算業務の効率化と円滑な事務処理をサポートする資料として、ぜひダウンロードしてご活用ください。
賞与支払届 かんたん書き方まとめ
賞与支払届を作成する際の書き方について、要点を絞ってまとめた解説資料です。
手続きを円滑かつ正確に進めるための手引きとして、実務の現場でご活用ください。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
賞与支払届は電子申請できる?
賞与支払届は、従来の紙ベースの方法だけでなく、電子申請を利用してオンラインでも提出が可能です。
電子申請の具体的な方法は、下記の通りです。
- e-Gov申請
- マイナポータル申請
- 届書作成プログラムからの申請
次項で、それぞれの申請方法の特徴について詳しく解説します。
e-Gov申請
e-Govとは、デジタル庁が運営する総合的な行政ポータルサイトです。
賞与支払届だけでなく、「健康保険・厚生年金保険任意適用申請書」や「納付猶予申請書」など、約270種類もの書類の電子申請が可能です。
政府が運営しているため、安心して利用できるでしょう。
申請の流れは、賞与支払届のデータを作成し、e-Govを通じて提出するだけです。
賞与支払届をe-Gov申請で提出する詳しい方法については、本記事の「e-Govを利用した賞与支払届の申請手続きの流れ」で解説しています。
マイナポータル申請
マイナポータル申請は、企業が行う従業員の社会保険・税手続きを、まとめてオンライン申請ができるサービスです。
マイナポータル申請は、現在利用中の人事給与ソフト・システムと連携するため、手続き該当者の情報が事前に登録されており、入力の手間が省けます。
そのため、対象となる人事給与ソフト・システムを利用している方は、マイナポータル申請を活用して賞与支払届を提出するのがおすすめです。
届書作成プログラムからの申請
届書作成プログラムは、日本年金機構が提供する無料ツールで、賞与支払届だけでなく、「資格取得届」や「算定基礎届」など、さまざまな届書を簡単に作成できます。
フォーマットに従って入力すれば、入力ミスを防げます。
作成した賞与支払届は、e-Govやマイナポータルを通じて提出可能です。
届書作成プログラムのダウンロードや、利用の流れに関しては、「日本年金機構|電子申請(届書作成プログラム)」をご覧ください。
賞与明細の無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、賞与明細の無料テンプレートをご用意しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
e-Govを利用した賞与支払届の申請手続きの流れ
e-Govを利用した賞与支払届の申請手続きの流れについて、事前準備と申請手続きの流れに分けて解説します。
事前準備
e-Govで賞与支払届を電子申請する際は、下記の画像にしたがって事前準備をしましょう。

まず、アカウントの準備をします。
e-Govで使えるアカウントは、下記の通りです。
- e-Govアカウント
- GビズID
- Microsoftアカウント
e-Gov電子申請を利用するアカウントの準備ができたら、ブラウザの設定を行います。
ブラウザの設定では、下記の画像のようにポップアップブロックを解除します。

ポップアップブロックが有効のままだと、正しく画面が表示されない可能性があります。
ここまでの準備が完了したら、「Windows版」または「macOS版」のe-Gov電子申請アプリケーションをダウンロードして、事前準備は完了です。
より詳しい事前準備の手順を知りたい方は、「e-Gov電子申請|利用準備」をご覧ください。
申請手続き流れ
e-Govを利用した賞与支払届の申請手続きの流れは、下記の通りです。
| 順番 | 手順 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | e-Govのウェブサイトにアクセス | e-Govのウェブサイトにアクセスし、IDとパスワードを入力してログイン |
| 2 | 申請手続きを選択 | 「健康保険・厚生年金保険被保険者 賞与支払届」の申請手続きを選択 |
| 3 | 必要事項を入力 | 事業者情報や対象者の情報、賞与額などを正確に入力 |
| 4 | 添付書類をアップロード | 必要に応じて届書作成プログラムや給与ソフト・システムで作成したCSVファイルをアップロード |
| 5 | 確認と送信 | 入力した内容や添付書類に誤りがないかを確認したら、「送信」ボタンをクリック |
上記の手順で申請は完了です。
申請後は、e-Govの「申請履歴」から進捗状況を確認できます。
万が一不備があった場合は、修正依頼が届きます。
なお、無事に賞与支払届の電子申請が完了した場合は、通知書(公文書)を忘れずにダウンロードしておきましょう。
e-Govを利用した賞与支払届の電子申請は、手順を覚えれば簡単です。
紙の書類を作成したり、郵送したりする手間が省けるため、積極的に電子申請を活用してみてください。
賞与支払届を電子申請する4つのメリット
賞与支払届の電子申請は、従来の紙での提出と比較して、下記のようなメリットがあります。
- 時間と手間が省ける
- ミスを減らせる
- コストを削減できる
- いつでもどこでも申請できる
次項で、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
時間と手間が省ける
賞与支払届を電子申請すれば、郵便局へ足を運んだり、切手を貼ったりする必要がありません。
また、1度入力したデータを再利用できるため、何度も同じ内容を入力する必要がなく、事務作業の負担も軽減できます。
そのため、時間と手間が省け、業務効率が向上します。
ミスを減らせる
電子申請システムでは、入力内容のチェック機能があるため、賞与支払届の記入漏れや誤入力を防げます。
また、一括でデータを処理できるため、大量の賞与支払届を作成する場合でも、書類の紛失や重複提出など、人為的なミスが発生しにくいというメリットがあります。
コストを削減できる
電子申請なら、紙で賞与支払届を作成する必要がないため、印刷費用や郵送費がかかりません。
また、入力や集計にかかる時間も短縮でき、経費や担当者の人件費などのコストを削減できます。
いつでもどこでも申請できる
賞与支払届の電子申請は、24時間いつでも可能です。
また、インターネット環境さえあれば、職場だけでなく自宅や出先など、どこでも賞与支払届の申請ができます。
そのため、業務の柔軟性や効率化につながります。
電子申請を活用して賞与支払届を効率よく作成・管理しよう!
賞与支払届を電子申請は、企業の業務効率化に大きく貢献します。
具体的には、郵送や手続きの手間を省き、時間の節約やコスト削減が可能です。
また、ミスを防げるため、事務作業の正確性が向上します。
さらに、いつでもどこでも申請できるため、人事労務担当者の業務負担を軽減できます。
賞与支払届の電子申請を検討している企業は、自社の状況に合わせて最適な方法を選択し、効率よく作成・管理していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
退職金の住民税・所得税は優遇されている!?
会社を辞めたときなどに受け取る退職金は、退職所得として税金が課されることになります。 ただ、給与所得などの他の所得と違い、退職所得に課される所得税・住民税の計算は優遇されています。…
詳しくみる定額減税で毎月いくら入る?税額と手取りについて解説!
2024年に実施される定額減税の額は1人4万円です。内訳として、所得税3万円、住民税1万円が控除されます。配偶者または扶養親族がいる場合には、その人数分控除されるため、単身者では4…
詳しくみる最低賃金とは?制度の概要や種類をわかりやすく解説
労働者に は契約に従って労働する義務はありますが、使用者にも労働の対償として賃金を支払う義務があります。また、賃金には最低の額が定められており、その額を下回ることは許されません。 …
詳しくみる新潟県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
新潟県は豊かな自然に恵まれ、特に米や日本酒の生産で知られています。また、製造業や電子機器産業も盛んで、港を活かした物流業も重要な役割を担っています。このような多様なビジネス環境では…
詳しくみる中途採用者の住民税の手続きまとめ!一括徴収とは?
会社には住民税の特別徴収が義務付けられており、中途採用者も原則として特別徴収の対象となります。 ただ、下記のように疑問に思う人もいるでしょう。 「中途採用した場合はどのような手続き…
詳しくみる代休と有給休暇の違いとは?給与計算の方法や運用のポイントを解説
休日出勤をした場合、代わりの休日として代休を取得してもらうことがあります。しかし、従業員が代休ではなく有給休暇を申請するケースもあり、どのように対応するべきか迷う担当者の方もいるで…
詳しくみる
-e1763462562443.jpg)
シート-1.png)