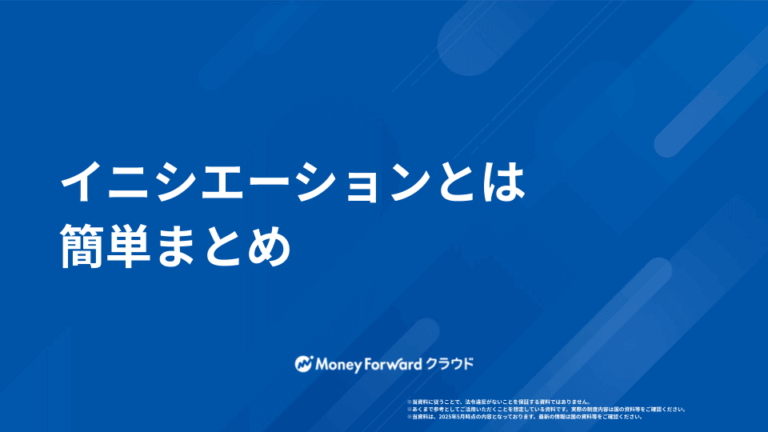- 更新日 : 2025年6月23日
イニシエーションとは?意味やビジネスでの用例を紹介
イニシエーションとは、元々は宗教的な意味を持つ言葉で「通過儀礼」という意味です。医療や心理学、ビジネスなど分野によって異なる意味で用いられる点に留意しましょう。この記事では、イニシエーションの概要や注目されている理由、ビジネスにおける使用例、人事労務担当者が行うべき対策などを解説します。
目次
イニシエーションとは?
ここでは、イニシエーションの概要や一般的な使用例について見ていきましょう。
元々は宗教上の言葉
イニシエーションとは、元々は宗教上の言葉で、信徒になる際の「通過儀礼」を意味します。広義は「ある社会的集団からほかの社会的集団へ加入するための一連の行為・手続き」を指しますが、それには何らかの通過儀礼が行われることがほとんどです。新しく所属する集団に受け入れてもらうためには、通過儀礼、すなわち、多かれ少なかれ困難を伴います。イニシエーションは「大きな状態変化に適応するために必要な困難」と認識するとわかりやすいでしょう。
イニシエーションの翻訳語は?
イニシエーション(initiation)を直訳すると、「加入」「入門」「儀式」という意味になります。これらの意味に基づき、「新たに加入する組織に承認されるための儀式」と解釈されるようになったのです。そのほか、「入社式」「成人式」とも訳されます。イニシエーション(通過儀礼)における意味は、使用される分野によってさまざまです。
一般的に使用されるイニシエーションの例
イニシエーションは、一般的に以下の分野で使用されます。
- 宗教
信徒になる際の儀式や儀礼 - 社会学
「子ども社会から大人社会への仲間入り」といった生活環境や待遇が一変するような形態 - 医療
発がん過程の初期ステップ - 心理学
失恋など心理的ショックを克服して成熟に向かうこと
ビジネスにおけるイニシエーションの使用例については後ほど詳しく解説します。
イニシエーションはなぜ注目されている?
近年、ビジネス分野においてイニシエーションが注目されています。その背景にあるのは、「終身雇用制度の崩壊」です。働き方改革によって多様な働き方が推進されたことでキャリアの幅が広がり、年齢を問わず人事異動や異業種への転職が活発化しています。それに伴い、イニシエーションを経験する回数が増え、組織や仕事に馴染めないというトラブルが生じるようになりました。この現状を受けて、日本企業においてもイニシエーションに配慮する必要性が高まったのです。
ビジネスにおけるイニシエーションの使用例
ここでは、ビジネスにおけるイニシエーションの使用例を2つ見ていきましょう。
グループイニシエーション
グループイニシエーションとは、新卒社員や中途入卒者が新たに加入する組織に忠誠心や協調性を示し、周囲から組織の一員として受け入れてもらう経験のことです。「集団への加入」と呼ばれることもあります。具体的には、「歓迎会」「クレドの共有」などです。グループイニシエーションを行うことで、早期離職の原因となる「組織に馴染めない」を取り除けます。グループイニシエーションが成功すれば、新入社員や中途入社者の心理的安全性の構築やモチベーションの向上につながるでしょう。
タスクイニシエーション
タスクイニシエーションとは、新入社員や中途入社者が新たな組織に加入したあと業務の遂行面や組織への貢献を通して周囲から認められることです。タスクイニシエーションを実現させるためには、新入社員や中途入社者の能力や性格を考慮し、適切な教育係となる人物を配置することがポイントとなります。業務を遂行するためには、周囲のサポートが不可欠のためです。まずはグループイニシエーションで信頼関係を構築してから、適切な人材を配置して質問や相談をしやすい環境下でタスクイニシエーションを実現させましょう。
ビジネスでのイニシエーションと呼ばれるケース
ここでは、ビジネスにおけるイニシエーションと呼ばれるケースを2つ紹介します。
就職・転職
新しく企業の一員になる就職は、新入社員にとって大きなイニシエーションとなります。同僚や先輩社員、上司は新入社員と積極的にコミュニケーションを図り、組織として受け入れる体制をとることが重要です。教育担当になる上司や先輩社員は新入社員の能力や適正を考慮しながら業務スケジュールを組んだ丁寧なサポートが求められます。周囲との相互理解が深まり、業務を着実に覚えられれば、新入社員は就職時のイニシエーションを乗り越えやすくなるでしょう。
転職もビジネスにおけるイニシエーションのひとつです。ほかの会社から新しい会社に入社するにあたって、職場風土や業務内容が変化します。会社は中途入社者が馴染みやすい環境を整備し、経験があるからといって指導や説明を怠ることがないようにしなければなりません。新卒採用者とは別に中途入社者向けの研修内容を用意することも重要です。
出向・配置転換
コロナ禍において、事業を縮小せざるを得ない企業から人手不足に悩む企業への出向事例が増加しました。特に、出向先企業に 一定期間継続して勤務する「在籍出向」が注目されています。在籍出向は、出向元の企業に籍を置いたままの状態で出向先の企業と雇用契約を結ぶため、一定期間勤務したあとに出向元に戻ることが前提です。出向先での新しい人間関係や業務内容の違いなど、出向社員が乗り越えなくてはならないストレスは、大きなイニシエーションとなります。
職種や業務内容の変更、勤務地の変更・転勤などの配置転換もビジネスにおける身近なイニシエーションです。在籍企業には変化がありませんが、人間関係や業務内容が変わることになります。チームに馴染む努力や業務への貢献などが求められることから、大きな負担がかかるでしょう。出向や配置転換においても、受け入れる側は馴染みやすい環境づくりと丁寧なサポートを行う必要があります。
イニシエーションはなぜ重要?その目的は?
ビジネスにおいてイニシエーションはなぜ重要なのでしょうか。ここではイニシエーションの重要性とその目的について解説します。
リアリティショックの防止
リアリティショックとは、理想と現実のギャップに衝撃を受けることです。特に新入社員が組織の新たな一員として加わったときに起こりやすいとされています。具体的には、学生時代に背負ったことのない責任や新たな人間関係の構築、自己評価と実際のスキルの乖離などです。リアリティショックを防止するためにも、グループイニシエーションによって信頼関係を構築し、タスクイニシエーションによって社員が達成感を得られるようにすることが重要なのです。
リアリティショックで起こる弊害
社員がリアリティショックに陥ると、モチベーションやエンゲージメントが低下し、早期離職につながるきっかけになります。理想と現実のギャップを受け入れないまま働いていると、やる気や会社への愛着心が失われてしまうためです。1人の社員のモチベーションやエンゲージメントが低下すると、ほかの社員がフォローしなければならなくなり、周囲の人間の負担が増えます。その結果、周囲の社員までモチベーションやエンゲージメントの低下を引き起こすリスクも生じるのです。
人事労務担当者が行うイニシエーションの整備・対策
リアリティショックを予防するためにも、事前に対策を講じることが重要です。ここでは、人事労務担当者が行うべきイニシエーションの整備・対策を紹介します。
風通しの良い職場を作る
普段から質問や相談をしやすい風通しの良い職場づくりを心がけておきましょう。新卒採用者や中途入社者の様子を意識的に観察し、定期的に1on1の場を設けることも大切です。入社後は程度の差はあれど誰もがリアリティショックを感じるものです。社員がリアリティショックを感じても「この職場なら乗り越えられる」と思えるような環境を整えておきましょう。
新卒・中途入社の人へのフォロー制度の確立
新卒採用者・中途入社者の不安を取り除くためにも、フォロー制度を確立しておきましょう。具体的には、研修制度の整備やチーム全体でのサポート体制の構築、メンター制度などです。研修制度を通じて業務の内容と社員の能力のギャップを埋めていき、さらにチームで積極的に声掛けすることが重要です。メンター制度とは、年齢や社歴が近い先輩社員がサポートする制度で、新卒採用者や中途入社者は不安や悩みを相談しやすく職場に馴染みやすくなるといった特長があります。
オンボーディングツールの活用
そもそもオンボーディングとは、新しいメンバーが早期に組織に馴染み、組織への定着・戦力化を促進するための取り組みのことです。オンボーディングを支援するソリューションであるオンボーディングツールを活用すると、より効果的なオンボーディングを実施できます。オンボーディングツールには、研修や体験型のプログラムが備わっているものや、HRテクノロジーによるもの、動画・eラーニングを用いたものなどがあるため、自社に適したものを採用すると良いでしょう。
リアリティショックを防ぐためにも、イニシエーションを整備しておきましょう
終身雇用制度の崩壊や働き方の多様化によって転職の機会が増え、それに伴いイニシエーションを経験する機会も増加しました。就職や転職、出向、配置転換などのイニシエーションにおいてリアリティショックを感じる人も少なくありません。リアリティショックは、モチベーションやエンゲージメントの低下を引き起こし、早期離職につながるきっかけになり得ます。リアリティショックを予防するためにも、イニシエーションの整備・対策を徹底しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
借り上げ社宅と家賃補助の違いを解説|住宅制度の理解を深めよう
住宅制度には「借り上げ社宅」と「家賃補助」があり、各制度で仕組みや税金の取り扱いが異なります。 本記事では、借り上げ社宅と家賃補助の違いや、導入するメリット・デメリットについて解説します。ぜひ参考にしてください。 借り上げ社宅と家賃補助の違…
詳しくみるオーナーシップとは? 意味や従業員が持つメリット、リーダーシップとの違いを解説
オーナーシップとは、仕事に対して当事者意識を持ち、主体的に取り組む姿勢やマインドのことです。従業員がオーナーシップを持つことで組織の力を強化し、生産性向上や会社の成長につながります。 本記事では、オーナーシップの意味や求められている理由…
詳しくみるムーンショット目標とは?制定された背景や企業との関わり
ムーンショット目標とは、内閣府の政策の一つであるムーンショット型研究開発制度において掲げられている、9つの目標のことです。日本が抱える問題を解決するために破壊的イノベーションの創出を目指す目標で、2024年または2050年までの実現を目指し…
詳しくみるストライキとは?意味や仕組み、企業の賃金対応や防止策について簡単に解説
本記事ではストライキの意味・仕組み・権利としての性格について紹介します。さらに過去の事例に簡単に触れ、企業の対応や防止策についてもわかりやすく解説していきます。 ストライキとは? 「ストライキ」は英語「Strike」に由来する外来語です。遡…
詳しくみる従業員貸付制度は信用情報に影響する?理由や利用するデメリットなども解説
従業員貸付制度は、従業員が急な出費や生活費の確保を目的に会社から有利な条件でお金を借りられる制度です。一方、制度の利用にあたって気になるのが、自分の信用情報への影響でしょう。この記事では、従業員貸付制度が個人の信用情報にどのように影響するの…
詳しくみる任命書とは?書き方や委嘱・委託との意味の違いも解説
組織では、構成員に対して「任命書」を交付することがあります。小・中学校では、生徒会長などに就任させる際に交付するのが一般的です。 では、社会人の場合はどのような時に交付されるのでしょうか。任命と類似した用語に、委嘱や嘱託、委任、辞令などがあ…
詳しくみる