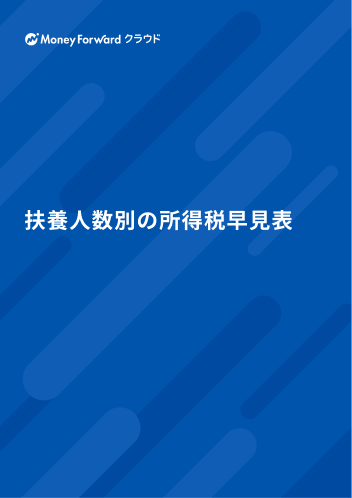- 更新日 : 2025年5月27日
所得税は扶養人数でいくら変わる?年齢による違いや給与計算の注意点
家族を扶養する従業員は、その人数に応じて源泉所得税が減額されます。そのため、給与計算においては、所得税と扶養人数の関係を理解することが欠かせません。当記事では、所得税と扶養人数の関係について解説します。扶養親族の年齢による違いや人数の数え方なども紹介しますので参考にしてください。
目次
所得税は扶養人数で変わるのか?
源泉所得税の額は、従業員の扶養対象となる人数に応じて変動します。扶養する人数が増えれば増えるほど減額幅も大きくなりますが、その幅は月々数千円程度の範囲です。しかし、年間を通して見れば決して無視できるような額ではありません。
社会保険料は扶養人数で変わるのか
社会保険においても扶養の制度は存在します。家族や親族を扶養に入れることで、保険料を負担することなく健康保険の給付を受けることなどが可能です。しかし、社会保険料は所得税と異なり、扶養人数によって増減することはありません。扶養人数が1人であっても2人であっても、保険料額に差が生じることはありません。
所得税は扶養人数でいくら変わる?
源泉所得税における扶養親族の数は、「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」を合計した人数です。合計人数に制限はなく、対象として含まれる親族等がいれば全てが対象となります。
「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」は、以下のような者を指します。
- 源泉控除対象配偶者
納税者の合計の所得金額が900万円以下となる場合において、納税者と生計を一にしており、合計所得の金額が95万円以下である配偶者が該当します。ただし、給与の支払いを受ける青色申告者の事業における事業専従者、および白色申告者の事業専従者は除かれます。
- 控除対象扶養親族
扶養親族であって、16歳以上となる者が該当します。扶養親族とは、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であって、納税者と生計を一にしている所得金額の合計が48万円以下となる者を指します。ただし、給与の支払いを受ける青色申告者の事業における事業専従者、および白色申告者の事業専従者は除かれるため注意が必要です。
では、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計人数は、具体的にどの程度、所得税に影響を及ぼすのでしょうか。月収と扶養人数ごとの所得税額について解説します。
月収30万円の場合
社会保険料等が控除された後の給与等が月300,000円である場合、「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」において、299,000円以上302,000円未満に該当します。そのため、扶養人数ごとに以下の金額が源泉徴収されます。
| 扶養する人数 | 源泉所得税(月) | 源泉所得税(年間) |
|---|---|---|
| 0人 | 8,420円 | 101,040円 |
| 1人 | 6,740円 | 80,880円 |
| 2人 | 5,130円 | 61,560円 |
| 3人 | 3,510円 | 42,120円 |
| 4人 | 1,890円 | 22,680円 |
| 5人 | 280円 | 3,360円 |
| 6人 | 0円 | 0円 |
| 7人 | 0円 | 0円 |
扶養する親族等がいない場合には、月に8,420円徴収されます。しかし、扶養親族が1人いれば6,740円となり、その差額は1,680円です。月々では大きな金額ではありませんが、年間では20,160円の差が出てしまいます。6人以上では0円となるため、さらに大きな差となります。
上記金額は、甲欄が適用される場合です。扶養控除等申告書を提出していない場合には、甲欄ではなく高い税率の乙欄が適用されます。その場合の金額は、月間で53,700円、年間では644,400円です。
月収40万円の場合
社会保険料等が控除された後の給与等が月400,000円である場合、「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」において、398,000円以上401,000円未満に該当します。そのため、扶養人数ごとに以下の金額が源泉徴収されます。
| 扶養する人数 | 源泉所得税(月) | 源泉所得税(年間) |
|---|---|---|
| 0人 | 16,510円 | 198,120円 |
| 1人 | 13,270円 | 159,240円 |
| 2人 | 10,040円 | 120,480円 |
| 3人 | 7,560円 | 90,720円 |
| 4人 | 5,930円 | 71,160円 |
| 5人 | 4,320円 | 52,840円 |
| 6人 | 2,710円 | 32,520円 |
| 7人 | 1,080円 | 12,960円 |
扶養する親族がいない場合に比べて、扶養親族が1人いれば月々3,240円、年間で38,880円の差額が生じます。月収が上がったことによって、さらに扶養人数ごとの差が大きくなっていることがわかるでしょう。なお、乙欄が適用される場合には月額89,800円、年間で1,077,600円が徴収されます。
月収50万円の場合
社会保険料等が控除された後の給与等が月500,000円である場合、「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」において、500,000円以上503,000円未満に該当します。そのため、扶養人数ごとに以下の金額が源泉徴収されます。
| 扶養する人数 | 源泉所得税(月) | 源泉所得税(年間) |
|---|---|---|
| 0人 | 29,890円 | 358,680円 |
| 1人 | 23,430円 | 281,160円 |
| 2人 | 18,370円 | 220,440円 |
| 3人 | 15,140円 | 181,680円 |
| 4人 | 11,900円 | 142,800円 |
| 5人 | 8,670円 | 104,040円 |
| 6人 | 6,870円 | 82,440円 |
| 7人 | 5,250円 | 63,000円 |
扶養親族の有無による差がさらに大きくなっています。扶養親族が1人いれば、0人の場合に比べて、月々6,460円、年間77,520円も所得税が安くなっています。この月収における乙欄適用時の徴収額は、月額146,800円、年間1,761,600円です。
月収60万円の場合
社会保険料等が控除された後の給与等が月600,000円である場合、「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」において、599,000円以上602,000円未満に該当します。そのため、扶養人数ごとに以下の金額が源泉徴収されます。
| 扶養する人数 | 源泉所得税(月) | 源泉所得税(年間) |
|---|---|---|
| 0人 | 47,100円 | 565,200円 |
| 1人 | 40,640円 | 487,680円 |
| 2人 | 34,160円 | 409,920円 |
| 3人 | 27,700円 | 332,400円 |
| 4人 | 21,240円 | 254,880円 |
| 5人 | 17,280円 | 207,360円 |
| 6人 | 14,040円 | 168,480円 |
| 7人 | 10,810円 | 129,720円 |
この額になると、扶養親族がいても月々の徴収額はかなり大きなものとなります。扶養親族0人と1人の場合の差額は月々6,460円、年間77,520円です。なお、乙欄適用時は、月々196,300円、2,355,600円が徴収されます。甲欄適用時と比べて極めて大きな負担となる額です。
所得税の扶養親族の年齢による違い
控除対象扶養親族となるためには、16歳以上であることが求められるなど、扶養親族は年齢が重要な要素です。配偶者控除も、控除対象配偶者が70歳以上の場合には「老人控除対象配偶者」として、通常の38万円から48万円に控除額が引き上げられます。
しかし、基礎控除や寡婦控除、ひとり親控除など、他の控除では年齢に応じた差は生じていません。年齢による差は、扶養控除や配偶者控除特有の傾向といえるでしょう。以下では、年齢が重要な要素となる扶養親族について、その年齢による違いを解説します。
一般の扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)
控除対象扶養親族のなかでも、16歳以上18歳以下の者と23歳以上69歳以下の者を他の親族と区別して、「一般の扶養親族」と呼びます。高校生や大学卒業後の子どもなどが該当し、扶養控除額は38万円です。
特定扶養親族(19歳以上22歳以下)
「特定扶養親族」は、19歳以上22歳以下の扶養親族が該当します。大学等に通う年齢で経済的負担が大きいことから、一般の扶養親族よりも高い63万円が控除額として設定されています。大学や専門学校に通う子どもなどが対象です。
老人扶養親族(年齢70歳以上)
扶養親族のなかでも、年齢が70歳以上の者を「老人扶養親族」と呼びます。同居せずに扶養する両親や祖父母などが該当し、控除額は48万円です。
同居する老人扶養親族(年齢70歳以上)
老人扶養親族のなかでも、同居する両親や祖父母などの直系尊属は、「同居老親等」として、通常の老人扶養親族よりも高い58万円が控除額として設定されています。同居する両親や祖父母などが該当しますが、老人ホーム等に入居している場合には該当しません。
税制上の扶養人数の数え方
これまで解説した通り、扶養親族の数に含めるには、一定の条件を満たすことが必要です。しかし、この人数は実際の扶養親族の人数とは異なる場合があります。税制上の扶養親族の数え方について解説します。
扶養親族の人数:プラス1人
扶養親族をそのまま、「プラス1人」として数えるのは、以下のような場合です。
- 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合
- 親族が控除対象扶養親族に該当する場合
- 本人が「ひとり親」「寡婦」「勤労学生」に該当する場合
- 本人または配偶者、扶養親族が、税法上における一般または特別障害者に該当する場合
源泉控除対象配偶者に該当するかは、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄や、基礎控除申告書の「給与所得者の基礎控除申告書」の項目で確認します。また、控除対象扶養親族に該当するかどうかは、扶養控除等申告書の「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄で確認可能です。
参考:
令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
扶養親族の人数:プラス2人
扶養親族をそのままの数ではなく、「プラス2人」とするのは以下の場合です。
- 本人や配偶者または生計を一にする親族が、特別障害者に該当する配偶者・扶養親族と同居する場合
特別障害者とは、重度の障害を持つ障害者であって、常時介護が必要な者等が該当します。同居特別障害者とは、特別障害者に該当する扶養親族であって、給与所得者等と同居する者を指します。また、これらの者に該当するかどうかは、扶養控除等申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄で確認可能です。
参考:令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
扶養の人数変更で所得税はいつから変わる
扶養する親族等の人数は、年度途中でも変化する可能性があります。年度の途中で離婚した場合や、子供が独立した場合などが該当するでしょう。扶養人数は源泉所得税の額に影響するため、人数の変更は月々の給与に対しても影響があります。
いつから扶養人数を変更すべきかについて、法律などによる特定の決まりはありません。年末調整において、金額の調整を行えばよいことになります。所得税の扶養控除の対象とするためには、その年の12月末日時点において、扶養に含まれる者であることが必要です。年末調整のタイミングで扶養人数の変更を反映できていれば、その年における扶養控除の計算に反映が可能なためです。
ただし、扶養人数の減少があった場合、月々の源泉所得税額を低額のままにしておくと、年末調整において給与から大きな金額を差し引く必要があります。扶養人数が変更されることが確実な場合は、できる限り早い時点で源泉所得税額に反映させておいたほうがよいでしょう。
扶養の人数変更にはマネーフォワード クラウド給与で対応
扶養人数の変更は、給与計算に大きな影響を与えます。給与は従業員の生活に直結する非常に重要な労働条件であり、その額に誤りなどがあってはなりません。誤りなどがあれば、従業員の業務に対するモチベーションが低下し、最悪の場合には離職を選択してしまう場合もあります。しかし、扶養人数の計算や扶養の対象となる条件を把握するのは難しく、知識や経験がなければ、なかなか上手く管理できないでしょう。そのような場合には、クラウド型の給与計算ソフトの導入がおすすめです。
「マネーフォワード クラウド給与」は、子どもの年齢を考慮し、自動で源泉所得税の額を計算する便利な機能を備えています。子どもの生年月日を登録しておけば、扶養の対象となるかどうかの判断はソフト側が自動で行います。扶養の人数変更に悩んでいる方は、ぜひ「マネーフォワード クラウド給与」の導入をご検討ください。
参考:無料で試せる給与計算ソフト – マネーフォワード クラウド給与|マネーフォワード クラウド給与
扶養人数の影響を理解して正しく給与計算しよう
扶養人数は、源泉所得税の計算に大きな影響を与える要素であり、正確に把握しなければなりません。しかし、扶養の条件や人数の数え方などは、正確な知識がなければ難しいものです。当記事の解説を参考に、扶養についての理解を深めるとともに、効率化を図れる給与計算ソフトの導入も併せてご検討ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
福利厚生費として社宅の費用を計上する条件とは
社宅制度に興味がある方のなかには、社宅費用を福利厚生費として計上するための条件が気になっている人も多いでしょう。 本記事では、福利厚生費の基礎知識のほか、法定外福利費の実態調査、社宅の家賃を福利厚生費として計上するための条件などを解説します…
詳しくみる給与明細の控除項目とは?計算から記載方法まで解説
給与明細にはさまざまな支給項目や控除項目があります。支給項目は、雇用契約書や労働条件通知書に記載の賃金や手当ですので分かりやすいと思います。しかし、控除項目は、「どうしてこの金額が控除されるのか?」と疑問を持つことがあるのではないでしょうか…
詳しくみる現物給与とは?具体例や価額、課税の有無について分かりやすく解説!
現物給与にはどのようなものがあり、その価額がどのように決められているのかをご存知でしょうか。一般的には社員の給料は現金で支払いますが、食事、通勤定期券、住宅の提供など、現金以外のものを現物で支給することもできます。 現物給与の種類や価額、課…
詳しくみる青色事業専従者に給与明細は必要?テンプレートをもとに書き方を解説
青色事業専従者に給与明細の発行義務はありませんが、税務署への説明責任や正確な給与管理を考えると、発行するのがおすすめです。 給与明細を作成すれば、経費計上の証拠となり、税務調査の際にも信頼性が高まります。 本記事では、青色事業専従者の給与明…
詳しくみる給与テーブルとは?作り方やメリット・デメリット、注意点を解説
給与テーブルとは、賃金を決めるときに基準になる表のことです。新人からベテランまでの賃金を一覧できるため、人件費の把握や予測に役立ちます。給与テーブルの作り方には、会社の方針や賃金決定の際に重視する事項などが表れるものです。 本記事では、給与…
詳しくみる障害者雇用の給料は低い?平均給料や減額の特例について解説!
障害者雇用の労働者の給料は、一般雇用の労働者と比べ低いと言われています。 本記事では、障害者雇用の労働者の給料の現状、給料の水準が低い理由、給料の決め方などについて解説します。障害者雇用の労働者の給料に関するこれらの情報を踏まえ、意欲や能力…
詳しくみる