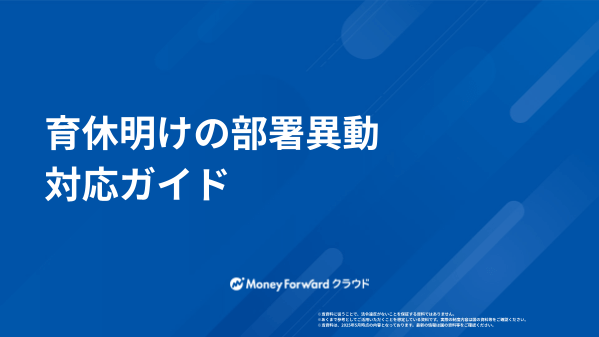- 更新日 : 2025年5月21日
育休明けの部署異動がしんどい!その理由と対処法を解説
育休明けに「元の部署には戻れない」と言われると、不安や戸惑いを感じる方が多いのではないでしょうか。この記事では、育休明けの部署異動がしんどい理由や乗り切るためのポイントを解説します。育休明けの部署異動について人事側が配慮すべきことも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
育休明けは元の部署に戻れない?
まずは、育休明けに元の部署へ戻ることが難しくなる理由について解説します。
本人の業務負荷を考慮した場合
育児と仕事の両立を考えたとき、業務負荷が比較的軽い部署への異動を提案されることもあります。会社なりに配慮した結果ではあるものの、本人の希望や将来のキャリアと合わない場合はしんどいと感じる原因になります。
人員配置の見直しがあった場合
育休中に社内の組織編成や配置転換が行われており、戻るはずのポジションが埋まってしまうケースです。特に育休期間が長期に及ぶ場合は、業務の継続を優先して新たな担当者が決まっていることもあります。
会社全体の人事異動があった場合
年度末などの大きな節目に合わせて広範囲の人事異動が行われることがあります。育休明けのタイミングと人事異動の時期が重なると、もとの部署に戻れない可能性があります。
育休明けの部署異動がしんどい理由は?
育休から復帰した直後は、生活リズムが変化しやすい時期でもあるため、部署異動の負担が大きく感じる場合があります。なぜしんどいと感じるのか、主な理由を詳しく見ていきましょう。
新しい環境に慣れるまで負担がかかる
部署が変わると、日々の仕事の進め方やコミュニケーションの取り方、職場の雰囲気などが一気に変わる可能性があります。例えば、新しい分野や役割を担う場合、育児で忙しいなかでも業務内容をキャッチアップしなければなりません。また、職場のメンバーが変われば、コミュニケーションの方法も変わります。一度は育休前の部署で築き上げた人間関係をリセットすることになるため、心理的な負荷がかかります。
通勤時間やスケジュールが変化する
異動に伴い、勤務地や通勤経路が大きく変わることがあります。育児中は保育園の送迎や子どもの体調不良への対応など、時間管理がシビアになるため、以下のようなデメリットが生じやすいです。
- 送迎時間の調整が難しくなる
保育園や学童までの距離が遠いと、送迎だけで体力や時間を消耗します。業務開始時間に遅れないか、迎えの時間に間に合うかなど、常に気を配る必要があります。 - 家事や育児の時間が少なくなる
通勤時間が長い分、家庭で過ごせる時間が減ります。その結果、家事・育児と仕事を両立する負担が増え、しんどいと感じやすくなるのです。
周囲からの理解やサポートが不足している
部署によっては、子育て中の社員をサポートする体制が十分に整っていないこともあります。以下のような状況に直面すると、働きにくいと感じるかもしれません。
- 育児と仕事を両立するための配慮がない
時短勤務やリモートワークなどを希望しても、「前例が少ない」「部署の仕事柄難しい」などの理由から却下される場合があります。 - 家庭の事情を理解されにくい
保育園の呼び出しで急に帰らなければならないなど、想定外の休暇が必要になるケースがあります。
キャリアへの不安でモチベーションが低下する
以前の部署で培ったスキルやキャリアが十分に活かされない場合は、「キャリアがリセットされたのでは」と思うこともあります。さらに、復帰してすぐの異動ではどのように評価されるかが見通せないため、不安を感じる方が多いでしょう。中長期的に見て、キャリアアップできるかどうかをイメージしづらいと、モチベーションが維持しにくくなります。
育休明けの部署異動を乗り切るポイント
育休明けに新しい部署でスタートを切ることは、期待と同時に不安も大きいものです。慣れない環境で戸惑うこともあるかもしれませんが、しっかりと準備や相談を行えば、少しずつ負担を減らしながら成長していくことができます。ここでは、具体的な対処法やアドバイスをいくつか紹介します。
上司や人事担当とコミュニケーションをとる
まずは、上司や人事担当とコミュニケーションをとることが大切です。部署異動に関して不安を抱えている場合は、早めに上司や人事担当へ相談し、自分の希望や状況を率直に伝えましょう。異動後の仕事内容や期待される役割を把握しておくと、必要なスキルや時間の使い方もイメージしやすくなります。
自分のメンタル面を大切にする
育児と仕事を同時にこなすことで、知らないうちにストレスがたまりやすくなります。頑張りすぎず、心の健康を保つ工夫も忘れないようにしましょう。例えば、大きな目標を掲げるだけでなく、日々の小さな達成を認めてあげることがモチベーション維持につながります。定期的な息抜きや休息も忘れないようにしましょう。カウンセリングや産業医など、メンタルヘルスをサポートしてくれる機関を頼るのも有効です。
周囲のサポートを上手く活用する
しんどいと感じたときは、遠慮せず周囲のサポートを得ることも大切です。自分一人で抱え込まず、職場や家族、友人などとの連携を図りましょう。例えば、家庭内での役割分担を見直すことで、負担を分散できます。また、すでに子育てと仕事を両立している同僚や先輩の意見は、参考になることが多いです。具体的な方法や心構えを聞くことで安心感が得られます。自治体の子育て相談やキャリアカウンセリングなど外部サービスを利用する方法もあります。
育休明けの部署異動は違法ではない?
育休から復帰したタイミングで部署異動があると、「違法性はないの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。ここでは、部署異動の法的な観点を解説します。
法律上、同じ部署へ復帰させる義務はない
結論からいえば、法律上「必ず元の部署へ復帰させなければならない」という規定はありません。ただし、説明が不十分なまま異動が強行すると、トラブルやモチベーション低下につながる可能性があります。業務上の必要性が合理的に説明できることが望ましいです。
法律で定められた「不利益取扱いの禁止」
育児休業を取得した労働者に対しては、下記のように不利益な扱いをしてはいけないことが法律で定められています。
- 育児・介護休業法
育児休業の取得を理由に、解雇や降格、減給などの不利益取扱いをすることは禁じられています。部署異動の場合も、実質的に条件が著しく悪化するような異動であれば問題になる可能性があります。 - 男女雇用機会均等法
性別や妊娠・出産を理由とした差別的な扱いが禁じられています。妊娠・出産関連で保護される範囲は広く、育児休業後の復帰においても同様に配慮が求められます。
違法性が疑われる具体的なケース
部署異動が直ちに違法となるわけではありませんが、次のような事例は違法性を疑う余地があります。
- 大幅な賃金ダウンや降格を伴う異動
育休取得を理由に、明らかに立場や給料が不当なほど下がる部署への配属が行われた場合、不利益取扱いに該当するとみなされる可能性があります。 - 本人の意思を無視した配置転換
子どもの保育園が決まっているにもかかわらず、極端に遠方の事業所への転勤が命じられるなど、実質的に仕事と育児の両立が困難になるケースは不当とされることがあります。 - 異動による退職の誘導や強要
「異動先に行けないなら辞めてもらうしかない」などと退職を迫る場合も、違法行為やパワハラと判断されることがあります。
異動の違法性を相談できる窓口
育休明けの部署異動に対して「これは違法かもしれない」「納得できない」と思った場合は、まずは会社の人事部や上司に異動理由や条件について詳細な説明を求めてみましょう。それでもなお不安が解消されない場合、次のような機関への相談も検討してみてください。
- 労働基準監督署
労働基準法や育児・介護休業法などに関してアドバイスを受けられます。違法行為が疑われる場合の相談先として有効です。 - 各地方自治体の総合労働相談コーナー
労働条件や職場環境の問題を気軽に相談できる窓口が設けられています。弁護士による無料相談ができる場合もあります。 - 労働組合や労働組合連合会
会社に労働組合がある場合は、早めに相談することで解決を図れるケースもあります。未加入の場合でも、外部の労働組合がサポートしてくれることがあります。
育休明けに元の部署に戻りたい場合のアプローチ
「元の部署で引き続きスキルを磨きたい」「部署異動がしんどいので、なるべく戻してほしい」という希望がある場合は、早めに行動することが大切です。以下のアクションを検討してみてください。
社内制度や規定を確認する
会社によっては、復帰後の配置転換に関するガイドラインや、相談窓口を設けていることがあります。知らないだけで利用できる制度があるかもしれませんので、就業規則や社内ポータルなどをしっかり確認してみましょう。
希望の理由を明確に伝える
キャリアパスの継続や通勤時間や業務負荷のバランスなど、具体的な根拠とともに元の部署を希望する旨を上司や人事担当へ話してみましょう。感情論だけでなく、数字や事実を交えて話すと理解を得やすくなります。
自分の適正やスキルの活かし方を考える
もし「異動は避けられない」とわかった場合、新たな部署で活かせるスキルや経験を洗い出し、前向きに取り組む方法を考えるのも一つです。長期的なキャリア形成を視野に入れ、柔軟に行動することで、結果的にプラスに転じることもあります。
育休明けの部署異動について人事側が配慮すべきこと
育休明けの従業員が新しい環境にスムーズに馴染めるかどうかは、会社側の受け入れ体制に大きく左右されます。人事担当者としては、法律で定められたルールを守るだけでなく、従業員が安心して復帰し、活躍できるように配慮を行うことが求められます。ここでは具体的にどのような点を意識するとよいかをまとめました。
従業員との話し合いの場を設ける
育休明けの部署異動で重要になるのが、従業員との十分な話し合いです。以下のような取り組みを行うことで、復帰後の不安を軽減しやすくなります。
- 異動理由と業務内容を明確化する
業務上の必要性や期待する役割を説明し、従業員が納得できる形で異動を進めると、モチベーションの低下を防げます。 - 今後のキャリアを相談する機会を提供する
従業員が「将来的にどう成長できるのか」をイメージできると、新部署での役割に前向きになりやすいです。目標設定や評価基準をわかりやすく示すとよいでしょう。
人事評価の透明性を高める
育児休業からの復帰後に、不当に給与やポジションが下がるといった扱いは法律で禁止されています。人事評価の透明性を高め、基準を公開しておくと不当な評価の疑いを回避できます。そして、業務上の正当性や組織戦略による配置転換であることを本人にも理解してもらえるよう説明しましょう。
仕事と育児を両立できる人事制度を設計する
育休から復帰したばかりの従業員は、子どもの生活リズムや体調などに左右され、突発的に休む必要が生じる場合があります。そうした状況を想定し、企業として柔軟に対応できる制度を整備しておくことが大切です。例えば、時短勤務やフレックスタイム制度を整備すると、無理なく業務を続けることができます。業務内容によっては、オフィスに通わなくても十分対応できるケースがあります。在宅勤務などリモート対応も検討しましょう。
職場全体でのサポート体制の強化
育休明けの従業員を支えるためには、上司や同僚の理解と協力が欠かせません。異動後しばらくは、定期的な面談やフォローアップを実施し、必要に応じて業務量の調整や追加サポートを検討しましょう。また、育児中も職場の情報を共有する仕組みがあると安心して業務に取り組めます。
会社と話し合い、納得感のある職場復帰を目指しましょう
育休明けの部署異動は、業務内容の変化や生活リズムへの影響、サポート体制の差など、さまざまな要因が重なってしんどいと感じることがあります。人によってはなかなか周囲に相談できない場合もありますが、一人で悩みを抱え込むと精神的な負担が大きくなってしまいます。必要なサポートや情報を得ながら、前向きに対処していくことが大切です。会社とコミュニケーションを取りながら、納得感のある形で復帰できれば、子育てと仕事を両立しながら成長するチャンスにつながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
リクルーターとは?役割や選定基準、制度の導入方法、企業事例を解説
リクルーターとは、主に現場で業務にあたる社員が採用活動を行う採用活動です。求職者に直接アプローチして面談を実施し、コミュニケーションを取りながら自社の魅力を伝える活動を行います。 本記事ではリクルーターの概要や役割、制度のメリットやデメリッ…
詳しくみる休職中に有給消化はできる?休職中にもらえる傷病手当や保険金も紹介
休職中は労働が免除されているため、有給は消化できません。有給は労働の義務があるときに消化できます。 ただ「休職中に有給の時効が来たら?」「休職終了後は有給を消化できる?」などと疑問に思う人もいるでしょう。そこで本記事では、休職中や休職終了後…
詳しくみるデジタル人材とは?職種や必要スキル、人材育成・採用ポイントを解説
デジタル人材とは、AIなどの最新技術に精通したDX推進を担う人材を指します。企業の成長のため、社内体制の刷新やビジネスモデルの変革、新しいサービスの開発などに携わります。 市場変化の激しい現代において、自社のサービスを理解したうえでDXを推…
詳しくみる外国人労働者が増加している理由とは?企業側のメリットも紹介
日本で外国人労働者がなぜ増えているのか疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では日本で外国人労働者の数や増加している理由を解説します。また、これから外国人労働者の雇用を検討している企業向けに、メリットや注意点なども解説します。 外国人労働者…
詳しくみる改正障害者総合支援法とは?改正による事業者への影響まで解説
障害者総合支援法等の障害者支援関連の法律が、2022年4月、厚生労働省により改正が決定され、2024年4月(一部は2023年4月ないし10月)から施行されます。障害者総合支援法とはどのような内容の法律か、改正によって変わるポイントをまとめま…
詳しくみるダイアローグとは?意味や実施方法を解説!
ダイアローグとは、単なる情報交換にとどまらずに相互理解を通じて意識や行動の変化を引き出し合う創造的コミュニケーション手法です。チーム内のコミュニケーションの質を高め、パフォーマンスを向上させるものであり、昨今注目されています。この記事ではダ…
詳しくみる