- 更新日 : 2025年6月10日
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の記入・申請方法
高年齢者及び障害者雇用状況報告書は、毎年7月15日までに対象企業からハローワーク宛てに提出するものです。未提出や虚偽の報告をした場合、企業名を公表されたり罰金の対象となったりすることもあり、人事・労務担当者にとっては必須の手続きです。
そこで今回の記事では「高年齢者及び障害者雇用状況報告書」の目的をはじめ、記入・申請方法なども解説します。
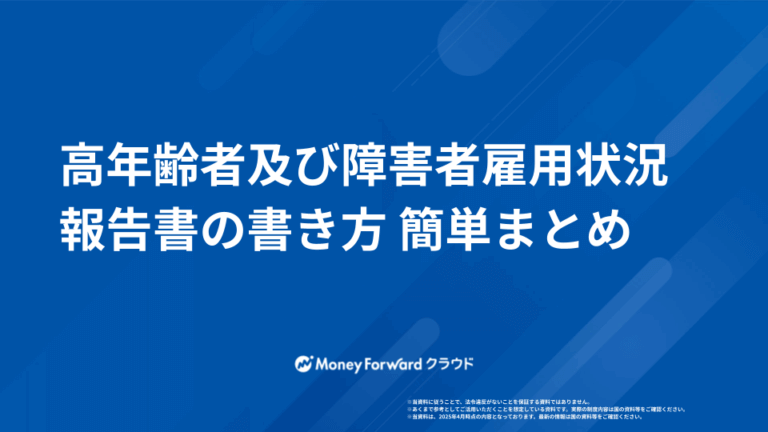
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の書き方
「高年齢者雇用状況報告書 記入例」「障害者雇用状況報告書 提出期限」などで検索された方向けに、無料で提供しています。ぜひご自由にダウンロードしてご活用ください。
目次
高年齢者及び障害者雇用状況報告書とは?
高年齢者及び障害者雇用状況報告書とは、就業困難な高齢者や障害者の雇用状況の確認や有効な雇用対策づくりなどを目的として設けられました。毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用に関する状況を報告するものです。
高年齢者雇用状況報告書
高年齢者雇用状況報告書は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」で義務づけられた報告です。
| 主な目的 | 高年齢者の雇用状況と高年齢者雇用制度の導入状況の確認 |
| 対象企業 | 常用労働者 (※1)が31人以上の企業 |
| 主な内容 | 高年齢者雇用確保措置(※2)と、66歳以上まで働ける制度等の状況 など |
(※1)1年以上継続雇用予定の1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
(※2)65歳までの安定した雇用を確保するための措置(定年引上げ等)
障害者雇用状況報告書
障害者雇用状況報告書は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法) 」で義務づけられた報告です。
| 主な目的 | 障害者の雇用状況と、障害者雇用率(※)の達成状況の確認 |
| 対象企業 | 常用労働者が45.5人以上の企業(独立行政法人、公団などは40人以上) |
| 主な内容 | 常用労働者数、雇用する障害者数、障害者雇用率の達成状況など |
(※)労働者に占める障害者の割合
高年齢者雇用状況報告書の記入方法と注意点
高年齢者雇用状況報告書の主な記入方法と注意点は下記の通りです。
定年制の状況
まず、「7.定年」欄に、定年の有無や定年年齢を記入します。「定年あり」とは、就業規則に定年について記載されている状況をいいます。
次に「8.定年の改定予定等」欄に改定予定の有無と予定年月日を記入します。
定年がない場合は、以降の「継続雇用制度の状況」「66歳以上まで働ける制度等の状況」の記入は不要です。理由は、報告の目的である65歳まで、あるいは66歳以降の雇用が確保されていると判断できるからです。

継続雇用制度の状況
定年制と同様に、「9.継続雇用制度」と「10.継続雇用制度の導入・改定予定」を記入します。継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を対象とすることが求められていますが、一定の基準を設けている場合は、現状通りに報告しましょう。
「9.継続雇用制度」で「(注)」として記載されている内容については、平成25年3月末までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めた事業主以外は該当しません。
また、前述の定年がない場合と同様の理由で、継続雇用が66歳以降まで続く場合は「11.66歳以上まで働ける制度等の状況」の記入は不要です。

66歳以上まで働ける制度等の状況
平成30年度から「11.66歳以上まで働ける制度等の状況」が報告項目に加わりました。従来は65歳までの雇用確保を目的としていましたが、高齢化の進展や労働人口の減少などにより、政府は希望する人が70歳まで働ける環境づくりをスタートさせています。

常用労働者数と離職者数
「12.常用労働者数(うち女性)」は、6月1日現在の状況を年齢別で記載し、「13.過去1年間の離職者の状況(うち女性)」は、過去1年間の状況を記載します。
離職者数は、離職者全員の人数ではなく「解雇等による45歳以上65歳未満の離職者数」を記載します。「解雇等」とは、下記理由によるものです。
- 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)
- 継続雇用制度の対象者の基準に該当しなかったことによる退職
- その他事業主の都合による退職
つまり、自身の希望に反して離職した可能性が高い人について報告するよう求めています。

過去1年間の定年到達者等の状況
「14.過去1年間の定年到達者等の状況(うち女性)」は、前述の7~11で報告した高齢者雇用に関する制度を、定年した人や継続雇用が終了した人が実際に利用しているかどうかを報告するものです。高齢者雇用に関する諸制度が、有効に機能しているかを検証する材料のひとつといえるでしょう。

障害者雇用状況報告書の記入方法と注意点
障害者状況報告書の主な目的は、前述の通り、障害者の雇用状況と障害者雇用率の達成状況の把握です。雇用率の計算に使う労働者数と障害者数の定義は複雑なので、注意が必要です。
法定雇用率と実雇用率
従業員が45.5人以上の企業は、従業員に占める障害者の割合を一定以上にする義務があります。この割合を「法定雇用率 」といい、民間企業は2.2%と定められています。つまり、従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければならない、ということです。
義務である法定雇用率に対し、企業ごとの現状を算出したのが「実雇用率」です。実雇用率が法定雇用率を上回れば義務を果たしたことになり「障害者雇用調整金」を受給できる可能性があります。逆に、下回ってしまうと「障害者雇用納付金」を支払わなければならない場合もあります。
労働者数と除外率
実雇用率を計算するにあたって基礎となる労働者数は、次の計算式で算出します。
「除外率」は業種ごとに定められていて、建設業は20%、金属鉱業は40%など、危険率が高い業種ほど高く設定されています。逆に危険率の低い業種には除外率の設定はありません。
また、常用労働者数を算出する際、短時間労働者(1週間の労働時間が30時間未満)は0.5人として計算し、1週間の労働時間が20時間未満の労働者はカウントしませんので気をつけましょう。

実際に報告書を記入する際は、まず事業所ごとに「7.除外率」を確認します。そして「8.常用労働者の数」項目の「(イ)常用労働者の数(短時間労働者を除く)」と「(ロ)短時間労働者の数」を記入すれば、「(ハ)常用雇用労働者の数」と「(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」は簡単に計算できます。
実雇用率の計算基礎となる障害者数
障害者雇用促進法では身体障害者や知的障害者の雇用を義務づけていますが、精神障害者保健福祉手帳の所有者も障害者とみなして報告します。
労働者数の計算と同様に、短時間労働者を0.5人で計算するほか、重度身体障害者と重度知的障害者は2人として計算するなどして、実雇用率の計算基礎となる障害者数「10.計」を算出します。
実雇用率と障害者雇用の不足数
「11.実雇用率」は、前述の「8.(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」を分母、実雇用率の計算基礎となる障害者数「10.計」を分子として計算します。
最後に、法定雇用率で義務づけられた障害者雇用数と実際の雇用数を比較して、「12.身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」を算出します。

報告書の提出は電子申請も可能
高年齢者及び障害者雇用状況報告書の提出先は、最寄りのハローワークです。持参、郵送のどちらでも受け付けています。
電子申請による報告
高年齢者及び障害者雇用状況報告書は、電子申請もできます。e-Gov電子申請システムを使うとハローワークに行かなくても手続きが完了します。
e-Gov電子申請システム 高年齢者雇用状況報告
e-Gov電子申請システム 障害者雇用状況報告書
まとめ
高年齢者及び障害者雇用状況報告書は、法律で提出が義務づけられているので、ハローワークから案内があった企業は報告が必要です。
高年齢者雇用の重点は、65歳までの雇用確保から希望すれば66歳以上も働ける環境づくりに変化してきました。また、障害者雇用は、企業が法定雇用率を達成することを強く求めています。報告書の提出はもちろんですが、企業は、報告を機に高年齢者や障害者の雇用維持・拡大をすすめることが期待されています。
【参考】
厚生労働省 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
厚生労働省 高年齢者及び障害者雇用状況報告 記入要領
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
障害者雇用の関連記事
新着記事
再雇用制度の就業規則の記載例!ルールの決め方や変更手続きも解説
高年齢者の雇用確保が求められる中、再雇用制度の整備は企業にとって重要な課題です。就業規則において再雇用制度を明確に定めることで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、円滑な人事運営が可能となります。本記事では、再雇用制度の就業規則への記載方法や注…
詳しくみる60歳再雇用は何歳まで?更新や拒否、無期転換、給与や規則の決め方まとめ!
60歳で定年を迎えた後も働きたいと考える人が増えていますが、再雇用の給与や契約更新、就業規則など不安や疑問も多いものです。本記事では、再雇用制度の基本から、給与の決まり方、更新や拒否のルールまで、企業と働く側の両視点でわかりやすく解説します…
詳しくみる60歳以上の高齢者雇用の助成金や給付金、支援、手続きまとめ
人手不足が深刻化する中、60歳以上の高齢者を積極的に雇用する企業が増えています。こうした取り組みに対して、国や自治体は助成金を支給し企業を支援しています。高齢者雇用助成金は、60歳以上の雇用に対して一定の条件を満たすことで受け取ることができ…
詳しくみる退職者への源泉徴収票の発行はどうする?再発行の対応や注意点を解説
退職者への源泉徴収票の発行は、企業が必ず対応すべき重要な法定業務のひとつです。これは退職者が確定申告や転職先での年末調整を行う際に必要不可欠な書類であり、正確かつ期限内に交付しなければなりません。発行手続きには給与情報の集計や送付方法の確認…
詳しくみる再雇用で活用できる助成金や給付金とは?シニアの支援、手続きまとめ
60歳以上の再雇用や継続雇用を支援するため、企業や個人が活用できる助成金や給付金制度があります。人手不足が深刻化する今、高齢者の雇用を促進するための支援策を知り、適切に活用していきましょう。この記事では、助成金の種類、条件、手続き、金額、注…
詳しくみる給与計算における日割りの端数処理のやり方!欠勤・遅刻・早退時の計算例まとめ
給与計算では、日割り計算や端数処理が必要になる場面が多くあります。例えば、入社日や退職日が月の途中、欠勤や時給制社員の勤務日数が変動する場合などです。基本給や手当の一部に小数点以下の金額が生じた際、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のどれ…
詳しくみる