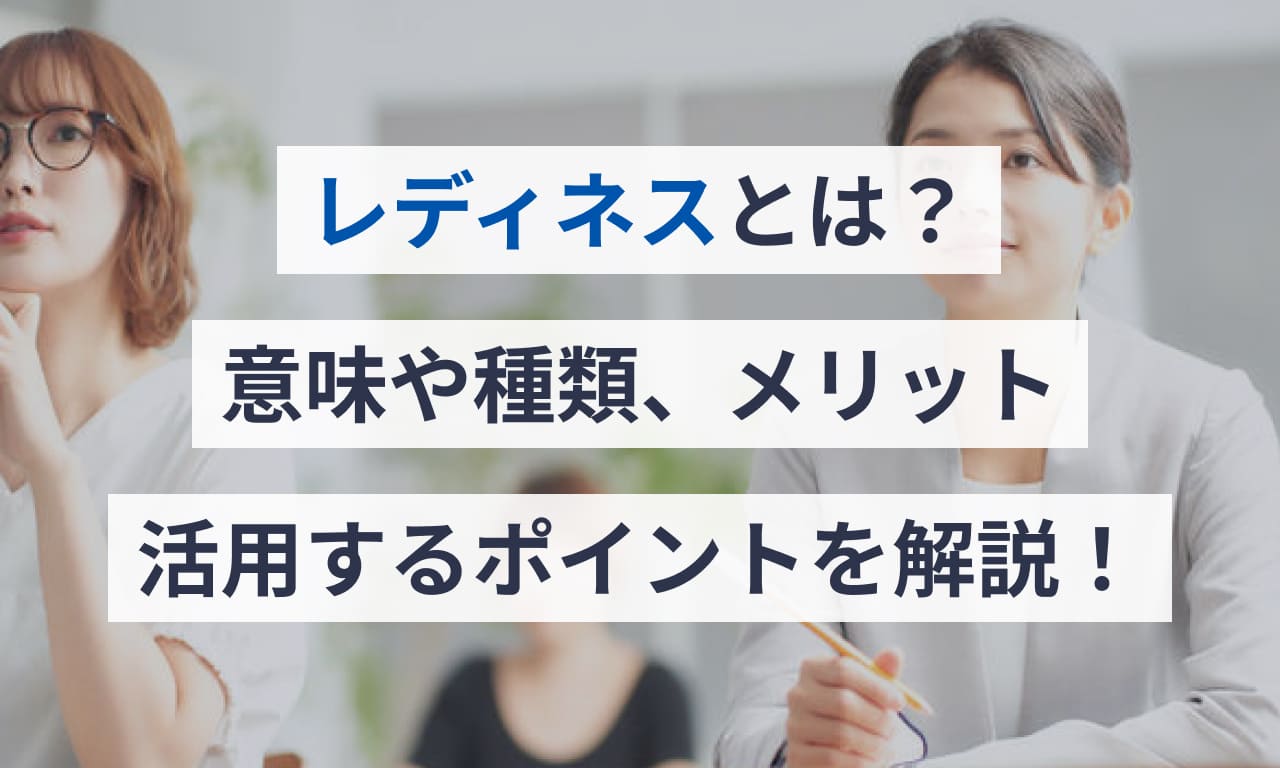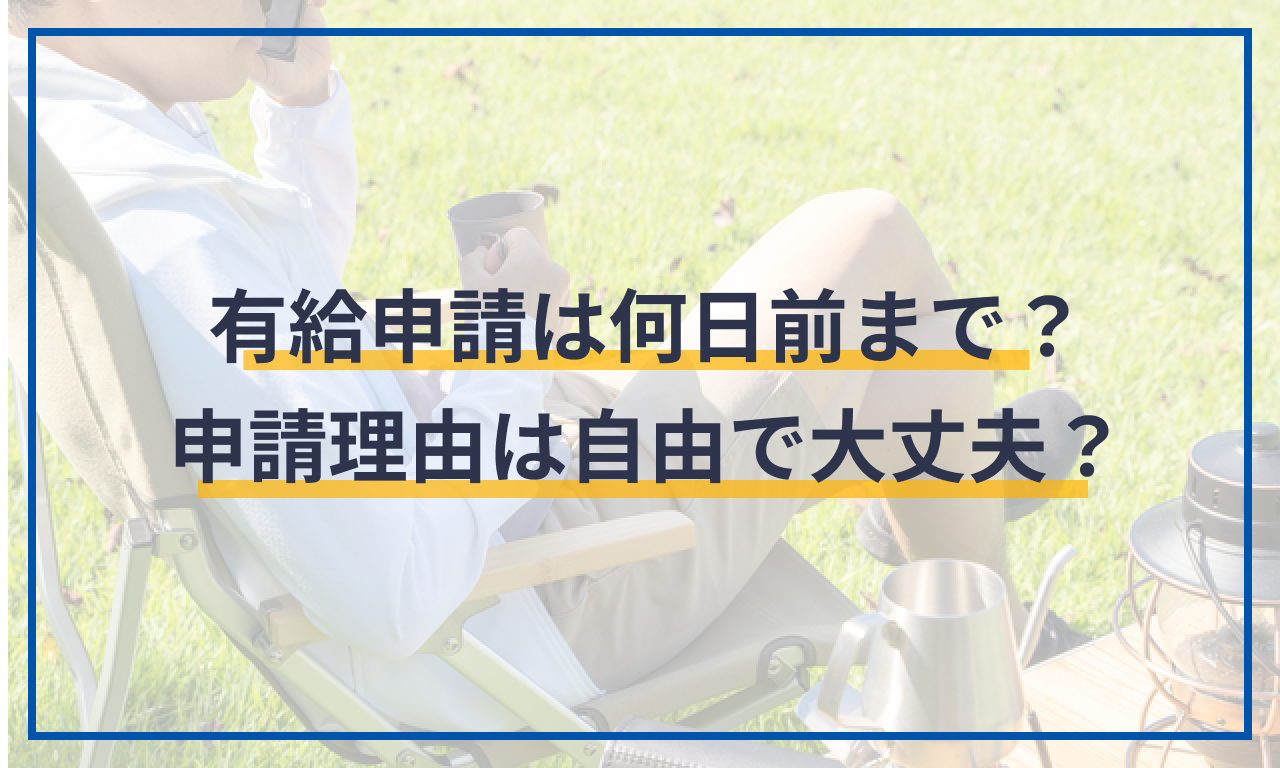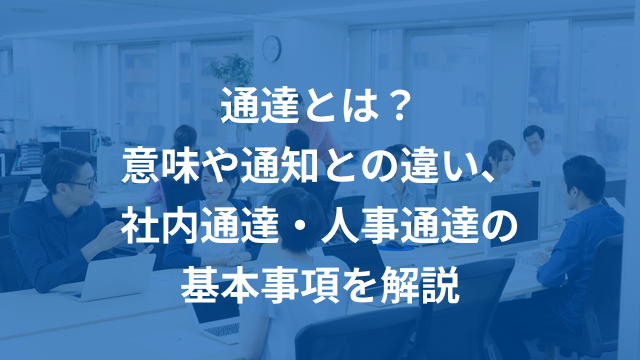- 作成日 : 2022年8月26日
アルバイト・パートでも有給休暇を取れる – 拒否された場合は?
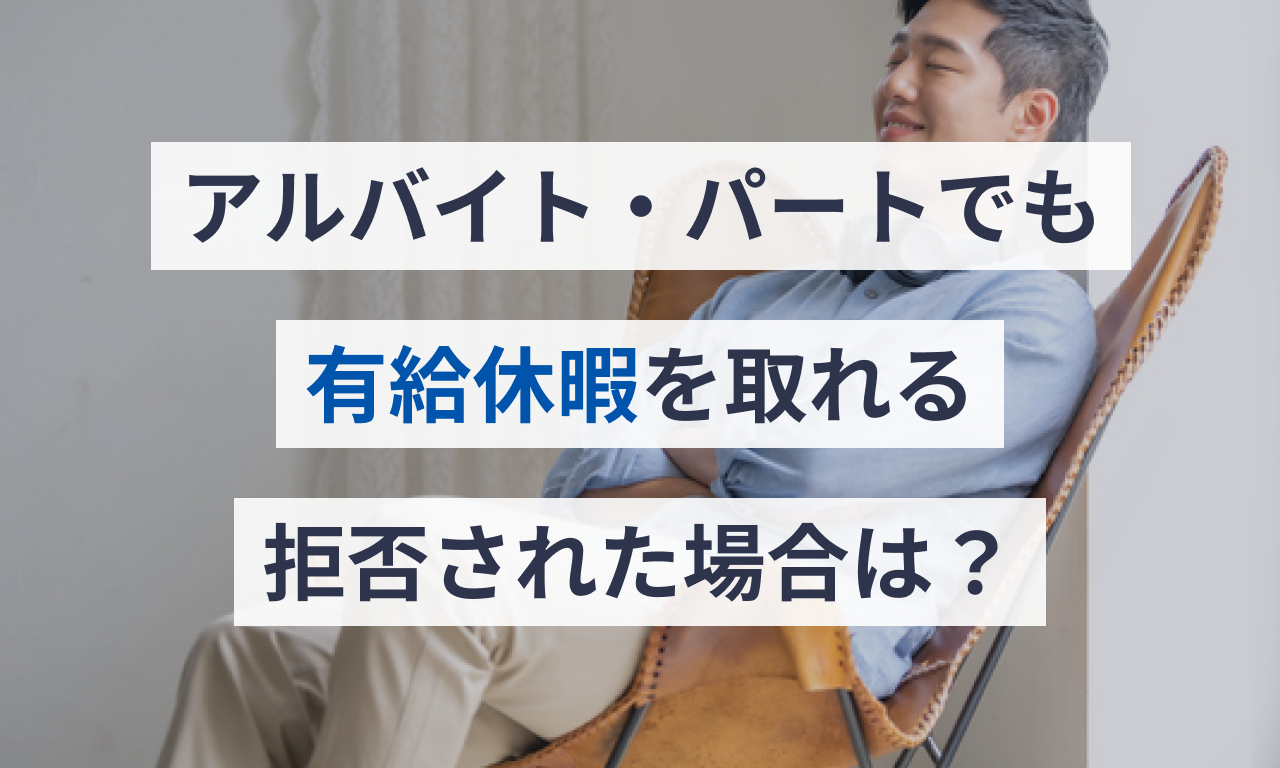
アルバイトやパートで働いている人でも、条件を満たしていれば有給休暇を取ることが可能です。
ここでは、アルバイト・パートの人が有給休暇をもらえる条件や日数について解説します。また、「勤務先から有給休暇の取得を拒否された」「有給休暇の日数を教えてもらえない」といったトラブルへの対処法もあわせて紹介します。
目次
アルバイト・パートが有給休暇をもらえる条件は?
アルバイトやパートで働いている人であっても、一定の条件を満たしている場合には、有給休暇を取れるようになります。アルバイト・パートの人が有給休暇をもらえる条件は、大きく分けて2つです。ここでは、それぞれの条件の詳細を解説します。
入社してから半年以上、継続して勤務している
1つ目の条件は、入社日(雇い入れ日)から6ヶ月以上、継続して勤務していることです。
また、試用期間を経て本採用された場合は、試用期間も含みます。例えば、試用期間が3ヶ月の場合は、本採用3ヶ月後に有給休暇が付与されます。
正確な入社日がわからない場合には勤務先に問い合わせるか、雇用契約書などを確認してください。
所定労働日の8割以上に出勤している
2つ目の条件は、雇用契約書などで定められている所定労働日のうち、8割以上に出勤していることです。
所定労働日とは労働者が働くべき日数を指します。例えば半年間の所定労働日が100日の場合には、80日間出勤すれば有給休暇がもらえることになります。
なお、遅刻や早退、産休・育休で出勤しなかった期間も出勤日にカウントされます。
アルバイト・パートが有給休暇をもらえる日数と計算方法
前述の条件を満たしているアルバイト・パートの人は、どれくらいの日数の有給休暇をもらえるのでしょうか。ここでは、もらえる有給休暇の日数と、その計算方法について解説します。
前提として、もらえる有給休暇の日数は、会社ごとの規定によって決まります。そのため、以下で挙げるのは、労働基準法で定められている最小の付与日数です。
有給休暇の日数の計算方法は、「勤務しているのが週5日または週30時間以上の人」と「週4日以下の人」で異なります。また、途中で労働条件が変わった場合は有給休暇付与日の労働条件によって決まります。それぞれの詳細を見ていきましょう。
週5日または週30時間以上の人
週5日または週30時間以上、または年間217日以上勤務している人は、正社員のようなフルタイム労働者と同じ基準で有給休暇の日数を計算します。
もらえる有給休暇の日数は、継続して勤務している年数によって変動します。継続勤務6ヶ月で10日の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに日数が追加されていきます。

法律で定められている有給休暇付与日数の上限は20日であるため、原則6年半勤務した時点で、1年間にもらえる有給休暇の日数が最大になります。
週4日以下の人
勤務しているのが週4以下かつ30時間未満の人は、継続勤務年数と所定労働日の数に応じて、もらえる有給休暇の日数を計算します。

例えば1年半の間、週に3日(または年に121日から168日)出勤している人では、もらえる有給休暇は6日です。
アルバイト・パートの方で有給休暇に関する注意点と対処法
有給休暇の取得は、法律で定められている労働者の権利です。しかし勤務先によっては、有給休暇を取るのを拒否されたり、そもそも有給休暇があること自体を教えてもらえなかったりするケースも考えられます。
ここでは、アルバイト・パートの人が有給休暇をとるうえで、ありがちなトラブルとその対処法を解説します。
有給休暇の取得を拒否された
原則として、有給休暇は労働者の好きなタイミングで取れるとされています。保有している有給休暇は、理由や時期を問わず、勤務先へ取得を申し出ることが可能です。
勤務先から有給休暇の取得を拒否されたときには、まず直属の上司にあたる人に、再度取得を申請してみましょう。その際には、有給休暇の取得が法律で認められた権利である旨を伝えると効果的です。
それでも回答が変わらない場合は、所轄の労働基準監督署など、外部の機関に相談するのも一つの方法です。
しかしながら一方で、企業には「時季変更権(時季指定権)」と呼ばれる権利があります。時季変更権は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、労働者が有給休暇を取る時季を事業所側が調整できるとする権利を指します。
強制力はないため必ずしも従う必要はありませんが、「勤務先にも事情がある」という点は押さえておくと良いでしょう。
「有給休暇はない」と言われた
勤務先から、「アルバイトやパートに有給休暇はない」と言われた経験がある人もいるかもしれません。しかしここまで解説したとおり、継続して半年以上・所定労働日の8割以上に勤務している場合には、アルバイト・パートでも有給休暇が付与されます。
直属の上司が有給休暇について正しく把握していない可能性も考えられるため、こちらのケースでは、勤務先の本部などに問い合わせをしてみることをおすすめします。それでも解決しないときは、労働基準監督署などの外部の機関に相談する選択肢も考慮すると良いでしょう。
有給休暇の日数を教えてくれない
企業は労働者に対して有給休暇を付与する際に、「年次有給休暇管理簿」を作成・保存しなければなりません。
年次有給休暇管理簿は、労働者ごとの有給休暇の保有日数や取得日時が記載されている書類です。つまり、企業は労働者一人ひとりが、どれだけの有給休暇を保有しているのかを把握する義務があります。
有給休暇の日数自体は、労働者自身でも、前述の方法で計算することが可能です。しかし、問い合わせても日数を教えてくれない勤務先の場合には、そもそも有給休暇に対する考え方自体がルーズな可能性も考えられます。
まずは本部などに有給を取得したい旨を伝えたうえで、進展がない場合には労働基準監督署などの外部機関に相談するのも一つの方法です。
仕組みを正しく理解して、有給休暇を活用しよう
有給休暇の取得は、法律で保証された労働者の権利です。アルバイトやパートの人でも条件を満たしていれば有給休暇の取得ができ、原則として勤務先は拒否することができません。
有給休暇の日数や取得する条件といった仕組みを正しく理解しておけば、勤務先とトラブルになったときにも落ち着いて対処することが可能です。また、社内での話し合いで解決しない場合には、労働基準監督署などの外部機関に相談すると良いでしょう。
よくある質問
アルバイト・パートに有給休暇はありますか?
継続して半年以上・所定労働日の8割以上に勤務している人は、アルバイトやパートでも有給休暇が付与されます。詳しくはこちらをご覧ください。
アルバイト・パートが有給休暇をもらえる日数に上限はありますか?
1年間あたり20日が上限です。継続勤務年数と所定労働日数によって、もらえる有給休暇の日数は変動します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。