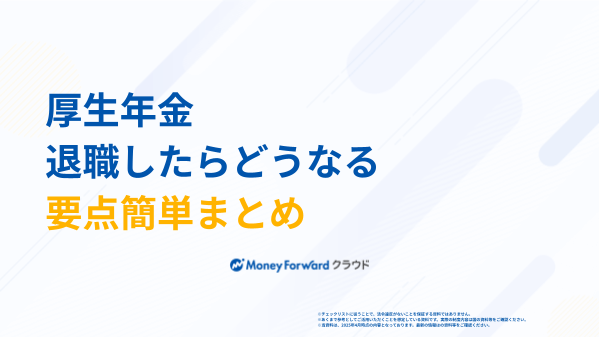- 更新日 : 2025年4月9日
厚生年金は任意継続できる?任意継続のメリットを解説!
厚生年金には任意継続制度がないため、退職後に継続して加入できません。しかし、60歳で定年退職後は国民年金に任意加入が可能です。厚生年金保険料はいつまで払うかというと、最長70歳までですが、受給資格を満たしていない場合は高齢任意加入ができます。この記事では、年金保険における任意加入の概要とメリットを詳しく紹介します。
目次
厚生年金に任意継続はある?
厚生年金には任意継続という制度はないため、退職後に引き続き加入することはできません。厚生年金保険と共に社会保険に分類される健康保険には任意継続制度があるため、退職後2年間に限り継続して加入することが可能です。国民皆保険制度に従い、任意継続被保険者期間が終了したら国民健康保険に切り替えなければなりません。
年金保険についても、日本は国民皆年金制度を採用しているため、全国民に何らかの年金制度への加入が義務付けられています。厚生年金加入者が60歳で定年退職した後は、以下のいずれかの年金制度に加入するのが一般的です。
- 国民年金に加入する(第1号被保険者)
- 引き続き社会保険適用事業所で働き厚生年金に加入する(第2号被保険者)
- 配偶者の厚生年金に扶養加入する(第3号被保険者)
老齢基礎年金の受給が開始となる65歳まで、国民年金に加入することが可能です。これを「任意加入」といいます。また、定年退職後に引き続き社会保険適用事業所で働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することも可能です。70歳時点で老齢年金の受給資格を満たしていない場合、働いている間は要件を満たすまで加入を継続することができます。これを「高齢任意加入」といいます。
ここでは厚生年金と任意加入の概要、任意加入できる条件を紹介します。
そもそも厚生年金とは?
厚生年金とは、会社員や公務員など、会社や組織に雇用されている人が加入する被用者年金です。国民皆年金制度に従い全国民に国民年金への加入が義務付けられているため、厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者でもあります。個人事業主や自営業者、学生や無職の人は第1号被保険者、主婦や主夫など、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者といいます。
厚生年金は被用者年金なので、退職や独立などをした場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。国民皆年金制度に則り、厚生年金の資格喪失後14日以内に国民年金への切り替え手続きを行わなければならないため気を付けましょう。
なお、国民年金は20歳以上60歳未満の全国民に加入が義務付けられていますが、厚生年金の加入開始年齢は定められていません。会社等に就職したタイミングで加入となるため、例えば20歳未満で就職した場合は厚生年金には加入、国民年金には未加入という状態になるため注意が必要です。加入上限については、基本的に70歳までとなります。

任意加入とは?
年金保険の任意加入には、国民年金に任意加入するパターンと厚生年金に高齢任意加入するパターンの2通りあります。一つずつ紹介していきましょう。
国民年金の任意加入
厚生年金の被保険者が60歳で定年を迎えた際、老齢基礎年金の受給資格である10年以上の加入期間を満たしていない場合や、未納期間等により納付済期間が40年に満たないため満額受給できず、年金受給額の増額を希望する場合は、65歳まで国民年金に任意加入することが可能です。
厚生年金の高齢任意加入
定年後引き続き社会保険適用事業所で働き続ける場合は、70歳まで厚生年金に加入することができます。基本的には70歳で資格を喪失しますが、資格喪失時点で老齢年金の受給資格を満たしていない場合は、要件を満たすまで加入を継続することが可能です。これを高齢任意加入といいます。なお、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く70歳以上で、老齢年金における受給資格を満たしていない場合、下記要件を満たすことで、厚生年金保険に任意加入することが可能です。
- 厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること
- 厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣が認可すること
希望する場合には「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出しましょう。
ちなみに、老齢年金の受給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げられてきました。一般的に65歳から老齢年金の支給が開始されますが、定年後も再雇用などで働き続ける場合は、給与をもらいながら年金を受け取ることが可能です。これを在職老齢年金といいます。在職老齢年金受給中は年金支給と厚生年金保険料の納付が並行して行われ、退職後に年金額が再計算されてこの期間に支払った年金を受給することが可能です。ただし、在職老齢年金は給与と年金受給額の合計が47万円を超えると、一部または全額支給停止されるため気を付けましょう。
参考:
な行 任意加入|日本年金機構
か行 高齢任意加入|日本年金機構
厚生年金を任意加入できる条件
国民年金の任意加入と厚生年金の高齢任意加入について紹介しました。ここからは、任意加入するための条件をそれぞれ解説します。
国民年金に任意加入するには、下記の1~5の条件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金を繰り上げ受給していない
- 20歳から60歳までの保険料納付済期間が40年(480ヶ月)未満
- 厚生年金保険または共済組合等に加入していない
- 日本国籍を有しない方で在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方でない
上記に加え、以下に該当する方も任意加入可能です。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
なお、国民年金の加入期間には上限が定められているため、40年(480ヶ月)に達した時点で強制的に任意加入被保険者の資格を喪失します。
厚生年金に高齢任意加入するには、下記の条件を満たす必要があります。
- 老齢年金の受給資格を満たしていない
- 厚生年金保険の被保険者となることについて事業主の同意を得ている
- 厚生年金保険の加入について厚生労働大臣の認可を受けている
高齢任意加入するには「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を所管の年金事務所に提出しなければなりません。なお、保険料は原則全額本人負担ですが、事業主が同意すれば労使折半にすることも可能です。
参考:
任意加入制度|日本年金機構
70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き|日本年金機構
厚生年金を任意加入するメリット
厚生年金には健康保険のような任意継続制度はありませんが、定年退職後は国民年金に任意加入することが可能です。また、老齢年金の受給要件を満たしていないなど、一定の要件を満たした場合、厚生年金の資格を喪失する70歳以降も高齢任意加入することができます。ここでは、それぞれのメリットを紹介します。
国民年金に任意加入するメリット
60歳時点で受給要件を満たしていなかった場合は、任意加入することで受給要件を満たし老齢基礎年金を受け取ることができます。受給要件は満たしているものの未納期間等で満額受給できない場合は、任意加入で老齢基礎年金の受給額を増やすことが可能です。
厚生年金に高齢任意加入するメリット
高齢任意加入は受給要件を満たすまで継続するため、70歳時点で受給要件を満たしていな方が高齢任意加入すれば確実に老齢基礎年金を受け取ることができます。さらに、労使間の合意が得られれば保険料を労使折半することも可能です。
年金に任意加入して確実に老齢年金を受給しよう
年金保険における任意加入制度を紹介しました。厚生年金には健康保険のような任意継続制度がないため、退職後に加入を継続することはできません。しかし、一定の要件を満たした場合、国民年金に任意加入が可能です。任意加入することで、老齢基礎年金が受け取れたり年金受給額を増やしたりできます。また、厚生年金の資格を喪失する70歳時点で老齢年金の受給資格を満たしていない場合は、受給要件を満たすまで高齢任意加入することが可能です。高齢任意加入は受給要件を満たすまで継続するため、確実に老齢年金を受け取れます。この記事を参考に、年金保険の任意加入制度を理解し老後に備えましょう。
よくある質問
厚生年金は任意継続できますか?
任意継続はできませんが、定年退職後は国民年金に任意加入できます。また、厚生年金の資格を喪失する70歳時点で受給資格を満たしていない場合は、高齢任意加入することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金を任意継続するメリットについて教えてください。
年金保険に任意加入することで、確実に老齢年金を受給できます。さらに、未納期間等で満額受給できない場合は、国民年金に任意加入することで老齢基礎年金の受給額を増額することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
雇用保険の給付の種類とそれぞれの受給資格
雇用保険の給付には、失業時にもらえる基本手当(失業保険)のほかにも、さまざまな種類があるのをご存じですか? ここでは、雇用保険の4つの給付の説明と、各給付の主な手当、そしてその受給資格について紹介します。 求職者給付 求職者給付とは、定年や…
詳しくみる社会保険の定時決定・随時改定とは?概要や適用条件、重なる場合の対応を解説
定時決定と随時改定は、従業員の給与にもとづいて標準報酬月額を見直すための制度です。しかし、制度の違いや適用条件を正しく理解していないと、手続きの遅れや誤りにつながり、従業員の保険料負担や企業の信用に影響を与えます。 本記事では、両者の違いや…
詳しくみる労災申請を本人が行うデメリットとは?弁護士に依頼するメリットも解説
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気など万が一のときに労働者を守る大切な制度です。しかし、手続きが複雑だったり、補償内容に制限があったりと、申請者本人には見えにくいデメリットも存在します。本記事では、労災保険の基本的な内容から、本人が申請…
詳しくみる社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!
社会保険労務士の資格は人気の国家資格の1つです。人気の理由は、企業の人事・総務で労働・社会保険の手続き、就業規則の作成、ハラスメント対策などの実務を行うことも、独立して開業することもできることにあります。 今回は、年金問題、働き方改革、ハラ…
詳しくみる労災を使うと会社の信用や責任はどうなる?従業員への不利な扱いも解説
労災(労働災害)が発生した場合、会社は法令に基づく手続きを進める必要がありますが、その対応次第では、社会的信用の低下や法的責任が問われることもあります。一方で、従業員側も「申請すると不利な扱いを受けるのでは」「申請後、職場にいづらくならない…
詳しくみる国民健康保険に扶養はある?加入手続きの注意点も解説
日本は国民皆保険制度を採っているため、全国民に健康保険への加入を義務付けています。退職によって社会保険の資格を喪失した際や、フリーター・アルバイトで親の扶養から外れた場合、自営業の方などは国民健康保険への加入が必要です。この記事では、国民健…
詳しくみる