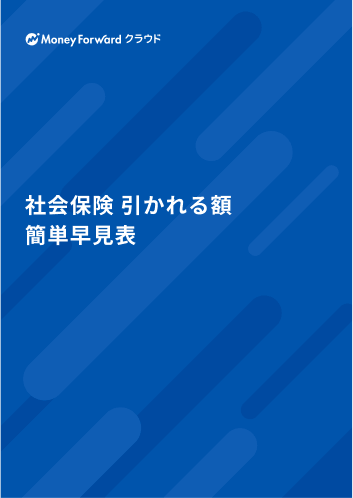- 更新日 : 2025年4月22日
給料から社会保険料が引かれる額 – 具体例を用いて解説
社会保険料は毎月給与から天引きされるため、いくら引かれているのかを気にする従業員は少ないかもしれません。しかし、企業の人事労務担当者としては、給与から天引きする社会保険料の金額や社会保険料が変更されるタイミングなどの正確な知識が必要です。
この記事では、給与から引かれる社会保険料の金額について、具体例を用いて解説します。
目次
給料から引かれる社会保険料の金額は?
社会保険は健康保険と厚生年金保険からなり、40歳以上65歳未満の被保険者は介護保険の保険料も負担しなければなりません。これらの社会保険に労災保険、雇用保険からなる労働保険をあわせて広義の社会保険と呼ばれることもあります。
ここでは狭義の社会保険、すなわち健康保険・介護保険と厚生年金保険に的を絞り、社会保険料がいくら引かれるのかを解説していきます。
社会保険料とは
企業に加入が義務付けられている社会保険には、健康保険・介護保険、厚生年金保険があります。企業はこれらの保険料を毎月給与から天引きで徴収します。保険料の負担は労使折半で、給与から天引きした保険料に企業負担分を加えて日本年金機構に毎月納付しなければなりません。
保険料は、原則として毎年4月から6月までの3ヶ月間に支払われる給与(報酬)の平均額から決定される「標準報酬月額」に基づき算出されます。
報酬には基本給のほか、役職手当・住宅手当・家族手当・月割りの通勤手当なども含まれるため注意が必要です。一方、祝い金や見舞い金など恩恵的に支給するもので労働の対償とはいえないもの、出張旅費や交際費など実質弁償的な費用、退職金など臨時的・一時的に支給するものは、報酬には含まれません。
標準報酬月額は、報酬月額に応じて健康保険では第1等級から第50等級、厚生年金保険では第1等級から第32等級に区分されています。
なお、以前は賞与には社会保険料が課されませんでしたが、公平な保険料の負担を目的に「総報酬制」が導入され、賞与にも保険料が課されるようになりました。年3回以下の賞与は、税引前の賞与総額から千円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」をもとに保険料を算出します。なお、年4回以上の賞与は、毎月の報酬に含まれることに注意が必要です。標準報酬月額が決定される定時決定や随時改定の手続きで、「算定基礎届」や「月額変更届」を提出する際には、毎月の報酬に賞与の合計額を12で割った1ヶ月分の金額を加えるのを忘れないようにしましょう。
参考:
標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会
標準報酬月額の決め方|全国健康保険協会
標準報酬月額、賞与等|日本年金機構
社会保険料の計算方法
社会保険料は、標準報酬月額、もしくは標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
健康保険の保険料率は、都道府県によって異なります。また、毎年3月に保険料率の改定が行われているため、4月に支払う給与から新しい保険料率で計算した健康保険料(介護保険料も含む)を控除することにも注意が必要です。なお、健康保険組合に加入する企業では、各健康保険組合によっても保険料率が異なります。
介護保険の保険料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、毎年3月に保険料の改定があるものの、保険料率は全国一律です。40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者となる従業員の場合は、介護保険料を加算するのを忘れないようにしましょう。
厚生年金保険の保険料率は2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年で引き上げが終了し、現在は全国一律18.3%となっています。保険料の計算方法は下記の通りです。
健康保険料
賞与の健康保険料=標準賞与額×保険料率(健康保険料率+介護保険料率)
厚生年金保険料
賞与の厚生年金保険料=標準賞与額×保険料率(18.3%)
なお、健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料は労使折半なので、上記計算式で求めた保険料の半額が従業員負担額となります。
参考:
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)|全国健康保険協会
協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会
厚生年金保険の保険料|日本年金機構
給料が10万円の場合の社会保険料
ここからは実際にいくら社会保険料が引かれるのかを計算していきます。
まず、月の給料が10万円の場合の社会保険料です。ここでは4月から6月までの3ヶ月間の平均総支給額も10万円とします。東京都の企業に勤めており、介護保険制度の対象ではない従業員の2023年5月現在の社会保険料は下記の通りです。
健康保険料
98,000円(標準報酬月額:第5等級)×(10.00%÷100)(健康保険料率)=9,800円
9,800円(健康保険料)÷2(労使折半)=4,900円(従業員負担額)
厚生年金保険料
98,000円(標準報酬月額:第2等級)×(18.3÷100)(厚生年金保険料率)=17,934円
17,934円(厚生年金保険料)÷2(労使折半)=8,967円(従業員負担額)
子ども・子育て拠出金
98,000円(標準報酬月額)×(0.36%÷100)(拠出金率)=352.8円
社会保険料
9,800円(健康保険料)+17,934円(厚生年金保険料)=27,734円
27,734円+352.8円(子ども・子育て拠出金)=28,086.8円(総納付額)
27,734円(社会保険料)÷2(労使折半)=13,867円(従業員負担額)
上記28,086.8円が会社が日本年金機構に社会保険料として納付する金額、13,867円が従業員負担額です。ただし、実際に支払う納入告知書の保険料の金額は従業員個々の保険料額の合計額です。合計額に円未満の端数がある場合、端数は切り捨てます。
なお、社会保険料の一部として、児童福祉に係る「子ども・子育て拠出金」もあわせて徴収されるため注意しましょう。子ども・子育て拠出金は全額会社負担で、拠出金率は0.36%です。
参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
給料が20万円の場合の社会保険料
続いて月の給料が20万円の場合の社会保険料を計算してみましょう。4月から6月までの3ヶ月間の平均総支給額も20万円とします。上記と同様に東京都の企業に勤めており、介護保険制度の対象ではない労働者の2023年5月現在の社会保険料で計算します。
健康保険料
200,000円(標準報酬月額:第17等級)×(10.00÷100)(健康保険料率)=200,000円
20,000円(健康保険料)÷2(労使折半)=10,000円(従業員負担額)
厚生年金保険料
200,000円(標準報酬月額:第14等級)×(18.3÷100)(厚生年金保険料率)=36,600円
36,600円(厚生年金保険料)÷2(労使折半)=18,300円(従業員負担額)
子ども・子育て拠出金
200,000円(標準報酬月額)×(0.36÷100)(拠出金率)=720円
社会保険料
20,000円(健康保険料)+36,600円(厚生年金保険料)=56,600円
56,600円+720円(子ども・子育て拠出金)=57,320円(総納付額)
56,600円(社会保険料)÷2(労使折半)=28,300円(従業員負担額)
上記57,320円が会社が日本年金機構に社会保険料として納付する金額、28,300円が従業員負担額です。
参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
給料が30万円の場合の社会保険料
最後に月の給料が30万円の場合の社会保険料を計算します。4月から6月までの3ヶ月間の平均総支給額も30万円です。東京都の企業に勤めており、介護保険第2号被保険者の2022年8月現在の社会保険料は下記のようになります。
健康保険料
300,000円(標準報酬月額:第22等級)×{(10.00+1.82)÷100}(健康保険料率+介護保険料率)=35,460円
35,460円(健康保険料)÷2(労使折半)=17,730円(従業員負担額)
厚生年金保険料
300,000円(標準報酬月額:第19等級)×(18.3÷100)(厚生年金保険料率)=54,900円
54,900円(厚生年金保険料)÷2(労使折半)=27,450円(従業員負担額)
子ども・子育て拠出金
300,000円(標準報酬月額)×(0.36÷100)(拠出金率)=1,080円
社会保険料
35,460円(健康保険料)+54,900円(厚生年金保険料)=90,360円
90,360円+1,080円(子ども・子育て拠出金)=91,440円(総納付額)
90,360円(社会保険料)÷2(労使折半)=45,180円(従業員負担額)
上記91,440円が会社が日本年金機構に社会保険料として納付する金額、45,180円が従業員負担額です。
参考:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
社会保険料があがるタイミングは?
標準報酬月額がが変更されるタイミングは、毎年9月もしくは給与に大幅な変動があった時から4ヶ月目です。
社会保険の算定基礎である標準報酬月額は、毎年7月に所管の年金事務所に「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することで決定されます。これは「定時決定」と呼ばれ、4月から6月までの3ヶ月間の給与の平均額から標準報酬月額を決める手続きです。定時決定により決定された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されるのが原則です。
年度の途中で2等級以上変動するような大幅な給与の増減があった場合は、その都度、随時改定の手続きが必要です。随時改定では、大幅な給与の増減があった月から数えて4ヶ月目に標準報酬月額が変更されます。随時改定の条件に該当する場合には「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となりますので、忘れないようにしましょう。
参考:
定時決定(算定基礎届)|日本年金機構
随時改定(月額変更届)|日本年金機構
労使負担割合を理解し社会保険料の従業員負担額を把握しよう
社会保険料は毎月給与から天引きされているため、従業員は保険料をあまり意識していないかもしれません。健康保険・厚生年金保険は労使折半となるため、企業は従業員の給与から控除した保険料に企業負担分を加えて納付しなければなりません。
社会保険料は、毎年9月の定時決定による変更、もしくは給与が大幅に増減した場合の随時改定による変更、毎年3月の健康保険料や介護保険料の保険料率改定の3つのタイミングで変更されます。ただし、給与から控除する社会保険料は先月分となるため、変更後の保険料を給与から控除するのは、従業員の退職など一部例外を除き、保険料の変更が行われた翌月に支払う給与からです。
労使負担割合や保険料率、保険料変更のタイミングを理解し、正確な給与計算を行いましょう。
よくある質問
給料が30万円の場合、社会保険料が引かれる額はいくらですか?
44,625.0円です。なお、社会保険料は労使折半なので、会社が日本年金機構に納付する保険料は倍額の89,250.0円に子ども・子育て拠出金1,080.0円を足した90,330.0円となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険料があがるタイミングについて教えてください。
毎年9月の定時決定、もしくは大幅に給与が増減した際に実施される随時改定のタイミングで社会保険料が変更されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険の適用対象者とは?特別加入者についても解説!
労災保険の補償対象は、業務災害と通勤災害です。対象者はすべての労働者で、特別加入制度により中小企業事業主や一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者も給付を受けられます。療養補償等給付や休業補償等給付といった、さまざまな種類の給付があります。労…
詳しくみる契約社員も育休をとれる!取得条件や手続き方法を分かりやすく解説
出産後も仕事を続ける予定でいるけれど、契約社員でも育休はとれるの?と不安を抱いている方もいるでしょう。しかし、契約社員も一定の条件を満たせば、法律上育休を取得できます。 とはいえ、契約社員の場合は契約期間や更新の有無によって育休の取得可否が…
詳しくみる健康保険の適用事業所とは?企業や個人事業主の加入条件と加入手続き
一般的に、企業に勤める従業員は、健康保適用事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。険に加入します。また個人事業主や自営業の場合でも、条件にあてはまる事業所では、従業員を健康保険に加入させる必要があります。ここで…
詳しくみる派遣社員は社会保険に加入できるか
派遣社員にとって「事業所」とは、派遣元となる事業所のことです。派遣元事業所が適用事業所ならば、そこで使用される派遣社員は被保険者となり、一般の労働者と同じく社会保険が適用されます。 派遣社員とは 派遣社員は一般の労働者とは異なり、就業先では…
詳しくみる国民年金保険料が免除される年収はいくら?申請に伴う注意点も解説!
収入の減少や失業、産前産後といった理由により国民年金保険料の支払いが困難になった場合には、免除や猶予を受けることができます。前年の年収(所得)が基準の範囲内である場合に対象になりますが、収入の見込額を用いる新型コロナウイルスの特例も設けられ…
詳しくみる厚生年金の保険料は一括払い・前納ができる?
厚生年金保険料は毎月支払う必要があり、数ヵ月分をまとめて支払う一括納付は認められていません。厚生年金の一括適用とは、社会保険の被保険者資格に関する各種手続きや保険料納付などを本社でまとめて行うことです。国民年金保険料は前納制度があり、定めら…
詳しくみる