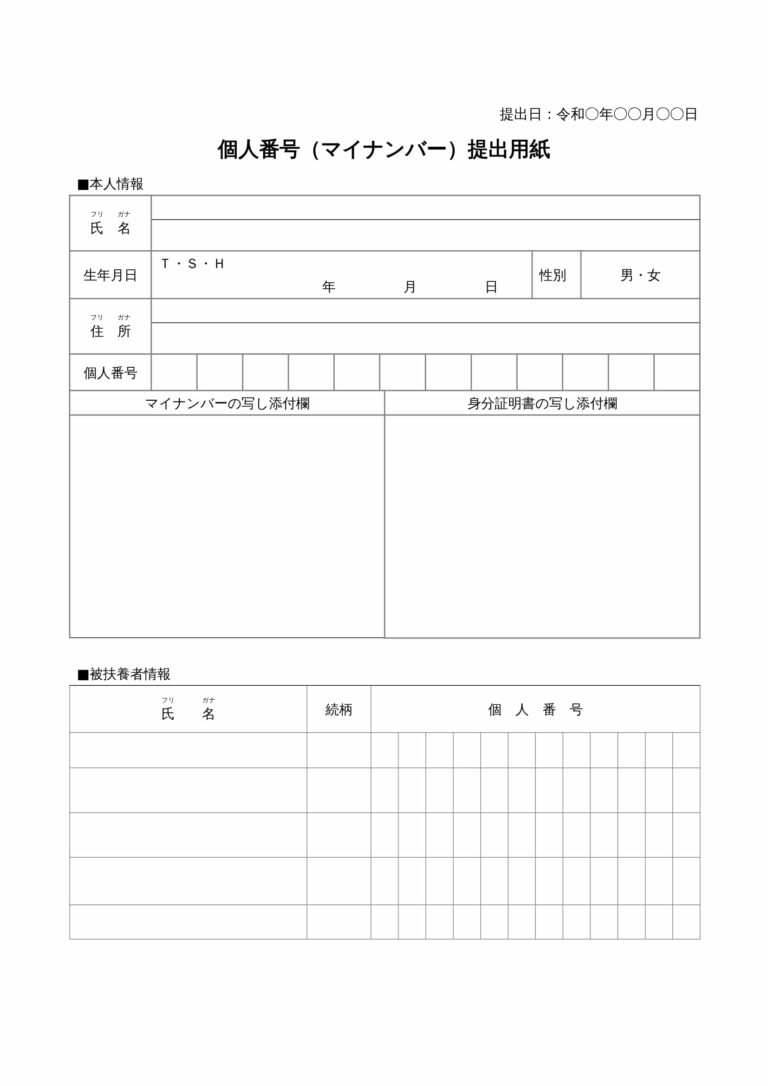- 更新日 : 2024年12月24日
マイナンバーとは?申請手続きや受け取り期限を解説!
マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り振られた番号です。税金や社会保障の分野で活用されます。2022年に入ってからは、マイナンバーカードの保険証利用など、マイナンバー制度が広がりを見せています。ここでは、マイナンバーがなぜ必要なのかという基本知識から、マイナンバーカードのメリットや申請方法について解説します。
目次
マイナンバーとは?
マイナンバーとは、日本国内に住民票をもつ個人すべてに振り分けられた12桁の番号をいいます。2015年10月より税・社会保障・災害対策の分野での使用を目的に運用がはじまりました。2016年1月からは、個人証明として利用できる「マイナンバーカード」が登場し、行政手続きのオンライン申請や健康保険証としての利用など、年々実用的な場面で便利に利用できるシーンが広がっています。
マイナンバーの詳しい設立背景についてはこちらの記事をご確認ください。
マイナンバーはなぜ必要?
マイナンバーが導入された目的は、行政手続きの簡素化・国民の利便性向上です。行政手続きで必要となる番号には、住民票の「住民登録番号」や年金の「基礎番号」、健康保険の「被保険者番号」などがあり、実にさまざまな番号が個人に割り振られています。しかし、税金や社会保障などの制度や手続きごとに使用する番号が異なるため、書類の確認・発行に時間がかかったり、必要書類が不足して申請者が何度も窓口に足を運ばなければいけなかったりと手間がかかることが多く、煩雑なフローとなっていました。
マイナンバーは、こうした縦割りの行政の橋渡し役として業務を効率化させる役割を担います。これにより、コンビニでの住民票発行やオンラインでの行政手続きの申請などが可能となり、年を追うごとに活用できるシーンが広がってきました。今後も、さらなる国民生活の利便性向上が期待できるでしょう。
2022年現在、すでにマイナンバーカードと連携しコンビニでの各種証明書の発行や、個人認証サービスによる電子証明書としての使用、マイナポータルでの個人の税金状況の確認が可能となっています。
マイナンバーと個人番号は違う?
マイナンバーと個人番号は同じものです。「マイナンバー(個人番号)」といった表記でも使われます。住民票を持つ個人に割り振られ、マイナンバーは生涯変わることはありません。
マイナンバーと納税者番号は違う?
納税者番号とは、税金を納める個人に対して国が固有の番号を割り振り、資産状況や税金額などを把握するために利用されています。マイナンバーも同様に個人に割り振られる番号であり、税金の分野で活用されることから、納税者番号とほぼ同様の機能を有するものです。しかしながら、日本ではすべてを統一して管理できる納税者番号がないこともあって、実務的には税務署が用いる整理番号にマイナンバーを紐づける形で運用されています。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードとは、マイナンバーを証明する書類です。プラスチック製のICチップつきカードで、表面に顔写真、住所や氏名などの個人情報が記載されているほか、裏面にマイナンバーが記載されています。
マイナンバーカードは、本人確認のための公的な書類として認められています。また、保険証としての利用も始まり、政府は将来的に、運転免許証との一体化の方針を掲げています。
マイナンバー交付の対象者
マイナンバーの交付の対象となるのは、日本の市区町村に住民票を持つ個人全員です。子どもやお年寄りなど、住民票を持つ個人には年齢に関係なく付与されます。また、外国人が海外から転入した場合、中長期滞在者で在留カードを保持する人には、市区町村での転入届が提出されたあとにマイナンバーが付与されます。旅行などの短期滞在の外国人は、マイナンバーの対象外です。
マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードは、公的な書類の発行などさまざまなシーンで活用できるメリットがあり、今後さらなる利便性の向上が期待されています。
本人証明書として利用できる
有効期限があるマイナンバーカードは、公的な本人証明書類として使用可能です。たとえば、運転免許証やパスポートがない方が、マイナンバーカードを持っていることで市役所や金融機関の手続き・クレジットカードの登録手続きなどをスムーズに行えます。
健康保険証として使用できる
マイナンバーカードの専用リーダーがある医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。マイナンバーカードを健康保険証として使用したい場合には、利用する前に申込みを済ませておきましょう。対応している医療機関や薬局には、「マイナ受付」のステッカーが張ってあります。
また、2021年分の確定申告以降は、医療費控除の手続きの際、専用サイト「マイナポータル」からe-TAXに連携することで医療費の情報の自動入力が可能になりました。
マイナポイントが貯まる
政府はさらなるマイナンバーカードの普及率向上を目指していることもあって、マイナンバーカードの新規取得、健康保険証への利用登録、公金受取口座の登録などにより、お店のキャッシュレス決済で使用可能なマイナポイントをもらうことができます。
参考:マイナポイント|総務省
コンビニでの各種証明書取得が可能に
マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニで各種証明書を取得することができます。取得できる証明書の種類は市区町村によって異なりますが、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しなどが取得可能です。
参考:コンビニエンスストア等における証明書などの自動交付|コンビニ交付
マイナンバーカードの交付手続き
マイナンバーカードを受け取るには、交付手続きを行う必要があります。申請は郵送もしくはオンライン申請が可能です。以下に、手続きの流れを説明します。
ステップ1 申請を行う
郵送もしくはオンラインで申請可能です。また、まちなかの証明写真機から申請できるものもあります。
- 郵送申請
申請には、個人番号通知書、通知カードに同封されている「交付申請書」が必要です。
- 郵送申請
- オンライン申請
サイトより申請します。申請には、メールアドレスの登録や顔写真登録が求められます。
ステップ2 交付通知書(はがき)が届く
申請後、交付通知書が本人に郵送で届きます。交付通知書が届くまでにはおよそ1カ月程度かかります。
ステップ3 マイナンバーカードを受け取る
交付通知書を、お住まいの市区町村窓口に持っていき、カードを受け取ります。カードを受け取る際は、以下の書類が必要です。なお、病気やケガ等で本人が移動できないやむを得ない理由がある場合には、代理人に委任することができますので、担当窓口でご確認ください。
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている場合)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
マイナンバーカードの注意点
マイナンバーカードには交付の受け取り期限が設定されています。またマイナンバーカードには有効期限があるため、期限が近づいた際には再申請の必要があります。以下に、マイナンバーカードの注意点について解説します。
マイナンバーカードの再申請は可能?
マイナンバーカードの盗難や紛失、番号の漏えいなど、不正利用されるおそれのある場合のみ、マイナンバーの変更が認められています。再発行については、お住まいの市区町村窓口でご相談ください。
マイナンバーカードに受け取り期限はある?
マイナンバーカードは、申請者のお住まいの市区町村に送られ、交付通知書と引き換えに本人に手渡す仕組みです。交付通知書には受け取り期限が表示されており、一定期間(最低3カ月)過ぎても受け取りにこない場合には、安全性の確保のためマイナンバーカードが処分されます。その際は、再度申請手続きが必要となります。
マイナンバーカードの有効期限は?
マイナンバーカードには、有効期限が表示されています。18歳以上の場合は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は5回目の誕生日までが有効期限です。マイナンバーカードの有効期限が近づくと、「有効期限通知書」が届きますので、案内に従い再発行の手続きを行います。
受け取ったマイナンバーカードは大事に保管しよう
マイナンバーは、税金や社会保障の分野で行政の手続きを簡単にし、国民の生活の利便性を向上させるための制度です。マイナンバーカードの利用シーンは広がっている最中であり、今後もさらに拡大することが予測されます。
マイナンバーおよびマイナンバーカードが、自身の生活にどのような影響を与えるのかをよく検討した上でマイナンバーカードを取得しましょう。取得したあとは、マイナンバーカードは大切に保管してください。
よくある質問
マイナンバーとはなんですか?
個人に割り振られる12桁の番号です。住民票を持つ個人すべてに交付されており、生涯変わることがありません。税金・社会保障・災害対策の範囲で活用され、2015年の運用開始後、利用範囲が広がっています。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードのメリットについて教えてください。
コンビニで各種公的な書類の発行ができるほか、運転免許証やパスポートのように個人の身分証明書としても利用できます。また、登録することで保険証として活用でき、ポイントがたまるといったサービスもあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナンバーの規程整備について、事業者なら知っておきたいこと
マイナンバーは、支払調書や源泉徴収票提出時に使用します。従業員が数名しかいなくても、きちんと考えておきたいのがマイナンバーの規程整備です。 個人情報であるマイナンバーは、情報漏えいしないように徹底した保管や管理が求められるものです。いずれの…
詳しくみるマイナ保険証を使うメリット・デメリットは?手続きの流れ〜よくある疑問を解説
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みのことを指します。 2021年から導入が進み、2024年には従来の健康保険証が原則廃止され、現在はマイナ保険証の利用が原則となっています。 とはいえ、「本当に便利になるの…
詳しくみるマイナンバーの社会保険への実務利用
平成28年度から国の行政機関や地方公共団体等に書類を提出する際には、社員や法人のマイナンバーを記載することになりました。ここでは、社会保険では実務的にどのように利用するのかを解説します。 社会保険へのマイナンバーの実務利用について マイナン…
詳しくみるマイナンバーで病歴は分かる?マイナ健康保険証スタート後は?
2015年に導入されたマイナンバーは、社会保障や税務処理などに利活用されています。さらに、2021年からはマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。政府はより良い医療の提供を謳っていますが、マイナンバーから病歴や通院履…
詳しくみるマイナンバーのガイドラインをわかりやすく解説
マイナンバーを取り扱うのは国や自治体などの行政機関だけではありません。中小企業をはじめとする民間事業者も、従業員の源泉徴収票作成時などで、マイナンバーを取り扱うことになります。 ここではマイナンバーを取り扱う際のガイドラインについて解説して…
詳しくみるマイナンバーと住基ネットの関係って何?
住基ネットの導入。 当時は様々な議論を引き起こしましたが、そのためもあってか結局はあまり普及しませんでした。普及率はいまだ5パーセント前後。今回、新たに導入されるマイナンバー、住基ネットとの関係に迫りたいと思います。 この記事で人気のテンプ…
詳しくみる