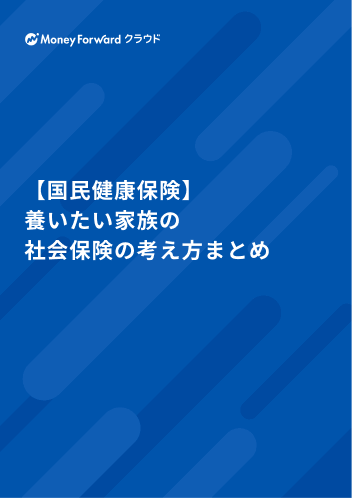- 更新日 : 2025年3月27日
国民健康保険に扶養はある?加入手続きの注意点も解説
日本は国民皆保険制度を採っているため、全国民に健康保険への加入を義務付けています。退職によって社会保険の資格を喪失した際や、フリーター・アルバイトで親の扶養から外れた場合、自営業の方などは国民健康保険への加入が必要です。この記事では、国民健康保険における「扶養」の扱いや、加入方法などをご紹介します。
目次
国民健康保険に扶養はある?
国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。一般的な給与所得者が加入する社会保険には扶養制度があり、配偶者や生計を一にしている親族を扶養に入れることが可能です。
社会保険の扶養制度では追加の保険料負担は発生しませんが、国民健康保険は加入者1人1人が保険料を負担する必要があります。
また、世帯主が社会保険に加入し、他の家族が国民健康保険に加入している世帯のことを「擬制世帯」と言います。この世帯の世帯主は「擬制世帯主」として、世帯員の国民健康保険料の納付義務を負うことになるのです。
例えば、世帯主が会社で健康保険に加入しており、配偶者が国民健康保険に加入している場合は、たとえ世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても保険料の納付義務を負います。被保険者と納付義務者が一致しない点に注意しましょう。
国民健康保険への加入手続き
社会保険の「被扶養者」として認定されるには、様々な条件があります。条件に該当せず扶養から外れた場合は、国民健康保険への加入が必要です。ここでは、国民健康保険への切り替え手続きの流れと必要書類をご紹介します
資格喪失証明書や扶養削除証明書を準備する
まず、社会保険の扶養から外れた事を証明する「健康保険資格喪失(被扶養者削除)証明書」を取得します。資格喪失証明書は、所管の年金事務所に申請することで取得できます。
国民健康保険への切り替えには期限があり、資格喪失証明書に記載された「扶養削除日」を起点に換算されます。資格喪失証明書を取得したら必ず扶養削除日を確認し、早めに国民健康保険への加入手続きを進めましょう。
世帯主と被扶養者から外れた方全員のマイナンバーが確認できるものを準備する
次に、世帯主と扶養から外れた方全員のマイナンバーが必要です。まずはマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書などを用意しましょう。国民健康保険には「擬制世帯主」という考え方があるため、申請者本人だけでなく世帯主のマイナンバーも必要になります。
なお、マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書などが用意できない場合は、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」で確認可能です。加入手続きを行う際に合わせて役所で取得しましょう。
申請者の本人確認ができるものを準備する
マイナンバーと合わせて、申請者本人の本人確認書類を用意しましょう。運転免許所やパスポート、マイナンバーカードなどが利用できます。マイナンバーカードを本人確認書類とした場合は、マイナンバー確認と本人確認を同時に実施することが可能です。本人確認書類は「原本」が必要なので注意しましょう。
保険料の振替用口座を準備する
最後に、保険料の納付に使われる振替用口座を用意しましょう。キャッシュカードがあれば、専用端末を利用してその場で口座振替申込手続きが完了します。市区町村によってキャッシュカードによる口座振替申込手続きができる金融機関が異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
また、キャッシュカードによる口座振替申込手続きに対応していない金融機関や、キャッシュカードが無い場合は通帳と届出印を用意しましょう。必要書類へ記入捺印することで口座振替を申し込むことが可能です。
退職した場合の国民健康保険への加入手続き
国民皆保険制度によって、日本国民は全員健康保険への加入が義務付けられています。
そのため、退職によって社会保険の資格を喪失した場合、国民健康保険に切り替える人も少なくありません。しかし、多くの退職者が国民健康保険に切り替える一方で、人によっては社会保険の任意継続を行うケースもあります。任意継続するためには2つの条件を満たしたうえで健康保険協会への申し込みが必要です。任意継続の条件や手続き手順などをあらかじめ把握しておきましょう。
前章では、条件に該当せず被扶養者でなくなった方の、国民健康保険への加入手続きについてご説明しました。こちらでは、退職によって社会保険から国民健康保険に切り替える方の、加入手続きの流れや必要書類をご紹介します。
資格喪失証明書や扶養削除証明書を準備する(退職証明書や離職票などでも可)
扶養から外れ国民健康保険に加入する際は資格喪失証明書が必要でしたが、退職によって社会保険から国民健康保険に切り替える場合は、「退職証明書」や雇用保険の「雇用保険被保険者離職票(離職票)」など退職日がわかる書類で代替可能です。これらは退職時に会社から交付される書類です。なお、「雇用保険被保険者証」では手続きできないので注意しましょう。
扶養家族を含めた、国民健康保険に加入する方全員の健康保険資格喪失証明書
会社を退職した本人のみが国民健康保険に加入する場合は退職証明書や離職票で手続き可能ですが、扶養家族がいる場合は扶養者がこれまで加入していた健康保険の、健康保険証のコピーや資格喪失証明書が必要となります。所管の年金事務所に申請し、国民健康保険に加入する全員の資格喪失証明書を取得してください。
申請者の本人確認ができるものを準備する
次に、申請者の本人確認書類が必要です。運転免許所やパスポート、マイナンバーカードを用意しましょう。本人確認と同時にマイナンバー確認もあるので、マイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書も合わせて用意する必要があります。なお、申請者が世帯主ではない場合は、扶養から外れて国民健康保険に加入するときと同様に、世帯主のマイナンバーも必要となるため注意しましょう。
保険料の振替用口座を準備する
最後に、振替用口座を用意しましょう。キャッシュカードがあればその場で口座振替申込手続きが完了します。無い場合は通帳と届出印が必要です。
国民健康保険に加入する際の注意点
国民皆保険制度のある日本では、全ての国民に健康保険への加入を義務付けているため、社会保険から国民健康保険への切り替えも期限が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、保険料ならびに保険給付の面で不利益を被ることになるため、社会保険の資格を喪失したらなるべく早く国民健康保険の加入手続きを行うようにしましょう。ここでは、国民健康保険に加入する際の注意点として、加入期限に着目してご紹介します。
加入手続きは、資格喪失から14日以内に行う
国民健康保険への加入手続きは、健康保険の資格喪失から「14日以内」に行うことと国民健康保険法に定められています。これは、健康保険への未加入期間をなるべく無くすための制限と考えられます。国民健康保険への切り替えは、役所に出向いたり必要書類を用意したりする必要があるため、社会保険の資格を喪失したら速やかに国民健康保険の加入手続きを進めるようにしましょう。
14日を過ぎてしまった場合は?
国民健康保険への加入が遅れ14日を過ぎてしまった場合、何か罰則はあるのでしょうか。国民健康保険法第127条には「十万円以下の過料を科す」と罰則規定が定められていますが、14日を過ぎたからと言って、ただちにこの罰則が適用されるわけではありません。
この罰則より気を付けなければならないのが、手続き完了日まで保険給付が受けられず、医療費が全額自己負担となる点です。保険料については加入手続きを終えていなくても社会保険の資格を喪失した月からかかります。
例えば、6月10日に会社を退職した場合、24日までに国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。手続きが遅れ、7月に入ってしまいました。その間に体調を崩し、6月27日に医療機関を受診したとします。この場合、保険料は6月分から支払う必要がありますが、6月27日の医療費は全額自己負担となります。
国民健康保険への加入が遅れてしまうと、保険給付は受けられないのに保険料だけ支払わなければいけない事態となるため、早めに加入手続きを行いましょう。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の無料テンプレート
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
必要書類や手順を把握し期限内に加入手続きを進めよう
国民健康保険における扶養の考え方や、加入手続きについてご紹介しました。日本には国民皆保険制度があるため、社会保険か国民健康保険のいずれかには必ず加入しなければなりません。会社を退職した場合や、扶養から外れた場合は国民健康保険への切り替え手続きが必要です。加入手続きには14日以内という期限が設けられており、期限を過ぎてしまうと不利益を被ってしまいます。この記事を参考に手続きの流れと必要書類を確認し、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。
よくある質問
国民健康保険に扶養はありますか?
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません。社会保険には扶養制度があり、条件を満たせば配偶者や両親などを扶養に入れることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険に加入するうえでの注意点を教えてください
国民健康保険への加入は、社会保険の資格喪失から14日以内に行うことと定められています。期限を過ぎてしまうと、様々な不利益を被ることになるため注意しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険は、要介護状態になった場合に介護サービスを受けることができる制度ですが、被保険者になる年齢は第1号被保険者と第2号被保険者では異なります。 今回は、介護保険サービスを受けるための手続きについて解説していきます。 介護保険の被保険者年…
詳しくみる外国人労働者が雇用保険で適用除外となるケースと手続きの注意点を解説
外国人労働者の採用において、雇用保険の手続きに悩む担当者は多くいるでしょう。 この記事では、外国人労働者の雇用保険の加入条件や雇用保険適用除外となるケース、手続きの注意点などを解説します。手続きのミスは罰則やトラブルの原因になるため、正確な…
詳しくみる健康保険とは?被用者保険と国民健康保険の違い
健康保険は、日本の医療制度を支える重要な保険制度です。会社員や公務員が加入する政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合のほかに、個人事業主や自営業者が加入する国民健康保険があります。 ここでは、日本の健康保険制度の種類や加入対象者について解…
詳しくみる会社役員の社会保険は義務?加入条件や取り扱いを解説
会社に雇用される社員は、要件を満たせば社会保険に加入できます。では、会社役員にはどのような加入要件があるのでしょうか? 役員と社員の場合における社会保険の加入義務、役員の社会保険が加入要件を満たして適用になるタイミング、個人事業主でも社会保…
詳しくみる厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?申請方法や結婚後の年金について解説!
厚生年金保険に結婚を対象とする給付はありませんが、企業による厚生年金基金には被保険者が結婚した際に支給する祝い金制度が設けられていることがあり、定められた方法で申請すると給付を受けられます。厚生年金被保険者が結婚後も働き続ける場合は、そのま…
詳しくみる契約社員も産休はとれる?取得条件や手続きの流れを解説
契約社員として働きながら出産を検討していると「産休は取得できるの?」と不安になる方もいるでしょう。結論、労働基準法が定める女性労働者であれば、契約社員やパートなどの有期契約労働者も産休を取得できます。 本記事では、契約社員の産休取得に必要な…
詳しくみる