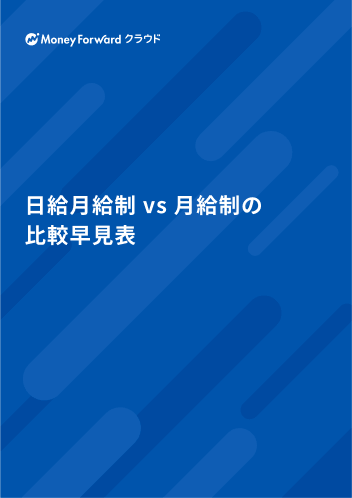- 更新日 : 2025年4月22日
日給月給制とは?月給制との違いや給与計算、メリット・デメリットを解説
求人票などを見ると、給与形態の欄には、日給制、月給制、時給制などさまざまな形態があります。
給与形態によってそれぞれ特徴がありますので、ここでは日給月給制を中心に、給与形態ごとのメリット、デメリットや残業、休日出勤の給与への影響、遅刻・早退・欠勤の場合の給与の計算方法について見ていきます。
目次
日給月給制とは?
「日給月給制」という言葉は正式な用語ではなく、厳密な定義は定められていません。ここでは、一般的な「日給月給制」について説明します。
日給月給制とは、1日を計算単位として、あらかじめ定められた月額から遅刻や早退など不就労分を差し引く給与形態です。
遅刻や欠勤などがあったときは、基本給だけでなく、役職手当や資格手当など月ごとに支払われる手当も減額されます。また時間外労働や深夜労働には、別途割増賃金を支払わなければなりません。
給与形態には、日給月給制以外に、日給制、月給制、時給制、月給日給制、完全月給制があります。
日給月給制とこれらの給与形態の違いについて見ていきます。
日給制との違い
日給制とは、1日を計算単位として定められた額(日給)を支給する給与形態です。1ヶ月の給与は「日給×働いた日数」で計算します。
日給月給制と日給制の違いは、働いた日数によって給与が決まるのが日給制であるのに対して、休んだ(遅刻・早退を含む)日数で給与が決まるのが日給月給制です。
日給月給制は基本になる月額は決まっていますので、遅刻や欠勤などがなければ給与は変わりませんが、日給制は月単位で見ると働く日数の多少により給与額が変わります。
月給制との違い
月給制とは、1ヶ月を単位として賃金が固定されている給与形態です。
日給月給制と月給制の違いは、休んだ(遅刻・早退を含む)日数で給与が決まるのが日給月給制であるのに対して、遅刻・早退・欠勤があっても給与額が変わらないのが月給制です。
しかし実際は、日給月給制や月給日給制を「月給制」と呼ぶことも少なくないため、注意が必要です。
時給制との違い
時給制とは、1時間あたりの給与額が定められている給与形態です。時給制の給与は、時給×労働時間で計算されます。
日給月給制と時給制の違いは、日給月給制が休んだ(遅刻・早退を含む)日数で給与が決まるのに対して、時給制は働いた分だけ給与になるというところです。
決められた月額から欠勤(遅刻・早退を含む)分を減額する日給月給制と異なり、時給制には減額という考え方がなく、働いていない時間は最初からカウントされません。なお、法定時間外労働や深夜労働があった場合は、割増賃金の支払いが必要です。
時給制は1時間単位で給与が支払われることから、1日の労働時間が変動する労働者や短時間労働者などによく使われる給与形態です。
月給日給制との違い
月給日給制とは、日給月給制と同様にあらかじめ決められた給与の月額があり、遅刻・早退・欠勤があった場合には、その分を月額から減額するという給与形態です。
日給月給制と月給日給制の違いは、欠勤や遅刻などがあった場合の減額方法です。日給月給制では、基本給だけでなく役職手当や職務手当なども日割りして減額しますが、月給日給制は基本給のみを減額し、役職手当など月単位で支給される手当は満額を支給します。
そのため、同じ月給の人が同じ日数の欠勤をした場合、月給日給制の方が日給月給制よりも総支給額が多くなります。
完全月給制との違い
完全月給制とは、月給制と同様に1ヶ月を単位として賃金が固定されている給与形態です。単に「月給制」と呼ばれることもあります。
遅刻や欠勤、早退などがあった場合、日給月給制では不就労分を減額しますが、完全月給制では減額されず、満額が支給されます。
完全月給制は、役員や役職者などに適用されることが多い給与形態です。
月給制、完全月給制については、会社によって言い方が違うだけで運用方法が同じ場合もありますので、具体的な給与形態の内容については確認が必要です。
年俸制との違い
年俸制とは、1年の給与総額が決められている給与形態です。年俸制では「年額給与を12等分して各月に支給する」「16等分して夏冬の賞与に各2ヶ月分を充てる」など、企業によって支払い方が異なります。
年俸制では給与の年額があらかじめ決定されているため、年の途中で昇給・降給などは行われません。なお、時間外・深夜などの割増賃金は別途支払う義務があります。
日給月給制のメリット
ここからは日給月給制のメリットについて見ていきます。
日給月給制は給与の月額があらかじめ決められていますので、安定的な収入が得られることによる安心感があること、残業などで収入が増える可能性があることなどがメリットとして考えられます。
そのあたりを中心に見ていきましょう。
休日出勤や残業などで給与が増えるケースがある
日給月給制はあらかじめ月額給与が決まっている制度ですが、残業や休日出勤などをすれば、時間外手当や休日手当などが加算されます。ケース毎に見ていきましょう。
会社が定めた所定労働時間を超過した労働に対しては割増賃金の支払いが必要になります。ただし、法定労働時間の1日8時間以内の範囲であれば割増ししない時間単価に時間数を乗じた賃金を支給します。
残業が1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超過した労働に対しては通常の残業代の支払いが必要になります。
また、労働時間が法定休日に当たる場合には休日割増賃金、夜10時から翌朝5時の深夜時間帯に当たる場合には深夜割増賃金の支払いが必要になります。
祝日の日数にかかわらず一定の給料がもらえる
生活していくために必要な最低限の収入額は人にはよりますが、概ね決まっています。
給与は労働者の生活の糧になるものですから、毎月安定的な収入を得られないと不安になるものです。
祝日を公休日としている企業では、2月や5月などは勤務日数が少なくなります。日給制や時給制の場合、勤務日数や勤務時間が少なければ、給与支給額も減ってしまうものです。
日給月給制は給与の月額があらかじめ決められていますので、毎月安定した収入が得られます。この点で、日給月給制は、日給制や時給制と比べ、安心感がある給与形態といえるでしょう。
不公平感が少ない
日給月給制では、遅刻や欠勤などがあると給与が減額され、休まず働けば満額が支払われます。出勤や欠勤などの状況が給与に反映されるため、従業員の理解を得やすく、不公平感が少ないものです。
一方、完全月給制の場合は、遅刻や欠勤が多い従業員でも給与を減額されることがないため、休まずに働いている従業員は、不公平感を持つかもしれません。
会社としては人件費を抑えられる
日給月給制では、従業員が遅刻や欠勤をした場合、その分の賃金を支払わずに済みます。出勤状況にかかわらず欠勤控除などをしない完全月給制と比べ、日給月給制は人件費を抑えられる給与形態といえるでしょう。
日給月給制のデメリット
日給月給制にはメリットばかりではなく、デメリットも考えられます。
ここでは、日給月給制のデメリットについて見ていきます。
欠勤が多い場合、月の給与が少なくなる
日給月給制のデメリットは、欠勤した分は必ず控除されてしまうため、欠勤が多くなればなるほど給与の額が少なくなることです。また、やむを得ない事情で欠勤した場合にも給与が少なくなります。
ただし、有給休暇の取得等で給与を減額することを防げる場合もあります。
残業時間を調整されることがある
日給月給制は、あらかじめ給与月額を決め、欠勤や遅刻があった場合は賃金を減額する制度です。月額給与が決まっているとはいえ、1日8時間・1週40時間を超えて働いた場合は時間外手当が加算され、給与月額を超える賃金が支払われます。
そのため会社によっては、時間外手当の支払いを抑制するために、そもそも時間外労働が発生しないような勤務時間にすることもあるでしょう。
従業員が無理をしてしまう恐れがある
日給月給制では、遅刻や欠勤をした分の給与が減額されるため、従業員によっては無理をしてしまうことがあります。
体調が悪い日や家庭の事情がある日など、本来は休むべき日でも、無理をして出勤してしまうことがあるのです。その結果、体調の悪化や過剰なストレスを招く心配があります。
日給月給制の給与計算方法
日給月給制の基本的な計算方法は、
で求めますが、通常はあらかじめ給与月額が決められており、遅刻・早退・欠勤があった場合は、その分を控除する計算を行います。
遅刻・早退・欠勤した場合の控除計算について見ていきましょう。
欠勤日についての計算方法
日給月給制で、欠勤があった場合の計算をしてみましょう。
- 基本給:30万円
- 職務手当:3万円
- 1ヶ月平均所定労働時間数:160時間
- 1日の所定労働時間:8時間
Aさんが4日間欠勤した場合
欠勤控除額=(基本給+職務手当)/所定労働時間×欠勤時間
(30万円+3万円)/160時間×(8時間×4日)
=66,000円
上の計算により、欠勤控除額は66,000円、総支給額は330,000円から66,000円を差し引いた264,000円になります。
欠勤については「就業規則」に記載しなければならない事項です。就業規則は会社ごとに異なりますので、会社ごとの規定に従うことになります。
厚生労働省の「モデル就業規則」を例に挙げると、以下のように規定されています。
(欠勤等の扱い)
第〇条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分
の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給/1か月平均所定労働時間数
(2)日給の場合
基本給/1日の所定労働時間数
上記の例で、欠勤した場合に欠勤分は給与からどのくらい引かれるのかについて具体例を挙げて見ていきます。
- 基本給:30万円
- 職務手当:3万円
- 1か月平均所定労働時間数:160時間
- 1日の所定労働時間:8時間
Aさんが4日間欠勤した場合
欠勤控除額=その月の月給額/1か月平均所定労働時間数×欠勤時間数
=(30万円+3万円)/160時間×(8時間×4日)
=66,000円
よって、給与から控除される欠勤控除額は、66,000円になります。
- 基本給(日給):1万円
- 1日の所定労働時間:8時間
Aさんが1日欠勤した場合
欠勤控除額=その日の日給額/1日の所定労働時間数×欠勤時間数
=1万円/8時間×8時間
=1万円
よって、給与から控除される欠勤控除額は1万円になります。
早退についての計算方法
早退した場合に、早退分は給与からどのくらい引かれるのかについて具体例を挙げて見ていきます。
- 基本給:30万円
- 職務手当:3万円
- 月間所定労働日数:20日
- 1日の所定労働時間:8時間
Aさんが30分早退した場合
賃金控除額=その月の月給額/その月の所定労働時間(時間)×早退時間(時間)
=(30万円+3万円)/(20日×8時間)×(30分/60分)
=1,031.25円
=1,031円(小数点以下切り捨て)
よって、30分の早退による賃金控除額は、1,031円になります。
遅刻についての計算方法
最後に、遅刻した場合に、遅刻分は給与からどのくらい引かれるのかについて具体例を挙げて見ていきます。
- 基本給:30万円
- 職務手当:3万円
- 月間所定労働日数:20日
- 1日の所定労働時間:8時間
Aさんが15分遅刻した場合
賃金控除額=その月の月給額/その月の所定労働時間(時間)×遅刻時間(時間)
=(30万円+3万円)/(20日×8時間)×(15分/60分)
=515.625円
=515円(小数点以下切り捨て)
よって、15分の遅刻による賃金控除額は、515円になります。
日給月給制は正社員に対しても導入されている
日給月給制は、正社員の給与形態として広く採用されています。その理由をみていきましょう。
遅刻や欠勤を抑制できる
遅刻や早退、欠勤などをすれば給与が減額されることは、従業員の遅刻や欠勤を抑制する効果があります。その結果、正当理由のない遅刻などが減少し、職場の規律保持にも役立つでしょう。
従業員のモチベーション維持に役立つ
日給月給制では、休まずに働いてくれる従業員には満額の月額給与を支給できます。一方、欠勤や遅刻が多い従業員の給与からは、不就労分を減額できます。
出勤状態が給与に反映されるため、出勤状態の良い従業員の納得を得やすく、モチベーション維持にも効果的です。
日給月給制を導入する際の注意点
日給月給制を導入するときは、従業員への説明が必要です。特に遅刻や欠勤などの減額方法は就業規則などに明確に定めましょう。
日給月給制の詳細を取り決める
日給月給制については法令に明確な定めがないため、日給月給制の具体的な運用方法については、各会社が取り決める必要があります。
日給月給制にする従業員の範囲、1日あたりの賃金の計算方法、減額した賃金の端数処理方法など、制度の詳細を決定しましょう。
「公共交通機関の遅延の場合は遅刻として扱わない」などのルールを定めることも自由です。
就業規則を変更する
日給月給制の詳細が決定したら、就業規則の変更をします。賃金の減額方法については計算式なども表示し、わかりやすく記載することがポイントです。
会社に適切な就業規則がない場合は、次のテンプレートをご利用ください。
なお、完全月給制や月給日給制から日給月給制への変更は、労働条件の不利益変更となるため、従業員へ制度導入の理由などを説明し、同意を得る必要があります。
就業規則を届出・周知する
就業規則の変更後は、所轄労働基準監督署への届出を行い、従業員にも周知します。
従業員へ変更内容を説明する際は、日給月給制の減額方法だけでなく、年次有給休暇の取得促進や病欠時に利用できる傷病手当金制度なども、併せて周知するとよいでしょう。
雇用契約前に日給月給制について正しく理解しておこう!
日給月給制は、あらかじめ決められた月額から、遅刻や欠勤、早退などの時間分を差し引いて支払う給与形態です。月額給与が決められていることから収入が安定しやすく、残業などがあれば、更に時間外手当が加算されます。
日給月給制は、月給制や月給日給制としばしば混同されます。そのため日給月給制を導入している場合は、従業員が制度について理解しやすいよう、給与の減額方法などを就業規則などに明確に定めることが重要です。
よくある質問
日給月給制はどのような給与制度ですか?
日給月給制は、給与の月額があらかじめ決められており、遅刻・早退・欠勤があった場合には、その分を月額から減額するという給与制度です。 詳しくはこちらをご覧ください。
日給月給制のメリットは何ですか?
日給月給制のメリットは、給与の月額があらかじめ決められていることで安定的な収入が得られ安心感があること、残業などで収入が増える可能性があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働基準法第25条の賃金の非常時払いとは?事例をもとにわかりやすく解説
労働基準法第25条は、労働者が緊急時に必要な費用をまかなうため、通常の給与支払日より前に賃金を受け取れる制度「賃金の非常時払い」を定めています。 本記事では、賃金の非常時払いの概要と適用条件、前借りとの違い、認められる理由と法的根拠、支払期…
詳しくみる退職金制度は変更できる?変更や廃止を検討するタイミングと変更・廃止に必要な手続きについて解説
退職金制度を変更するタイミングとしては、人件費削減や従業員の満足度を向上させたい場合などが考えられます。 しかし退職金制度を変更するには、原則、従業員や労働組合へ説明したうえでの合意が必要です。 従業員にとって有利な変更であれば合意を得るこ…
詳しくみる源泉徴収票に印鑑は必要?社印やシャチハタなどの決まりはある?
企業が給与の支払いをした者に対して発行する「源泉徴収票」は、押印がないのが一般的です。社印がなくても法的には問題はありません。ただし、銀行への住宅ローン申請では社印のある源泉徴収票が求められるケースがあります。その際、シャチハタなど、どんな…
詳しくみる産休中の給与は?計算方法や社会保険料の控除、給付金・手当を解説
産前や産後、育児中は、業務を行うことが困難です。そのため、公的な休業制度を定めることで、母体の保護や子育て支援が行われています。また、休業中の給与は社会保険料等の扱いについて、特別な処理が必要です。当記事では、産休中の給与や社会保険料の扱い…
詳しくみる住民税の第4期は何月分にあたる?各期間の納期や住民税の支払い方法を解説
住民税を普通徴収で支払う場合、4期に分けて納付できます。支払う住民税額が4期分のみ高い場合、何月分の住民税が含まれているのか気になる人もいらっしゃるでしょう。 しかし、あくまで住民税を4回に分割して納付しているため、何月分を支払っているか?…
詳しくみる源泉徴収の「納期の特例」を徹底解説!
源泉徴収義務者は、期限までに所轄の税務署に源泉徴収税を納めることになっていますが、条件によってはその納税を年2回に分けてまとめて納付できる特例があります。どのような場合に発生するのかをご紹介しましょう。 この記事で人気のテンプレート(無料ダ…
詳しくみる