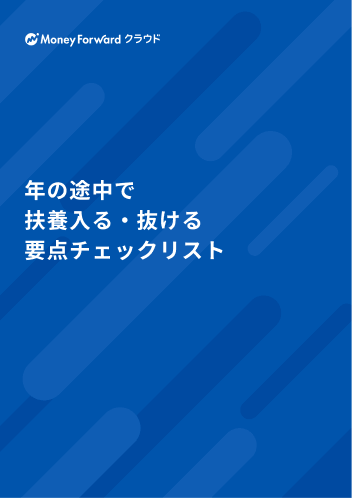- 更新日 : 2025年4月22日
社会保険における扶養・被扶養者とは?年の途中の手続きや加入条件も解説
社会保険とは、ケガで働けなくなったり、休業中で給料がもらえなかったりするときの補償をしてくれる重要な保険です。社会保険の扶養とは、自分自身が保険に入らなくても保険給付が受けられることです。扶養に入るためにはいくつかの条件があります。この記事では、社会保険における扶養とはなにかを解説するとともに、扶養・被扶養者の変更に関する注意点について解説します。
目次
社会保険における扶養とは
社会保険における扶養とは、なんらかの理由により一人では生計を維持するのが難しい家族や親族を経済的に援助することをいいます。未成年である子を親が扶養するのが代表的な例といえるでしょう。
そもそも社会保険とは、以下の5項目のことを指します。
ケガや病気で働けなくなった場合の補償や、介護休業や育児休業など取得した際に受け取る手当など、生活を保護してくれる重要な保険です。被扶養者は自ら社会保険に入らなくても、保険給付が受けられます。
社会保険の扶養に入るには、被扶養者となる要件を満たし、扶養認定を受ける必要があります。扶養認定の条件は「被扶養者の範囲」と「収入要件」の2種類です。それぞれについて解説します。
社会保険の扶養条件1「被扶養者の範囲」
社会保険の扶養条件の一つは、「被扶養者の範囲」です。被扶養者の範囲には「被保険者との同居が必要ない者」と「被保険者との同居が必要ある者」の2種類があります。
被保険者との同居が必要ない者
被保険者と同居する必要がない者は、その被保険者の「配偶者」「子」、「孫」及び「兄弟姉妹」ならびに「直系尊属」の三親等までです。
「配偶者」には、民法上の「婚姻関係」はないけれども生活を共にしている夫婦同様のいわゆる「事実婚」である場合も含まれます。
「直系尊属」とは、父母や祖父母など自分よりも上の世代の中で、被保険者本人と直接つながっている親族のことです。養父、養母は直接の血のつながりがありませんが「養子縁組」を行った時点で、血族間にあるのと同じ親族関係として「直系尊属」となります(民法第727条)。
また、自分より上の世代でも、叔父や叔母といったように、兄弟姉妹の関係でつながった親族は「傍系尊属」となりますので注意が必要です。
被保険者との同居が必要ある者
「配偶者」「子、孫及び兄弟姉妹」「直系尊属」以外にも、同居を条件に社会保険上の扶養にできる者がいます。
例えば「甥っ子・姪っ子」や「ひ孫」「伯父母」など「3親等以内の親族」に当てはまる場合には、同居していれば扶養と認められます。
また「内縁関係の配偶者の父母及び子」も同居であることを条件に扶養にすることができます。内縁関係の配偶者の父母及び子は、その内縁関係の配偶者が死亡したあとも引き続いて同居する場合、被扶養者として認定されることになっています。
「3親等以内の親族」の「親等」とは親族関係の世代を表す単位で、次の図のように数えます。

引用:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
0親等は本人と配偶者です。1親等には本人の父母と配偶者の父母、そして本人の子どもが入ります。2親等は本人と配偶者の祖父母、そしてそれぞれの兄弟姉妹も含まれます。自分たちの孫も2親等です。
兄弟姉妹は一見すると1親等のように思えるかもしれませんが、本人から直接つなげるのではなく、父母にさかのぼって1親等、そこから兄弟姉妹への横のつながりが1親等になるので2親等となります。3親等は本人と配偶者の曾祖父母、ひ孫とその配偶者が含まれます。
さらに、本人、配偶者の父母の叔伯父母、それぞれの兄弟姉妹の子どもである甥姪・その配偶者も3親等内の親族です。
社会保険の扶養条件2「収入要件」
社会保険の扶養条件には、親族関係のほかに、扶養となる方自身の収入要件もあります。
収入要件は「年間収入130万円未満」
被扶養者の収入に関する要件は「年間収入が130万円未満であること」と定められています。ただし、60歳以上である、または障害者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められます。しかし収入要件はこれだけではありません。
被扶養者の定義は、「主として被保険者の収入によって生計を維持されており、後期高齢者医療制度などの対象とならない75歳未満の人」となります。
つまり、130万円または180万円未満の年間収入だとしても、その収入によって生計を維持しており、被保険者の収入により生計が維持されているとはいえない場合は、被扶養者とは認められません。誰の収入で生計を維持しているかどうかは、次の基準で判断されます。
- 同居の場合
収入要件を満たし、かつ、被保険者(扶養者)の収入の1/2未満であること - 同居でない場合
収入要件を満たし、かつ、収入が被保険者からの仕送りより少ないこと
ただし同居している場合には例外があります。それは、収入が被保険者本人の収入の2分の1以上だとしても、被保険者の収入を上回らず、被保険者の収入が生計維持の主となりが当該世帯の生計を維持していると認められる場合です。
このような場合には、扶養条件を満たしていると判断されるケースがあります。
「年間収入」とは?
ここで注意しなければならないのが、「年間収入」です。社会保険における年間とは、1月から12月までのことを指すわけではありません。扶養に入ると決まった日から将来に渡っての1年間の収入です。将来の収入要件を満たすかどうかで扶養に入れるか入れないかを判断します。
「将来的に一定以上の収入の見込みがないので扶養に入りたい」ということになりますので、認定に際しては認定日までの年間収入が問われることはありません。
目安としては、収入が給与所得のみであれば「総支給額が月給108,333円以下」で「年間収入130万円未満」をクリアすることになります。
したがって、例えばアルバイトをしている子どもが6ヶ月で72万円稼いでいたとすると、72万円÷6ヶ月=12万円であるため、扶養にすることはできません。
雇用保険の失業給付を受給している場合は、失業給付を含んだ収入により各保険者が判断します。収入には健康保険の傷病手当金や公的年金なども含まれるため、被扶養者となる従業員の親族の収入状況を確認する際には注意しましょう。なお、事業収入や不動産収入がある場合は、収入から必要経費を差し引いた残額で「年間収入130万円未満」を判定してよいとされています。
従業員の親族がパートやアルバイトで働いている場合には、年間収入が130万円未満だったとしても被扶養者になれない場合があります。厚生年金保険の被保険者数が100人を超える特定適用事象所で働いている場合には、以下の要件をすべて満たすと働いている本人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるからです。
- 所定労働時間が週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当など最低賃金法で算入しないような一定の賃金は除く)
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる
- 学生以外(夜間学生などは除く)
そのため、社会保険における被扶養者となることはできません。
2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大
2024年10月から特定適用事業所の規模要件が緩和され、社会保険の適用範囲が拡大されました。変更前は、101名以上の企業で働くパート・アルバイトが対象でした。しかし、適用範囲が変わり、対象となるのが従業員数51〜100名の企業で働くパート・アルバイトとなっています。
パート・アルバイトでも、週の所定労働時間が20時間以上の場合にのみ適用されます。
また、所定内賃金が8万8000円以上を受け取っていて、2ヶ月以上雇用される予定がある、学生ではないという要件があります。
このように、適用範囲が拡大されたことで、パート・アルバイトでも将来の年金が増えたり、出産手当金や傷病手当金が支給されたり、手厚い保険が受けられるのがメリットです。
配偶者特別控除の計算方法 – 収入と控除額
配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が48万円以上のため、納税者本人(この場合従業員本人)が配偶者控除を受けることができない場合に受けることのできる税法上の所得控除をいいます。配偶者特別控除の金額の計算方法は、配偶者の所得だけではなく、従業員本人の所得の金額によっても控除額が変わります。
以下の表で、縦軸の「配偶者の合計所得金額」と横軸の「控除を受ける納税者本人の合計所得金額」の交差するところが、配偶者特別控除の金額になります。
【配偶者特別控除の金額(令和2年分以降)】
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
引用:配偶者特別控除|国税庁
例えば、配偶者の合計所得金額が102万円(給与所得だけの場合の収入金額は157万円)で納税者本人の合計所得金額が930万円(給与所得だけの場合の収入金額は1,125万円)であれば21万円になります。
社会保険における扶養の要件では「収入金額」がポイントになりますが、配偶者特別控除は税法上の従業員本人が受ける所得控除であり、「所得金額」がポイントになります。したがって、給与収入だけであれば、給与所得控除を差し引いたあとの給与所得を表に当てはめて算出します。「収入金額」と間違えやすいので注意しましょう。
一時的な収入も配偶者控除の対象になる?
パートやアルバイトの一時的な収入も配偶者控除の対象になることがあります。
例えば、会社が9月から10月が繁忙期で一時的に残業が増えてしまい、年間収入が130万円を超えそうな場合です。
その際は、会社が「繁忙金のために一時的に収入が増えた」と証明する必要があります。130万超えてしまったのは一時的なものであるという証明ができれば、引き続き扶養に入れます。
年の途中で社会保険の扶養に入る条件や手続き
扶養者が仕事を辞めてしまったり、出産して子どもが生まれたりして、年の途中から社会保険の扶養に入ることになる場合もあるでしょう。その際、どのようなことを確認すればよいのか、以下に解説します。
- 年の途中または月の途中で扶養に入る場合の条件
- 加入手続きについて
- 加入期日について
1つずつ見ていきましょう。
年の途中または月の途中で扶養に入る場合の条件
社会保険の扶養の場合、入る時点から将来に向かって年収が130万以内に収まるかが条件です。
例えば、これまで会社員として働いていて、年収130万円を超えている場合です。会社を退職したために、現時点からすぐに働かない場合は無収入です。または、パートなどする際でも、収入が130万円以内でなければなりません。
この2つの条件を満たせば、配偶者の扶養に入れます。
生まれたばかりの子どもはもちろん無収入であるため、扶養に入れます。
加入手続きについて
扶養に入れる条件が合えば加入できるため、会社で社会保険の加入手続きを行います。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
- 続柄が確認できる書類
- 被扶養者の戸籍謄本(抄本)または住民票の写し
- 被扶養者の収入が確認できる書類(源泉徴収票や給料明細書など)
被扶養者の収入が確認できる書類に関しては、事業主が従業員に確認し、認めると添付書類は不要です。
加入期日について
加入期日は、扶養に入ると決まった日から原則5日以内です。
社会保険の扶養に入れる日も合わせて確認しましょう。
- 子どもが生まれた場合の加入日は、子どもの生年月日
- 扶養者が仕事を辞めた場合は、仕事を辞めた日の翌日
条件等を確認し、速やかに加入手続きを行いましょう。
年の途中で社会保険の扶養から外れる条件や手続き
扶養者が仕事を始めて、年の途中から社会保険の扶養を外れることになった場合、どのようなことを確認すればよいのか、以下に解説します。
- 年の途中または月の途中で扶養から外れる場合について
- 外れるときの手続きについて
- 外れる期日について
1つずつ見ていきましょう。
年の途中または月の途中で扶養から外れる場合について
社会保険を途中で扶養から外れる場合は、扶養者の見込み年収が130万円を超えるとわかったときです。
例えば、130万円を12ヶ月で割ると、10万8333円となります。月に11万以上を継続的に受け取っている場合には、130万円を超えると予想ができます。
一時的な増収であれば、そのまま扶養に入れますが、収入が増え続ける場合には、扶養から外れるため、注意しなければなりません。
外れるときの期日や手続きについて
扶養が外れるとわかれば、外れると確定した日から5日以内に手続きを行います。扶養している者の会社側が、被扶養者(異動)届を記入して提出します。
その際、保険証を返却するのを忘れないようにしましょう。扶養から外れた日より扶養者の保険証は使えなくなるためです。
扶養から外れたら速やかに新しい保険への加入を進めましょう。
社会保険加入状況の無料テンプレート
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
社会保険の扶養・被扶養者の変更に関する注意点
社会保険の扶養・被扶養者の変更に関する注意点として3つ挙げます。
- 親を扶養に入れるときには、条件を確認する
- 扶養は加入日をさかのぼれないため注意する
- 社会保険の適用範囲を確認する
扶養の加入や変更は速やかに手続きをしなければなりません。変更などがあれば、すぐ伝えてもらうように従業員へ周知しましょう。
1.親を扶養に入れるときは条件を確認する
扶養は配偶者や子どもだけでなく、親も扶養に入れます。親の扶養にも条件があるため、以下の項目を確認しましょう。
- 親の年収が130万円未満であること
- 60歳以上であれば180万円未満であること
- 親が扶養者と同居している場合、扶養者の半分未満の収入であること
- 親が75歳未満であること
別居している場合は、定期的に仕送りをしていれば、扶養に入れる可能性があります。親を扶養に入れたいと申し出た場合は、よく確認しましょう。
2.扶養は加入日を遡れないことがあるため注意する
配偶者が退職して扶養に入るときは、社会保険の扶養に入る手続きを行います。その際、退職した翌日から扶養に入れます。
もし、退職をしてしばらく扶養に入る手続きをしておらず、退職日翌日から扶養に入りたいと言われた場合、申し出た日からの加入となります。退職日翌日までさかのぼって加入はできないことに注意が必要です。
そのため、扶養者の変更がないか、定期的に従業員に確認することが重要です。扶養に入れる場合には、速やかに手続きを行いましょう。
3.社会保険の適用範囲を確認する
2024年10月に社会保険の適用範囲が改正されました。従業員が51〜100人の場所でアルバイト・パートをしている方も社会保険に加入する対象となりました。
そのため、週に20時間働いており、月額8万8000円以上賃金を受け取っている場合などは、自分で保険に入る必要があります。
社会保険手続き担当者は、扶養に入っている方の会社の規模や年収などよく確認して、そのまま扶養に入るのか、外れなければならないのか、判断しましょう。
社会保険の扶養の条件を確認しよう
この記事では、社会保険の扶養について解説しました。扶養に入れるときの条件は、扶養の範囲や、扶養者の年収の2つです。
同居している場合としていない場合、年収130万未満であることなど確認する必要があります。
加入する際は、年の途中や月の途中でも可能です。扶養に入ると確定したら5日以内に手続きを行いましょう。手続きには、収入がわかる書類や登記簿謄本が必要です。
扶養から外れないといけない条件は、扶養者の年収が130万円を超えることです。超えてしまう場合は、自分で社会保険に入るように伝えましょう。
扶養に入ると、保険料の支払いはないため負担が減ります。子どもが生まれたり、配偶者を扶養に入れたりする場合は、条件を確認し手続きをしましょう。
よくある質問
社会保険における扶養とは何ですか?
社会保険における扶養とは、未成年や高齢であるなどの理由で、一人では生計をたてるのが難しい人を家族や親族が援助することをいいます。扶養に入るには、あらかじめ決められた扶養条件を満たす必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
社会保険の関連記事
新着記事
60歳以降の再雇用、給与の目安は?決め方や下がる理由、違法となる場合を解説
60歳以降も働き続ける再雇用制度を利用する方が増えていますが、多くの人が気にするのは、再雇用後の給与ではないでしょうか。定年前よりも減額されることが一般的ですが、どのくらい下がるのか、どんな場合に違法になるのかを理解しておくことは、安心して…
詳しくみる平均賃金の端数処理とは?欠勤や3ヶ月未満の計算方法や具体例を解説
平均賃金における端数処理は、平均賃金の計算時に生じる1銭未満や、手当支給時の1円未満の扱いを定めたものです。この記事では、平均賃金の計算方法や含める賃金の範囲、算定期間の考え方、そして端数処理の具体例までを簡潔に解説しています。 平均賃金の…
詳しくみる不正打刻とは?タイムカードの事例や違法時の処分、対策を解説
不正打刻は労働時間を偽り、賃金や残業代の不当支払いにつながる行為です。放置すれば労働基準監督署の是正勧告や送検、詐欺罪の適用など企業にも従業員にも重大な不利益が生じます。本稿では法的リスク、発覚プロセス、判例、処分方法、そして最新勤怠システ…
詳しくみる定年後の再雇用は嘱託が多い?メリット・デメリット、給与や契約の決め方を解説
定年後の再雇用では、嘱託契約を採用する企業が多く見られます。少子高齢化が進む中、経験豊富な人材を活かす手段として注目されています。この記事では、嘱託という働き方の特徴、メリット・デメリット、給与や契約内容の決め方、企業が留意すべき点をわかり…
詳しくみる従たる給与についての扶養控除等申告書の提出とは?意味や書類の書き方を解説
副業や兼業で複数の勤務先から給与を得ている方にとって、「従(じゅう)たる給与についての扶養控除等申告書」は、所得税の源泉徴収手続きにおいて大きな意味合いを持つ書類です。この申告書の提出状況は、毎月の源泉徴収税額や年末調整、さらには確定申告の…
詳しくみる残業時間の端数処理とは?1分と15分単位の違い、計算例を解説
残業代の計算時に「端数処理」はどのように行えばよいのでしょうか。1分単位で処理すべきか、15分単位でも問題ないのか。 労働基準法では、原則として労働時間は1分単位で計算し、働いた分すべてに賃金を支払うことが求められています。ただし、一定の条…
詳しくみる