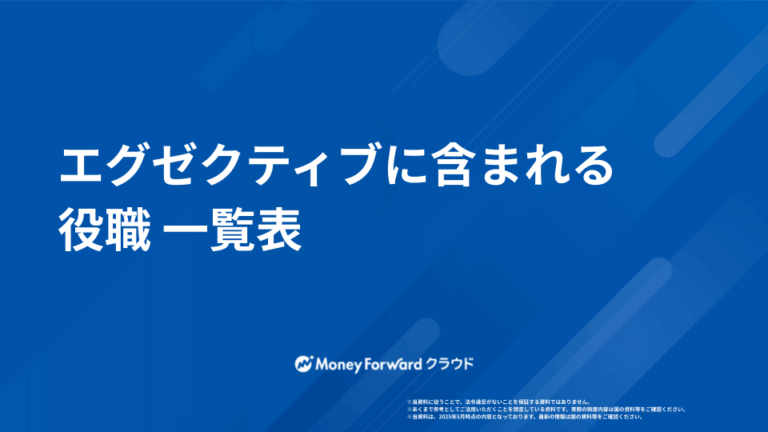- 更新日 : 2025年6月23日
エグゼクティブとは?意味や該当する役職を紹介
近年、日本でもよく耳にするようになった「エグゼクティブ」という言葉ですが、ビジネスにおけるその意味をご存知でしょうか。いざ聞かれると分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、そもそもエグゼクティブとは?からエグゼクティブに含まれる役職の種類、エグゼクティブと言われる役職になる方法を解説します。
目次
エグゼクティブとは?
エグゼクティブは英語で「Executive」と表記し、複数の意味があります。意味には「実行力のある」「役員」「重役」「重要な」「高級な」「優雅な」「特別な」「上級の」などがあり、ビジネスシーンで使われる時の意味とビジネスシーン以外で使われる時の意味には違いがあります。以下、ビジネスで使用される意味とビジネス以外で使用される意味について解説します。
ビジネスで使用される意味
エグゼクティブという言葉がビジネスで使用される時は、会長や社長、役員をはじめとする上級管理職のことを指します。もとの意味である「実行力のある」「役員」「重役」が転じて、企業経営に深く携わる上級管理職や幹部を意味するようになりました。
また、他の語句を付け加えた「エグゼクティブサマリー」という使われ方もあり、事業計画書の中でも大事なポイントをまとめた要約のことを指します。一般的には事業計画書の1ページ目に記載されている内容で、投資家に伝えたい要約などのことを表します。このように、ビジネスでは「重要な」という意味で使われる場合もあります。
ビジネス以外で使用される意味
エグゼクティブという言葉がビジネス以外で使用される時は、「高級な」「優雅な」「特別な」という意味で使われることが多いです。例えば、ホテルの「エグゼクティブルーム」や映画館の「エグゼクティブシート」などが挙げられます。「エグゼクティブ会員」といった場合には「上級の」という意味で使われることもあります。
エグゼクティブに含まれる役職の種類
ビジネスで使用される場合には上級管理職のことを指すと前述しましたが、実際にどのような役職が含まれるのでしょうか。続いて、エグゼクティブに含まれる役職の種類を紹介します。
最高経営責任者(CEO)
CEOは「Chief Executive Officer」の略語で、取締役会で決定した方針に従って会社を経営する役職のことを指します。代表取締役との違いは、代表取締役は企業の最高責任者である一方で、最高経営責任者は責任の範囲を経営に限定した「経営に対する責任者である」ということです。ですが、日本では代表取締役会長や代表取締役社長などが最高経営責任者を兼務しているケースが多いです。
最高執行責任者(COO)
COOとは「Chief Operating Officer」の略語で、実務や運営に対する責任を負う役職のことを指します。最高経営責任者に次ぐNo.2のポジションとして考えられることが多く、最高経営責任者が策定した経営戦略を実行するための、具体的な業務オペレーションの構築を担います。日本では代表取締役会長が最高経営責任者を、代表取締役社長が最高執行責任者を兼務するケースが多いです。
最高技術責任者(CTO)
CTOとは「Chief Technical Officer」の略語で、企業の技術面に関する責任を負う役職のことを指します。製造技術・IT・研究開発技術などの技術部門のトップポジションです。最高技術責任者は、技術職として優れた能力が備わっていると同時に、経営視点から戦略的に技術の活用・方針策定などを行う能力も求められます。デジタル変革の潮流が強まっている今、重要視されるようになってきている役職の1つです。
最高財務責任者(CFO)
CFOとは「Chief Financial Officer」の略語で、財務や会計に対する責任を負う役職のことです。予算やコストの管理・資金調達・財務戦略立案などを担います。最高財務責任者には、財務や会計に関する専門知識に加えて、経営的観点で財務戦略を立案して企業価値を向上させるスキルや、高度なコミュニケーションスキルも求められます。単に資金管理をするだけではなく、資金面からマネジメントする点がポイントです。
最高情報責任者(CIO)
CIOとは「Chief Information Officer」の略語で、情報戦略を統括する役職のことを指します。最高情報責任者はシステム構築をするだけではなく、経営戦略に基づいた情報化戦略の立案をすることや、部門を超えてそれを実行することを担います。効果的なIT投資を行うことで売上アップやコストダウン、顧客満足度の向上など、企業価値を増大させていくことが求められてる役職で、重要性が増している役職の1つです。
エグゼクティブプロデューサー
エグゼクティブプロデューサーはプロデューサーよりもさらに上級職で、何かの制作における管理職・幹部のことを指します。制作費の捻出や企画作成、脚本作りから完成まで、全てにおいて責任を負う役割です。基本的には出資側のプロデューサーのことを指しますが、制作会社側でも社長など最終判断を下す責任者のことをエグゼクティブプロデューサーと呼ぶこともあります。
エグゼクティブマネージャー
エグゼクティブマネージャーとは、経営を担う上級管理職のことを指します。基本的には代表取締役会長・社長・専務・常務・事業部長といった上級のマネジメント層をエグゼクティブマネージャー、もしくはエグゼクティブと呼びます。また、一般的に役職名が「Chief」から始まる「Cレベル人材」がこのエグゼクティブマネージャーに含まれます。こうしたCレベル人材は外資系企業の経営幹部によくみられる役職です。
エグゼクティブと言われる役職になる方法
エグゼクティブとは企業経営に携わる上級管理職であることがわかりました。では、エグゼクティブになるためにはどうしたら良いのでしょうか。続いて、エグゼクティブになる方法を解説します。
現職でのキャリアアップを狙う
1つ目は、現職でエグゼクティブにキャリアアップする方法です。重要なポストを任せてもらうためにはマネジメントの経験・実績と経営の知見が必須です。部長などの管理職のポストに挑戦したり新規事業の立ち上げ責任者を担ったりしながら、エグゼクティブを目指します。
転職をする
転職を通してエグゼクティブになることも方法の1つです。エグゼクティブを目指して現職で努力を重ねていても、上級管理職に空きポジションがあるとは限りません。現職でのキャリアアップが望めない場合は、培ったスキルや実績を活かして社外へ転職を検討するという選択肢もあります。
自分で起業する
自分で起業をして、自ら経営上で重要なポジションに就くというのも方法の1つです。一人で起業した場合には自身が最高経営責任者となるため、必然的にエグゼクティブ職に就くことができます。そのためにも現職でマネジメントの経験を積んだり、個人で経営の勉強をしたりしておく必要があります。
ヘッドハンティングの対象になる
エグゼクティブを目指すにあたって、ヘッドハンティングを待つという手法もあります。その場合、異業種交流会へ参加したり、ビジネス系SNSで実績をアピールしたりして、自分から人脈形成に取り組む姿勢が欠かせません。また、登録型のヘッドハンティングサービスに登録して、スカウトを待つのも方法の1つです。
エグゼクティブになるには準備が必要
ここまで、エグゼクティブに含まれる役職の種類や、エグゼクティブと言われる役職になる方法について解説しました。エグゼクティブの概要や役職の種類、なる方法などについて、ご理解いただけたでしょうか。エグゼクティブになるためには、どのような方法をとっても事前に準備し努力を重ねることが重要です。エグゼクティブを目指したい方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
評価基準とは?適切な作り方や具体例、数値化の方法、ポイントを解説
評価基準とは、主に人事評価に用いられるもので、どのくらい目標を達成できたかなどを評価する基準のことです。人事評価を適切に運用するには欠かせないものであり、従業員の意欲を向上させることができます。本記事では、評価基準とはどのようなものか、適切…
詳しくみるセルフハンディキャッピングとは?陥る原因や克服方法を具体例と共に解説
セルフハンディキャッピングとは、故意にハンディキャップを設ける行為を指します。わざと不利益を背負うことで、失敗した際に責任転嫁をして自分を守ることができます。自己防衛ができ傷つかなくて済むというメリットがある一方、自分の能力を発揮できなくな…
詳しくみる社員の資格管理をエクセルで効率化するには?テンプレートの活用方法も解説
社員が保有する資格の管理は、人材育成やコンプライアンスの観点から重要ですが、多くの企業では複雑で煩雑な作業となっています。そこで便利なのが、多くの企業で普及しているエクセルです。エクセルを上手に活用することで、社員資格の取得状況や更新期限を…
詳しくみる労働基準法第9条とは?労働者の定義や判断基準などをわかりやすく解説
労働基準法は労働者を保護するための法律ですが、「そもそも労働者とは誰を指すのか」を明確に定めているのが労働基準法第9条です。本記事では、労働基準法第9条において誰が労働者に含まれ、誰が含まれないのかを最新の法改正や判例、ガイドラインを踏まえ…
詳しくみる勤務態度はどう評価すべき?具体的な項目や方法、ポイントを解説
勤務態度とは、仕事に対する責任感や協調性、積極性など、働くうえでの姿勢や行動全般を指す言葉です。 社員一人ひとりの勤務態度が、企業の成長に大きな影響を与えることは言うまでもありません。しかし、勤務態度をどのように評価すればよいか悩んでいる企…
詳しくみるジョブディスクリプション(職務記述書)とは?目的や書き方を解説!
ジョブディスクリプションは職務記述書とも呼ばれ、職務内容、求められるスキル等をまとめた書類のことです。ジョブ型雇用という雇用システムで活用されるもので、経団連の提言などでジョブ型雇用の導入機運が高まり、注目を集めています。この記事ではジョブ…
詳しくみる