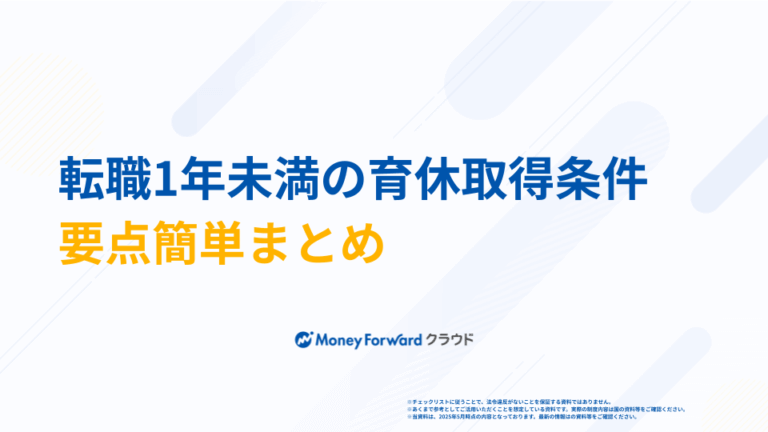- 更新日 : 2025年10月31日
転職して1年未満だと育休は取れない?伝え方や給付金について解説
転職して1年未満でも、2022年4月の法改正により原則として育児休業の取得が可能です。ただし、労使協定が存在する場合や、雇用形態によって制約を受けることもあります。
この記事では、転職して1年未満でも育休を取得できる条件や具体的なケースを紹介します。スムーズに育休を取得するためのポイントも解説するので、参考にしてみてください。
目次
転職して1年未満だと育休は取れない?
転職後の育児休業取得は、2022年4月の育児・介護休業法改正によって、原則勤続年数に関係なく取得できるようになりました。
なお、雇用形態によって細かな違いがあるため、詳しく解説します。
原則1年未満でも育休を取得できる
正社員のような無期雇用契約の場合は、原則として入社1年未満でも育児休業を取得できます。
ただし、会社が労使協定を結び「入社1年未満の従業員を対象外とする」規定を設けている場合は例外なため、注意が必要です。
また、パートタイム労働者や契約社員などの有期雇用でも、「子どもが1歳6ヶ月に達するまでに労働契約が満了することが明らかでない場合」は取得可能です。令和4年4月の法改正で、それまで有期雇用契約に課されていた「入社1年以上の勤続」という条件が撤廃されたため、1年未満の有期雇用従業員も育休を申し出る権利を持つことになりました。たとえば、契約が1年更新で、更新の可能性が高い人や、更新実績がある人などが該当します。
なお、派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元の企業との契約が基準です。派遣元との契約が継続的で、子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約満了が明らかでないなら、育休を取得できます。
参考:厚生労働省|改正育児・介護休業法について(8p・17p)
転職して1年の基準とは育休の申し出の時点
育休が取得できるかの判断基準は、育休を申し出た時点での勤続期間です。育休を開始するタイミングではなく、申し出を行った日付が基準となります。
育休の取得を計画する際には、申し出時点で勤続期間が1年に達しているかを確認することが重要です。
たとえば、転職後11ヶ月目に育休を申し出た場合は、その時点では勤続1年未満とみなされます。育休を実際に開始する日が勤続13ヶ月目でも、申し出時点で1年未満なら労使協定による制限の対象となることがあるので、注意しましょう。
一方、勤続1年を過ぎてから申し出をすれば、育休開始日がそのあとでも取得が認められる可能性が高いです。
このため、入社後のタイミングを考慮した育休取得の計画が大切です。出産予定日や家庭の状況から育休の開始時期を逆算し、申し出をするタイミングを計画するとよいでしょう。
申し出が早すぎると勤続1年に達していない場合があるため、慎重なスケジュール管理が必要です。
労使協定により取得できない場合もある
企業は、労働組合や従業員の代表と締結した労使協定によって、下記の従業員を育児休業の対象外とできます。
- 入社1年未満の従業員
- 申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
労使協定とは、会社と従業員の代表が合意のもとで締結する、労働条件に関する取り決めです。この中に「入社1年未満の従業員を育休対象外とする」旨が含まれていれば、会社は育休取得の申し出を拒否できます。
しかし、労使協定があるからといって、自動的に育休取得ができないわけではありません。内容や運用状況によっては、柔軟な対応が可能な場合もあります。
育休を取得したい事情があるなら、特例として認めてもらえないか交渉することも視野に入れましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ
育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。
従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと
育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。
この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。
転職1年未満の育休取得はどう伝えたらいい?
育休取得を希望する際には、適切なタイミングと方法で上司や人事に相談しましょう。
まず、自分の勤務先の就業規則や労使協定を確認します。育休取得が可能か、条件や規定を把握しておくことが大切です。
また、育休期間中の業務引き継ぎや対応策をあらかじめ計画しておきましょう。妊娠が判明したら、出産予定日や希望する育休期間を具体的に伝えるために、早めに上司や人事に相談することが重要です。
伝える際には、相手の立場や職場の状況を考慮した丁寧な言葉遣いを心がけましょう。具体的な伝え方の例は、下記のとおりです。
| 「このたび妊娠が判明しました。出産予定日は○月○日で、産休・育児休業を取得したいと考えています。引き継ぎについては事前に計画を立て、ご相談させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。」 |
伝え方次第で、職場の理解や協力が得られるかどうかが大きく変わる場合もあります。準備を整えた上で相談を進めることが、スムーズな育休取得につながるでしょう。
転職して1年未満の従業員に育休について相談されたら
従業員から育休取得の相談を受けた際は、人事担当者として迅速かつ的確に対応することが求められます。以下のような対応が望ましいでしょう。
| 対応手順 | 詳細 |
|---|---|
| 就業規則や労使協定を確認する |
|
| 育児休業給付金の条件を説明する | 従業員が給付金を受け取るための条件について、明確に説明する |
| 業務の引き継ぎ計画を検討する | 育休期間中の業務分担や引き継ぎについて、チームで共有する計画を立てる |
なお、育休を理由に解雇や降格を行うことは、育児・介護休業法で禁止されています。不当な対応がないように注意が必要です。
転職して1年未満でも育休手当はもらえる?
転職して1年未満でも、一定の条件を満たせば受給できます。ここでは、育児休業中の収入を支える育休手当の条件やもらえないケースなどを解説します。
育休手当(育児休業給付金)がもらえる条件
育児休業給付金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
なお、前職の雇用保険加入期間は通算できるため、転職後1年未満であっても条件を満たせば受給可能です。ただし、前職を退職してから1年以内に転職していること、前職退職後に失業給付を受給していないことが条件となります。
参考:
厚生労働省|育児休業給付関係(11p)
育休手当(育児休業給付金)がもらないケース
給付金の支給には厳格な基準があり、以下のような場合は受給できない可能性があります。
- 雇用保険未加入の場合
- 育児休業開始前2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月未満の場合
- 育児休業中に給与の8割以上が支払われる場合
- 転職後の加入期間が短く、条件を満たせない場合
ギリギリで条件を満たせない際は、会社と相談して就業日数を調整したり、給与支給額を調整したりすれば、受給できる可能性があります。
たとえば、前職の雇用保険加入期間は通算できるため、転職前に一定期間を確保しておくことが重要です。また、退職後1年以内に転職し、失業給付を受け取らなければ受給資格を維持できます。
さらに、雇用契約を継続しながら欠勤や休職を利用すれば、条件を整えられる場合もあります。転職や勤務状況を考慮しつつ、事前に計画を立てることで育休手当を受け取れる可能性が広がるでしょう。
育休手当(育児休業給付金)の支給額
育休手当の支給額は、休業前の給与額にもとづき計算されます。
支給額の計算方法は、下記のとおりです。
| 期間 | 支給額の計算方法 |
|---|---|
| 育休開始から180日間 | 休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×67% |
| 育休開始から181日以降 | 休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×50% |
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額を指します。
月収が30万円の場合は、休業開始時賃金日額が1万円となり、育休開始から180日間は201,000円です。181日目以降は、15万円の給付金がもらえます。
なお、給付金には一定の上限額と下限額が設けられています。2025年7月31日までの支給上限額・下限額(支給日数が30日の場合)は、下記のとおりです。
| 給付率 | 支給上限額 | 支給下限額 |
|---|---|---|
| 給付率67% | 315,369円 | 57,666円 |
| 給付率50% | 235,350円 | 43,035円 |
参考:厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続(10p)
育休手当は原則として、2ヶ月に1回のペースで支給されます。申請後すぐには支給されないため、計画的な資金管理が必要です。
転職して1年未満のため育休は取れないと言われたら?
入社1年未満という理由で育休を取れないと会社から言われた場合、まずは冷静に状況を整理しましょう。労使協定が存在するか、またその内容が法的に適切かを確認する必要があります。
確認すべきポイントは、下記のとおりです。
| 就業規則や労使協定 | 入社1年未満で育休が対象外とされる旨が明記されているか確認する |
|---|---|
| 会社の対応が法律違反ではないか | 総合労働相談コーナーに相談することで、適切な指導が得られる |
育休が取れない場合の代替案として、休職や欠勤を相談する方法もあります。育児休業給付金は受給できませんが、雇用契約を維持しながら育児期間を確保することが可能です。
また、入社1年が経過した時点で、再度育休を申し出ることも検討しましょう。子どもが1歳未満であれば育休を取得する権利が認められます。
育休取得を拒否された場合でも、就業規則や法律を確認し、専門機関に相談することで適切な対処が可能です。
転職して1年未満でも産休は取得できる
産前産後休業(産休)は、育児休業とは異なり、労働基準法で定められた強制的な休業制度です。転職後の勤続年数に関係なく、すべての女性労働者に認められている権利です。
産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産日の翌日から8週間取得できます。ただし、産後6週間は、会社は就業させてはいけないことが労働基準法第65条で定められています。
この制度は、妊産婦の健康管理と母体保護が目的です。正社員、パートタイム、契約社員など雇用形態による制限はありません。
また、産休取得に必要な手続きも比較的シンプルです。出産予定日が近づいたら、医師の診断書を添えて会社に申請すれば取得できます。
参考:
産休手当はもらえるか
産休中は会社からの給与支給義務はありません。しかし、健康保険に加入している場合は、出産手当金を受け取れます。
支給期間は、産前42日間(多胎妊娠は98日間)と、産後56日間の間で給与が支払われていない日が対象となります。
1日あたりの支給額の計算式は「標準報酬月額の12月間の平均額÷30日×2/3」です。標準報酬月額とは、年金や保険料の額の決定に使用される一定ごとに区分した報酬額のことです。
月給30万円の場合は、1日あたりの支給額は約6,700円となります。
また、出産時には健康保険から出産育児一時金が支給されます。金額は下記のとおりです。
| 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合 | 1児につき50万円 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 |
スムーズに産休中の収入を確保するためにも、出産予定が分かった段階で早めに手続きを進め、必要書類を整えておきましょう。
法改正【2025年4月~】育休手当の給付額が実質10割に
2025年4月の改正により「出生後休業支援給付」が新設されます。この改正は、育児休業中の給付額を実質的に休業前賃金の100%相当額に近づけ、育児休業取得を経済的に支えることが目的です。
現行制度では、育休開始から180日間が67%、181日以降は50%が支給されるものでした。しかし、改正後は「出生後休業支援給付」の新設によって、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされます。
さらに社会保険料が免除され、給付金が非課税となるため、手取り額が実質的に休業前賃金と同程度になります。対象者は、男性・女性問わず育休を取得した全員です。
とくに、男性の育児休業取得を後押しする取り組みとして注目されています。
出生後休業支援給付
出生時支援給付金を受給するためには、夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取得することが条件です。支給期間は最長28日間で、父親は「産後パパ育休」の期間内、母親は産後休業後8週間以内(育休開始後8週間以内)が対象期間です。
月収30万円の場合は、現行制度では28日間の育休で約18.8万円の支給でした。しかし、新制度では約22.4万円となり、約3.6万円の増額が見込まれます。
従業員の産休・育休で会社がもらえる助成金
企業が従業員の産休や育休取得を支援した際は、さまざまな助成金を受け取れます。以下におもな助成金制度を紹介します。
| 助成金の種類 | 支給金額 | 支給要件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 両立支援等助成金 出生時両立支援コース (第1種) |
※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円
|
| ||
| 両立支援等助成金 出生時両立支援コース (第2種) |
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算 |
または 第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となる
が2人以上いる | ||
| 両立支援等助成金 育児休業等支援コース | 育休取得時 | 30万円 | 育休取得時 |
|
| 職場復帰時 | 30万円 | 職場復帰時 |
| |
| 働くパパママ育業応援奨励金 (東京都の例) | 働くパパコースNEXT:最大410万円 働くママコースNEXT:最大165万円 | 都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6ヶ月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等 (従業員数300名以下) | ||
参考:
厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(令和6年度版)
企業はこれらの助成金を活用することで、より充実した育児支援体制を整備できるでしょう。
産休・育休に関わる申請書類のテンプレート
産休や育休を申請する際は、正確な手続きが重要です。以下に、マネーフォワードのテンプレートを紹介するので、活用してみてください。
産休申請書テンプレート
産休の申請には、出産予定日や産前休業の開始日を記載した書類が必要です。マネーフォワードが提供するテンプレートを利用すれば、記載項目を漏れなく網羅できます。
以下のリンクからダウンロードして活用してみてください。
育児休業申請書テンプレート
育休の申請では、育児休業の開始日と終了予定日、子どもの状況などを明記する必要があります。マネーフォワードのテンプレートを使用すると、簡単かつ正確に準備できます。
以下のリンクからダウンロードしてみてください。
仕事と育児の両立に向けた制度を理解しよう
育休制度は、働く親が育児と仕事を両立するための大切な制度です。2025年から「出生後休業支援給付」の制度がスタートすることで、経済的な不安なく育児休業を取得できる環境が整います。
従業員が安心して育児に取り組める環境を整えることは、会社の持続的な成長にもつながります。双方が理解を深め、制度を適切に活用していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
同一労働同一賃金は福利厚生にも適用?正社員と非正規の待遇差の見直し方
同一労働同一賃金という言葉を耳にする機会が増え、企業の経営者や人事・労務担当者の中には、その対応に頭を悩ませているかもしれません。給与だけでなく福利厚生にも影響が生じるため、現状の…
詳しくみる会社側が行う入社手続きの流れは?スケジュールが分かるチェックリストとあわせて解説
会社が行う入社手続きには、法律に基づくものや雇用管理に必要なものなどがあります。手続きは多岐にわたるため、人事労務担当者は漏れがないように注意が必要です。 本記事では、会社側が行う…
詳しくみるモンスター社員へ退職勧奨を行う際に取るべき対応とは?注意点や流れを解説
モンスター社員は、職場の雰囲気に悪影響を与え、生産性の低下などを引き起こしてしまう存在です。モンスター社員への対処法のひとつに退職勧奨がありますが、適切に対処しなければ企業側が不利…
詳しくみる自己肯定感とは?低い人の特徴や高める方法、仕事での人材の育て方を解説
自己肯定感は、現状の自分を認め、長所だけではなく短所も含めたありのままの自分を肯定する感覚をいいます。友人関係の構築や仕事など、さまざまな面で人の行動に影響を与えます。 ここでは、…
詳しくみるKJ法とは何の略?やり方や活用方法をわかりやすく解説!
KJ法という言葉を耳にしたとき、「また新しい海外のビジネス用語なのだろうか」「特別なツールが必要な難しい方法なのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。 KJ法は日本の文化人類学者で…
詳しくみる仕事で一人に負担をかけるとパワハラ?適切に割り振るポイントも解説
仕事を一人に負担させることは、時にはパワハラにつながる可能性があります。過度な負担は心身の健康に悪影響を及ぼし、休めない状況になるため、注意が必要です。 本記事では、仕事の偏りがパ…
詳しくみる