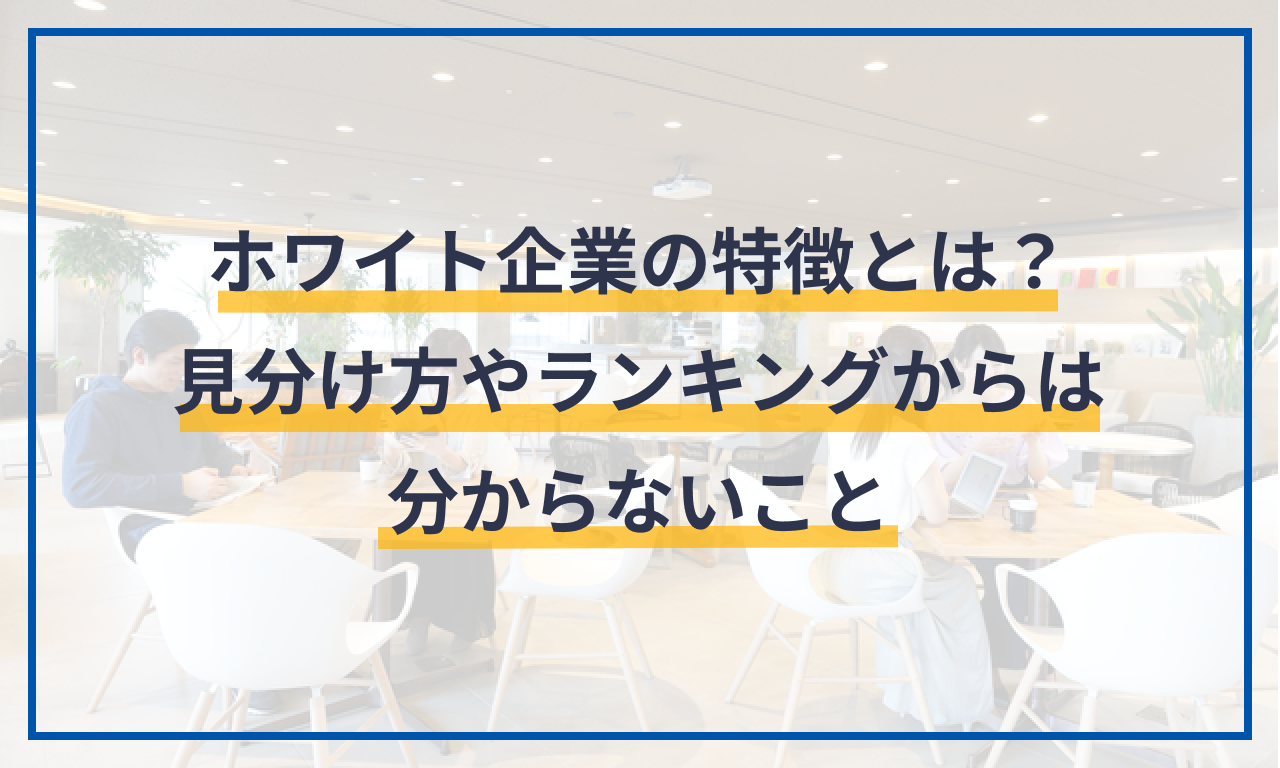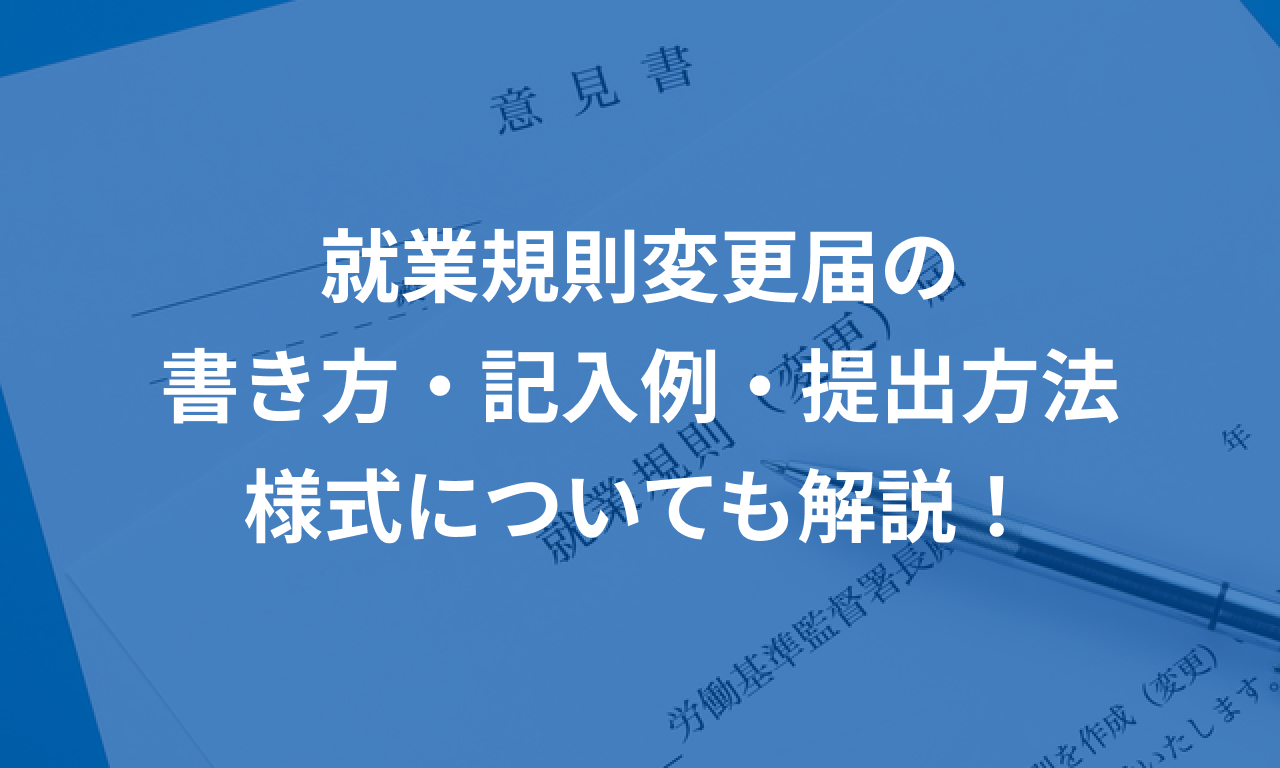- 更新日 : 2022年10月13日
民間事業者がマイナンバーの取扱いで注意すべきポイントとは?罰則もある?

マイナンバー(個人番号)制度とは、行政手続きなどにおいて特定の個人を識別するための制度です。しかし、行政手続きだけではなく、民間事業者でも「社会保障」や「税」の手続きにおいてマイナンバーの収集、利用・提供、保管・廃棄、管理などが必要です。ここでは、民間事業者のマイナンバーの取扱い、注意点、罰則などについて見ていきます。
目次
民間事業者もマイナンバー(個人番号)の取扱いが必要
民間事業者も、事業者自身や法人のマイナンバーだけでなく、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱う場合があります。
というのも、マイナンバーが大きく関わる分野に「社会保障」と「税」があるからです。「社会保障」といえば厚生年金や雇用保険などが含まれますし、「税」には所得税や住民税などが含まれます。したがって従業員の所得の大部分を管理している事業者にあっては、従業員のマイナンバーに触れないわけにはいかないのです。
民間事業者がマイナンバーを記載する場面は?
民間事業者がマイナンバーを記載する場面は、従業員の社会保障や税に関する手続きに必要な時に限られます。社会保障、税のそれぞれの書類の手続きについて見ていきましょう。
税務関係の書類の手続き
税務署に提出する源泉徴収票や法定調書などを提出する手続きの際に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得する必要があります。
また、支払調書や支払報告書を提出する際にも、弁護士や業務委託で仕事を依頼しているフリーランスなどの支払を受ける方からマイナンバー、または、法人番号の提供を受け、手続きします。
社会保障関係の書類の手続き
雇用保険の届け出の手続きの際にマイナンバーの記載が必要です。
具体的には以下の書類になります。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
また、社会保険の届け出の手続きの際には、以下の手続きの際にマイナンバーが必要になります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
- 健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)(3号)届
- 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 など
民間事業者がマイナンバーを利用する際のポイントは?
ここでは、民間事業者がマイナンバーの収集から廃棄まで、利用する際のポイントについて見ていきます。
マイナンバーの収集
マイナンバーを収集する際には、マイナンバーが正しい番号であるということの確認(番号確認)と番号の正しい所持者であることの確認(身元確認)の2種類の本人への確認が必要になります。
従業員がマイナンバーを持っていればマイナンバーカードだけで両方の確認が可能です。通知カードの場合は、通知カードのほかに運転免許証やパスポートなどで確認する必要があります。
利用目的の明示
事業者は自身のマイナンバーや、法人のマイナンバーだけでなく、従業員からそれぞれのマイナンバーを提供してもらわなくてはならない場面があります。
では「○○さん、マイナンバー教えて」と聞くだけでいいのかというともちろんダメで、きちんとルールが定められています。まず、事業者が従業員にマイナンバーの提供を求め、取得できるのは、社会保障・税に関係する手続き書類の作成業務に必要な時だけです。例えば源泉徴収票を作る、あるいは年末調整の書類を作るといった目的がなくてはならないのです。
本人確認の実施
また、上述したように、マイナンバーを収集する際には、番号確認と身元確認の2種類の本人確認が必要です。
本人確認を行った上で取得した従業員のマイナンバーを「使う」「渡す」ことができるのも、同じく社会保障・税関連の業務の時だけです。
マイナンバーの利用・提供
マイナンバーの利用の範囲は、法律で決められた社会保障や税ならびに災害対策関係の事務に限定されています。
また、社会保障、税に関する手続き書類作成の事務作業を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることができるとしています。この限定された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
マイナンバーの保管・廃棄
マイナンバーは番号法に書かれてある場合以外は保管してはいけないことになっています。ではこの「番号法に書かれてある場合」とはどういう場合なのでしょうか。これは端的に「マイナンバー関連業務のために保管する場合」です。
以下のような場合は全てマイナンバー関連業務を行うために必要なことなので、保管が許されます。
- マイナンバーの提供を従業員から受けるにあたって提示される本人確認書類(マイナンバーカードや身元確認書類)をコピーして保管する
- 個人番号が書かれている手続き書類をパソコンのデータとして保管しておく
対してマイナンバー関連業務に関係なく、単に社内資料として保管する場合は番号法違反です。
また従業員が退職するなどしてそのマイナンバーが必要なくなるなど、従業員のマイナンバーを関連業務に用いることがなくなった場合はできるだけ速やかに廃棄をする必要があります。とはいえこれもその都度ではなく、毎年度末などあらかじめ廃棄のタイミングを決めるなどしていれば、事務手続き上の効率性を考慮しても問題ないとされています。
ただし、最も注意しなければいけないのは、保管をするにせよ、廃棄をするにせよ、常にマイナンバーの安全管理措置は講じておく必要がある、という点です。そのため、保管や廃棄に関しても社内ルールを設け、それを担当者などに浸透させておかなくてはなりません。
マイナンバーに関する主な罰則とは?
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」)には、マイナンバーを不正に使用・提供した場合や、人をだまして取得した場合には、最も厳しい罰として4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることとなっています。
このような罰則を受けるのは基本的に不正を働いた本人ですが、場合によっては事業者にも罰金刑が課されることがあります。そのような従業員を身内から出さないよう、あらかじめ対策をとっておくべきでしょう。
実行に移しやすい対策の1つはマイナンバー制度導入にあたっての社内ルール(=内部統制)を設けることです。例えばマイナンバーに関連する業務に携わる担当者を決めたり、その担当者を各自治体が開催している企業向けマイナンバーセミナーに参加させたりなどして制度への理解を深めてもらうといいでしょう。他にも関連業務を行うパソコンを決めて、担当者以外がマイナンバー関連の情報に触れられないようにしておく措置も有効です。
特定個人情報に関する安全管理措置とは?
番号法は、マイナンバーを利用できる事務の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲などを制限しています。よって事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止などのために安全管理措置を検討するにあたっては、下記を明確にすることが重要です。
- マイナンバーを取り扱う事務の範囲
- 特定個人情報などの範囲
- マイナンバーならびに特定個人情報を取り扱う事務に従事する従業者
特定個人情報の安全管理措置について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。
マイナンバーは厳格な取り扱いを行いましょう
マイナンバーは、収集時、利用・提供時、保管・廃棄時のそれぞれの段階ごとに厳格な管理が必要です。法律に違反した場合には罰則もありますので、事業者ごとに適確な安全管理体制を検討して、安全管理措置を講じていくことに注意して取り扱っていきましょう。
よくある質問
民間事業者がマイナンバーを利用する際のポイントは?
マイナンバーを利用するにあたっては、収集時には利用目的の明示と厳格な本人確認の実施、利用・提供時には利用目的以外の利用を行わない、保管・廃棄時には、安全管理措置を講じるところがポイントになります。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーに関する主な罰則とは?
マイナンバー制度の主な罰則は、特定個人情報ファイルの提供について、懲役4年もしくは罰金200万円または併科、マイナンバーの提供または盗用について、懲役3年もしくは罰金150万円または併科などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。