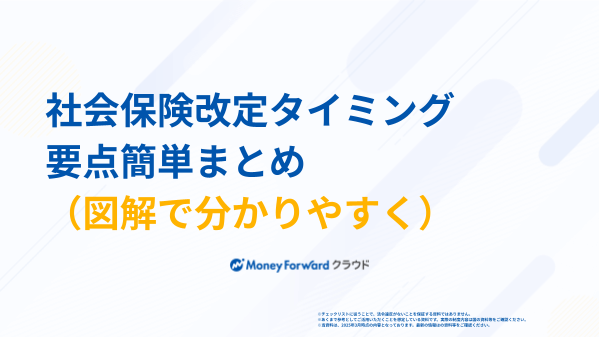- 更新日 : 2025年6月23日
社会保険の改定まとめ!社会保険の種類・対象・保険料の計算方法も解説
日本の社会保険制度は大きな改定期を迎えており、企業の人事・法務担当者や被保険者にとって最新情報の把握が欠かせません。社会保険改定のポイントとして、短時間労働者への適用拡大、保険料率の変更などが挙げられます。
本記事では、これらの改定内容と注意すべきポイントを解説します。
目次
社会保険とは?
社会保険とは、病気やけが、出産、老後、失業など、人生で起こりうるさまざまなリスクに備えるための公的な制度です。国民が安心して生活できる社会の土台を支える仕組みとして、すべての働く人とその家族に深く関わっています。給与から自動的に差し引かれる保険料の内訳にも社会保険が含まれており、企業に勤めている人にとっては身近な制度のひとつといえるでしょう。
社会保険制度の目的は、個人では備えきれないリスクに対し、社会全体で支え合うという考えに基づいています。そのため、加入は任意ではなく、法令によって定められた条件に該当する場合には自動的に加入することとなります。企業側にも一定の手続き義務があり、従業員を雇用した際には社会保険の手続きを適切に行う必要があります。
働く環境の変化や多様な働き方の広がりにあわせて、社会保険の適用対象は拡大されつつあり、以前は対象外とされていたパートタイマーや契約社員なども一定の条件を満たせば加入できるようになっています。これにより、非正規雇用の方も老後や病気への備えができるようになり、社会全体のセーフティネットとしての機能がより強化されています。
社会保険の種類
社会保険にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる目的や給付内容を持っています。企業に勤める労働者が主に関係するのは「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの制度です。これらは「社会保険」「労働保険」として区別されることもありますが、給与計算や保険料の納付においては一体的に扱われる場面も多くなっています。
健康保険は、病気やけがの際に医療機関を受診した場合の自己負担額を軽減するための制度です。医療費の一部を保険者が負担することで、経済的負担を軽くする仕組みとなっています。また、出産手当金や傷病手当金など、就労不能時の生活を支える給付も用意されています。
厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の年金を支える制度です。自営業者などが加入する国民年金に加え、会社員や公務員が上乗せで加入することで、老後の生活資金に余裕を持たせる役割を果たします。厚生年金に加入している期間や報酬額によって、将来受け取れる年金額が決まります。
介護保険
介護保険は、40歳以上の被保険者を対象とした制度で、要介護状態になった際に介護サービスを受けられるよう支援する制度です。健康保険と一体で運営されることが多く、介護が必要になったときに安心してサービスを利用できる基盤となります。
雇用保険
雇用保険は、失業した場合や育児休業を取得した場合などに給付が支給される制度です。失業給付や育児休業給付、教育訓練給付などが含まれており、再就職までの支援やキャリアアップの促進にもつながっています。
労災保険
労災保険は、業務中や通勤途中に事故や病気が発生した際に、治療費や休業補償を支給する制度です。労働者を雇用するすべての事業者に適用され、保険料は全額事業主が負担する形となっています。
このように、社会保険は複数の制度によって構成されており、働く人々の生活や健康、老後を総合的に支える仕組みとなっています。
社会保険の対象者
社会保険の対象者は、その働き方や雇用形態、勤務時間、報酬額などによって異なります。基本的には、常時雇用されている正社員や正社員に近い働き方をするパートタイマーは加入の対象となりますが、近年の制度改定により、短時間労働者についても段階的に適用が拡大されています。
例えば、2016年からは大企業に勤める週20時間以上勤務のパートタイマーが社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるようになり、2022年には対象が中堅企業にまで広がりました。
2024年10月には、従業員数51人以上の企業でも一定の条件を満たす短時間労働者が加入対象となっています。週の労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8千円以上、雇用期間が2か月を超える見込みがあること、かつ学生でないことなどが主な加入条件です。条件を満たす場合、非正規雇用であっても社会保険に加入し、各種の保障を受けられるようになります。
一方、従業員数が50人以下の企業については、現時点では法的な加入義務はありませんが、事業主と従業員が合意すれば、任意で適用を受けることも可能です。従業員の福利厚生を充実させたいと考える企業では、積極的に社会保険の加入を進めているケースも見られます。
また、自営業者やフリーランスなどの個人事業主については、厚生年金や健康保険ではなく、国民年金と国民健康保険に加入する仕組みとなっています。
社会保険制度は働く形態によって加入先や内容が異なるため、自分の状況に応じて正確な知識を持つことが重要です。
社会保険の適用範囲に関する改定の振り返り
日本の社会保険制度では、これまで主に正社員などフルタイムで働く労働者が対象とされてきましたが、少子高齢化や多様な働き方の進展に伴い、パートタイマーや短時間労働者にも適用を広げるための見直しが段階的に行われてきました。
2016年10月の改定
最初の大きな転機となったのは2016年10月の改定です。この改定により、従業員数501人以上の企業において、一定の条件を満たす短時間労働者が社会保険に加入することとなりました。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8千円以上(年収ベースで約106万円)、継続雇用見込みが1年以上、学生ではないことなどが加入条件とされました。
2022年10月の改定
その後、2022年10月には対象企業の規模が従業員数101人以上に引き下げられました。これにより、より多くの中堅企業で働くパートタイマーや契約社員などが新たに厚生年金・健康保険の対象となり、扶養の範囲を意識して働いていた人々の働き方にも影響を与える結果となりました。
2024年10月の改定
さらに2024年10月には、適用範囲がさらに拡大され、従業員数51人以上の企業にも同様の義務が課されることとなりました。この拡大により、中小企業で働く非正規労働者にも厚生年金や健康保険が適用されるケースが一段と増加しています。従業員50人以下の企業については、現時点では義務の対象外とされていますが、将来的にはこの規模要件も撤廃され、すべての事業所での適用が検討されています。
こうした一連の改定は、働く人々のセーフティネットを広げる一方で、企業側にとっては保険料負担の増加や労務管理の複雑化といった課題も伴います。今後の法改正の動向に注目しつつ、柔軟な対応が求められます。
2024年の社会保険の改定まとめ
2024年には社会保険制度の基本に関わる改定が相次ぎました。社会保険適用拡大と保険料率の改定について概要を整理します。
短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月改定)
2024年10月1日施行の改正により、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象がさらに拡大されました。
従来は「従業員101人以上」の企業に勤める短時間労働者(週20時間以上勤務など)が社会保険の適用対象でしたが、この要件が「従業員51人以上」に緩和されています。これにより、従業員51~100人規模の企業で働くパートやアルバイトの方も新たに社会保険に加入する義務が生じました。一方、従業員50人以下の小規模企業については法定適用外のままですが、従業員と企業が合意すれば同様に社会保険へ加入することも可能です。
適用拡大の対象となる短時間労働者には一定の条件があります。週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金8万8千円以上(年収換算約106万円以上)、継続雇用期間2ヶ月超の見込みがあること、そして学生ではないことなどが加入要件です。
この収入要件(106万円)は、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれ、従来から社会保険適用の目安となっていた金額です。2022年10月の改正で従業員101人以上の企業に対し導入されたこの基準が、2024年10月から51人以上の企業にも拡大された形になります。
結果として、パートやアルバイトであっても一定の収入・労働時間がある従業員は幅広く厚生年金・健康保険へ加入し、保険料負担と給付の対象となるよう制度が見直されました。
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の改定(2024年3月)
社会保険料の負担額も毎年見直しが行われています。
2024年3月分(4月納付分)から協会けんぽ管掌の健康保険料率および介護保険料率が改定されました。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが概ね10%前後の水準となっており、介護保険料率(40~64歳対象)は全国一律1.60%に設定されています。
厚生年金保険料率は2017年9月以降変動がなく、引き続き18.3%(労使合計)の固定です。
このように2024年時点では、社会保険料率そのものの大幅な変更はないものの、健康保険について地域別の微調整が行われています。
その他の改定事項(2024年)
労働保険分野では労災保険料率が業種別に3年ぶりに見直されています(一部業種で0.1‰の引き下げ・引き上げ)が、労災保険料は全額事業主負担であるため従業員の給与控除には影響しません。一方、雇用保険料率は前年度から変更なく、一般の事業で労使合計1.55%(うち労働者負担0.6%)が維持されました。このため2024年度中に雇用保険料率に関する給与計算上の変更対応はありません。
ただし、雇用保険二事業(事業主のみ負担)の料率など細目は引き続き注意が必要です。
2025年の社会保険改定の展望
2025年には社会保険制度のさらなる改革が控えており、現在その具体像が議論されています。年金制度改正の一環として更なる社会保険適用拡大や収入要件の見直しが検討されており、企業・被保険者ともに今後の動向から目が離せません。
社会保険適用拡大の検討
厚生労働省の審議会等では、社会保険の適用対象を一層広げる案が議論されています。2024年10月の適用拡大施策が実施されたばかりですが、その先の課題として年収要件や企業規模要件の撤廃が俎上に載せられています。パートタイマーなど短時間労働者への社会保険適用について、現行では年収106万円以上かつ勤務先規模51人以上という条件がありますが、これらのハードルをさらに引き下げ、将来的に企業規模要件を撤廃する方向が検討されているのです。
政府内では、被扶養配偶者(第3号被保険者)の範囲を縮小していくことで全体の保険料負担の公平性を高める狙いがあるとされています。
また、注目されるのが、現在年間130万円とされる「130万円の壁」の行方です。130万円以下の年収であれば夫(または妻)の扶養に入り自身は保険料を納めずに厚生年金に加入できますが、近年の少子高齢化や女性活躍推進の流れを受け、この仕組みの見直しが議論されています。報道や有識者の予測では、2025年の改正でこの扶養範囲の収入上限が大幅に引き下げられる可能性があり、金額は未定ながら年収70万円程度になるのではないかとも言われています。
仮に年収の壁が70万円前後となれば、これまで130万円未満で扶養範囲に収まるよう調整して働いていたパート従業員は、同じ収入を維持することが難しくなります。もっとも、一度に制度を変更すると家計や企業運営への影響が大きいため、段階的に扶養要件を見直す可能性が高いと指摘されています。どのような改正案が立案され国会に提出されるか、注視が必要です。
社会保険料率の動向
毎年見直される社会保険料率について、2025年度(令和7年度)の動向も明らかになりつつあります。厚生年金保険料率は18.3%で据え置きが継続されます。一方、景気動向や雇用保険財政の改善を受けて、2025年4月から雇用保険料率が0.1ポイント引き下げられる見込みです(労使折半で各0.05%ずつ低減)。この改定により、例えば一般の事業では労働者負担が0.6%から0.55%に減り、事業主負担は0.95%から0.90%へ変わることになります。
協会けんぽの健康保険料率は、大分県を除く46都道府県で変更となりましたが、全国平均10%は維持されています。
また、介護保険料率は2025年度に1.59%へ引き下げられ、前年より0.01ポイント減となります。いずれの改定も大幅な負担増減ではありませんが、複数の保険料率が同時に動く年度替わりとなるため注意が必要です。
社会保険料の計算方法
医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険、5つの社会保険料の計算方法について整理してみましょう。
医療保険の計算方法
医療保険、すなわち健康保険の保険料は、給与や賞与に対して「保険料率」をかけることで算出します。計算のもととなるのは「標準報酬月額」と「標準賞与額」です。給与支給額を基に一定の等級に分けて設定され、保険料の計算基礎となります。
計算式は次のとおりです。
例えば、標準報酬月額が30万円、東京都の協会けんぽ料率が10.00%の場合、
30万円 × 10.00%(=0.10)=30,000円
このうち、従業員と事業主で折半するため、実際の負担額はそれぞれ15,000円となります。賞与にも同じ料率が適用され、以下のように計算します。
なお、賞与については年間573万円までが上限です。
年金保険の計算方法
厚生年金保険も同様に標準報酬月額と賞与額をもとに計算され、全国一律の保険料率が適用されます。2024年度の厚生年金保険料率は18.3%(0.183)です。
計算式は次のとおりです。
例えば標準報酬月額が30万円であれば、
30万円 × 0.183 = 54,900円
従業員と事業主が半額ずつ負担するため、それぞれ27,450円ずつの支払いとなります。賞与に対しても以下の式で同様に計算されます。
なお、標準賞与額には1ヶ月につき150万円の上限があるため、高額な賞与に対しては調整が入ります。
介護保険の計算方法
介護保険料は、40歳から64歳の被保険者が対象で、健康保険料と一緒に計算されます。2024年度の介護保険料率は全国一律で1.60%(0.016)です。
計算式は以下のとおりです。
給与が30万円の場合、
30万円 × 0.016 = 4,800円
このうち、従業員の負担は半額の2,400円となります。賞与に対しても同じように、
という式で保険料が計算されます。なお、40歳未満および65歳以上の方には介護保険料の徴収はありません。
雇用保険の計算方法
雇用保険料は、事業の種類ごとに料率が異なりますが、一般の事業における2024年度の料率は1.55%(うち従業員負担0.6%、事業主負担0.95%)です。対象となるのは給与総額であり、標準報酬月額ではありません。
計算式は次のとおりです。
月給が30万円の場合、
30万円 × 0.0155 = 4,650円
このうち、従業員負担は30万円 × 0.006 = 1,800円、事業主負担は30万円 × 0.0095 = 2,850円となります。賞与に対しても同様の計算が行われます。
なお、雇用保険料は給与と賞与の合計額に対して、月ごとに徴収されます。65歳以上の従業員も対象となっているため、すべての労働者に関係する制度です。
労災保険の計算方法
労災保険は、業務中や通勤途中の事故に対する補償を目的とした制度で、全額を事業主が負担します。労災保険料は、年間の総賃金額に対して業種別に定められた料率をかけて計算します。
計算式は以下のとおりです。
例えば、年間賃金が500万円、保険料率が0.5%(0.005)の業種であれば、
500万円 × 0.005 = 25,000円
この金額を事業主が納付します。保険料率は業種ごとに異なり、一般的な事務職では0.3%前後、建設業のようにリスクが高い業種では5%を超えることもあります。
労災保険料は「概算保険料」として年度のはじめに見込みで申告・納付し、翌年に実績ベースで「確定保険料」を精算します。この仕組みによって、企業の負担額が適切に調整されるようになっています。
マイナンバー制度と社会保険手続きの改定
社会保険分野ではデジタル化の動きも加速しています。健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する改定は、被保険者・企業双方に影響の大きいトピックです。
健康保険証の廃止とマイナンバーカード活用(2024年〜2025年)
政府は従来の健康保険被保険者証(保険証)をマイナンバーカードへ統合する方針を進めており、2024年末をもって現行の保険証は原則廃止されました。2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は停止され、今手元にある保険証も有効期限まで(最長で2025年12月1日まで)しか利用できません。2024年12月以降に転職や引越しで保険証の資格変更があった場合、あるいは保険証の有効期限が切れた場合は、マイナンバーカードが健康保険証(マイナ保険証)として必要になります。
マイナンバーカードを持たない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人は、保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)から送付される「資格確認書」を提示することで受診が可能とされています。この資格確認書は申請不要で送付されるため、マイナンバーカード未所持者への救済措置として機能します。
企業・被保険者への影響と対応策
マイナンバーと社会保険手続きの連携が進むことで、企業には個人情報管理の厳重化と事務手続きの効率化という二面の対応が求められています。社員のマイナンバーを取得して健康保険関連の届出(被保険者資格取得届や喪失届、扶養異動届など)をオンライン提出することも可能になりつつあります。人事労務システムのアップデートや担当者の研修を実施し、新しい電子申請の仕組みに対応できる体制を整備しましょう。また、社員からマイナンバーを収集・管理する際には漏洩防止策を講じ、目的外利用をしないよう十分な配慮が必要です。
被保険者(社員)にとっても、マイナンバーカードを活用したオンラインサービスの充実により、自身の年金記録の確認(ねんきんネット)や各種給付申請がスムーズになります。マイナポータルから育児休業給付金のオンライン申請を行う試行が始まるなど、社会保険手続きのデジタル化は利便性向上につながります。社員への周知として、マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法や、紛失時の対応(マイナンバー総合フリーダイヤルへの連絡等)について案内しておくと安心です。
社会保険改定への対応と今後の備え
2024年から2025年にかけて、社会保険制度は大きく見直されつつあります。短時間労働者への適用拡大や保険料率の調整、マイナンバーカードと保険証の一体化など、加入者一人ひとりに関係する改定が進んでいます。これまで対象外だった働き方でも、条件を満たせば厚生年金や健康保険の対象となることがあり、知らないうちに制度が変わっている可能性もあるため注意が必要です。
社会保険への加入は、保険料の支払いが発生する一方で、万一のときの保障や将来の年金受給に直結します。扶養範囲で働いている方にとっても、適用基準の見直しが今後さらに進むことで、これまでと異なる判断が求められる場面が増えていくでしょう。制度の変化を知ることは、自分自身の働き方やライフプランを見直す第一歩です。
社会保険は暮らしの安心を支える土台です。制度改定の内容を正しく把握し、自分に関係する点を確認しておくことが、将来への備えにつながります。今後の動向にも目を向けながら、賢く制度を活用していきましょう。
よくある質問
これまでの社会保険改定についてはどういったものがありましたか?
パート・アルバイトの方の社会保険加入の適用条件が緩和されました。2016年10月には従業員501人以上の企業、2022年10月には従業員数101人以上の企業が対象に加わりました。詳しくはこちらをご覧ください。
2023年以降の社会保険における改定について教えてください
2024年10月から従業員数が51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方が、新たに社会保険の適用対象になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
算定基礎届の提出期限はいつ?遅れた場合の対処法や提出方法を解説
算定基礎届は社会保険料を決定する大切な届出書で、毎年決まった時期の提出が必要です。提出方法には窓口での提出や郵送、電子申請などがあり、会社の規模やシステム環境によって選択できます。 この記事では、算定基礎届の概要や具体的な提出期限、遅れてし…
詳しくみる厚生年金の受給額はいくら?計算方法も解説
企業などに雇われている方のほとんどは、給与から社会保険料として年金や健康保険、雇用保険などを天引きされていることでしょう。このうち年金については、実際にはどのような仕組みで将来いくらもらえるのかなど、気になる方も多いのではないでしょうか。 …
詳しくみる医療費の限度額とは
重症の病気やけがによる長期入院や療養が必要となった場合、自己負担すべき医療費が高額になってしまいます。そのため、個人の負担を軽くできるように、健康保険には「高額療養費制度」が設けられています。 この制度を利用すると、高額な医療費を支払った場…
詳しくみる労災の通院交通費は請求できる?タクシー代や自家用車も対象?条件を解説
通勤災害や業務災害によって通院が必要になった際、交通費は労災で補償されるのでしょうか。労災保険制度における通院交通費の支給範囲や支給条件、公共交通機関やタクシー、自家用車など交通手段ごとの対応、請求方法について詳しく解説します。 労災で交通…
詳しくみる厚生年金に45年加入により受給できる金額が増える?44年特例について
現行制度では、厚生年金は原則65歳以上で受給することができます。しかし、厚生年金制度の改正に伴う経過措置として、一部の被保険者は60歳から受給することが可能です。さらに、厚生年金に44年以上加入した被保険者は、長期加入者特例によって受給額が…
詳しくみる厚生年金の受給前に対象者が死亡した場合 – 手続きや金額
厚生年金に加入している方が亡くなった場合、本人の受給資格はなくなります。遺族は、亡くなった方が受給前だった場合には遺族年金を、受給中だった場合には遺族年金や未支給年金を受け取れる場合があります。ただし、そのためには請求手続きが必要です。本記…
詳しくみる