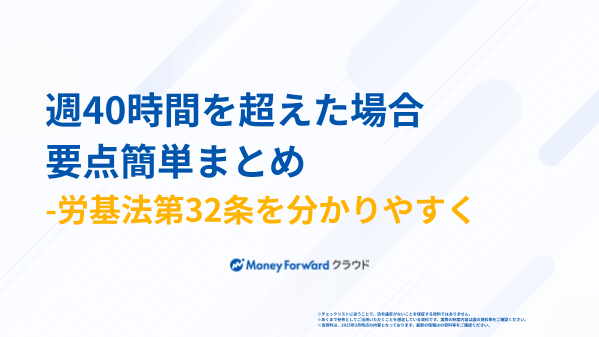- 更新日 : 2025年3月28日
労働時間が週40時間を超えたらどうする?労働時間の計算方法や対応を解説!
労働者に課すことのできる労働時間は労働基準法で厳格に制限されており、原則1日8時間・週40時間以内となっています。超えた場合は36協定を締結し割増賃金を支払わなければなりません。変形労働時間制・裁量労働制・アルバイトなど働き方の多様化に伴い労働時間の数え方が複雑になっているため、この記事では具体的な計算方法等を紹介します。
目次
1週間の労働時間は40時間が上限
冒頭でもお伝えしたとおり、事業主が労働者に課すことができる労働時間は労働基準法によって厳格に定められています。具体的には、1日あたりの労働時間は原則8時間以内、1週間あたりの労働時間は40時間以内(一部の特例事業場では週44時間以内)でなければなりません。労働基準法第32条を一部引用すると、下記の通りです。
労働基準法
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この章では、労働基準法で定められた労働時間の上限について紹介します。
労働時間は「法定労働時間」によって定義される
労働基準法第32条で定められた労働時間の上限は、休憩時間等を除いて原則1日8時間・週40時間です。労働基準法に定められた労働時間のことを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働を課す場合は、労使間で「時間外・休日労働に関する協定」いわゆる「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
なお、法定労働時間外の労働のことを「時間外労働」といいます。時間外労働を課すには36協定を締結した上で、一定の割増賃金を支払わなければなりません。
所定労働時間と法定労働時間の違い
一方、労働条件通知書や就業規則などにおいて、労使間合意に基づき規定された労働時間を「所定労働時間」といいます。所定労働時間は業務形態に合わせて任意に規定することができますが、法定労働時間内でなければなりません。例えば、所定労働時間が7時間のところを9時間働いた場合、以下のような支給が必要になります。
<時給換算1,000円の場合>
- 所定 1,000円×7時間
- 法定内残業 1,000円×1時間
- 法定外残業 1,250円×1時間
所定労働時間が7時間の場合は割増賃金が発生しませんが、時間外労働(法定内残業)には該当します。そのため、時間外手当は発生することとなります。また法定内残業は割増賃金にはあたりませんが、時間外労働には該当するため手当の支給が必要です。
労働基準法で定められた週40時間の定義
労働基準法に定められた「週40時間」は、「法定休日労働」を除く実働時間の累計として定義されます。「法定休日」とは、労働基準法で定められた休日を指します。労働基準法第35条には下記の通り定められており、事業主は労働者に対し週に1日以上、4週間あたり4日以上の休日を与えなければなりません。
労働基準法
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
法定休日に働くことを「法定休日労働」といいます。法定休日労働を課した場合、事業主は休日労働割増賃金を支払う必要があります。時間外労働割増賃金と重複して支給されることはないため、週40時間には含みません。
一方、労使間合意に基づき就業規則等に定められた法定休日以外の休日を「所定休日」といいます。週休二日制などを採用している場合は、1日は法定休日、もう1日は所定休日です。所定休日に働いた場合は法定休日労働には該当せず割増賃金も支払われませんが、法定労働時間として週40時間には含まれます。具体的な計算方法については、次章で詳しく解説しましょう。
週40時間上限が定められた背景 – 働き方改革
従来も労働時間の上限に関する規定はあったものの、厚生労働大臣による勧告に留まっていました。そのため「特別条項付き36協定」を締結することで、上限なく労働を課すことが可能でした。「特別条項」とは、労働基準法で定められた上限時間を越えて時間外労働を課す際に労使間で締結しなければならない条項です。現行制度では年6回以内かつ、通常予見できない臨時的な業務量の増加等に伴う場合にのみ締結することが許されています。
このような背景から、バブル経済とともに過労死などが社会問題化しました。現在では、社会的な課題を解決して多様な働き方を実現するため、「働き方改革」が推進されています。働き方改革関連法の施行に伴い、時間外労働についても上限規制が設けられるのに至りました。大企業においては2019年4月から、中小企業は猶予期間を経て2020年4月から上限規制が適用されます。
週40時間の計算方法・数え方
それでは実際に、週40時間の計算方法を紹介しましょう。週40時間をカウントする際には法定休日労働に加え、1日8時間を超える時間外労働も除いて計算することが重要です。なぜなら、1日8時間を超える時間外労働は、別途時間外労働割増賃金の支給対象となるからです。1日8時間超と週40時間超で、重複して時間外労働割増賃金が支給されないよう、分けてカウントする必要があるのです。
例えば、所定労働時間7時間の労働者が月曜から金曜まで週5日間働き、木曜に3時間残業した場合、法定労働時間を超えた2時間は時間外労働に該当します。週の実働時間が40時間を下回っていても、1日あたりの実働時間が8時間を超過した分に関しては時間外労働として割増賃金の支給対象です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実働時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 10時間 | 7時間 | 0時間 | 0時間 |
| 週の累計 | 7時間 | 14時間 | 21時間 | 29時間 | 36時間 | 36時間 | 36時間 |
| 時間外労働 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 2時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 |
※土曜:所定休日・日曜:法定休日
木曜に実施した3時間の残業のうち、法定労働時間を超過した2時間については週の累計にカウントされない点に注意しましょう。
さらに、1日8時間を超える時間外労働を行わなかったとしても、所定休日を含めた労働時間が週40時間を超過した場合は割増賃金の支給対象となります。例えば、所定労働時間7時間の労働者が月曜から土曜まで週6日間働いた場合、週の累計で見ると40時間を超過しているため、超過した2時間は時間外労働扱いです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実働時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 0時間 |
| 週の累計 | 7時間 | 14時間 | 21時間 | 28時間 | 35時間 | 42時間 | 42時間 |
| 時間外労働 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 2時間 | 0時間 |
※土曜:所定休日・日曜:法定休日
このように、1日8時間もしくは週40時間のいずれかを超過した分が時間外労働として扱われ、割増賃金の支給対象となります。1日あたりの労働時間が法定労働時間内であっても、週の累計で見ると時間外労働に該当する場合もあるため注意が必要です。
なお、週の起算日と所定休日・法定休日については、業務形態に合わせて任意に決めることが可能です。
週40時間を超えた場合、違法になる?超えた場合の対応
労働基準法で定められた1日8時間・週40時間を超えて労働を課す場合は、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者と労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。前章で解説したとおり時間外労働にも上限規制が設けられており、労働基準法第36条に定められた時間外労働の上限は下記の通りです。
- 年360時間
- 月45時間
さらに、通常予見できない臨時的な業務量の増加に伴い当該上限を超えて時間外労働を課さなければならない場合は、特別条項付き36協定を締結しなければなりません。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回に限られ、別途下記の上限規制が設けられています。
- 年720時間以内(法定休日労働除く)
- 月100時間未満(法定休日労働含む)
- 2~6ヶ月の平均が80時間以内(法定休日労働含む)
- 締結できるのは年6回まで
上限を超えて労働を課した場合は、労働基準法第119条に則り6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため十分注意しましょう。
参考:労働基準法(第三十六条) | e-Gov法令検索
参考:労働基準法(第百十九条) | e-Gov法令検索
勤務形態別の労働時間
働き方改革に伴い、業務形態や労働者のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が実現しました。変形時間労働制や裁量労働制、パートやアルバイトなどに多く見られるシフト制における労働時間の扱い方を紹介します。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働時間を月単位や年単位で調整することで、繁忙期など一時的な労働時間の増加を時間外労働に含めない勤務形態です。ただし、変形労働時間制であっても法律で定められた上限を超えた場合は、時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。
変形労働時間制には月単位と年単位があり、それぞれ法定労働時間が設定されています。それらの時間を超過した分は、時間外労働として割増賃金の支給対象です。
- 月単位の変形労働時間制における法定労働時間
28日 160.0時間 29日 165.7時間 30日 171.4時間 31日 177.1時間 - 年単位の変形労働時間制における法定労働時間
365日 2085.7時間 366日(閏年) 2091.4時間
働き方改革の一環として新たに規定されたフレックスタイム制は、労働者のライフスタイルに合わせて始業・就業時間と労働時間を決めることができる制度です。変形労働時間制は労働時間の決定権が会社側にあるのに対し、フレックスタイム制は労働者側にある点が異なります。
フレックスタイム制では、働かなければならない労働時間の総量である「総労働時間」をあらかじめ設定し、その範囲内で自由に労働することが可能です。総労働時間を設定する期間を「清算期間」といいます。清算期間は従来1ヶ月でしたが、法改正に伴い最大3ヶ月に延長されました。フレックスタイム制における労働時間は清算期間における法定労働時間の総枠で管理され、これを超えた分が時間外労働となります。
1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数/7日
清算期間の暦日数と、1ヶ月あたりの法定労働時間の総枠は下記の通りです。
| 清算期間の暦日数 | 1ヶ月あたりの法定労働時間の総枠 |
|---|---|
| 28日 | 160.0時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
参考:フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き|厚生労働省
裁量労働制
裁量労働制はみなし労働時間制の一種で、労働者の裁量に基づき労働時間を決めることができる勤務形態です。例えば、所定労働時間が7時間と規定されている場合、5時間働いても9時間働いても、一律7時間働いたものとみなされます。裁量労働制には時間外労働という概念がないため、何時間働いても残業代などは支払われません。ただし、深夜労働に対する深夜労働割増賃金や、法定休日労働に対する休日労働割増賃金などは支給しなければならないため気をつけましょう。
似たような制度に、みなし残業制があります。みなし残業制は、あらかじめ会社が合理的判断に基づき残業時間を規定し、実際の残業時間に関わらず一律残業代を支給する制度です。残業が規定を超過した場合は、所定の残業代が追加で支給されます。
裁量労働制との相違点はみなす労働時間の範囲にあり、裁量労働制は労働時間全般を通して一定の労働時間としてみなすのに対し、みなし残業制はあくまで残業時間に限られます。
シフト制(パート・アルバイト等)
シフト制は、業務形態に合わせて勤務日や勤務時間帯を交代する勤務形態です。例えば、パートやアルバイトなどで、勤務シフトに合わせて早番・遅番などに分かれて働いたことがある方もいることでしょう。勤務する曜日や時間帯は労働者ごとに異なりますが、労働時間については1日8時間・週40時間の上限に従います。
この上限を超えて労働を課す場合は、36協定の締結が必要となるため注意が必要です。なお、労働基準法に定められた労働時間の上限や36協定と特別条項に基づく時間外労働の上限規制については、雇用形態を問わず適用されます。正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用されるため、十分気をつけましょう。
週40時間の労働時間の数え方について注意点
働き方の多様化に伴い、週40時間の数え方も複雑になっています。特に、月跨ぎや祝日がある場合などは複雑になりがちです。ここでは週40時間をカウントする際に間違えやすいケースを紹介します。
月を跨いだ場合の数え方
月末月初で月を跨ぐ場合、週40時間のカウントは通常通り週単位で行うのか、月末締めで行うのかどちらが正しいのでしょうか。結論から言うと、起算日を基準とし、通常通り週単位でカウントするのが正解です。
週40時間を超過した場合、割増賃金は翌月の給与と合わせて支給すれば問題ないでしょう。なお、起算日は特段の規定がない限り暦週に従い日曜日となります。業務形態等に合わせて別途規定したい場合は、就業規則等に明記しましょう。
参考:・改正労働基準法の施行について(◆昭和63年01月01日基発第1号婦発第1号)|厚生労働省
祝日がある週の数え方
祝日は所定休日のため、その日に働いた場合は、8時間を超えていない、週40時以内の場合は割増賃金は発生しません。しかし、法定内残業として別途手当の支給は必要です。
| 2月 | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) 祝日 | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実働時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 0時間 | 0時間 |
| 週の累計 | 8時間 | 16時間 | 24時間 | 32時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 |
| 時間外労働 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 |
※土曜・祝日:所定休日、日曜:法定休日
週40時間は月の平均や年の平均で問題ない?
1ヶ月ないし1ヶ月以上1年以内の一定期間を平均し、労働時間が40時間を超えない範囲内で労働を課すことも可能です。これを変形労働時間制といいます。前章でも説明したとおり、変形労働時間制には月単位と年単位があり、それぞれ法定労働時間の総枠が規定されています。
下記の例では、週単位でみると40時間を超えているものの、月単位で見ると法定労働時間の総枠である177.1時間を満たしているため問題ありません。

引用:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省
時間外労働にも該当しないため、割増賃金の支給も不要です。ただし、変形労働時間制を採用するには、就業規則に規定し労使間の合意を得なければならないため気をつけましょう。
週40時間を守って働きやすい労働環境を実現しよう
法律で定められた労働時間である週40時間の扱いについて解説しました。労働基準法には労働時間の上限が規定されており、事業主が労働者に課すことができるのは1日8時間・週40時間までとなります。上限を超えて労働を課す場合は、36協定を締結しなければなりません。
一方、近年では働き方改革に伴い勤務形態が多様化しています。変形労働時間制・裁量労働制・シフト制などでは、週40時間の扱いが異なる場合もあるため注意が必要です。法定労働時間である1日8時間・週40時間を守って、働きやすい労働環境を実現しましょう。
よくある質問
労働時間が週40時間を超えた場合、どうなりますか?
労使間で36(サブロク)協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。36協定の締結を怠ったり、上限を超えて時間外労働を課したりすると罰則が科されるため注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
週40時間の計算方法について教えてください
法定休日労働と、1日8時間を超える時間外労働を除いた実働時間の累計でカウントしましょう。法定休日労働と1日8時間超の時間外労働は別途割増賃金が支払われるため、週40時間に含めないのがポイントです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
外国人雇用の注意点 – 関連する法律や手続きを解説
少子高齢化による労働人口の減少に歯止めが効かないなか、外国人の雇用を検討している人事担当者もいることでしょう。外国人労働者の受け入れ状況は、現時点では増加傾向で推移しています。一方で、外国人を就労させるには法律に則った手続きが必要となるため…
詳しくみるシフト作成のコツは? エクセルなどを使ったシフト表の作り方をご紹介
飲食店や小売店などに代表されるシフト勤務制を採用している職場では、必須業務のひとつにシフト作成があげられます。しかし、この記事をご覧になっている方のなかには、スタッフの希望をヒアリングしシフトを作成することに不慣れだったり、苦手意識を持って…
詳しくみる労働基準法に則した正しい残業時間の考え方とは?
そもそも労働時間とは?労働基準法での規定は? まず、「労働時間」とは何かについて定義しておきます。 労働基準法において「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従…
詳しくみる裁量労働制実施の手続き~専門業務型と企画業務型の違いとは?~
裁量労働制とは? 「裁量労働制」とは、実労働時間に関わらず、あらかじめ労使間で定めた時間「労働したものとみなす」制度です。業務遂行手段や時間配分等を労働者の裁量に大幅にゆだねるため、対象業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し、使用者が対象労…
詳しくみる年間労働日数の平均は?年間休日との関係や日数の決め方を解説
従業員は、年間で何日程度働くべきなのでしょうか。また、その日数はどのように決めればよいのでしょうか。平均して、どの程度の日数働いているのかも気になるところです。 当記事では年間労働日数について解説します。年間労働日数の平均や目安、決定方法、…
詳しくみる17連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
17日間連続で働き続けると、自分の時間や家族との時間が削られていきます。趣味やリラックスするための時間を取ることができないため、気分転換ができず、日々の疲れがさらに増していくように感じられます。 本記事では 「17連勤は違法なのか?」 とい…
詳しくみる