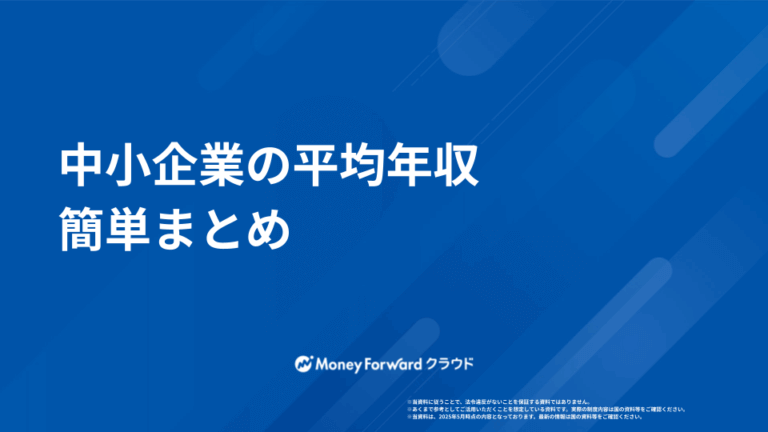- 更新日 : 2025年7月3日
中小企業の平均年収は?現在の状況と今後の展望
日本の経済を支える中小企業の平均年収はどれくらいなのでしょうか。
ここでは統計データからその数値を割り出すとともに、今後経営者が従業員の賃金についてどのように対応すべきかを考えます。
目次
中小企業の平均年収の現在の状況
中小企業の平均年収と、大企業の平均年収
厚生労働省の「平成26年賃金構造基本統計調査の概況」(以下、賃金構造基本統計)によると大企業の男性の平均賃金が38万1,900円で、中企業が31万2,100円、小企業が28万5,900円となっており、女性は大企業が26万5,200円、中企業が23万3,800円、小企業が21万4,600円となっています。
中企業の男性の平均賃金は大企業に対して82%、小企業の場合は75%となっており、中企業の女性の平均賃金は大企業に対して88%、小企業の場合は81%です。
これらの比較に加えて、賃金に12ヶ月を掛けて計算した平均年収を計算したのが以下の表です。
都道府県が指定・監督を行うサービス | 【居住介護サービス】 | 予防給付 |
(訪問系) | ||
訪問介護(ホームヘルプ):訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴、食事、排泄などの身体介護のほか、掃除、洗濯、買い物、調理などの生活援助を行うもの | ||
訪問看護:利用者の自宅を訪問した看護師や保健師などが、医師の指示による健康チェックや補助的な診療などを行う | ◯ | |
訪問リハビリテーション:利用者を訪問した理学療法士や言語聴覚士などが日常生活の自立や心身機能の改善、維持のためのリハビリテーションを行う | ◯ | |
訪問入浴:利用者の自宅を訪問した看護職員や介護職員が、移動入浴車などにより入浴のサービスを行う | ◯ | |
居宅療養管理指導:利用者の自宅を訪問した医師や看護師などが、療養する上での指導や必要な助言を行う | ◯ | |
(通所系) | ||
通所介護(デイサービス):自宅にこもったままの利用者の孤立感の解消、心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的に、施設に通い食事や入浴などの支援、機能訓練、口腔機能向上サービスを日帰りで提供する。自宅から施設までの送迎も実施する | ||
通所リハビリテーション:利用者が医療機関などに通い、日帰りでリハビリテーションなどを受ける | ◯ | |
(短期入所系) | ||
短期入所生活介護(ショートステイ):利用者が介護老人福祉施設に短期間入所して、食事や機能訓練などの支援や排泄などの介護を受ける | ◯ | |
短期入所療養介護:利用者が介護療養型医療施設や介護老人保健施設に短期間入所して、医療や看護、機能訓練などを受ける | ◯ | |
(その他) | ||
特定施設入居者生活介護:指定を受けた有料老人ホームなどが、入浴・食事などの生活の支援や機能訓練を行う | ◯ | |
福祉用具貸与:福祉用具の貸出を行う | ◯ | |
特定福祉用具販売:貸出になじまない福祉用具の販売を行う | ◯ | |
【介護施設サービス】 | ||
介護老人福祉施設:特別養護老人ホームとも呼ばれ、入所者の可能な限り在宅復帰を念頭に、入浴や食事などの生活支援、機能訓練、療養上の世話を提供する | ||
介護老人保健施設:老健とも呼ばれ、在宅復帰を目指している人の入所を受け入れ、リハビリや必要な医療、介護などを提供する | ||
介護療養型医療施設:長期にわたって療養が必要な人の入所を受け入れ、機能訓練や必要な医療、介護などを提供する | ||
介護医療院:長期にわたって療養が必要な人の入所を受け入れ、療養上の管理、介護、看護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスを提供する | ||
市町村が指定・監督を行うサービス | 【地域密着型介護予防サービス】 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:利用者の心身の状況に応じて、必要なサービスを24時間365日必要なタイミングで柔軟に提供する。訪問介護員だけでなく看護師との連携も可能 | ||
夜間対応型訪問介護:利用者が24時間可能な限り自宅で自立した生活を送れるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問するサービス | ||
地域密着型通所介護:通所介護(デイサービス)と同様の目的で、利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い食事や入浴などの支援、機能訓練、口腔機能向上サービスを日帰りで提供する。自宅から施設までの送迎も実施する | ||
認知症対応型通所介護:軽度の認知症を患っている利用者が、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターなどで、日帰りの食事や排せつなどの介護や機能訓練、助言などを受ける | ◯ | |
小規模多機能型居宅介護:通所を基本に訪問や短期入所も組み合わせて利用者が選択し、食事や機能訓練、排せつなどの支援を受ける | ◯ | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム):認知症を患っている利用者が、グループホームで食事や機能訓練、排せつなどの支援を受ける | ◯(要支援2の方のみ) | |
地域密着型特定施設入居者生活介護:指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームで食事や入浴などの支援や機能訓練を受ける | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:定員30人未満の介護福祉老人施設(特別養護老人ホーム)で食事や入浴などの支援や機能訓練、療養上の世話を受ける | ||
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護):利用者の選択に応じて、施設への通いを中心に、短期宿泊や自宅での訪問介護、看護師の訪問看護を組み合わせるサービス | ||
療養通所介護:常に看護師による観察を必要とする難病や認知症、がん末期患者などを対象にしたサービスで、利用者が療養通所介護の施設に通い、生活上の支援や機能訓練などを日帰りで提供 | ||
【居住介護支援】 | ||
居住介護支援:ケアマネージャーが、利用者に必要な介護支援サービスについてケアプランを作成し、そのプランに基づいた介護が実施されるよう関係者との連絡・調整を行うもの | ||
その他 | 住宅改修:利用者が自宅での生活を続けるために、手すりの取付けやバリアフリーにする住宅改修費用を支給する | ◯ |
※男女ともに大企業の年収を100%とする。
なお賃金構造基本統計における企業規模の定義と、賃金の定義は以下の通りです。
・中企業…常に雇用されている従業員が100人~999人。
・小企業…常に雇用されている従業員が10人~99人。
・賃金…平成26年度の6月分の所定の給与から時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交替手当を差し引いた額で、税引き前の金額。
これらの定義はこれ以降の内容においても同様です。
都道府県別の年収の違い
続いて、都道府県別の平均年収の違いについて見ていきましょう。最も平均賃金が高いのは東京都で、37万7,400円。最も低いのが沖縄県で、22万7,700円です。その差は約15万円、年収に換算すると約180万円です。
ここでの平均賃金は企業規模別ではないため、中小企業の平均年収にどれだけの差があるのかは正確にはわかりません。しかし地域によってその差が出ることは間違いないでしょう。
年齢別の年収の違い

上表は年齢別、企業規模別の平均賃金と、大企業を100とした企業規模間の賃金格差、20歳〜24歳の平均賃金を100とした年齢階級間の賃金格差を男女別に示したものです。
年齢を重ねるほど平均賃金も上昇していき、企業規模が大きくなるほど年齢階級間での差は広がる傾向にあります。ただし60歳以上になると嘱託社員も増えるため、どの企業規模でも平均賃金は減少し、企業規模間での格差も小さくなっています。
平均年収にさらに差をつける「賞与」
賃金構造基本統計の「賃金」には「賞与」いわゆるボーナスは含まれていません。しかしこの賞与の金額、有無は平均年収に大きく関わってきます。
例えば38万1,900円の賃金を受け取っている大企業の男性が、賃金6ヶ月分の賞与を受け取った場合、年収は687万4,200円になります。一方で28万5,900円の賃金を受け取っている小企業の男性が賞与なしだった場合の年収は343万800円です。その差は約2倍です。
さらに「賃金」からは時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交替手当が差し引かれているため、さらに格差は広がります。
賃金構造基本統計で挙げられているのは平均値なので、この数値だけを見て単純に比較はできません。しかし、それでも年収において大企業と中企業、小企業の間には大きな差があることは事実です。
中小企業の平均年収の今後の展望
中小企業の賃上げが進んでいる
商工組合中央金庫(以下、商工中金)の「中小企業の賃金動向に関する調査」によると、中小企業のうち約72%が2016年に定期昇給やベースアップ、賞与の引き上げなど、何らかの形での賃上げを行う予定であることがわかっています。2015年にも同様の調査を行ったところ、全体の77.3%の企業が何らの賃上げを行っています。
ベースアップに踏み切る企業が全体の約25%にとどまっていることから、未だ慎重な姿勢は見られるものの、中小企業の賃上げが進んでいることは事実です。
賃上げの背景
2015年に賃上げを行った中小企業のうちの45.6%、2016年に賃上げ予定の中小企業のうちの44.1%が、賃上げの理由に「自社の業績改善を反映」と回答しています。つまり景気回復に伴う、従業員への還元というわけです。しかしこのような前向きな理由だけで賃上げを行っているわけではありません。
2015年に賃上げを行った中小企業のうちの61.7%、2016年に賃上げ予定の中小企業のうちの64.6%は「処遇改善による人材の定着化」を理由に挙げ、2015年に賃上げを行った中小企業のうちの37.1%、2016年に賃上げ予定の中小企業のうちの43.3%が「人材確保(採用)のために必要」を理由に挙げています。
中小企業はどの業種でも慢性的な人手不足に悩まされており、それを打開する方法として賃上げを行っているというわけです。
中小企業は賃金をどう考えるべきか
「賃上げを行わない」と回答した中小企業の多くは業績低迷や景気見通しの不透明さを理由に挙げています。
しかし賃上げを行っている企業の多くが人材の定着化や確保を賃上げの理由に挙げていることからもわかるように、賃上げをしないままでは人材が流出してしまったり、良い人材を採用できないという不安感も広がっています。とはいえ無理に賃上げを実行して、今後の経営にリスクを抱えるわけにもいきません。
中小企業は「賃上げ」をあくまで1つの手段として認識し、他の様々な施策とバランスをとりながら、適正な賃金設定を行う必要があるでしょう。
まとめ
大企業と中小企業、都市部と地方部を比べると年収の格差は間違いなくあります。
この格差は中小企業の人手不足にも影を落としており、その影響を懸念する中小企業の多くは賃上げを対策として打ち出しています。しかし賃上げは人手不足解消のための唯一の施策ではありません。
賃上げができる中小企業も、できない中小企業も、他の施策とのバランスを考え、大局を見失わない経営を心がけたいところです。
関連記事
・課税所得とは?同じ年収でも税金に差が出る理由
・中小企業をサポートするための税制について
・退職金制度はどうやってつくる・廃止するのか 制度比較や注意点を詳細解説
よくある質問
中小企業の平均年収は?
厚生労働省によると中企業の男性の平均賃金が31万2,100円、小企業が28万5,900円となっており、女性は中企業が23万3,800円、小企業が21万4,600円となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業は賃上げする?
商工組合中央金庫によると、中小企業のうち約72%が2016年に定期昇給やベースアップ、賞与の引き上げなど、何らかの形での賃上げを行う予定であることがわかっています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所定労働日数22日の給与計算のやり方は?残業や欠勤の調整方法を解説
従業員は、「所定労働日数」という形で何日働くべきか定められています。所定労働日数は給与計算だけでなく、有給休暇にも関係する重要なものです。当記事では、所定労働日数の重要性や計算・決定方法などについて解説します。具体的な所定労働日数を挙げたう…
詳しくみるWeb給与明細システムとは?メリットや導入時の注意点
給与明細を紙での配付から電子化してWeb上で見られるようにすると、会社は業務負担軽減やコスト削減を図ることができ、従業員はいつでもどこでも自分の給与明細の閲覧・確認が可能になります。専用型・給与計算一体型・労務管理一体型の3種類のシステムが…
詳しくみる給与辞令とは?作成は義務?
給与辞令とは、等級変動による昇給や降給などの給与改定時に交付される辞令です。給与辞令の交付は義務ではありませんが、給与支給額の変動は社員の評価を意味するため極力交付の機会を設けると良いでしょう。なお、給与辞令に特定のフォーマットはありません…
詳しくみる茅ヶ崎の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
茅ヶ崎は、湘南エリアに位置し、美しい海岸線と活気あるサーフカルチャーで知られるリゾート都市です。観光業や地元ビジネスが盛んなこの地域では、給与計算の正確性と迅速な対応が求められます。 本記事では、茅ヶ崎における給与計算代行の料金相場を詳しく…
詳しくみる日払いバイトにも給与明細が必要?テンプレートをもとに書き方も解説
給与明細は、日払いバイトにも必要です。アルバイトと正社員は給与形態も異なるため、給与明細の発行の必要性について混乱することも珍しくありません。給与トラブルを防ぐためにも、日払いバイトに対する給与明細の交付について知ることが重要です。 本記事…
詳しくみる60歳以降の再雇用、給与の目安は?決め方や下がる理由、違法となる場合を解説
60歳以降も働き続ける再雇用制度を利用する方が増えていますが、多くの人が気にするのは、再雇用後の給与ではないでしょうか。定年前よりも減額されることが一般的ですが、どのくらい下がるのか、どんな場合に違法になるのかを理解しておくことは、安心して…
詳しくみる