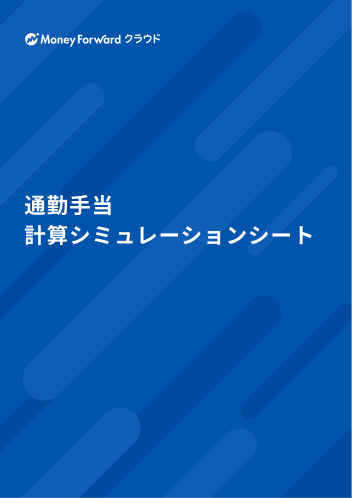- 更新日 : 2025年4月24日
通勤手当とは?計算方法と課税範囲について紹介
通勤手当は、諸手当のなかでは最も一般的な手当といえますが、意外に正確な取り扱いは知られていません。計算方法、交通費との違いや、電車やバスではなく、マイカーやタクシー、徒歩で通勤した場合の取り扱いはどうするのか。また、非課税限度額など、課税上の問題もあります。ここでは、知られているようで実はあまり知られていない通勤手当について、詳しく解説していきます。
目次
通勤手当とは
通勤手当とは、事業主が従業員の通勤にかかる費用の全部、または一部を手当として支払うものです。交通費とはどう違うのでしょうか。また、支給する場合、会社の服務規律である就業規則などに記載する必要はあるのでしょうか。はじめに通勤手当の基本的な知識について解説しましょう。
通勤手当と交通費の違い
通勤手当と紛らわしいものに交通費があります。仕事をするための交通手段に要した費用の支払いという意味では、同じものといえるかもしれません。
帳簿の勘定科目の扱いでは、通勤手当は従業員が会社へ通勤するために支出した費用を表す「通勤費」、交通費は従業員の出張や営業など業務上の移動に要した「旅費交通費」で処理するのが一般的ですが、「旅費交通費」一本で処理することもあります。
大きな違いは、税法上の取り扱いです。
通勤手当は「給与所得」として扱われ、一定の範囲内までは非課税ですが、超えれば所得税が課税されます。一方、交通費は非課税です。
企業は従業員に通勤手当を支払う必要がある?
そもそも通勤手当は、法律的には事業主に支払い義務はありません。支給の有無、支給基準、限度額などは、事業主が作成する就業規則、あるいは就業規則の一部として独立させた賃金規程に定めればよいことになっています。
ただし、労働契約法により、労働契約で従業員と約束した支給額と就業規則などで定めた支給額が異なる場合は、高いほうの通勤手当を支払わなければなりません(法7条)。就業規則などで支払額や支払い基準が明確に定められれば、通勤手当は労働基準法上の「賃金」の一部とみなされます。
通勤手当の対象となる通勤手段
どのような交通手段に対して通勤手当を支給するかは、就業規則などで決めることになります。一般的な通勤手段としては、次のものが挙げられるでしょう。
- 公共交通機関(電車、バス等)
- マイカー
- 自転車
- 徒歩
就業規則は事業主側が作成するものですから、公共交通機関に限定することも可能です。いずれにしても、支給対象者が利用する通勤手段を明確にしておくことが大切です。
マイカー通勤における通勤手当の計算方法
マイカー通勤を支給対象とする場合、その計算方法も就業規則のなかでルールを決めておく必要があります。事業主側が独自に決めるため、法律で定められた計算方法があるわけではありません。一般的には、次のいずれかの方法で計算されます。
- ガソリン単価と燃費による計算方法
- 距離による計算方法
ガソリン単価と燃費による計算方法
マイカーによる通勤手当をガソリン単価と燃費で計算する場合、次のような計算式になります。
勤務日数については、公共交通機関の場合の定期代と同じように1カ月の支給額を固定したほうが煩雑になりません。1カ月の平均勤務日数は、次の計算式で出すことができます。
「燃費」とは、ガソリン1Lで何km走行できるのかを数値で表したものです。ガソリン単価を燃費で割ることで、1km当たりのガソリン単価を算出することができます。
距離による計算方法
距離で計算する場合は、次のような計算式になります。
距離単価については、事業所ごとに決めているため、1km当たり10円から15円とバラツキがあるようです。従業員にとって納得のある単価とするのであれば、ガソリン単価と燃費による方法でも計算し、比較してみるのもよいでしょう。
電車・バスにおける通勤手当の計算方法
公共交通機関を利用する場合は、通勤定期券による運賃相当額を支給するのが一般的です。通勤定期券は、1カ月、3カ月、6カ月の3種類があり、どの期間にするか決めておく必要があります。
回数券を使用する場合の1カ月の計算方法は次のようになります。
また、出勤日数に応じて毎月支給する場合は、次の計算式になります。
以上が、従来の公共交通機関利用による通勤手当の支払い方ですが、今はPASMOやSuicaなどのICカードを使用する人も増えています。
ICカードを使用した場合の計算はどうなる?
PASMOなどのICカードを使用した場合の計算法は、次のようになります。
なお、PiTaPaのように買物の額に応じて電車の運賃が割り引かれるものもあります。通勤手当の不正受給に当たるという声もあり、管理するのも非常に煩雑になるため、ICカードを通勤手当や交通費として利用する場合は、PASMOやSuicaなどに限定することをおすすめします。
また就業規則に「通勤手当の額は公共交通機関を合理的に利用した場合の通勤定期券の額に準ずる」旨を定め、ある程度一律に支給するケースで対応する方法もあります。
自転車や徒歩出社における通勤手当の計算方法
通勤の距離が数km程度であれば、健康を考えて自転車や徒歩で通勤する人もいるでしょう。その場合の通勤手当を支給対象とするかどうかは、やはり就業規則で事業主側が決めることができます。
しかし、通勤手当は非課税限度額があるため、課税されないのであれば、自転車や徒歩であっても通勤手当として支給されるほうが従業員にとっては利益になります。
支給対象とする場合は、片道通勤距離を例えば「2km以上の場合に限る」としたうえで、公平性の観点からマイカー通勤による通勤手当の計算方法で支給するケースが一般的かと思います。
タクシー出社における通勤手当の計算方法
普段の通勤で、タクシー利用に対して通勤手当を支給する会社は極めて少数派といえるでしょう。例外的に、普段、公共交通機関を利用している従業員が緊急業務のために早朝あるいは深夜に利用した場合や、交通機関のストライキの際に利用した場合などに限定し、通勤手当を支給することを就業規則で規定しているケースはあります。
その場合の支給額は、実費相当額とするのが一般的です。
通勤手当の課税は?手段別に紹介
事業所が、従業員に支払う基本給以外の諸手当は、給与所得の一部と考えられるため、基本的に支給額に応じた所得税が発生します。しかし、通勤手当の場合は一定額までは非課税となります。
現在の通勤手当の非課税の上限は15万円となっていますが、交通手段によって非課税限度額のルールは異なります。
マイカー通勤の場合
マイカー通勤している従業員の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤経路に沿った通勤距離に応じて定められています。非課税となる1カ月当たりの限度額の表は、次のようになっています。

マイカーだけを使用した場合は、通勤に要する往復距離をもとに通勤交通費を算出することになります。
電車・バスの場合
公共交通機関を利用し、最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が1カ月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
ここでいう「経済的」とは、基本的にほかの経路と比較して運賃などが低額であること、「合理的」とは、基本的にほかの経路と比較して所要時間が短いことを指すとされています。
事業所によっては、従業員の長距離通勤に対しても通勤手当を支給するケースがあります。例えば新幹線を利用した場合、運賃額は「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
なお、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合は、次の2つを合計した金額が非課税限度額となります。
- 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1カ月間の通勤定期券などの金額
- マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1カ月当たりの非課税となる限度額
自転車の場合
自転車通勤者の通勤手当も非課税限度額は、マイカー通勤の場合と同じです。前記のマイカー通勤の非課税となる1カ月当たりの限度額の表の通りです。
徒歩の場合
所得税法では、給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通勤手当に一定の非課税限度額を定めています(法9条)。
こうしたことから、交通機関の利用やマイカー、自転車などの交通用具を一切使用しない徒歩通勤については通勤手当は非課税になりません。
タクシーの場合
前述したように、普段、公共交通機関を利用している従業員が緊急業務で早朝あるいは深夜労働をした場合に利用したり、交通機関のストライキの際に利用した場合などに限定し、例外的に通勤手当を支給するケースはありますが、いずれの場合も課税されません。
緊急業務のためのタクシー通勤の場合は、給与所得ではなく、会社の負担すべき費用の立替払とされ、会社の従業員への支払いは、その立替金の精算として扱われます。
また、交通機関のストライキの場合は、会社の業務遂行のための費用負担になるとされています。
従業員が納得する通勤手当の制度を整えよう
今回は、通勤手当について、計算方法から、交通費との違い、税法上の扱いまで詳しく解説してきました。通勤手当は、あくまでも事業主側が作成するもので、法律的には事業主に支払い義務はありません。しかし、社員のモチベーションを考えた場合、納得性を考慮することが大切です。
見直しが必要であれば、就業規則を改定することも検討してみてはいかがでしょうか。
また、以下のページから通勤手当関係通勤経路確認書のエクセルテンプレートを無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
よくある質問
通勤手当と交通費の違いはなんですか?
通勤手当は、一定の範囲内までは非課税ですが、超えれば所得税が課税されます。交通費は非課税です。 詳しくはこちらをご覧ください。
通勤手当の計算方法について教えてください
マイカー、バス・電車などの公共交通機関によって異なります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
新入社員でもわかる「給与明細の見方」 保険料は何のためにいくら引かれる?
この4月から働き始めた新入社員のみなさんにとって、待ちに待った初任給を受け取る時期が近づいてきました。期待に胸を膨らませながら給与明細を見てみると……総支給額からいろいろと差し引かれた手取り額に落胆するかもしれません。どの項目が、何のために…
詳しくみる特別手当とは?税金はかかる?種類や金額の相場、企業事例を解説
特別手当とは、基本給や賞与とは別に、特定の条件や目的で企業が従業員に支給する手当です。 業績達成時の一時金や役職手当、住宅手当などが代表例で、従業員のモチベーション向上や福利厚生の充実、人材確保などに活用されています。 しかし、支給要件や税…
詳しくみる労働基準法第25条の賃金の非常時払いとは?事例をもとにわかりやすく解説
労働基準法第25条は、労働者が緊急時に必要な費用をまかなうため、通常の給与支払日より前に賃金を受け取れる制度「賃金の非常時払い」を定めています。 本記事では、賃金の非常時払いの概要と適用条件、前借りとの違い、認められる理由と法的根拠、支払期…
詳しくみる給与計算業務の流れは?一般的な手順とクラウド給与計算ソフトを活用した方法をわかりやすく解説!
経理業務の中でも、給与計算はミスが発生しやすい煩雑な業務です。特に、はじめて給与計算を行う場合は、「何から手をつけていいかわからない…」といったお悩みも多いのではないでしょうか。 この記事では、給与計算の概要や一般的な業務の流れと、クラウド…
詳しくみる有給休暇の保有日数は最大40日?35日?保有の条件を紹介
有給休暇は最大で40日保有可能だと聞いたことはないでしょうか。しかし、それは単純に付与された日数全てを繰り越せる場合に限られます。また、入社したら誰でも有給を使えるわけではなく、有給付与には2つの条件があります。 この記事では有給の最大保有…
詳しくみる賞与の算定期間とは?査定期間との違い、休業・休暇は含まれるか解説
賞与は、従業員のモチベーションに大きく関わる重要な要素です。そのため、正しく働きを評価し、賞与額に反映させなければなりません。その際に重要となるのが、賞与の算定期間や査定期間です。 当記事では、賞与の算定期間について、査定期間との違いや、期…
詳しくみる