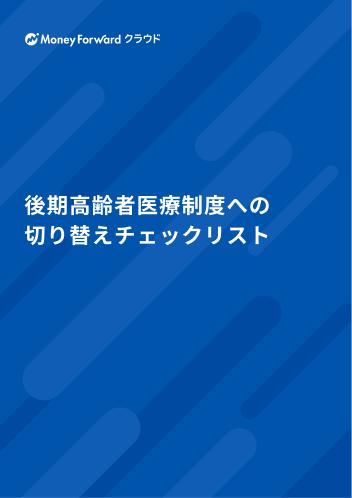- 更新日 : 2025年5月27日
社会保険の後期高齢者医療制度とは?切り替え手続きを解説
社会保険の後期高齢者医療制度とは、主に75歳以上の後期高齢者を対象とした公的医療制度のことです。それまで社保に加入していた場合は、脱退手続きを行わなくてはいけません。なお、後期高齢者保険証は1人につき2枚ではなく、1枚ずつ交付されることが特徴です。今回は後期高齢者医療制度の概要と切り替え手続きを解説します。
目次
社会保険の後期高齢者医療制度とは?
社会保険の後期高齢者医療制度とは、主に後期高齢者を対象とした公的医療保険制度の1つです。
日本の国民皆保険は、大きく「被用者保険」と「国民健康保険」の2本立てで実現しています。被用者保険とは基本的に労働者が加入するもので、国民健康保険は被用者保険に加入しない人が入ります。
しかし、所得は高く医療費が少ない傾向にある現役世代は、被用者保険に加入する割合が高い一方で、高齢期になると国民健康保険に加入するという構造的な課題がみられました。そのため、高齢者医療を国民健康保険だけで支えるのではなく、社会全体で支援する必要性が高まっている状況です。
このような背景のもと、老人保健法の改正によって後期高齢者と現役世代の負担を明確にして、後期高齢者自身が保険料を負担する後期高齢者医療制度が誕生しました。
後期高齢者医療制度は、後期高齢者の心身の特性や生活の実態を考慮した診療報酬体系となっている点が特徴です。また財源の構成は1割の患者負担分を除き、4割の現役世代からの支援金と5割の公費のほか、高齢者一人ひとりに保険料を負担してもらうしくみです。
なお、後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体とされています。
後期高齢者医療制度の対象
後期高齢者とは、75歳以上の方を指す言葉です。なお高齢者は一般的に65歳以上を指し、65歳以上75歳未満の方を前期高齢者といいます。
後期高齢者医療制度の対象者は、以下のとおりです。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で、政令で定める程度の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
上記はいずれも、後期高齢者医療広域連合の区域内に住んでいることが要件とされています。また、前述のとおり後期高齢者は75歳以上の方を指しますが、後期高齢者医療制度は65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあると認められた方も対象です。
75歳以上になると勤めているかいないかにかかわらず、それまで加入していた被用者保険や国民健康保険から、自動的に高齢者医療制度に加入するしくみになっています。
参考:75歳以上の方が全国健康保険協会管掌健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて|全国健康保険協会
後期高齢者医療制度によって社会保険料がどう変わる?
後期高齢者医療制度の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の2つの合計額です。それぞれの概要は以下のとおりです。
| 概要 | 東京都の場合(令和4・5年度) | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 被保険者一人ひとりに均等に賦課される | 年額46,400円 |
| 所得割額 | 被保険者の所得に応じて決定される | 9.49% |
均等割額と所得割額はいずれも、都道府県ごとに存在する後期高齢者医療広域連合によって異なります。たとえば東京都後期高齢者医療広域連合では、令和4・5年度の均等割額は年額46,400円、所得割率9.49%で、保険料の賦課限度額は被保険者1人につき66万円です。
所得割額の計算方法
東京都に住んでいる年金収入のみの方の場合、上記の均等割額46,400円に所得に応じた所得割額を加えた金額が、後期高齢者医療制度の保険料となります。所得割額の計算方法は以下のとおりです。
なお、公的年金控除は収入金額などに応じて決められています。65歳以上で収入金額が330万円未満の場合、110万円です。
ここからは、具体的な計算例を確認していきましょう。たとえば、公的年金などの収入が250万円ある、東京都に住む単身で77歳の方の後期高齢者医療制度の年額保険料は、下記のとおりです。
- 均等割額:46,400円
- 所得割額:(250万円-110万円-43万円)×9.49%=92,053円
- 後期高齢者医療制度の保険料【年額】:
46,400円+92,053円=138,400円(※100円未満切り捨て)
後期高齢者医療制度の切り替え手続きについて
基本的に国民健康保険の加入者が75歳になった際は、自動的に後期高齢者医療制度に加入するため、加入の手続きは必要ありません。後期高齢者医療広域連合から、誕生月の前月の下旬頃に被保険者証(保険証)が送付されるのが一般的です。また保険料の案内は、誕生月の翌月あるいは翌々月を目処に郵送されてくるケースが多いです。
ただし、被用者保険(会社の健康保険組合など)に加入していた場合は、それまで加入していた健康保険からの脱退手続きなどが必要になることがあります。そのほか、次の証書が必要な場合には別途手続きが必要になる可能性が高いです。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 限度額適用認定証
- 特定疾病療養受療証
また、後期高齢者医療制度に加入する方が家族を社会保険の扶養に入れている場合、家族の方の国民健康保険などへの切り替え手続きが必要になる点に注意しましょう。
参考: 来月75歳になるのですが、何か加入の手続きをする必要はありますか。|船橋市
参考:【制度加入】もうすぐ75歳を迎え後期高齢者医療制度の対象となりますが、何か手続きが必要ですか。|岡山市
後期高齢者医療制度の保険証は2枚?それとも1枚?
後期高齢者医療制度の保険証は、1人につき1枚が交付されます。なお老人保健制度では、医療保険の保険証のほか「老人医療受給者証」も交付されていました。つまり医療機関などにおいては、これら2枚を提示する必要があったのです。
また現行制度においても、70歳から74歳までは協会けんぽをはじめとする加入している保険から「高齢受給者証」が交付されています。
高齢受給者証は、医療機関などの窓口で支払う金額の、自己負担割合を証明するものです。そのため、70歳以上74歳未満の方が医療機関などを受診する際には、健康保険証と一緒に高齢受給者証を提示する必要があります。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者が提示するのは保険証1枚のみになります。
後期高齢者医療制度に関する手続きを確認しよう
社会保険の後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の後期高齢者を対象とした公的医療制度の1つです。
もともと所得が高く、医療費が少ない傾向にある現役世代は、被用者保険に加入する割合が高い一方で、高齢期になると国民健康保険に入るという構造的な課題がみられました。そのため、高齢者医療を国民健康保険だけで支えるのではなく、社会全体で支援する必要性が高まっており、こういった課題認識を踏まえて誕生したのが後期高齢者医療制度です。
国民健康保険の加入者が75歳になった際には、自動的に後期高齢者医療制度に加入するため、特に手続きは必要ありません。しかし、75歳になるまで会社の健康保険組合などに加入していた場合は、脱退手続きなどをおこなわなければならない可能性があります。
後期高齢者医療制度の概要を理解し、各社で必要な手続きも把握しておきましょう。
よくある質問
社会保険の後期高齢者医療制度とはなんですか?
老人保健法の改正によって誕生した、主に75歳以上の後期高齢者を対象とした公的医療制度のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度の保険証は何枚ですか?
1人につき1枚ずつ交付されます。なお、老人保健制度では医療保険の保険証と「老人医療受給者証」が交付されていたため、1人2枚ずつ交付されていました。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金の死亡一時金 – 手続きや支給金額について
国民年金に加入し、一定期間保険料を収めていた被保険者が亡くなった際に、遺族は死亡一時金を受け取ることができます。厚生年金加入者が亡くなると遺族厚生年金が支給されますが、条件を満たした場合は死亡一時金も併給が可能です。 この記事では、死亡一時…
詳しくみる雇用保険被保険者証とは?再発行の方法や離職票との違い
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを示す書類で、事業主を通じてハローワークから交付されるのが一般的です。 原則は雇入れ時に渡されることとなっていますが、重要書類であることから会社が保管し、退職時に雇用保険被保険者証を渡すケー…
詳しくみる同月得喪における社会保険料を解説!厚生年金や健康保険の保険料はどうなる?
会社は、要件を満たした人を社会保険に加入させます。会社は社員に長く働いてもらいたいのですが、実際は1ヵ月未満など、短期間で退職する人も出てきます。その際に社会保険の同月得喪が生じる場合があります。 今回は、社会保険の同月得喪の定義や概要と、…
詳しくみる60歳以上の厚生年金加入は義務?加入によるメリットを解説!
2023年度から地方公務員の定年延長がスタートするなど、60歳以降も働く方が増加する傾向にあります。「生活のため」「社会とのつながり」など、働く理由はさまざまです。60歳以降の就労は、定期収入を確保する以外に「老後の公的年金の額を増やす」と…
詳しくみる労働保険への加入方法
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入方法を知っていますか?ここでは、労働保険に加入するため手続き、労働保険の加入に必要な各種届出、申告書の主な内容について解説します。 労働保険へ加入するための手続き 労働保険料の徴収に関しては、すべての事…
詳しくみる派遣スタッフは社会保険に加入できる?条件や手続きについて解説!
社会保険は病気・ケガ・労働災害・失業・高齢化などの誰にでも発生しうるリスクに対して、社会全体で備えることを目的に運用されている制度です。派遣スタッフであっても加入条件を満たせば社会保険には加入しなければなりません。 そこでこの記事では社会保…
詳しくみる