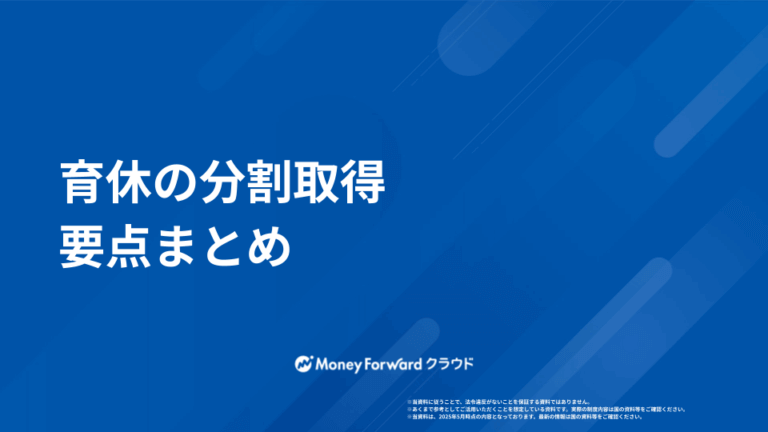- 更新日 : 2025年6月23日
育休の分割取得とは?パパ育休と育休の活用例、企業の対応を解説
育休の分割取得は、育児休業を複数回に分けて取得できる制度です。
本記事では、育休の分割取得の仕組みやメリット、具体的な活用例を解説します。
合わせて、育休の分割取得と産後パパ育休プラスとの組み合わせ方、2025年4月からの法改正情報なども解説します。
育児と仕事の両立に悩む方は、ぜひこの記事を参考に、自分に合った育休の取り方を見つけてみてください。
なお、従業員が育休の分割取得時に、企業が対応すべきことについても解説するので、企業の人事担当者の方もぜひ参考にしてください。
目次
育休の分割取得とは?
育休の分割取得とは、育児・介護休業法に基づき、育児休業を複数回に分けて取得できる制度です。
従来、育児休業は原則として子が1歳になるまでの間に1回しか取得できませんでしたが、2022年10月の法改正により、2回まで分割して取得可能になりました。
この改正の背景には、夫婦が協力して育児を行うことの促進や、育児と仕事の両立を支援する目的があります。
これにより、より柔軟な働き方や育児参加が可能となり、仕事と育児の両立を希望する労働者にとってメリットになるでしょう。
次項で、通常の育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の分割取得について、それぞれ詳しく解説します。
通常の育児休業の分割取得
通常の育児休業の分割取得は、子が1歳に達するまでの間に、2回まで育児休業を分割して取得できる制度です。
たとえば、母親の産後休業明けから父親が育休を取得し、その後母親が育休を取得、さらに父親が再度育休を取得するといった形で、夫婦交代で育児に専念する期間を設けられます。
通常の育児休業の分割取得をポイントにまとめると、下記の通りです。
- 子が1歳になるまでの間に2回まで取得できる
- 分割取得の申し出は、原則として休業開始日の1か月前までに行う必要がある
この制度を活用すれば、夫婦が育児の状況に合わせて柔軟に休業を取得し、協力して子育てを行いやすくなります。
産後パパ育休の分割取得
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる休業制度です。
この制度も、分割して2回まで取得可能です。
たとえば、出生直後に2週間、その後数週間後に再度2週間といった形で、父親が育児に集中的に参加する期間を設けられます。
産後パパ育休の分割取得をポイントにまとめると、下記の通りです。
- 子の出生後8週間以内に取得する必要がある
- 最大4週間まで取得可能で、2回まで分割できる
- 産後パパ育休の申し出は、原則として休業開始日の2週間前までに行う必要がある
産後パパ育休の分割取得を活用すれば、出産直後の大変な時期に父親もサポートでき、その後も状況に合わせて育児に関われます。
育休を分割取得するメリット
育休を分割取得するメリットは、下記の通りです。
- 夫婦で育児の負担を分担しやすい
- 家庭の状況に柔軟に対応できる
- 職場とのつながりを維持しやすい
次項で、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
夫婦で育児の負担を分担しやすい
育休の分割取得は、夫婦で育児の負担を分担しやすくなるのが1番のメリットです。
たとえば、出産直後は母親の身体的な負担が大きいため、父親が産後パパ育休を取得することでサポートができます。
さらに必要に応じて父親が再度育休を取得すれば、夫婦で育児に専念できます。
これにより、どちらか一方に負担が偏るのを防ぎ、夫婦で協力して育児に取り組むことが可能です。
家庭の状況に柔軟に対応できる
育休を分割取得すれば、家庭の状況変化に柔軟に対応可能です。
たとえば、保育園の入園時期に合わせて育休期間を調整したり、母親の体調に合わせて育休を取得したりできます。
従来の制度では、一度育休から復帰した後再度育休を取得することができなかったため、このような柔軟な対応はできませんでした。
育休の分割取得制度は、家庭の事情に合わせて柔軟に対応できるため、育児に対するストレスを軽減する効果も期待できます。
職場とのつながりを維持しやすい
育休を分割して取得すれば、職場とのつながりを維持しやすくなるのもメリットです。
長期間の休業は、職場復帰への不安を感じやすいものです。
しかし、分割取得であれば、比較的短い期間で職場に戻れるため、業務の進捗状況や職場の変化を把握しやすくなります。
これにより、育児と仕事の両立に対する不安を軽減し、より前向きに育児休業を取得できます。
育休を分割取得する活用例
育休の分割取得は、各家庭の状況に合わせて柔軟な育児体制を築くためにおすすめです。
具体的な活用例を知ることで、制度をより効果的に活用できるでしょう。
次項で、育休分割取得の活用例をいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてください。
出産直後に父親が産後パパ育休を取得する
出産直後は母親の体調回復と赤ちゃんのケアが重要な時期です。
この時期に父親が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得すれば、母親の身体的な負担を軽減し、精神的な支えになります。
また、父親にとっても、生まれたばかりの子どもと貴重な時間を過ごし、育児に積極的に参加するきっかけとなります。
父親が育児に積極的に関われば、夫婦間のコミュニケーションが向上し、家族の絆もより深まるでしょう。
夫婦交代で育児休業を取得する
育休の分割取得を活用すれば、夫婦が交代で育児休業を取得するという選択肢が生まれます。
たとえば、母親がまず一定期間育休を取得し、その後父親が育休を取得、さらに必要に応じて母親が再度育休を取得するなど、夫婦で育児に専念する期間を交代で設けられます。
これにより、どちらか一方に育児の負担が偏るのを防ぎ、夫婦で協力して育児に取り組むことが可能です。
また、母親が仕事復帰しやすくなり、父親も育児の大変さを実感し、育児スキルを向上させる機会にもなるでしょう。
母親が職場に復帰する前後に父親がサポート
子が1歳までの期間に限られますが、母親が職場に復帰する前後の期間に、父親が育休を取得すれば、スムーズな職場復帰をサポートできます。
復帰前は、生活リズムを整えたり、保育園の送迎の練習をしたりと、準備期間が必要です。
その期間に父親が率先して育児に参加すれば、母親は安心して復帰の準備ができます。
また、復帰後も、子どもの急な体調不良などに対応できるよう、父親が短期間の育休を取得しておけば、夫婦で協力して育児と仕事の両立ができるでしょう。
育休の分割取得+産後パパ育休プラスの場合の活用例
育休の分割取得と産後パパ育休(出生時育児休業)、パパママ育休プラスをうまく組み合わせれば、より柔軟な育児体制を作れます。
次項で、具体的な活用例をいくつか紹介するので、ご自身の状況に合わせてぜひ参考にしてください。
母親と父親が交代で切れ目なく育休をとりたい
育休の分割取得と産後パパ育休を組み合わせれば、夫婦が切れ目なく育休を取得できます。
たとえば、出産後すぐに父親が産後パパ育休を取得し、その後母親が育休を取得、母親の育休終了後すぐに父親が再度育休を取得するといった流れです。
具体的な例として、出産後8週間は父親が産後パパ育休を分割して取得し、その後母親が1年間育休を取得、母親の育休終了後、切れ目なく父親が育休を取得するといった方法です。
この方法であれば、長期にわたって切れ目なく親が育児に専念できます。
母親と父親が2人で一緒にできるだけ長い期間にわたって育休をとりたい
夫婦が同時に育休を取得して、2人で一緒にできるだけ長い期間にわたって育児時間を共有したいと考える場合もあるでしょう。
この場合、パパ・ママ育休プラスを活用すれば、通常よりも長く夫婦で育休を取得できます。
原則として、育休は子どもが1歳に達するまでですが、パパ・ママ育休プラスは、夫婦が同時に育休を取得する場合、保育所への入所の有無を問わず育休期間を子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。
たとえば、母親の産後休業後、夫婦同時に育休を開始し、子どもが1歳2ヶ月になるまで一緒に育児を行うという方法です。
この期間中、必要に応じて夫婦それぞれが育休を分割して取得することもできます。
これにより、夫婦で協力しながら育児の喜びを分かち合い、子どもの成長を間近で見守れます。
育休の分割取得により企業の対応すべきこと
育休の分割取得により企業の対応すべきことは、下記の通りです。
- 就業規則や社内規定の見直し
- 育児休業の申請書の整備
- 育休取得に伴う人員配置の調整
- 柔軟な働き方への対応
- 相談できる体制を整える
- 新しい育児休業の制度を従業員に周知
次項で、それぞれ対応すべき内容について詳しく解説します。
就業規則や社内規定の見直し
育休の分割取得に対応するためには、就業規則や社内規定の見直しが必要です。
具体的には、分割取得に関して、申出の時期、子どもが1歳に達した日以降に育休を開始できるタイミングなどを明確に記載する必要があります。
また、産後パパ育休に関する規定も併せて見直し、従業員が制度を正しく理解し、安心して利用できるように整えましょう。
育児休業の申請書の整備
育児休業の申請書についても、分割取得に対応した様式に変更する必要があります。
従来の申請書では、育休開始日と終了日を記載するのみでしたが、分割取得の場合は、それぞれの期間を明確に記載できるようにする必要があります。
また、産後パパ育休と通常の育休を組み合わせて申請する場合も考慮し、分かりやすい様式で作成しましょう。
育休取得に伴う人員配置の調整
従業員が育休を取得する場合、その期間中の人員配置を調整する必要があります。
分割取得の場合は、取得期間が短くなる場合もあるため、より柔軟な対応が求められます。
代替要員の確保や、業務の分担方法などを事前に検討し、業務に支障が出ないように配慮しましょう。
また、育休取得者の業務復帰後もスムーズに業務に戻れるよう、情報共有や研修などのサポート体制を整えておくのがおすすめです。
柔軟な働き方への対応
育休の分割取得を機に、従業員の多様な働き方に対応できる環境を整えましょう。
たとえば、短時間勤務制度やフレックスタイム制度、テレワーク制度などを導入すれば、従業員の育児と仕事の両立を支援できます。
柔軟な働き方への対応は、育休取得者だけでなく、他の従業員のワークライフバランス向上にもつながり、企業全体の生産性向上に期待できます。
相談できる体制を整える
従業員が育休に関する疑問や不安を気軽に相談できる体制を整えておくことも大切です。
人事担当者や相談窓口を明確にし、従業員が安心して相談できる環境を作りましょう。
また、育休に関する情報提供や、復職支援に関する情報提供なども行えば、従業員の不安を軽減し、スムーズな育休取得と復職を支援できます。
新しい育児休業の制度を従業員に周知
育休の分割取得や産後パパ育休など、新しい育児休業の制度について、従業員に周知徹底することも大切です。
社内研修や説明会を実施するほか、社内報を活用し、制度の内容や申請方法などを分かりやすく伝える工夫が必要です。
また、従業員からの質問や疑問に適切に対応できるよう、人事担当者への研修も併せて行うと良いでしょう。
法改正【2025年4月~】育休手当の給付額が実質10割に
2025年4月より、育児休業給付金に関する制度が改正され、育休中の手取り収入が実質10割となる仕組みが導入されます。
これは、育休中の経済的な不安を軽減し、より安心して育児に専念できる環境を整えるためです。
この改正により、新たに「出生後休業支援給付」が創設されます。
次項で、出生後休業支援給付について詳しく解説します。
出生後休業支援給付
2025年4月から新たに創設される「出生後休業支援給付」は、育児休業中の給付水準を引き上げることで、手取り収入が実質10割となるように支援する制度です。
この給付金は、育児休業給付金に上乗せして支給されるもので、下記の特徴があります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 支給対象者 |
|
| 支給要件 |
|
| 給付額 |
|
| 申請方法 |
|
具体例としては、月額30万円の賃金を得ている方が育休を取得した場合、育児休業給付金として約24万円(8割)が支給されます。
さらに、社会保険料が免除されるため、手取り収入は休業前とほぼ同水準となります。
産休・育休に関わる申請書類のテンプレート
産休・育休を取得する際には、会社への申請手続きが必要です。
そこでマネーフォワード クラウドでは、産休・育休に関わる申請書類のテンプレートをご用意しております。
次項で、それぞれの申請で使える無料のテンプレートを紹介するので、ぜひ活用してください。
産休申請書テンプレート
産休(産前産後休業)を取得する際に必要なのが「産休申請書」です。
産休申請書は、出産予定日や産後の休業期間などを会社に伝えるための書類です。
下記に産休申請書のテンプレートをご用意いたしましたので、必要に応じてご活用ください。
育児休業申請書テンプレート
育児休業を取得する際に必要なのが「育児休業申請書」です。
育児休業申請書は、育休の開始日や終了日、分割取得を希望する場合はその期間などを会社に伝えるための書類です。
下記に育児休業申請書のテンプレートをご用意いたしましたので、必要に応じてご活用ください。
育休の分割取得を活用し、育児と仕事の両立を目指そう!
本記事では、育休の分割取得の概要、メリット、活用例、企業の対応、法改正について解説しました。
具体的なメリットとしては、夫婦で育児負担を分担しやすいこと、家庭の状況に柔軟に対応できること、職場とのつながりを維持しやすいことです。
さらに、育休の分割取得と産後パパ育休プラスを組み合わせれば、夫婦交代での育休や母親・父親2人で長期にわたっての育児などが可能です。
2025年4月からは、育休手当が実質10割になる法改正も予定されており、経済的な不安も軽減されるでしょう。
企業としては、就業規則の見直し、申請書の整備、人員配置の調整など、従業員が安心して制度を利用できるように整えておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
パワハラは同僚間でも起こる?発生した場合の対応や防止策を解説
パワハラというと、職場で優位な立場の上司による行為が部下へのパワハラとイメージされがちですが、同僚間でもパワハラは発生しています。同僚からの行為であっても、状況によってパワハラと認定される場合があるでしょう。本記事では、同僚間で発生するパワ…
詳しくみる在宅勤務・テレワークの就業規則で規定すべき項目は?記載例や運用のポイントも解説
在宅勤務やテレワークが急速に普及し、働き方の選択肢が広がる一方で、企業には新たな労務管理の課題が生じています。従来のオフィス勤務を前提とした就業規則だけでは、労働時間管理、費用負担、情報セキュリティといった在宅勤務特有の状況に十分対応できず…
詳しくみるウィンウィンの言い換えは?意味や例文、ビジネスで良好な関係を築く方法
会社は営利を目的としているため、ビジネスにおける自社の利益追求は、ごく自然なことです。しかし、自社の利益のみを追求していては、取引相手が不満を抱き、良好な関係を構築できません。 当記事では、取引相手と良好な関係を構築するために重要なウィンウ…
詳しくみる労使協定方式の締結方法とは?派遣先均等・均衡方式の違いとあわせて解説
派遣労働者の同一労働同一賃金に対応するため、労使協定方式の導入を検討している人もいるでしょう。 しかし労使協定を締結する際に必要な情報を把握していなければ、派遣労働者に対して適切な労働環境を提供していないとみなされる可能性があります。 労使…
詳しくみる3K労働とは?新3Kや6Kについても正しい意味を解説!
3K労働とは、「きつい、汚い、危険」の頭文字から作られた言葉で、主に若い労働者が敬遠する「労働条件が厳しい職業」のことを言います。 3K労働のイメージによる人員不足で、最近は多くの外国人労働者が3Kの仕事に就いているのを目にします。この記事…
詳しくみるパワハラ防止法とは?法改正の内容や対策法を解説!
パワハラ防止法の対策方法を検討する企業が増えています。2022年4月には法改正が行われ、中小企業もパワハラ防止法の対象となりました。パワハラ防止法に違反すると職場環境が悪化するだけでなく、企業名公表といった罰則を受けるリスクも高まります。そ…
詳しくみる