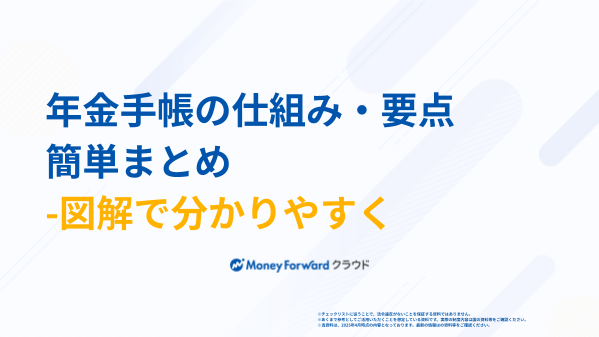- 更新日 : 2025年6月23日
基礎年金番号通知書と年金手帳の違いは?提出する場面やよくあるトラブルを解説
就職や転職の際に会社から提出を求められる「年金手帳」。令和4年4月以降は新規発行が終了し、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりましたが、制度変更の内容や会社とのやりとりについて、正しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、基礎年金番号通知書および年金手帳に関して、違いや提出が必要となる場面について解説します。
目次
年金手帳とは?まずは制度の基本を押さえよう
年金手帳は、基礎年金番号が記載された書類として長年使用されてきましたが、制度の見直しにより令和4年4月から新規発行が廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わりました。年金手帳の役割や通知書との違いを見ていきましょう。
年金手帳とは
年金手帳は、公的年金制度(国民年金・厚生年金など)の被保険者であることを証明するために交付される手帳です。加入者一人につき1冊のみ発行され、一生涯にわたって有効な基礎年金番号(10桁の番号)が記載されています。この番号は日本年金機構で個人の年金加入記録を管理するためのキーであり、公的年金制度共通のIDとして機能します。
転職などで加入する年金制度が変わっても新たに手帳が交付されることはなく、同じ基礎年金番号と年金手帳を引き続き使用します。例えば企業に入社して厚生年金に加入する手続きや、将来年金を受給するときの手続きなど、年金に関するほとんどの場面で基礎年金番号の提示が求められる重要な書類となっています。
年金手帳の廃止と基礎年金番号通知書の導入
令和4年4月1日から、年金手帳の新規発行が廃止され、公的年金に初めて加入する人には代わりに「基礎年金番号通知書」が発行される制度に変わりました。令和4年4月1日以降に20歳到達や就職などで年金加入手続きをする場合は従来の年金手帳が発行されず、基礎年金番号通知書が交付されます。
なお、年金手帳自体が完全になくなるわけではなく、令和4年4月より前に発行された年金手帳は今後も基礎年金番号を確認する書類として必要に応じて利用できます。
また、すでに年金手帳を持っている人には通知書の交付はありませんので、引き続き現在の年金手帳を大切に保管・利用してください。
基礎年金番号通知書のフォーマットと受け取り方法
基礎年金番号通知書は、年金加入者に基礎年金番号を知らせるためのカード型の書面です。用紙の色は黄橙色で、大きさは縦54mm×横85mmとクレジットカードとほぼ同じサイズになっています。記載事項は基礎年金番号(4桁-6桁の10桁数字)、氏名(カタカナのフリガナ付き)、生年月日、交付年月日であり、従来の年金手帳と比べてコンパクトながら必要な情報が簡潔にまとめられています。厚紙でできた小さいカード状のため、財布などに収めて保管しやすい点も特徴です。
通知書の受け取り方法は、従来の年金手帳の配布と若干異なります。以前は企業に就職した人の年金手帳が勤務先(事業所)宛てに送付され、会社経由で本人に手渡されるケースもありましたが、令和4年4月以降の基礎年金番号通知書は原則すべて加入者本人の住所に郵送されます。
国民年金(第1号被保険者)の場合、20歳の誕生日を迎えて加入手続きをしてからおおむね2週間程度で通知書が自宅に届く見込みです。また厚生年金(第2号被保険者)に加入した場合も、企業からの資格取得届の処理後に本人宛て郵送で交付されます。
基礎年金番号通知書と年金手帳の役割は違う?
基礎年金番号通知書への移行によって証明書の形式は変わりましたが、その役割や使われ方自体は従来の年金手帳と変わりません。年金の各種手続きや就職・転職の際など、これまで年金手帳の提示が必要だった場面では、今後は通知書を自治体窓口や会社に提示して基礎年金番号等を確認してもらうことになります。
令和4年4月以前に発行された年金手帳をお持ちの方には通知書は新たに発行されませんので、引き続きお手元の年金手帳をそのまま使用してください。
基礎年金番号通知書(年金手帳)を提出する場面
基礎年金番号通知書(または従来の年金手帳)は、公的年金に関するさまざまな手続きの場面で提示や提出が求められますので代表的なケースを解説します。
就職したとき(社会保険への加入手続き)
会社に入社して社会保険の加入手続きを行う際、雇用主から年金手帳または基礎年金番号通知書の提出を求められる場合があります。被保険者資格取得届に従業員の基礎年金番号を記入する場合もあるため、社員が基礎年金番号通知書(年金手帳)を提出しないと会社側で社会保険の加入手続きを完了できない恐れもあります。
ただし、マイナンバーが提供されている場合は、マイナンバーで手続きが可能です。そのため、マイナンバーを提供済みであれば、原則として年金手帳や基礎年金番号通知書を提出する必要はありません。これは転職の場合も同様です。
転職したとき
転職先の会社でも、前職と同様に基礎年金番号の提示が求められます。年金手帳や通知書は本人が管理する書類です。退職時に会社から返却された通知書(年金手帳)は忘れずに自分で保管し、転職先へ持参してください。同じ通知書(年金手帳)をキャリアを通じて使い続ける形になりますので、転職のたびに新しいものが発行されることはありません。
各種年金手続きをするとき
年金に関するさまざまな手続き(国民年金への種別変更届、年金保険料の免除申請、老齢年金の裁定請求など)の際にも、基礎年金番号の分かる書類の提示や番号の届出が求められる場合があります。
会社を退職して国民年金に切り替える手続きや、結婚による氏名変更届を出す場合などでも、通知書(年金手帳)を役所窓口で提示して本人の基礎年金番号を確認してもらうことがあります。年金を受給中の方であれば手元の年金証書に基礎年金番号が記載されていますが、現役世代の方は通知書(年金手帳)が自身の年金加入者であることを示す証明書となります。
マイナンバーがあれば基礎年金番号通知書(年金手帳)は不要?
マイナンバー制度の普及により、年金手続きの一部は基礎年金番号を直接提示しなくても進められるようになっています。被保険者資格取得届などの社会保険関連書類では、基礎年金番号に代えてマイナンバーを記入する形式も認められています。企業や自治体などがマイナンバーで本人確認と年金記録の照会を行える体制であれば、基礎年金番号通知書や年金手帳の提示が不要になる場合もあります。
しかし、すべての場面でマイナンバーだけで手続きが完結するとは限りません。企業の運用によっては、依然として基礎年金番号の確認を年金手帳や通知書の提示によって行うことを求める場合があります。また、マイナンバーの利用には本人の同意が必要とされるため、手続き時に同意を得られない場合や、本人確認のための補完資料として通知書(旧年金手帳)の提出が求められるケースもあります。
このように、マイナンバーが利用できることで通知書(年金手帳)が「常に不要」となるわけではありません。万一のトラブルや確認時に備え、通知書(年金手帳)は引き続き大切に保管しておくことが望ましいと言えます。
基礎年金番号通知書(年金手帳)についてよくある疑問やトラブル対処方法
基礎年金番号通知書(年金手帳)には重要な個人情報である基礎年金番号が記されています。十分に注意して取り扱い、トラブルがあった場合は適切に対処する必要があります。
基礎年金番号通知書(年金手帳)を会社に預けるのは義務?
年金手帳や基礎年金番号通知書を会社に提出する場面として最も多いのが、入社時に行う厚生年金の加入手続きです。企業は、従業員を社会保険に加入させる際に「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しますが、この届出には従業員の基礎年金番号が必要となる場合があります。そのため、会社側から通知書(年金手帳)の提出を求められることがあります。
ただし、年金手帳や通知書の提出は手続き上必要でも、それを会社が預かることまでが義務とされているわけではありません。従業員が提出した年金手帳や通知書は、基礎年金番号を確認した後、本人に返却されるのが基本的な取り扱いです。実務上は管理のしやすさから会社が保管しているケースもありますが、これはあくまで任意の取り決めです。
年金手帳や通知書は本人の重要な個人情報が記載された書類であり、紛失や誤用を防ぐためにも、会社に提出した場合でも適切な管理と返却の取り決めが必要です。
基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失した場合の対応方法
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合でも、再発行の手続きを行えば新たに交付を受けることができます。再発行の手続きは、最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金窓口で行います。申請には「基礎年金番号通知書再交付申請書」を記入し、本人確認書類とともに提出します。郵送での申請も可能です。
手続き後、再交付された通知書は原則として本人の住所宛に郵送されます。手続きから受け取りまでにはおおむね2~4週間程度かかるため、就職や転職などの手続きが控えている場合には、早めに対応することが大切です。なお、令和4年4月以降は年金手帳の新規発行は行われておらず、紛失時の再交付も「基礎年金番号通知書」として対応されます。
再交付を申請する際、自身の基礎年金番号が不明な場合でも、氏名・生年月日・住所などで年金記録を照会してもらうことができます。年金ネットやねんきん定期便などを利用して事前に番号を確認しておくと、手続きがよりスムーズに進みます。再交付された通知書は、再度の紛失を防ぐためにも安全な場所に保管しておきましょう。
基礎年金番号通知書(年金手帳)を会社が返してくれない場合の対応方法
年金手帳や基礎年金番号通知書は、本人の基礎年金番号が記載された私物であり、本来は従業員自身が保管すべきものです。入社時に厚生年金の手続きのため会社へ提出した場合でも、手続きが終われば返却されるのが基本的な取り扱いとされています。
退職時などに年金手帳や通知書の返却を求めたにもかかわらず、会社が返さない場合は、まずは人事や総務などの担当部署に対して文書やメールなど記録が残る方法で返却を求めましょう。それでも応じない場合には、労働基準監督署や年金事務所など、公的な相談窓口に助言を求めることができます。
なお、会社が年金手帳や通知書を正当な理由なく返却しない行為は、私物の不当な占有とみなされることがあります。
再発行手続きを行うことも可能ですが、元の書類が会社に保管されたままでは情報管理上の問題も生じかねません。適切な方法で返却を求めるとともに、やむを得ず再発行する際は事情を年金事務所に伝えるようにしましょう。
通知書や年金手帳を正しく管理し、会社とのやりとりに備えよう
基礎年金番号通知書や年金手帳は、本人の基礎年金番号が記載された私物であり、「人生に欠かすことのできないパスポート」とも言われる重要書類です。
提出が必要となる場合もありますが、会社に預けることは義務ではなく、手続き後に返却を受けることも可能です。
マイナンバーの活用により、提出が省略できる場面もありますが、会社の運用によっては提出が求められることもあるため、手元に保管しておくことが安心です。就職・転職・退職といった節目ごとに正しく取り扱えるよう、制度と実務の両面を理解し、自身の年金情報を適切に管理していきましょう。
よくある質問
年金手帳を会社に預ける理由はなんですか?
従業員雇入時の処理として、厚生年金の被保険者資格取得届への基礎年金番号記入に必要だからです。 詳しくはこちらをご覧ください。
年金手帳を紛失した場合どうすればよいですか?
基礎年金番号通知書再交付申請書を提出して、年金手帳の再発行を受けます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行?いつ届く?必要ケースや手続きを解説
会社退職後、国民健康保険へ加入するには健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)が必要です。しかし、会社の手続きが遅れ、すぐに発行してもらえないこともあるでしょう。 この記事では、退職後国民健康保険加入手続きをスムーズに行えるように、…
詳しくみる親を社会保険の扶養に入れることはできる?条件や保険料を解説!
社会保険には扶養という家族の生計を支援する大事な制度があります。そんな扶養制度ですが、親と同居していなくても親を扶養に入れることはできるのか、親を扶養に入れる際の条件は、など親を扶養に入れる際のルールはご存知でしょうか。当記事では親を扶養に…
詳しくみる労災保険の各種手続き
労災保険とは、労働者が勤務時間中に遭った災害や出退勤中に災害に遭った場合に、本人やその家族に補償するために、保険金を支払う制度です。 そのため、使用する従業員が正社員や契約社員、アルバイトかを問わず、労働者を使用する会社及び個人事業主は、労…
詳しくみる【2025年-28年】雇用保険法改正まとめ!図解資料も用意!
本記事では、2025年から2028年にかけて段階的に施行される雇用保険法の改正ポイントを、企業の人事労務担当者向けに解説します。 雇用保険の制度概要から始め、高年齢者雇用継続給付の支給率見直し、自己都合退職者に対する失業給付制限期間の短縮、…
詳しくみる厚生年金は強制加入?必ず加入しなければならない?
給与から引かれる厚生年金の保険料。「将来もらえる年金は減る」という話を耳にすると、「厚生年金に加入しなくてもいいのでは…」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、適用事業所に勤務する方は、原則として厚生年金保険は強制加入です。 ここで…
詳しくみる健康保険未加入のリスク
会社に勤めている間は、自分では何もしなくても、会社の社会保険に自動的に加入することになります。しかし、会社を退職したら自分で国民健康保険等の加入手続きを行わなくてはなりません。 転職先が決まっていれば、数週間は国民健康保険に加入しなくてもい…
詳しくみる