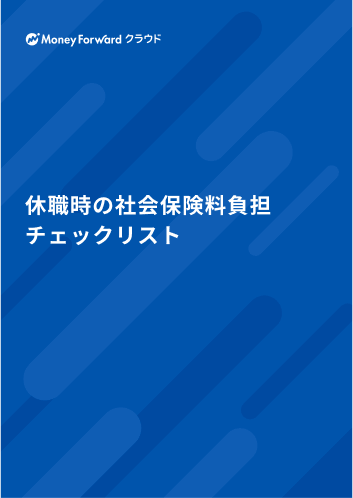- 更新日 : 2025年5月26日
休職中の社会保険料ガイド|払えない場合は?全額負担になる?
人事労務担当者やビジネスパーソンにとって、休職中の社会保険料の取り扱いは悩ましい問題ですが、休職中の社会保険料は原則として全額負担です。支払いが困難な場合においては、対応策があります。
本記事では、休職中の社会保険料の仕組みや支払い方法、負担軽減の可能性について解説します。適切な対応で従業員と会社双方の負担を軽減しましょう。
目次
休職中の従業員の社会保険料の扱いについて
従業員が休職する際、給与の支給が停止されることが一般的です。しかし、休職中であっても社会保険料の取り扱いは継続するため、企業や従業員がそれぞれどのように対応するべきかを明確に理解することが重要です。
ここでは、各種社会保険料および税金の取り扱いについて解説します。
健康保険料の取り扱い
休職中であっても、従業員が健康保険に加入している限り、健康保険料の納付義務は基本的に継続します。給与が支払われない場合は、以下のいずれかの方法で対応が必要です。
- 従業員からの直接支払い
企業は休職中の従業員に対して健康保険料を直接請求し、従業員は支払う
- 給与復帰後、まとめて支払い
休職明けに未納分を一括で徴収する方法、ただし労働者と使用者の間で事前に合意が必要
- 健康保険料免除の可能性
傷病手当金を受給する場合、一定の条件下で保険料が免除されることがある
※この条件については加入している健康保険組合または全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の案内を確認してください。
従業員からの直接支払いの場合、支払い方法は企業によって異なります。企業の銀行口座へ振込が必要、現金書留での郵送が必要などが、主な例です。休職からの復帰後のまとめて払いの場合も、具体的な支払い方法まで取り決めておきましょう。
厚生年金保険料の扱い方
休職中も厚生年金保険料は引き続き納付する必要があります。給与がない場合、対応方法は健康保険料と同様です。
- 直接徴収または給与復帰後の徴収
従業員が給与を受け取れない期間でも保険料の納付義務は消えないため、企業が休職者から直接徴収することが一般的
- 特例免除の制度はない
厚生年金保険料に関しては、休職中の免除制度は設けられていないため納付が必須
注意すべきは「特例免除の制度がない」という点です。厚生労働省では「厚生年金保険料等の猶予制度について」は取り決めがありますが、免除については触れていません。
育休や産休による厚生年金保険料の免除はありますが、休職についての免除規定がないため、休職中であっても厚生年金保険料については支払いが必要と解釈できます。
介護保険料の休職中の処理
介護保険料は40歳以上の被保険者が対象となるため、休職中であっても納付義務があります。
- 納付の継続
介護保険料は健康保険料とセットで徴収されるため、健康保険料と同様に従業員からの直接支払いや、給与復帰後にまとめて支払うといった、健康保険料免除の可能性で対応が可能
※休職中に介護保険の被保険者資格を失う場合(例:40歳未満に該当する、退職するなど)は、介護保険料の納付が不要となる場合があります。詳細は、各保険組合または協会けんぽの案内をご確認ください。
介護保険料については、協会けんぽなど各保険組合へ問い合わせできます。Webページ上や電話で問い合わせるなどして、自身にとって適切な案内を受けることをおすすめします。
雇用保険料の休職期間中の対応
雇用保険料は、原則として休職中に給与が支払われない場合には、企業も従業員も納付義務がありません。
- 給与が支払われない場合
雇用保険料は給与の支払額に対して算定されるため、給与がゼロの場合、雇用保険料の負担はない
- 部分給与支給時
休職中に一部給与が支給される場合、その支給額に応じて雇用保険料が算出される
- 失業など給付との関係
休職中に退職する場合、雇用保険の失業などといった給付の対象となる可能性があるため、詳細をハローワークまたは厚生労働省の雇用保険関連情報で確認する必要がある
雇用保険料は休職中に給与が発生しなければ、支払う必要がありません。しかし、休職中にそのまま退職をする場合は、失業などの給付と関連性があるため、ハローワークなどへの確認が必要です。
休職願(ワード)のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
休職中の従業員の税金の扱いについて
従業員が休職中であっても、税金に関する義務は完全に免除されるわけではありません。特に所得税と住民税は、休職期間中の給与や前年の所得に基づいて処理が必要です。
以下では、休職中の税金の取り扱いについて詳しく解説します。
所得税の計算と納付方法
所得税は、原則として給与が支払われた際に源泉徴収されます。休職中に給与の支給がない場合は以下の対応が必要です。
- 休職中に給与が支払われない場合
所得税は給与所得に基づいて課税されるため、給与がゼロの場合は源泉徴収も行われない
→休職期間中は所得税の納付義務が生じない
- 一部給与が支払われる場合
休職中でも傷病手当金や役員報酬が支払われる場合、傷病手当金は非課税所得であり、所得税は課されません。 ただし、役員報酬が支払われる場合は、所得税が課されます。
休職期間中に復職がない場合は年末調整が行われないため、従業員自身が確定申告を行う必要がある
→特に医療費控除や生命保険料控除などの適用を受ける場合、確定申告を通じて還付を受けることが可能
休職中の従業員の所得税は、給与が発生しなければ納付義務も生じません。しかし、一部給与が支払われる場合は注意が必要です。
また、従業員自身に確定申告を促す、または医療費や生命保険料控除の適用がある場合の還付については会社でも把握しましょう。
住民税の取り扱いと支払い
住民税は前年の所得に基づき課税されるため、休職期間中であっても納税義務は継続します。給与からの天引きができない場合、以下の方法で対応します。
- 給与天引きが停止する場合
休職により給与の支給が止まると、住民税は従業員が自ら納付することになる
→自治体から「普通徴収」の納付書が送付され、指定された期日までに支払わなければならない
- 会社が代理で支払う場合
企業が休職中も住民税を立て替えて支払うケースもある
→復職後にまとめて返済を求めることが一般的
病気で休職中の人は、住民税の納付など自治体からの郵送物に気づかず、延滞料が発生する可能性もあります。会社側は自治体から届く納付書関連の情報を的確に従業員に連絡をしましょう。
休職期間中の課税所得の考え方
課税所得の概念は休職中であっても重要です。課税所得がどのように計算されるかによって、税金の負担額が変わります。
- 給与所得がゼロの場合
休職中に給与が支払われない場合、課税所得もゼロとなる
→休職期間中に過去のボーナスや一時金が支払われる場合はそれらが課税所得に含まれるため、税額が発生する
- 傷病手当金などの非課税収入
健康保険法に基づく傷病手当金などは、所得税の課税対象外
→これらの収入は確定申告の際に申告が不要となるため、税務上の取り扱いに注意が必要
課税所得の計算について不明点がある場合は、従業員は勤務先の経理部門または税務署に相談できます。従業員からの問い合わせに備えて、正確な課税所得を把握し税務上のリスクを軽減しましょう。
休職中の従業員の社会保険料や税金を徴収する方法
従業員が休職中であっても、社会保険料や税金の納付義務は基本的に継続します。給与が支給されない場合でも、適切な徴収方法を検討しなければなりません。ここでは、社会保険料や税金を徴収する具体的な方法と注意点について解説します。
給与からの控除方法と注意点
休職中に給与が一部でも支給される場合、社会保険料や税金は給与から控除されます。ただし、休職中の特性を考慮した対応が必要です。
- 給与支給額が不足する場合
終業員の給与が少額で社会保険料や税金の全額を控除できない場合、不足分を従業員に別途請求する必要がある
→労使間で事前に徴収方法を確認しておくことが重要
- 控除額の確認と誤徴収防止
控除ミスを防ぐため、最新の社会保険料率や税率を確認することが望ましい
→特に年度途中で料率が変更されることもあるため、厚生労働省や国税庁の公式サイトで最新情報を確認する必要がある
休職中に一部の給与が発生する場合は、給与明細で控除内容を具体的に明記しておくことをおすすめします。控除内容を給与明細に明示することで、従業員に対して透明性を確保できます。これは、後日誤解やトラブルを避けるために重要です。
別途支払いの手続きと期限
給与が支給されない場合、社会保険料や税金を従業員から直接徴収する必要があります。以下の手順と注意点を押さえておきましょう。
- 直接請求の実施
社会保険料については、企業が従業員に対して毎月納付額を通知し、銀行振込や口座引き落としを利用して徴収する
→税金についても同様であり、従業員から直接納付を求めることが可能
- 納付期限の厳守
社会保険料は原則として毎月、税金は市区町村や税務署が指定する納付期限内に支払う必要がある
→納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、従業員には早めの対応を促す
- 支払計画の作成
社会保険料の一括での支払いが難しい場合、分割での納付を企業が提案することも可能
→ただし、社会保険料や税金の未納があると法的措置が取られる可能性もあるため、計画的な対応が求められる
休職中であっても発生する社会保険料や税金は、休職者にとっては大きな出費となりえます。しかし、滞納することによって支払う金額がまとまって大きくなることや、未納についての法的処置が取られるのは避けたいものです。
会社側の徴収義務と従業員の責任
社会保険料や税金の徴収において、企業と従業員それぞれに責任があります。以下の点を理解しておくことが重要です。
- 会社の徴収義務
企業は従業員が休職中であっても社会保険料の従業員負担分を徴収し、納付する義務がある
→源泉徴収義務者として所得税を適切に処理する必要もある。
- 従業員の納付責任
従業員は休職中も自身が負担すべき社会保険料や税金を支払う責任がある
→企業からの請求に応じて速やかに対応しなければならない
- 未納時のリスク
未納が発生した場合、従業員は保険給付の停止や税務上のペナルティを受ける可能性がある
→企業側も行政指導や罰則の対象となる場合があるため、適切な管理が求められる
休職者は在籍している従業員であるため、可能な範囲で相談に応じたり、アドバイスをしたりするとよいでしょう。
傷病手当金から社会保険料の控除はできる?
休職中の従業員が傷病手当金を受給する場合、その手当金から社会保険料を控除できるのかという疑問を抱く企業や従業員もいることでしょう。ここでは、傷病手当金の概要から社会保険料控除の可否、控除ができない場合の対応策について解説します。
そもそも傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入する被保険者が病気やけがのために働けなくなり、給与の支払いが停止された際に支給される給付金です。
この制度は、労働者が収入を失った場合の生活を支援するために設けられています。傷病手当金の支給条件には以下のようなものがあります。
- 業務外の病気やけがで療養中であること
労災保険の対象とならない、業務外の傷病が対象
- 仕事ができない状態であること
医師の診断書などで労務不能状態が証明される必要がある
- 連続して3日以上の待期期間を経過していること
傷病手当金の支給は、連続する3日間の労務不能が経過した後の4日目以降から開始される
- 給与が支給されていないこと
休職中に給与が支給されている場合は、その金額が傷病手当金よりも少ないときに差額分が支給される
傷病手当金の受給には、以上の条件を満たす必要があります。状況に応じて、労働者側での必要書類の準備(医師の診断書など)が必要となるため、提出書類の確認に注意しましょう。
傷病手当金からの社会保険料控除の可否
傷病手当金は給与とは異なる性質があるため、社会保険料の控除対象に含まれていません。ただし、休職中で傷病手当金の給付を受けていても、社会保険に加入している限りは社会保険料の支払いは続きます。傷病手当金の受給中の休職者の同意を得て、傷病手当金から社会保険料を控除することは可能です。
傷病手当金について、以下の通りまとめましたので、ご参考にしてください。
- 法的根拠
健康保険法および厚生年金保険法では、社会保険料は給与や賞与から控除されることを前提としている
→一方で、傷病手当金はこれらの「報酬」や「賞与」には該当しないため、手当金から社会保険料を控除することはできない
- 例外事項はない
労働者と会社の間で合意があったとしても、法律上認められていない
→傷病手当金から社会保険料を控除することは不可能
控除できない場合の対応策
傷病手当金から社会保険料を控除できない場合、企業や従業員は別の方法で社会保険料の納付を行う必要があります。
- 直接徴収による対応
企業が従業員に対して休職期間中の社会保険料を直接請求し、銀行振込や現金払いで徴収する方法がある
→従業員に毎月の納付額を通知し、期日までに支払ってもらう形を取ることが多い
- 給与復帰後の一括徴収
休職期間終了後、復職した際に給与から未納分をまとめて控除することも可能
→一括控除は従業員の生活に影響を与える可能性があるため、事前に労働者と会社の間で十分な協議を行う必要がある
- 国の猶予制度の活用
社会保険料の納付が困難な場合には、保険料納付の猶予制度を活用することも検討できる
→一定の条件を満たすことで、支払いを一時的に猶予または分割納付することが可能
上記3つの方法を紹介しましたが、共通しているのは「休職者本人との話し合いが必要」という点です。
休職者の休職理由によっては、電話などでも話し合いが難しい場合があります。メールなども利用して、休職者本人の意思確認ができるよう取り計らわなければなりません。
休職中の社会保険料でよくある質問
社会保険料の負担や処理方法について疑問がある休職中の従業員もいることでしょう。以下では、休職中の社会保険料に関するよくある質問について解説します。
休職中の社会保険料は全額負担になる?
休職中でも社会保険料は原則として給与と同様に徴収されます。ただし、給与が支給されない場合でも従業員負担分の納付が必要であり、事業主負担分は企業が継続して負担します。
給与から天引きできない場合、企業は従業員に社会保険料全額を直接請求し、従業員が振込などで納付します。
ただし、企業の規定や労使間の合意により、企業が立て替えるケースもあります。企業が立て替えた場合は、復職後に給与から控除することが一般的です。
休職中の社会保険料の等級はどうなる?
特別な理由がない限り、休職中の社会保険料の等級は、休職前の標準報酬月額が基準です。休職によって給与が支給されない場合でも、自動的に等級が変わることはありません。
ただし、休職期間中に標準報酬月額の変更が必要な特例的なケースもあります。
例えば、休職が長期間に及ぶ場合、一定の条件下で報酬月額変更届を提出することで等級が見直されることがあります。
休職中の社会保険料は年末調整で精算できる?
休職中の社会保険料は年末調整で直接精算されることはありません。年末調整は主に所得税や復職後の給与に基づく控除の調整を目的としているため、社会保険料の納付額は対象外です。ただし、確定申告を行う場合には、納付済みの社会保険料は控除の対象となります。
休職期間中に従業員自身で社会保険料を支払った場合、その支払い分を所得控除として申告することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
休職中の社会保険料が免除になるケースはある?
休職中でも、社会保険料の免除を受けられるケースは限られています。例えば、育児休業や介護休業中に企業が手続きを行うことで、健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度があります。全てのケースに適用ではありませんが、育児休業給付金を受給する場合も該当する場合があります。
一方で、傷病手当金を受給している場合は、社会保険料の免除は適用外なので、対象の従業員は通常通り保険料を負担するのが必須です。
休職中の社会保険料が払えない場合はどうしたらいい?
休職中の収入減少により、社会保険料の支払いが困難になるケースがあります。このような場合、適切な手続きを行い、負担を軽減する方法を検討することが重要です。以下では、具体的な対応策を紹介します。
会社との相談と支払い計画の立て方
社会保険料の支払いが難しい場合、まずは勤務先に相談しましょう。企業と従業員の合意に基づき、以下のような支払い計画を立てることができます。
- 分割払いの提案
月々の負担を軽減するため、分割での納付が検討されることがある
→企業が保険料を一時的に立て替え、復職後の給与から少しずつ控除する方法も一般的
- 納付期限の延長
企業が納付期限を調整することで、一時的な支払い負担を軽減できる
→従業員は一括支払いの回避が可能となる
分割払いや納付期限の延長の計画を立てる際には、企業の担当者や労働組合と密に連携し、計画を文書化しておくと安心です。
社会保険料の減額や猶予制度の活用
社会保険料が払えない場合、公的な猶予制度の利用が検討できます。日本年金機構や健康保険組合では、以下のような支援策を提供しています。
- 保険料納付猶予制度
一定の条件を満たす場合、健康保険料や厚生年金保険料の納付を一時的に猶予できる制度
→猶予期間中は延滞金が発生する場合もあるため、早めの手続きが求められる
- 減額措置
特定の事情がある場合、保険料の一部が減額されることがある
→例えば、災害などによる収入減少がこれに該当する
収入によっては社会保険料の金額が高いと感じる休職者もいることでしょう。休職中に支払いが難しいと悩まれる人もいるかもしれません。そのような時は、会社の担当者と話し合い、無理のない支払い計画を立てることをおすすめします。
公的支援や福祉制度の利用可能性
社会保険料の支払いが難しい場合、自治体や福祉制度を活用することで支援を受けられる場合があります。
- 生活福祉資金貸付制度
低所得者や一時的に収入が減少した人を対象にした、無利子または低利子で生活費や社会保険料を補うための資金を貸し付ける制度
- 生活保護制度
収入が最低生活費を下回る場合、生活保護の一環として社会保険料の支援を受けられる可能性がある
→各自治体の福祉窓口で相談が可能
社会保険料の支払いが難しく、会社との話し合いでも適切な解決策が見つからない場合は、自治体や福祉制度を利用することも可能性です。必要に応じて居住する自治体へ問い合わせてみるとよいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労災保険の特別加入とは
労災保険は、基本的に労働者を保護するための保険ですが、労働者に準じて保護することがふさわしい者については特別に、任意加入することができます。それが、特別加入制度です。今回は、労災保険に特別加入できる対象範囲について解説していきます。 特別加…
詳しくみる随時改定に残業代は含む?標準報酬月額との関係や社会保険料に与える影響を解説
残業代が増減した場合、随時改定の対象になるのか疑問を抱く方もいるでしょう。 結論、残業代の増減だけでは随時改定の対象にはなりません。ただし、支給割合や固定残業代に変更があった場合は、対象となるケースがあります。 本記事では、随時改定の概要や…
詳しくみる厚生年金の加入で年金が2万増える?保険料と受給額の計算方法を解説!
会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険。厚生年金保険に加入すると、将来もらえる年金額が増加します。 厚生年金保険料は会社から受け取る給与をいくつかの等級に分けて区分した標準報酬月額によって決定されますが、厚生年金保険の年金受給額の計算方法…
詳しくみる社会保険の算定基礎届とは
社会保険料は、会社と従業員である被保険者が必要な金額を折半して負担します。 そして、被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例した金額です。 しかし、実際に支給される報酬は毎月変動するものであるため、社会保険料やそ…
詳しくみる予防給付と介護給付の違いは?
予防給付と介護給付は、両方とも介護保険制度の介護サービスの種類の一つです。限度額はあるものの、介護の必要度合いに合わせて、市町村などが提供する介護サービスを自己負担1割〜3割で利用することができます。ここでは、利用できるサービスの違いや月額…
詳しくみる厚生年金の報酬比例部分とは?定額部分との違いや計算方法、支給開始年齢を解説
公的年金制度には厚生年金と国民年金がありますが、その仕組みは複雑です。 支給開始年齢が65歳であることは知っていても、年金を構成する報酬比例部分や定額部分がどのようなものなのか、理解している人は少ないのではないでしょうか。 本稿では年金制度…
詳しくみる