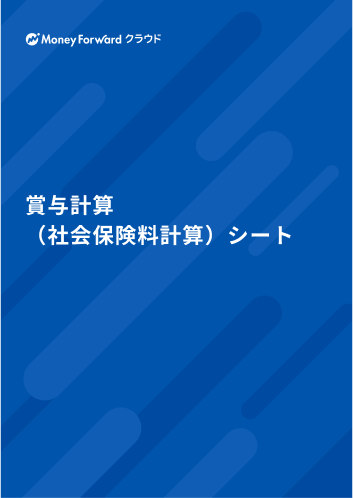- 更新日 : 2025年4月24日
賞与の計算方法について徹底解説!社会保険料の算出など
給与とは別に一時金として支払われる賞与(ボーナス)の支払いには、法律による規定はなく、企業が独自に支給額や支給基準、支払回数、支払時期を決めることができます。
今回は、賞与から控除する社会保険料、所得税の算出方法や計算時の端数の扱い、賞与に関するよくある疑問点などについて見ていきます。
目次
賞与(ボーナス)とは?
賞与(ボーナス)とは、毎月の給与とは別に臨時的・一時的に支払われる、労働の対象となる賃金の総称です。会社に支払いの義務があるわけではなく、賞与支払の有無を含めて会社が任意で賞与のルールを決めることが可能なため、夏季賞与、冬季賞与、決算賞与、ボーナス、期末手当、年末一時金など、その呼び方も様々です。
賞与の種類
賞与には、従業員の勤務成績などに連動して支給する賞与や、会社の業績に連動して従業員に利益を還元する目的で支給する決算賞与もあれば、役員賞与のように定期的に支給され、支給額が確定している賞与もあります。
毎月の給与に連動して支給する賞与
基本給や資格手当・役職手当など、毎月の給与と連動して賞与を支給する会社は多いでしょう。「基本給の2ヵ月分」「基本給+役職手当の1.5ヵ月分」などと、毎月支給する基本給や手当などの固定給に会社が決定した支給率を乗じて支給するタイプが、毎月の給与に連動して支給する賞与です。
就業規則などでは、「会社の業績の低下、従業員の勤務成績や業績評価、社会情勢、その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、また支給しないことがある」などと規定し、支給額(支給月数)はその都度会社で決定するのが一般的です。
必ずしも一律で支給する必要はなく、毎月の給与に連動していたとしても、業績が良好な従業員には賞与を5%増額するなどと、業績によって一定率を上乗せしたり、減額したりすることも可能です。
業績に連動して支給する賞与
従業員のモチベーションアップを目的に、支給対象期間の業績や成果によって賞与をインセンティブとして支給する会社も多いでしょう。業績に連動して支給する賞与は、個人の業績や部門の成果によって支給額が増減するのが特徴です。
営業担当やプロジェクトチームなどの業績や成果で金額が決定されることから、会社としても業績良好な従業員と業績が思わしくない従業員との公平性を保つことができます。歩合給を組み込むことで、賞与支給対象期間中に企業にもたらした利益を賞与で還元して支給するケースもあります。
支給額・支給時期が確定している賞与
例外的に、役員賞与のようにあらかじめ支給時期が決まっていて、支給額が確定している賞与がこの例に当たります。会社役員は労働者ではないため、そもそも役員報酬や役員賞与は賃金とはいえません。しかし、従業員に支給する賞与であっても、就業規則や労働条件通知書などで「毎年6月と12月に300,000円を支給する」などと、支払時期や金額が明記されているケースがあります。臨時で支給するとはいえ、このケースでは支給することを約束しているので、支払わなければ労働基準法の違反を問われることになるため注意が必要です。
決算賞与
決算賞与は、決算月前後に会社の決算の状況によって支給をする賞与です。会社の決算で利益計上が見込まれる際、従業員に利益を還元するために支給することが多く、必ずしも毎期支給するとは限りません。そのため、就業規則などで「会社の業績によっては支給しないこととすることができる」などと規定し、決算内容によっては支給しないケースも考えられます。
決算賞与と通常の賞与との違いは、決算賞与は、その会社の事業年度の業績に応じて支給されるのに対し、通常の賞与は、会社の規定や労働者の実績に応じて支給される給与である、という点にあります。
年俸制の賞与
年俸制で、年俸額を14回に分割して、6月や12月の賞与の時期に多く支払うケースもあります。しかし、このような支払方法は、正確には給与の支払い時期や支払い方法などの契約上の条件の問題であり、賞与とはいえません。ただし、年俸とは別にインセンティブなどを賞与として設定するケースもあり、賞与を含めて年俸を設定するか、業績や成果に応じて賞与を年俸とは別に支払うか、契約内容を慎重に検討してから設定する必要があるでしょう。
賞与の平均支給額の統計値は?
賞与はどの程度の金額を支給すればよいのでしょうか。賞与の平均支給額を様々な角度から見てみましょう。
企業規模別の賞与額の平均
厚生労働省の「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)」では、以下のように発表されています(2023年2月分結果速報・2023年9月分結果速報)。この表からは、企業規模が大きいほど、賞与の支給金額が多くなることがわかります。
| 企業規模 | 2023年の夏季賞与額(労働者一人平均賞与額) | 2022年の年末賞与額(労働者一人平均賞与額) |
|---|---|---|
| 500人以上 | 66.5万円 | 64.2万円 |
| 100~499人 | 45.6万円 | 45.3万円 |
| 30~99人 | 34.8万円 | 35.5万円 |
| 5~29人 | 27.1万円 | 27.5万円 |
| 調査産業計 | 39.7万円 | 39.3万円 |
参考:毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 結果の概要|厚生労働省
都道府県別の賞与額の平均
「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、都道府県によっても賞与の支給金額に大きな差が生じていることがわかります。大企業が多い都道府県は賞与額が多いといえるでしょう。
| 都道府県 | 年間賞与額(2023年賃金構造基本統計調査・一般労働者 都道府県別・年間賞与その他特別給与額・男女計) |
|---|---|
| 東京都 | 104.3万円 |
| 神奈川県 | 110.0万円 |
| 大阪府 | 102.3万円 |
| 愛知県 | 103.9万円 |
| 青森県 | 57.6万円 |
| 沖縄県 | 49.8万円 |
| 都道府県合計 | 90.9万円 |
参考:賃金構造基本統計調査(参考表)都道府県別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(47都道府県一覧)|政府統計の総合窓口
年齢別の賞与額の平均
同じく令和5年賃金構造基本統計調査によると、細かく見ると学歴による違いや男女差もありますが、全体的には年齢が上がるほど賞与の支給金額が大きくなり、定年を迎えると急激に下がっていることが伺えます。
| 年齢区分(企業規模10人以上) | 年間賞与額(2023年賃金構造基本統計調査・一般労働者・年間賞与その他特別給与額・男女計・学歴計) |
|---|---|
| ~19歳 | 14.9万円 |
| 20~24歳 | 37.9万円 |
| 25~29歳 | 66.3万円 |
| 30~34歳 | 80.2万円 |
| 35~39歳 | 93.8万円 |
| 40~44歳 | 103.1万円 |
| 45~49歳 | 112.0万円 |
| 50~54歳 | 119.6万円 |
| 55~59歳 | 121.9万円 |
| 60~64歳 | 72.4万円 |
| 65~69歳 | 36.2万円 |
| 70歳~ | 27.0万円 |
| 男女・学歴計 | 90.9万円 |
参考:賃金構造基本統計調査 2 学歴、年齢階級、勤続年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 産業計|政府統計の総合窓口
会社が賞与を支給する際に必要な手続き
賞与(ボーナス)といえば、夏と冬に支払われるとイメージする人が多いでしょう。賞与の種類は、従業員の勤務成績などに連動して支給する夏季賞与や冬季賞与のほか、会社の業績に連動して従業員に利益を還元する決算賞与などが代表的です。
従業員に賞与を支払うならば、あらかじめそのルールを就業規則などに定めておくことが必要です。また、賞与を支給した際には、日本年金機構へ届け出る手続きが発生します。なお、代表者や役員に賞与を支給する際には、あらかじめ税務署へ届け出ておく必要もあります。
賞与支払のルールは労働条件通知書や就業規則に定める
「臨時の賃金・賞与・1ヵ月を超える期間を要件とする手当」を支給するルールがある場合、労働条件通知書などで明示することが労働基準法で定められています。また、臨時の賃金などについてのルールがある場合には、就業規則にもそのルールを定めなければなりません。労働者が10人以上いる事業場では、就業規則の作成・変更をした際、労働基準監督署への届出が必要です。
労働基準法の通達では、賞与を以下のように説明しています。
「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと」
つまり、定期的または臨時的に支給し、従業員の勤務成績に応じて支給するため、支給額があらかじめ確定していない臨時の賃金が賞与ということになります。したがって、賞与は毎月支払う給与とは異なり、支給が約束されているものではありません。
賞与支払いの時季や金額、条件、評価方法などは会社が任意で定めることが可能であり、賞与を支給しないことも可能です。そのため、パートやアルバイトなど非正規の労働者には「賞与を支給しない」などとして、賞与が支払われないケースもあります。また、賞与の支給対象者を、6月1日や12月1日、賞与支給日などに在籍した従業員に限定する「在籍日の基準」を設けて、期間の途中で退職して基準日に在籍しない従業員に賞与を支給しないルールを設けることも可能です。
厚生労働省作成のモデル就業規則では以下のように定めているので、参考になるでしょう。

代表者や法人役員の場合は事前に税務署へ届出をする
会社経営者や役員に支給する賞与は、税法上の手続きが発生するため注意しましょう。従業員に支給する賞与と異なり、例外的に事前に賞与支払の時期や金額を決めて支給する必要があります。
役員賞与を支給する場合、株主総会を開催し、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」と「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用)」を提出してから、届出書に記載した内容どおりに支給しなければなりません。
届出期日は「役員賞与の支払いについて株主総会で決議した日から1ヵ月以内」「決算日から4ヵ月以内」のいずれか早い日までです。「事前確定届出給与に関する届出書」には、支給対象の役員の氏名、支給時期、支給金額などを記載します。届け出をすることなく役員賞与を支給すると役員賞与を損金算入できなくなってしまうため、忘れずに手続きをしましょう。
参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
賞与を支払い後には賞与支払届を提出する
賞与は、健康保険料(介護保険料を含む)・厚生年金保険料・雇用保険料のほか、源泉所得税などを控除して支給します。健康保険や厚生年金保険の保険料を納付するには、日本年金機構や健康保険組合に従業員に支払った賞与の金額を届け出なければなりません。この報告の際に提出するのが「被保険者賞与支払届」です。
届出期日は、「支給日から5日以内」です。賞与支払月に賞与を支払わなかったときには、「賞与不支給報告書」を提出します。なお、健康保険組合に加入している会社の場合、健康保険組合によって報告書式が異なることがあるため、加入している健康保険組合に確認しましょう。
賞与(ボーナス)の計算方法
次に、賞与(ボーナス)の計算方法について確認していきましょう。
支給項目には基本賞与が、控除項目には社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)と税金(所得税)があります。
この控除項目のそれぞれの金額の算出方法について見ていきましょう。
健康保険料の算出方法について
賞与における健康保険料の金額は、以下の計算式で算出します。
求められた健康保険料は、事業主と被保険者が労使折半で負担します。
(計算例)
東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)で、令和3年12月に従業員であるXさん(50歳、扶養家族1名)に賞与30万円を支払う場合
ただし、健康保険料については、標準賞与額の年度の上限額が573万円と決められており、年度の途中で573万円を超える場合は、573万円が標準賞与額になります。
厚生年金保険料の算出方法について
賞与における厚生年金保険料の金額は、以下の計算式で算出します。
求められた厚生年金保険料は、事業主と被保険者が労使折半で負担します。
(計算例)
東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)で、令和3年12月に従業員であるXさん(50歳、扶養家族1名)に賞与30万円を支払う場合
ただし、1回の賞与額が150万円を超える場合は、150万円が標準賞与額となります。
雇用保険料の算出方法について
賞与にかかる雇用保険料は、月額給与の雇用保険料の計算式と同様に以下の計算式で算出します。
雇用保険料率は、事業主、労働者ともに事業の種類により異なります。
※令和3年度の雇用保険料率
| ① 労働者負担 | ② 事業主負担 | ①+② 雇用保険労率 | |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
| 農林水産・ 清酒製造の事業 | 4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
| 建設の事業 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
参考:令和3年度の雇用保険料率について|厚生労働省
(計算例)
東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)で、令和3年12月に従業員であるXさん(50歳、扶養家族1名)に賞与30万円を支払う場合
=30万円×3/1000(一般の事業の場合)=900円会社が負担する雇用保険料
=30万円×9/1000(一般の事業の場合)-30万円×3/1000=1,800円
介護保険料の算出方法について
賞与における介護保険料の金額は、以下の計算式で算出します。
求められた介護保険料は、事業主と被保険者が労使折半で負担します。
(計算例)
東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)で、令和3年12月に従業員であるXさん(50歳、扶養家族1名)に賞与30万円を支払う場合
所得税の算出方法について
賞与の所得税については、下記の手順で所得税額の算出します。
1)前月の給与額と扶養人数から賞与の税率を求めます。
前月の給与(総支給額)から、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料[40歳から64歳の方]、雇用保険料)を差し引いて所得税率の基準額を算出します。
(計算例)
東京都にある会社(全国健康保険協会に加入)で、令和3年12月に従業員であるXさん(50歳、扶養家族1名)に賞与30万円を支払う場合
前月の給与額が25万円、社会保険料が39,672円とすると、
になります。
この所得税率の基準額と扶養人数から賞与にかかる所得税率を確認します。
(確認例)
所得税の基準額は上記の計算例により 210,328円で扶養家族の人数は1名ですので、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和3年分)」の甲欄の94千円以上243千円未満の欄と扶養人数1人の欄から、賞与の金額に乗ずべき率を2.042%と求めることができます。

2)賞与から社会保険料を差し引いて課税対象額を求めます。
これまでの計算例で、Xさんの賞与は30万円、社会保険料が45,810円ですので、課税対象額は次の金額になります。
(計算例)
=30万円-45,810円
=254,190円
3)課税対象額に賞与の税率を掛け算して賞与の所得税を算出します。
所得税の小数点以下は切り捨てですので、所得税は5,190円になります。
なお、扶養控除等申告書の提出がない従業員の場合は、1)で使用する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は「乙欄」を利用して算出してください。
また、前月の給与の支払がない場合や扶養親族に障害者などが含まれている場合には計算方法が異なります。
その場合には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の備考欄を参照して計算するようにして下さい。
最後に、これまでの計算方法について表にまとめます。
| 種 類 | 計算方法 |
|---|---|
| 健康保険料・ 厚生年金保険料 の計算方法 | ①1,000円未満切り捨て 賞与総額 - 1,000円未満 = 標準賞与額 (千円単位) |
| ②保険料率を掛け算する ・標準賞与額 × 健康保険料率 = 健康保険料 (千円単位) ・標準賞与額 × 厚生年金保険料率 = 厚生年金保険料 (千円単位) | |
| 雇用保険料の 計算方法 | 保険料率をかける 賞与総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料 |
| 所得税の計算方法 | ①前月の給与額と扶養人数から賞与の税率を求める。 |
| ②賞与から社会保険料を差し引いて課税対象額を求める。 | |
| ③課税対象額に賞与の税率を掛け算して賞与の所得税を 算出する。 |
年4回以上の賞与の支給がある場合の計算方法・注意点
従業員や会社役員に賞与を支払ったときには、日本年金機構や健康保険組合に「被保険者賞与支払届」を提出します。しかし、年4回以上賞与がある場合には、賞与として届けるのではなく、算定基礎届や月額変更届を提出する際の「通常の報酬」に含めて計算する必要があるため注意が必要です。
年4回以上の賞与の支給がある場合の計算方法や注意点を見ていきましょう。
標準賞与額の対象になる賞与とは
賞与に対する健康保険料や厚生年金保険料は、計算する際の基準となる「標準賞与額」をもとに計算します。具体的には、賞与支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」にそれぞれの保険料率を乗じて保険料額を計算し、保険料を会社と従業員で折半して負担します。標準賞与額には、健康保険と厚生年金保険でそれぞれ以下のように上限額が設けられています。
- 健康保険:年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円
- 厚生年金保険:1ヵ月あたり150万円(同月内に2回以上支給されたときは合算金額)
健康保険と厚生年金保険の保険料の対象となる賞与は、「年3回以下支払われる賞与」です。名称を問わず、労働の対償として年3回以下で支給されるものは、標準賞与額に含めなければなりません。一方、年4回以上支給されるものは、毎月支払う給与をもとに決定する標準報酬月額の対象です。標準賞与額の対象になるものには、以下のようなものがあげられます。
【賞与の対象になるもの】
- 賞与、ボーナス、夏季手当、当期手当、年末一時金
- 決算賞与、期末手当、期末一時金
- その他一時的に支給されるもの など
※自社製品など金銭以外で支給されるものも含まれますが、結婚祝金やお見舞金のように労働の対象とならないものは除かれます
年4回以上の賞与の支給がある場合の計算方法や注意点
年4回以上とは、7月1日を基準にして計算します。具体的には、前年7月1日から当年6月30日までの賞与の支給回数が4回以上になった場合に、その合計額を「12か月」で割って1ヵ月分を計算します。算定基礎届や月額変更届を提出する際には、ここで計算した1ヵ月分の金額を各月の報酬に含めて計算して提出しなければならないため注意しましょう。
普段は年3回以下の賞与でも、創立記念や30周年記念などのようにその年に限って臨時に賞与を支給したり、本来1回で支給している賞与を分割して支給したりすることもあるでしょう。このような場合には、結果として賞与の支給回数が4回以上になったとしてもカウントする必要はありません。このようなケースでは、これまで同様に「被保険者賞与支払届」に記載して提出します。
賞与計算規程の無料テンプレート・ひな形
賞与計算規程とは、企業が従業員に支給する賞与の計算方法や基準を定めた規定のことを指します。
賞与計算規程をどのように作成すべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。実際に自社に合わせた賞与計算規程を1から作成するのは大変なことです。
マネーフォワードクラウドでは、実務で使用できる、賞与計算規程のテンプレート(エクセル・ワード)を無料でダウンロードいただけます。
ベースを保ちつつ、自社の様式に応じてカスタマイズすれば使い勝手の良い書類を作成できるでしょう。この機会にぜひご活用ください。
賞与(ボーナス)に関してよくある疑問点
ここからは、賞与(ボーナス)に関して、民間企業と公務員の賞与(ボーナス)の違い、税金(所得税)の計算を行った際の端数はどうなるか?などの疑問について見ていきましょう。
公務員と民間企業の賞与(ボーナス)の違いは?
公務員と民間企業の賞与(ボーナス)の違いについて見ていきましょう。
公務員の賞与が景気の変動にあまり左右されることなく支給されるのに対して、民間企業の賞与は会社ごと、従業員の雇用形態ごとに支給する、支給しないを決めることができるので必ず支給されるわけではありません。
また、賞与の額についても、公務員の賞与が人事院勧告により決まるのに対して、民間企業の賞与は会社毎に算出方法が異なり、景気、業績の影響や従業員の考課により支給額も異なるため、景気や業績によっては賞与が出ないことがある点に違いがあります。
所得税の計算において端数はどう処理する?
賞与の所得税は、賞与額から社会保険料等を差し引いた金額に所得税率を掛け算して求めましたが、算出した所得税に小数点以下の端数が出た場合、1円未満の端数は切り捨てることになっています。
所得税計算で端数が出た場合には注意しましょう。
賞与(ボーナス)における額面と手取りの違いは?
賞与(ボーナス)には、「額面の支給額」と「手取り額」があります。
賞与計算の場合も、給与計算と同様に支給額から社会保険料や所得税が控除され、控除後の金額が手取り額になります。
具体的には次のような式になります。
=賞与(ボーナス)支給額-(厚生年金保険料+健康保険料(+介護保険料)+雇用保険料+所得税)
退職予定者の賞与(ボーナス)にかかる控除どうなる?
退職予定者に支払われる賞与(ボーナス)に関わる社会保険料の控除については、退職する月によって扱いが異なりますので注意が必要です。
具体的な例をあげてみます。
例えば、12月10日に賞与の支給を受け、12月31日付で退職する社員について考えてみましょう。
社会保険の「資格喪失日」は退職日の翌日であるため、退職日が12月31日であれば、資格喪失日は1月1日になります。
上記の場合、ボーナス支給月は12月ですので、当該社員の厚生年金保険等の資格喪失月も12月であれば、賞与支給月が資格を喪失した月とイコールになります。
「資格喪失日」が1月1日ということは、「資格喪失月」は1月です。そのため、賞与は「資格喪失月の前月」までに支払われていますので、社会保険料徴収の対象になります。
よって、12月31日に退職した本ケースでは、12月10日に支給した賞与からは「社会保険料を徴収する」のが正しい事務処理となるわけです。
もう一つ例を見ていきましょう。今度は、12月10日に賞与の支給を受け、12月25日付で退職する社員の場合です。
上記で述べたとおり資格喪失日は退職日の翌日ですので、退職日が12月25日の本ケースでは、資格喪失日は翌日の12月26日となります。
資格喪失日が12月26日ということは、資格喪失月は12月です。そのため、賞与は資格喪失月の前月に支払われていませんので、12月25日に退職した本ケースでは、「社会保険料を徴収しない」という事務処理となります。
以上のように、賞与支給月に退職した場合には、賞与支給月が社会保険の資格喪失月に該当するケースと該当しないケースが存在します。この違いは、退職日が月末であるか、月末以外かに起因して発生します。
賞与支給月の末日で退職した場合には、賞与支給月は資格喪失月の前月になり、社会保険料の徴収が必要となります。
これに対して、月の末日以外の日で退職した場合には、賞与支給月が資格喪失月に該当するため、社会保険料の徴収が不要となるという点を覚えておきましょう。
各種控除に注意して賞与の計算は正確に行おう!
賞与も給与と同様に、支給額があり、その支給額から社会保険料や所得税を控除して手取り額が決まります。
控除額の計算を行う際の社会保険料の中の「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」は、給与のように標準報酬月額を基に各保険料率を乗じて求めました。
しかし、賞与の場合は総支給額を1,000円単位にした「標準賞与額」に各保険料率を乗じて算出するというところに違いがあります。
また、所得税についても課税所得金額に掛け算する所得税率(賞与税率)が、給与計算の時とは異なります。
具体的には、前月の給与と扶養人数を賞与税額表に当てはめて賞与税率を求めます。
これらの控除計算に注意しながら正しく賞与計算するようにしましょう。
よくある質問
賞与の計算方法について教えてください
賞与の額面金額(総支給額)から社会保険料(健康保険料、(40歳以上65歳未満の場合)介護保険料、厚生年金保険料)、雇用保険料、所得税を控除した金額が手取り額になります。 詳しくはこちらをご覧ください。
計算において端数が出た場合の処理方法について教えてください
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、50銭以下の端数は切り捨て、50銭を超える端数は切り上げます。所得税は、1円未満の端数は切り捨てになります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働保険年度更新申告書の書き方
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度という。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業年度ごとに定められた保険料率を乗…
詳しくみる厚生年金と国民年金はいくらもらえる?受給額の計算方法を解説
厚生年金と国民年金がいくらもらえるかは、年金の種類によって異なります。国民年金は納付期間が長ければ長いほど満額の受取額に近づきますが、厚生年金の場合は報酬の額や加入期間に応じて変動します。 ここでは、年金制度の基本や計算方法を解説するととも…
詳しくみる労働保険確定保険料申告書とは?書き方や記入例、事業廃止の場合を解説
労働保険の確定保険料申告書は、労働保険料の計算や納付時には欠かせません。本記事では労働保険の確定保険料申告書について、書き方や記入例、事業廃止の場合の手続きなどをわかりやすく解説し、雇用保険や労災保険との違いもご紹介します。 労働保険確定保…
詳しくみる社会保険の資格取得届とe-Gov電子申請手続きのやり方
社会保険の資格取得届は、社会保険の取得義務が発生した場合に提出する書類です。資格取得届を提出するのは、社会保険の適用事業所が新たに従業員を雇った場合、および勤務形態の変更により社会保険の取得義務が発生した場合があります。 資格取得届が必要な…
詳しくみる労基署の臨検とは?書類の確認ポイント、是正勧告があった場合の対応
「立ち入り検査で何を見られるのか分からない」 「準備が整っていなかったらどうしよう」 労基署の臨検に対して不安を抱く人事労務担当者もいるでしょう。 臨検は企業の問題点を明らかにし、改善するための機会であり、適切な準備と対応を知れば、不安を軽…
詳しくみる厚生年金の試算・計算方法について – 将来もらえる年金額を予測
会社員や公務員は、老齢になると2種類の年金を受け取ることができます。国民年金から受け取る年金が老齢基礎年金、厚生年金から受け取る年金が老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、基本的に加入期間による定額部分だけであるのに対し、老齢厚生年金は加入期間…
詳しくみる