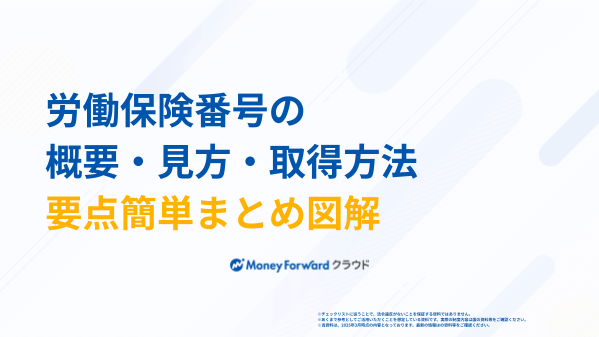- 更新日 : 2025年11月5日
労働保険番号とは?わからないときの調べ方を解説!
労働保険(労災保険、雇用保険)では、適用事業所に労働保険番号が割り振られています。労災事故が発生した場合の保険給付支給請求書に記載が必要になりますが、わからない場合はどうすればよいのでしょうか。また、類似したものに適用事業所番号がありますが、労働保険番号とは何が違うのでしょうか。今回は、労働保険番号の意味、見方、調べ方のほか、取得方法などについて解説していきます。
目次
労働保険番号とは?
労災保険と雇用保険を総称して労働保険と呼んでいます。事業を開始し、労働者を雇用した場合、一定の要件を満たすと労働保険の適用事業所となるため、労働基準監督署に保険関係の成立届の提出が必要となります。
手続きにより、都道府県労働局から整理番号が振り出されますが、これが労働保険番号です。異なる2つの保険関係が関わるため、制度はややわかりにくく、番号の名称も正確に使用されないことも少なくありません。
労災保険番号との違い
労働保険番号ではなく、労災保険番号と称する人もいるようです。しかし、正確には労災保険番号というものはありません。
労働保険では、保険料の徴収等については両保険を労働保険として、原則一体の一元適用として取り扱われています。
しかしながら、例外として建設業については、労災保険用の労働保険番号(元請としての現場労災や事務所の労災など)と雇用保険の労働保険番号を分け、二元適用として取り扱うことになっています。労働保険番号でありながら、労災保険だけの番号となっていることから、労災保険番号と呼ぶ人がいるものと思われます。
適用事業所番号との違い
雇用保険については、適用手続として保険関係成立届とは別の手続きもしなければなりません。公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届の提出も必要になります。
その際、整理番号として事業所番号が振り出されます。雇用保険適用事業所番号と呼ばれており、以後、雇用保険の各種給付の手続きの際に請求書等に記載します。雇用保険適用事業所番号は11桁(4桁-6桁-1桁)の番号で構成され、「1234-567890-1」のような形式で付与されます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
年度更新の手続きガイドブック
年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。
本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
労災対応がよくわかるガイド
前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。
一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。
労働保険番号がわからないときの調べ方
労災事故が発生した場合、労災保険では、治療費に当たる療養補償給付、休業中の休業損害に当たる休業補償給付などが支給されます。その際、各保険給付支給請求書には労働保険番号を記載しなければなりません。
しかし、労災事故は本来、発生させてはならないものであり、事業を開始して長年、事故が発生したことがないというケースもあるでしょう。労働保険番号がわからない、ということも考えられます。
こうした場合、どうすればよいのでしょうか。残念ながら、労働局のホームページなどで労働保険番号を検索することはできません。
電話で労働局や労働基準監督署で確認することになるのでしょうか。おそらく、電話で問い合わせても、次のように回答されると思います。
「毎年の労働保険料の年度更新の際の申告書の控を確認してください」
労災保険と雇用保険の保険料である労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に前年度に概算で納付したものを清算し、併せて次年度の保険料を概算で納付する方法で納付します。
毎年、更新するため、労働保険の年度更新と呼ばれています。年度更新申告書は、所轄の労働局から納付時期の前に送付されます。前年度に概算納付した保険料額と労働保険番号や事業所名などが印字されています。申告納付した場合、控えが返されますので、そちらを確認すれば、印字された労働保険番号がわかるわけです。
なお、事業所によっては、厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合の会員として、事業主を含めて労災保険に特別加入しているケースもあるでしょう。
原則として、労災保険は労働者だけしか加入できない制度です。しかし、働き方が一般の労働者に近い中小企業の経営者、一人親方などについては、例外的に労災保険に加入できる仕組みが特別加入制度です。
その場合、労働保険番号は会員となって事務を委託している労働保険事務組合に振り出されます。会員事業所には枝番号が付与され、労働保険事務組合で管理しています。
したがって、会員となっている労働保険事務組合に問い合わせればよいでしょう。
労働保険番号の見方
労働保険番号は、府県番号、所掌、管轄、基幹番号、枝番号の14桁で構成されています。それぞれについてみていきましょう。
労働保険番号の11桁と14桁の違い
前述のように、事業主も含めて特別加入している場合は、枝番号も振り出されて14桁になります。
しかし、個別の事業所で労災加入している場合の労働保険番号は、基幹番号までの11桁です。ちなみに年度更新の際の労働保険料申告書の労働保険番号記載欄は下記のようになっています。

① 府県の番号
最初の2桁の数字が都道府県を表記しています。北海道の「01」から沖縄県の「47」まで47の数字があります。東京都は「13」、大阪府は「27」となっています。
➁ 所掌(しょしょう)の番号
所掌は、府県番号に続く1桁の数字です。取り扱う行政機関が労働基準監督署なのか、公共職業安定所なのかを表記するものです。
「1」は労働基準監督署、「3」は公共職業安定所になります。
③ 管轄の番号
管轄は、所掌に続く2桁の番号です。都道府県管内に複数ある労働基準監督署または公共職業安定所のどこが管轄するかを表記しています。
例えば、神奈川県の労働基準監督署は12カ所ありますが、横浜南労働基準監督署は「01」、横浜西労働基準監督署は「12」となっています。
④ 基幹番号
基幹番号は、管轄に続く6桁の番号であり、事業所、労働保険事務組合ごとに付与されています。末尾番号に意味があり、「0」は一元適用の一般の事業所、「2」は二元適用事業所の雇用保険、「4」は二元適用事業所のうち林業等の労災保険、「5」は二元適用事業所のうち建設業等の労災保険、「6」は二元適用事業所の事務部門の労災保険、「8」は建設業の一人親方を意味します。
なお、基幹番号の冒頭番号が「9」の場合は、労働保険事務組合に振り出されたものです。
⑤ 枝番号
基幹番号に続く3桁の番号は枝番号と呼ばれています。労働保険事務組合の場合、複数の「9」で始まる基幹番号を有することが少なくありませんが、同じ基幹番号で複数の委託事業所を有するのが一般的です。その場合、基幹番号に枝番号を付けることになります。
労働保険番号の取得方法と変わるとき
労働保険番号はどのように取得するのでしょうか。また、一度、取得した労働保険番号が変わることはあるのでしょうか。
労働保険番号の取得方法
労働保険番号を取得するには、まず労働保険の適用事業所として保険関係成立届を労働基準監督署または公共職業安定所に提出することになります。
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う一元適用事業であれば、労働者を雇用し、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。
建設業などの二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険の保険関係は、別個のものとして成立させる必要があります。したがって、労災保険に係る保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。
これとは別に、雇用保険に係る保険関係成立届を上記の期限内に所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
労働保険番号は、以上の手続きによって取得できますが、一元適用事業の場合も二元適用事業の場合も、併せて概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)、雇用保険適用事業所設置届(設置の日の翌日から起算して10日以内)、雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)の手続きを行います。
労働保険番号の変更
なお、労働保険番号が変更されることもあります。事業所の移転によって所管の出先機関である労働基準監督署または公共職業安定所が変わる場合です。
例えば、同一都道府県内での移転によって出先機関の所管が変わるときには、次のような手続きになります。
一元適用事業では、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ労働保険名称・所在地等変更届を提出後、移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ、その控を添付して雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。
二元適用事業の場合は、移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ労働保険名称・所在地等変更届、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。
以上の手続きによって新しい労働保険番号が付与されます。
労働保険番号の意味と調べ方を知っておこう!
労働保険番号の意味、調べ方、取得方法などについて解説してきました。
労働保険制度が複雑であることや、類似した紛らわしい番号もあるため、労働保険番号の詳細な意味を理解しているのは、行政の担当者くらいではないでしょうか。
とは言え、労災事故が発生した場合は、給付請求書に記載が必要であり、調べ方については、知っておくことが大切です。
よくある質問
労働保険番号とは何ですか?
適用事業所の労働保険関係が成立したときに振り出される整理番号です。詳しくはこちらをご覧ください。
労働保険番号の確認方法について教えてください。
申告済みの労働保険の年度更新申告書の控えで確認できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
労災保険の関連記事
新着記事
役員社宅を賢く経費にする方法は?節税メリットから賃料計算まで徹底解説
Point役員社宅の経費化とは? 役員社宅は、賃料相当額を正しく計算・徴収すれば合法的に経費化でき、大きな節税効果があります。 会社負担の家賃は損金算入可能 賃料相当額の計算が必須…
詳しくみる組織開発とは?人材開発との違いや代表的な手法、成功に導くプロセスを徹底解説
Point組織開発とは、組織全体の関係性と機能を高める取り組み。 組織開発は、人と人の相互作用を改善し、変化に強い組織をつくるプロセスです。 関係性と対話に焦点 個人でなく組織全体…
詳しくみるキャリアパス面談で何を話すべきか?理想の将来を描き自己成長につなげるための完全ガイド
Pointキャリアパス面談とは、将来像を言語化し成長戦略を描く対話です。 キャリアパス面談は、理想の将来と市場価値向上を実現するための戦略設計の場です。 将来像と現状の差を明確化 …
詳しくみるストレスチェック結果の提供同意書とは?取得のタイミングや注意点を徹底解説
Pointストレスチェック結果の提供同意書とは、結果を事業者へ共有するための法定手続きです。 ストレスチェック結果は、本人の明示的同意がなければ会社は取得できません。 事前同意は無…
詳しくみるストレスチェックの方法とは?実施手順から事後措置までの実務を徹底解説
Pointストレスチェック方法とは、労働者の心理的負担を測定し、職場改善につなげる制度。 ストレスチェックは、正しい手順と事後措置まで実施して初めて有効です。 年1回以上の実施が原…
詳しくみるストレスチェック報告書の提出期限や書き方は?労働基準監督署への報告義務と作成手順を解説
Pointストレスチェック報告書とは、実施結果を労働基準監督署へ報告する法定書類です。 ストレスチェック報告書は、常時50名以上の事業場が年1回実施後、遅滞なく提出します。 対象は…
詳しくみる