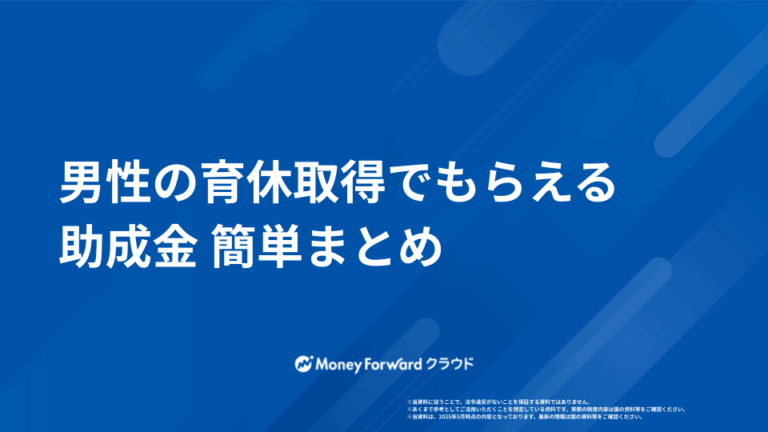- 更新日 : 2025年6月23日
従業員・男性の育休で会社がもらえる助成金・補助金とは?種類や金額を解説
従業員・男性の育休で会社がもらえる助成金・補助金は、「両立支援等助成金」です。
これは、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を支援するための助成金で、育休に関するものだけでも複数のコースが存在します。
本記事では、上記の各コースの支給要件や金額、申請方法などを詳しく解説します。
企業と従業員が共に成長できる環境を作りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
従業員の育休で会社がもらえる助成金・補助金とは?
従業員の育休で会社がもらえる助成金・補助金のひとつに「両立支援等助成金」があります。
働き方改革や少子化対策が必要とされているなかで、従業員が仕事と育児を両立しやすい環境を整えることが求められています。
両立支援等助成金は、企業の負担を軽減し、従業員が安心して育休を取得できる環境を整えるのが目的の1つです。
次項で、代表的な助成金である「両立支援等助成金」について解説します。
両立支援等助成金
両立支援等助成金は下記のように、仕事と育児や介護の両立を支援する企業に対して支給される助成金です。
- 従業員が育児休業を取得しやすい環境整備
- 育児休業からスムーズな職場復帰を支援する取り組み
- 育休中の代替要員の確保
両立支援等助成金には、いくつかのコースがあり、企業の取り組み内容に応じて支給される助成金が異なります。
たとえば、下記のようなコースがあります。
- 男性の育児休業取得を促進する「出生時両立支援コース」
- 育休からの復帰を支援する「育児休業等支援コース」
- 育休中の業務を代替する人材を確保する「育休中等業務代替支援コース」
- 育休明けの柔軟な働き方を支援する「柔軟な働き方選択制度等支援コース」
それぞれのコースの詳細については、後の見出しで詳しく解説します。
なお、今回紹介する助成金は、全て中小企業のみが対象です。
男性の育休取得で企業がもらえる助成金
男性の育休取得で企業がもらえる助成金として「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」があります。
助成金の概要や支給要件、金額などについて詳しく解説します。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい環境作りを行い、子の出生後8週間以内に男性従業員が育休を利用した場合に、企業に対して助成するものです。
男性の育児休業取得を促進し、男女ともに仕事と育児を両立できる社会を作る目的があります。
なお、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、下記の2つの段階に分けて支給されます。
- 第1種:男性の育児休業取得者が出た場合に支給
- 第2種:男性の育児休業取得率が上昇した場合に、追加で支給
具体的な条件や金額、手続きなどについては、後の見出しで詳しく解説します。
男性の育児休業の取得
企業が両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の第1種の支給を受けるためには、男性従業員が下記の要件を満たす育児休業を取得している必要があります。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※育児休業の期間は、1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上であること - 雇用環境整備措置を複数実施
※1人目は2つ以上、2人目は3つ以上、3人目は4つ以上(産後パパ育休の申出期限設定状況で1つ追加の場合あり)
上記の要件を満たせば、企業は第1種の助成金を受け取れます。
雇用環境整備措置の具体例としては、研修の実施や、制度周知のためのパンフレット作成などです。
受け取れる金額については、下記の通りです。
- 1人目:20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合は30万円)
- 2人目・3人目:10万円
詳細な要件については、厚生労働省の資料で確認するようにしましょう。
男性育休取得率の上昇
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)では、第1種の支給に加えて、男性の育休取得率が上昇した場合に第2種の助成金が支給されます。
これは、企業が継続的に男性の育児参加を推進する取り組みを評価するものです。
取得率上昇の要件は、下記の通りです。
- 第1種の助成金を受給済
- 雇用環境整備の措置を複数実施
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、 業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
- 第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率の数値が30ポイント以上上昇
※第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上でも良い - 第1種(1人目)の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が2人以上
上記の要件を満たせば、企業は第2種の助成金を受け取れます。
受け取れる金額については、下記の通りです。
- 1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
- 2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
- 3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
※プラチナくるみん認定事業主の場合は、上記の金額に15万円加算
具体的なポイントの計算方法については、厚生労働省の資料で確認するようにしましょう。
手続き・申請方法
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請手続きは、下記の流れで行います。
- 自社が支給要件を満たしているかを確認
- 必要な書類を揃えて支給申請書を作成
- 事業所の所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)に申請
なお、申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
- 支給申請書
- 育児休業取得者の労働時間管理に係る資料
- 雇用環境整備措置の実施状況がわかる書類
申請時期は、第1種が支給対象となる育児休業の終了日の翌日から起算して2ヶ月以内、第2種が申請に係る事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6ヶ月以内です。
従業員の育休・復帰支援で企業がもらえる助成金
従業員の育休取得と復帰支援に特化した助成金は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。
次項で、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について詳しく解説します。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、従業員が育児休業を取得し、スムーズに職場復帰するための取り組みを行った企業に対して支給される助成金です。
従業員の育休取得時と職場復帰時のそれぞれで助成が受けられる点が特徴です。
具体的な条件や金額、手続きなどについては、後の見出しで詳しく解説します。
育休を取得したとき
育休取得時に企業が助成を受けるために必要なおもな要件は以下の通りです。
- 育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰意を支援する方針の周知
- 育児休業取得者に対し、育休復帰支援プランを策定し、当該プランに基づき面談等を実施
- 育児休業開始前までに、業務の引継ぎを実施
- 3ヶ月以上の育児休業(育児休業と連続する産後休業期間を含む)を取得
上記の要件を満たせば、育休取得者1人につき30万円の助成金が支給されます。
職場に復帰したとき
育休取得者が職場復帰した際に企業が助成を受けるために必要な、主な要件は以下の通りです。
- 育児休業中の従業員に対して、職場に関する情報、資料の提供を実施
- 職場復帰前後に育児休業取得者と面談を実施
- 原職または原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用
上記の要件を満たせば、育休取得者1人につき30万円の助成金が支給されます。
手続き・申請方法
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の申請手続きは、支給対象となる取り組みの実施後に行います。
手続きの流れは、下記の通りです。
- 自社が支給要件を満たしているかを確認
- 育休取得前から復帰後を見据えたプランを策定し、実行
- 必要な書類(支給申請書、育休復帰支援プラン、面談記録など)を揃えて支給申請書を作成
- 事業所の所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)に申請
申請時期は、産後休業から連続して育児休業を取得した場合は産後休業開始日、それ以外は育児休業開始日から起算して3ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。
育休中の業務体制の整備(新規雇用・従業員への手当支給)をした企業への助成金
従業員が育休を取得している間の業務体制の整備をした企業に支給されるのは「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」です。
次項で、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について詳しく解説します。
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)は、従業員の育児休業等に伴い、代替要員の確保や業務分担を行った場合に、企業に対して助成金が支給される制度です。
これにより、企業は育休取得者の業務をスムーズに引き継ぎ、事業運営に支障が出ないように体制を整えられます。
具体的な条件や金額、手続きなどについては、後の見出しで詳しく解説します。
育児休業中の手当支給
育児休業取得者の業務を他の従業員に分担する場合、その従業員に対して手当を支給すると、企業は助成金を受け取れます。
助成金を受け取るための主な要件は、下記の通りです。
- 育児休業等を取得した労働者の業務を代替する労働者に対して、所定労働時間外労働を行わせた場合、または代替する労働者に対して手当等を支給した場合
- 代替する労働者に対して、通常の賃金に加えて手当等を支給した場合
上記の要件を満たせば、下記の助成金が支給されます。
- 業務体制整備経費として5万円(育休1ヶ月未満は2万円)
- 手当支給総額の¾(上限10万円/月、12か月まで)
上記2つを合わせて、最大で125万円の助成を受けられます。
なお、プラチナくるみん認定事業主の場合は、割増・加算があります。
短時間勤務中の手当支給
短時間勤務制度を利用する従業員の業務を他の従業員に分担する場合も、企業は助成金を受け取れます。
助成金を受け取るための要件は、下記の通りです。
- 短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する労働者に対して、所定労働時間外労働を行わせた場合、または代替する労働者に対して手当等を支給した場合
- 代替する労働者に対して、通常の賃金に加えて手当等を支給した場合
上記の要件を満たせば、下記の助成金が支給されます。
- 業務体制整備経費として2万円
- 手当支給総額の¾(上限3万円/月、子が3歳になるまで)
上記2つを合わせて、最大で110万円の助成を受けられます。
育児休業中の新規雇用
育児休業取得者の代替要員として新たに労働者を雇用した場合も、企業は助成金を受け取れます。
助成金を受け取るための要件は、下記の通りです。
- 育児休業等を取得した労働者の代替要員として、新たに労働者を雇用した場合
- 新たに雇用した労働者を一定期間以上雇用
上記の要件を満たせば、代替期間に応じて下記の助成金が支給されます。
- >7日以上14日未満 :9万円
- 14日以上1ヶ月未満 :13.5万円
- 1ヶ月以上3ヶ月未満:27万円
- 3ヶ月以上6ヶ月未満:45万円
- 6ヶ月以上:67.5万円
なお、プラチナくるみん認定事業主の場合は、加算があります。
手続き・申請方法
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の申請手続きは、支給対象となる取り組みの実施後に行います。
手続きの流れは、下記の通りです。
- 自社が支給要件を満たしているかを確認
- 必要な書類を揃えて支給申請書を作成
- 事業所の所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)に申請
申請期限については、下記の通りです。
| 申請する手当 | 申請期限 |
|---|---|
| 育児休業中の手当支給 |
|
| 短時間勤務中の手当支給 ※1年ごとに申請が必要 |
|
| 育児休業中の新規雇用の手当支給 |
|
引用:厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(令和6年度版)
助成金を確実に受け取るために、必要書類や申請期限について事前に確認しておきましょう。
育休明けの柔軟な働き方を支援する企業への助成金
育休明けの柔軟な働き方を支援する企業への助成金は「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」です。
次項で、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)について詳しく解説します。
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、育児中の従業員が柔軟な働き方を選択できる制度を複数導入し、実際に従業員が利用した場合に、企業に対して助成金が支給される制度です。
これにより、企業は育児と仕事の両立を支援する環境整備を促進できます。
具体的な条件や金額、手続きなどについては、後の見出しで詳しく解説します。
支給要件と支給金額
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)を受けるためには、育児中の柔軟な働き方に関する制度を複数導入し、実際に従業員がその制度を利用することが要件です。
上記の要件を満たせば、下記の助成金が支給されます。
- 制度を2つ導入し、対象者が制度利用した場合:20万円
- 制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用した場合:25万円
なお、導入すべき制度の例として、具体的には下記のようなものが挙げられます。
| 制度名称 | 詳細 |
|---|---|
| 短時間勤務制度 | 所定労働時間を短縮して勤務できる制度 |
| フレックスタイム制度 | 始業時刻と終業時刻を従業員が自由に選択できる制度 |
| テレワーク制度 | パソコンなどを活用して、場所にとらわれずに勤務できる制度 |
| 時間単位の年次有給休暇制度 | 年次有給休暇を時間単位で取得できる制度 |
| 子の看護休暇制度 | 子の病気やけがの看護のために休暇を取得できる制度 |
| 保育サービス費用補助制度 | 企業が従業員の保育サービス利用料の一部を補助する制度 |
上記で挙げたような制度を2つ以上導入し、実際に従業員が利用すれば助成対象となります。
手続き・申請方法
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の申請手続きは、支給対象となる取り組みの実施後に行います。
- 自社が支給要件を満たしているか、特に導入する制度が助成対象となる制度かどうか、従業員の利用状況などを確認
- 必要な書類(支給申請書、導入した制度の内容がわかる資料、従業員の利用状況がわかる資料など)を揃えて支給申請書を作成
- 事業所の所在地を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)に申請
申請時期は、6ヶ月間の制度利用期間の翌日から2ヶ月以内です。
法改正【2025年4月~】育休手当の給付額が実質10割に
2025年4月から、育児・介護休業法が改正され、育休手当(育児休業給付金)の給付額が実質10割になる制度が導入されます。
この制度は、出産後間もない時期の親の経済的な負担を軽減し、より安心して育児に専念できる環境を整備するのが目的です。
また、男性の育児参加を促進する効果も期待されています。
次項で、法改正に伴って新たに新設される「出生後休業支援給付」について詳しく解説します。
出生後休業支援給付
2025年4月から新設される「出生後休業支援給付」は、育児休業給付金に上乗せして給付される制度です。
現行の育児休業給付金は、育休開始から6か月までは賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
これは額面であり、社会保険料や所得税が控除されるため、手取り額は約8割程度です。
育児休業給付金に出生後休業支援給付(休業開始時賃金の13%相当額)が加わることで、給付率が上乗せされるため、手取りで約10割相当の給付を受けられます。
出生後休業支援給付を受けるための要件は、下記の通りです。
- 夫婦が共に育児休業を取得している
- 父親が子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を含む育児休業を取得し、母親も産後休業後8週間以内に育児休業を取得している
- 夫婦それぞれが14日以上(父親の場合は産後パパ育休を含む)の育児休業を取得している
なお、支給される期間は最大28日間です。
この制度は、父親の育児参加を促進することを目的の1つとしているため、男性も対象です。
申請手続きは、通常の育児休業給付金と同様に、事業主を通じてハローワークで行います。
育休によって受け取れる補助金を活用し、企業と従業員が共に成長できる環境を作ろう!
育休は、従業員が子育てに専念できる貴重な機会であり、企業にとっても人材育成や組織運営を見直すチャンスです。
国はさまざまな助成金制度を通じて、企業の育休支援を後押ししており、これらを活用すれば、経済的負担を軽減しつつ、従業員が安心して育休を取得できる環境を作れます。
本記事を参考に、企業の持続的な成長と、従業員の豊かな生活の両立を目指しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
外国人雇用に人数制限はある?特定技能の受け入れ上限や雇用時の注意点を解説
外国人労働者の雇用を考えている企業は、受け入れ人数に制限はあるのか気になる方も多いでしょう。 原則として外国人労働者の雇用に人数制限はありません。しかし、特定技能や技能実習制度においては受け入れ可能な人数が定められているケースがあります。 …
詳しくみる労働条件とは?明示義務や必須項目・変更の手続きについて解説
労働条件とは労働者が使用者の下で働く際に、どのような条件で働くかを取り決めたものです。使用者は、雇い入れの際の労働者への明示が義務付けられています。また労働者にとって不利益な内容に変更する場合、合理的な理由と労働者への周知が必要です。本記事…
詳しくみる法律上の退職ルールとは?退職は何日前に伝えるべき?手続き方法も紹介
正社員のような無期雇用の従業員の場合、法的にはいつでも退職の申し出が可能です。会社の合意がなくても、申し出から2週間後に契約終了となります。 ただ「実際は何日前に退職を伝えるべきなのか知りたい」という方もいるでしょう。そこで本記事では、退職…
詳しくみるタレントマネジメントとは?導入のメリットや方法、システム利用について解説!
タレントマネジメントとは、社員が持つ個々の経歴やスキル、経験などを一元管理し、人材戦略に活用する手法をいいます。 個々の社員の情報をシステムなどを用いて可視化することができれば、採用、人材育成計画の作成、配属などに役立てることが可能です。こ…
詳しくみるES(従業員満足度)とは?調査方法・ひな形、向上への取り組みを解説
ES(従業員満足度)とは、職務内容や待遇などの労働条件、労働環境や福利厚生、人間関係など、仕事や職場に対する従業員の満足度を表す指標のことをいいます。 近年、ES向上に取り組む会社が増えています。この記事では、ESの意味や構成要素、ESを高…
詳しくみる日本の離職率はどれくらい?高い会社や労働環境の特徴
離職率とは、一定期間に何人社員が離職したかを表す割合です。特に新卒社員の離職率は問題になることが多く、1年・3年・5年以内の離職率が一つの目安となっています。何パーセントから高いとは一概にはいえませんが、離職率が平均して20パーセントを超え…
詳しくみる