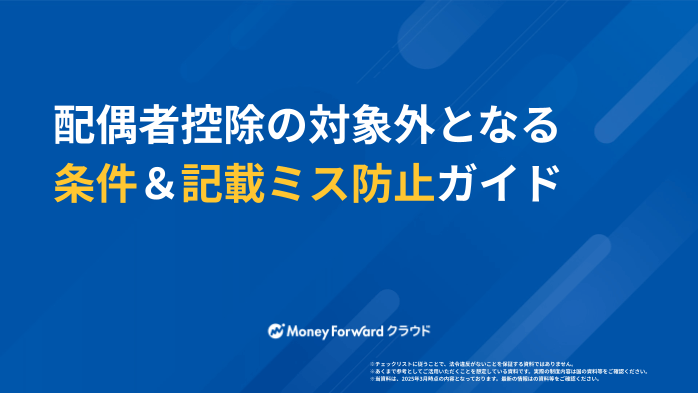- 更新日 : 2025年11月5日
年末調整で「配偶者控除」を受けられないケースとは?具体的な年収をもとに解説
年末調整のシーズンがやってきました。毎年11月頃になると勤務先から書類の提出を求められますが、後回しにしてまだ手続きをしていない方もいることでしょう。
2017年度の税制改正の影響を受け、「配偶者控除」の仕組みが変わりました。主な変更点を確認しましょう。
夫の年収1,220万円で「配偶者控除」なし
2017年度の税制改正で「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しがあり、配偶者控除の額が改正されています。
これまで最大控除額の38万円が適用される対象は、配偶者の年収(※ここでは給与のみを前提にする)が103万円以下の場合のみでした。しかし、改正後は配偶者の年収が150万円の場合まで基準額が引き上げられています。

引用:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて|国税庁
ただ、これは年末調整を行う“給与所得者本人”の年収が1,120万円以下のケースの話。
2017年までは給与所得者本人の年収による制限はありませんでしたが、2018年からは本人の年収が1,120万円以下の場合、1,120万超~1,170万円以下の場合、1,170万超~1,220万円以下の場合ごとに控除額が分かれ、1,220万円を超えると配偶者(特別)控除の適用を受けられなくなりました。
例えば、これまではパートの妻の収入が103万円を超えないよう気を付け、夫が年末調整を行い、38万円の配偶者控除を受けていたとしても、そもそも夫が年収1,220万円を超えていたら控除対象外になってしまいます。
配偶者控除の恩恵を受けていた家庭も、2018年以降は税負担が増える場合があるので要注意です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い
年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。
年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。
扶養控除等申告書 取り扱いガイド
扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。
扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。
年末調整業務を効率化するための5つのポイント
「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。
スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。
年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット
年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。
この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。
配偶者の年収201万円以下まで控除対象
とはいえ、最大額の38万円とまでは言わなくても、配偶者控除は受けたいものです。
2017年までは、配偶者特別控除の対象となるには、配偶者の年収が141万円未満でなければなりませんでしたが、2018年以降は年収201万円まで対象となります。
次の図の「【参考】配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額」の欄では、配偶者の「年収ベース」で控除額を確認できます。(※「配偶者の合計所得金額」とは、細かい計算方法はありますが、平たく言うと<収入>から<経費>を差し引いた金額です。収入金額とは異なるので注意しましょう)

出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて|国税庁
「源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)」を加工して作成
控除を受けられる配偶者の年収額は引き上げられましたが、収入が増えるといわゆる「130万円の壁」と言われる社会保険の話が出てきます。
配偶者が、社会保険への加入が必要なケースがありますので、ここにも注意しながら、いくらまで稼ぐかを家庭で検討する必要があります。ただし、従業員数が101人以上の企業で一定の要件を満たしていれば、130万円未満であっても、社会保険に加入する場合もあるため注意が必要です。
新たな書類! 「配偶者控除等申告書」が増えた
またガラッと変更があったのは、新たな書類として「配偶者控除等申告書」が増えたことです。
2017年までは、配偶者控除の申告は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という保険料控除の申告も兼ねた1枚の書類で手続きしていました。
しかし、配偶者控除の改正があり記入項目が増えたことで、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」が別々の2枚の書類に分かれています。
2018年以降の年末調整では、配偶者控除を受けるには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があるので注意しましょう。
【参考】
■配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
■平成 30 年分の年末調整における留意事項等(国税庁)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/04-07.pdf
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末調整を自動化するには?国税庁の無料ソフトやアプリでのやり方を解説
毎年、多くの担当者を悩ませる年末調整。膨大な書類の配布や回収、複雑な控除額の計算、度重なる修正依頼など、その業務は多岐にわたり、大きな負担となりがちです。 この記事では、年末調整を…
詳しくみる過不足税額とは?確認手段と計算方法について解説
年末が近づいてくると、会社員・公務員の方はその年の給与所得に対して年末調整を行って1年間の税額の精算をしなければなりません。 今回は、年末調整において生じる「過不足税額」(還付額や…
詳しくみる遺族年金に年末調整は必要?
受け取った遺族年金による年金収入は非課税であるため、年末調整は原則不要です。また、扶養に入るためには年間所得が一定額以下である必要がありますが、税法上、遺族年金はこの所得に含まれま…
詳しくみる年末調整に必要な申告書の書き方
会社が年末調整を行ってくれる人の場合、年末調整までに申告書と添付書類をそろえれば、自分で申請書類などの書き方を知らなくても各種の控除を受けることができます。所得税の計算を会社が行っ…
詳しくみる定額減税はふるさと納税に影響する?関連制度からわかりやすく解説
定額減税とは、2024年6月より行われる減税のことです。1人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が税金から控除されます。一方、ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附をする…
詳しくみる【チェック付】住宅ローン控除の年末調整・確定申告の書き方は?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は確定申告をする必要がありますが、2年目以降であれば年末調整だけで手続きが完了します。そのため、給与担当者は従業員から提出される申告…
詳しくみる