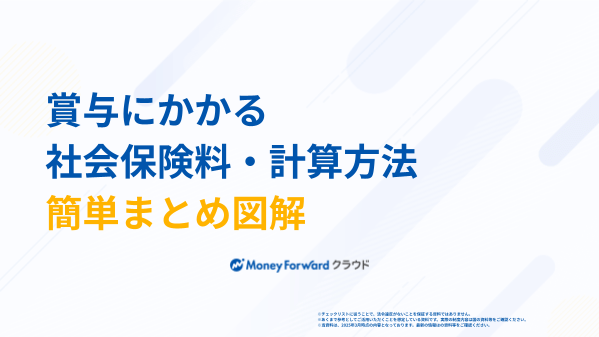- 更新日 : 2025年3月28日
賞与・ボーナスにも社会保険料がかかる?計算方法も分かりやすく解説!
社会保険料は、給料と同じように、賞与・ボーナスにもかかります。標準報酬月額の代わりに賞与・ボーナスの社会保険料の計算には、標準賞与額が用いられます。
率は給料と同じ値です。賞与・ボーナスからは、社会保険料の他に所得税や雇用保険料も控除されます。賞与明細には、これらの控除を記載しなければなりません。
目次
賞与・ボーナスにも社会保険料がかかる?
毎月の給料と同じように、賞与からも社会保険料と税金が控除されます。賞与から控除される社会保険料は健康保険料や介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料、雇用保険料です。税金は所得税のみで、住民税は賞与から控除されません。
ただし、社会保険料・税金ともに、金額の計算方法は次のように異なっています。
社会保険料
- 給料:標準報酬月額を用いて計算する
- 賞与:標準賞与額を用いて計算する
税金
賞与に社会保険料がかからない場合もある?
賞与には、所得税と社会保険料がかかります。従業員に賞与を支給する際はそれぞれの金額を計算して、控除しなければなりません。
しかし、退職する従業員に賞与を支給する場合と、産前産後や育児休業中の従業員に賞与を支給する場合の賞与には、社会保険料はかからないケースがあります。
かかるのは雇用保険料と所得税のみとなるので、気をつける必要があります。
退職する従業員に賞与を支給する場合
従業員が賞与を受け取った月に退職するケースには、次の2パターンが考えられます。
- 退職日が15日や20日のような月の半ばである場合
- 退職日が月末の場合
このうち賞与に社会保険料がかからないのは、1.の場合です。月の半ばに退職する場合は月末には会社に在籍していないため、その月の社会保険料はかかりません。したがって同じ月に支払う賞与にも社会保険料はかからず、徴収のための計算や控除も不要です。
2.の場合は、翌月1日が資格喪失日になり、月末時点では会社に在籍しています。その月は、社会保険料がかかるため、同じ月に支払われる賞与からも社会保険料が徴収されます。
産前産後や育児休業中の従業員に賞与を支給する場合
社会保険には、産前産後休業保険料免除・育児休業保険料免除制度があり、産前産後の休業中や育児休業中は、社会保険料の支払いが免除されます。このため産前産後の休業、および育児休業中に支給される賞与にも、社会保険料はかかりません。
ただし2022年(令和4年)10月からは、賞与支給の月の末日を含んだ、連続した1ヶ月を超える育児休業でなければ、社会保険料の支払いは免除されません。
社会保険上の賞与とは?
一般的に賞与やボーナスといわれる賃金でも、社会保険上は給与として取り扱われることがあります。社会保険料の計算方法を解説する前に、賞与についての基本を確認しておきましょう。
賞与の種類と支給要件
賞与とは毎月の給与と別に臨時的に支払われる賃金のことで、支給の有無や金額などは原則企業が任意で決めます。ただし賞与を支給する場合、その内容を就業規則や従業員との労働契約に記載しなければなりません。
賞与の支給要件やその意味合い(種類)も企業によって異なりますが、一般的には次の通りです。
(賞与の支給要件)
- 勤続期間:6ヶ月以上勤続
- 出勤率:出勤率〇〇%以上
- 在籍:賞与支給時に在籍している
など
(賞与の種類)
- 基本給連動型:基本給の〇ヶ月など業績に関係なく賞与を支給
- 業績連動型:企業業績や従業員の業績に応じて給与を支給
- 決算賞与:決算終了後に業績に応じて賞与を支給
社会保険上は年3回以内の賞与
社会保険料の対象となる賞与は、年3回以内に支給される賃金です。年4回以上に分けて支給される場合、社内では賞与と呼ばれていても、社会保険上は毎月の標準報酬とみなされます。ただし、所得税については「年3回」という定めはなく、賞与として課税される点に注意が必要です。
また、雇用保険料は実際に支給された賃金に対して雇用保険料率(被保険者負担分)を掛けて計算するため、賞与の支給回数を気にする必要はありません。
業績連動型を導入している企業は55.2%
経団連の「2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」によると、企業や従業員の業績に連動する業績連動型賞与を導入している企業の割合は55.2%と、2016年から6年連続で5割を超えています。
理由の1つは、支給する賞与の総額が企業の業績に連動するため、業績が良いときは増えた収益を従業員に還元でき、業績が悪いときは賞与による支出を抑えられることです。
また、従業員が努力した結果が賞与に反映するため、従業員のモチベーションアップも期待できます。従業員に評価基準を明示して、評価結果をフィードバックすることで、賞与に対する信頼性や公平感を高めることもできるでしょう。
企業を取り巻く環境変化は急速になり、終身雇用制が崩れて会社への帰属意識が希薄化していると言われます。対応策の1つとして、企業が環境変化に素早く対応し従業員の意欲向上に役立つ賞与の仕組みを検討してみましょう。
参考:2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果|日本経済団体連合会
賞与から控除される社会保険料の計算方法は?
賞与から控除される健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の金額は、給料と異なる計算方法で行われます。
健康保険料の計算方法
賞与から控除される健康保険料は、標準賞与額と健康保険料率を用いて計算します。標準賞与額は、賞与支給額を1,000円単位にした金額です。所得税を控除する前の賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた金額が標準賞与額になります。ただし、健康保険料は会社と従業員が折半して負担します。
健康保険料率は、賞与も給料と同じ料率で、全国健康保険協会の場合は都道府県別に定められている率が用いられます。健康保険料を計算する際に使用する標準賞与額には上限金額が定められていて、4月1日から3月31日までの年間累計額573万円が上限とされます。
介護保険料の計算方法
40~64歳までの従業員には、介護保険料の負担義務があります。賞与にも給料と同じように介護保険料がかかります。介護保険料率は健康保険組合によって異なりますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)は全国一律です。全国健康保険協会の料率は、2024年(令和6年)3月分(4月30日納付期限分)から1.60%(従業員負担分は0.80%)で、計算式で表すと以下の通りです。
介護保険料は健康保険料と一緒に計算するため、標準所与額の上限についても同じ取扱いになります。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料率は18.3%(従業員負担分は9.15%)で、賞与から控除される厚生年金保険料は、標準賞与額に厚生年金保険料率をかけて求めます。
厚生年金保険料を計算する際に使用する賞与額の上限金額は、1カ月あたり150万円です。
雇用保険料の計算方法
賞与から控除される雇用保険料は、賞与総支給額に雇用保険料率(従業員負担分)をかけた金額です。
2024年(令和6年)4月1日からの雇用保険料率は、以下の表の通りです。
| 従業員負担分 | 会社負担分 | 雇用保険料率 | |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
| 建設の事業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
1円未満の端数については以下のように処理します。
- 50銭以下:切り捨て
- 50銭1厘以上:切り上げ
控除される社会保険料の計算シミュレーション
社会保険料の計算方法について解説しましたが、モデルケースを使って控除される社会保険料の内訳と総額をシミュレーションしてみましょう。
(モデルケース)
- 賞与金額(標準賞与額)50万円、80万円、100万円の3パターン
- 健康保険料率は10%(従業員負担は5%)、介護保険料率は1.6%(従業員負担は0.8%)とする
- 雇用保険の「一般の事業」に勤務
賞与金額(標準賞与額)に各保険料率をかけると、社会保険料は次の通りです。
| 健康保険料 (5%) | 介護保険料 (0.8%) | 厚生年金保険料 (9.15%) | 雇用保険料 (0.6%) | 社会保険料合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 2万5,000円 | 4,000円 | 4万5,750円 | 3,000円 | 7万7,750円 |
| 80万円 | 4万円 | 6,400円 | 7万3,200円 | 4,800円 | 12万4,400円 |
| 100万円 | 5万円 | 8,000円 | 9万1,500円 | 6,000円 | 15万5,500円 |
賞与の約15%が社会保険料として控除されます。
賞与から控除される税金の計算方法は?
賞与からは、所得税の控除も行われます。ただし計算方法には、社会保険料とは大きく異なる点もあるので、間違えないように注意する必要があります。
賞与に対する所得税額の計算方法は?
賞与から控除される所得税は、賞与から社会保険料を差し引いた金額に所定の税額を掛けて計算します。
税率は国税庁ホームページに掲載されている「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で確認しましょう。社会保険料控除後の賞与の金額と扶養親族等の数によって税率が決まります。
ただし、前月給料の金額の10倍を超える賞与を支払う場合、前月に給与を支払っていない場合には、他の方法で賞与から控除される所得税を計算します。
参考:No.2523 賞与に対する源泉徴収|国税庁
参考:令和5年分 源泉徴収税額表|国税庁
社会保険料のシミュレーションで使用したモデルケースで、所得税額を計算してみましょう。扶養親族は2名として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」より税率を調べます。
| 社会保険料 | 賞与-社会保険料 | 税率 | 所得税額 | |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 7万7,750円 | 42万2,250円 | 12.252% | 9,525円 |
| 80万円 | 12万4,400円 | 67万5,600円 | 20.42% | 2万5,400円 |
| 100万円 | 15万5,500円 | 84万4,600円 | 28.588% | 4万円4,454円 |
保険料率が一定の社会保険料と異なり、所得税の税率は社会保険料控除後の賞与の金額が高くなるほど上がります。
事業主が賞与を支給する際に必要な手続きは?
賞与を支給するために、事業主は従業員一人ひとりの賞与額を計算したり資金を準備したりする必要があります。また以下の手続きを行うことも求められます。
賞与明細書を発行する
従業員に対する賞与の支給には、賞与明細書が必要です。賞与の支給額、控除する項目それぞれの金額を記した賞与明細書を添えて、従業員に賞与を支給しなければなりません。
被保険者賞与支払届を提出する
被保険者賞与支払届は、事業主が従業員に賞与を支給したことを届けるために提出します。賞与から控除した社会保険料を納付するために必要とされる届出で、支給日から5日以内に提出しなければなりません。被保険者賞与支払届により従業員それぞれの標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が算出されます。
2021年(令和3年)3月までは、被保険者賞与支払届を提出する際には、被保険者賞与支払届総括表を添付することが求められてきました。しかし、2021年(令和3年)4月から被保険者賞与支払届総括表は廃止され、代わりに「賞与不支給報告書」が新設されました。
賞与支払月に賞与を支給しなかった場合には、賞与不支給報告書を提出することになり、被保険者賞与支払届総括表の提出は不要です。
賞与支給の負担を軽減するには?
賞与の支給には、賞与額の算定だけでなく控除する社会保険料や税金の計算など手間と時間がかかり、担当者にとっては大きな負担です。また、賞与の支給時に負担が集中するというデメリットもあります。賞与支給の負担を軽減するための方法を2つ紹介します。
給与計算システムを導入する
給与計算システムを導入することにより、賞与支給の負担を大幅に減らすことができます。賞与の計算だけでなく、社会保険料や税金の計算ができたり給与の支給、年末調整の負担も抑えたりする効果があります。
また、給与計算システムによっては法改正に合わせて賞与の計算をしてくれるため安心です。システム導入によるコストはかかりますが、業務の効率化が期待できます。
賞与支給の負担を軽減し、担当者の長時間労働の是正やコア業務への集中、業務効率化によるコスト削減を図るという方法もあります。
アウトソーシングする
企業の人手不足が深刻な場合、賞与や給与の支給業務をアウトソーシングするという選択肢もあります。少子高齢化の進展により生産年齢人口は減少しているため、人手不足の状況がますます深刻化する可能性があるからです。
賞与支給は年に数回程度であるため、そのために余剰人員を抱えるのは非効率であるケースも考えられます。限られた人材を有効活用するために、思い切ってアウトソーシングすることも考えてみましょう。
賞与支給をアウトソーシングする場合、給与支給も同時にアウトソーシングするのが一般的です。給与支給の負担も給与振込手配直前に業務が集中しがちであるため、アウトソーシングによって業務の削減と平準化が期待できます。
賞与支給に限りませんが、システム導入やアウトソーシングによって企業の人材を生産性の高い仕事に投入すれば、システム導入やアウトソーシングのコストを上回る効果が得られる可能性もあります。
社会保険料が控除されるのはなぜ?いつから始まった?
社会保険料がボーナスから引かれるようになったのは、保険料逃れを防ぐための対策です。
賞与からも社会保険料が控除されるようになったのは、2003年(平成15年)4月からです。それまでは、「特別保険料」という保険料率が1%で労使が0.5%ずつ負担するという仕組みがありました。期間は1995年(平成7年)4月から2003年(平成15年)3月までです。
2003年(平成15年)4月から、賞与からも社会保険料控除が行われるようになった目的は、給料と賞与額の調整による会社間の社会保険料負担の公平化を図るためです。
それ以前は、賞与からの社会保険料控除がなかったため、会社によっては給料と賞与の割合を意図的に操作して社会保険料負担を免れることがありました。
つまり、以前は、企業が従業員の月給を下げ、その分ボーナスを増やすことで社会保険料の支払いを抑えることが可能でした。このような行為は、給与と賞与のバランスを意図的に変えることで、保険料の負担を不当に減らす企業が存在したため、問題視されていました。
このような会社間の不公平をなくすために(保険料逃れを防ぐために)、賞与からも社会保険料控除を行う「総報酬制」に移行されました。
賞与・ボーナスで引かれる社会保険料の金額がおかしいと思ったら?
賞与やボーナスから引かれる社会保険料の金額がおかしいと感じた場合、以下のステップで確認してみましょう。
| ①計算の確認 |
|---|
| 最初に、自分で賞与・ボーナスから引かれる社会保険料の計算を確認してみましょう。社会保険料は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などがあり、それぞれの保険料率に基づいて計算されます。賞与・ボーナスに対する社会保険料の計算方法は、通常の給与とは異なる場合があるため、正しい計算方法を理解することが重要です。 |
| ②給与明細の確認 |
|---|
| 給与明細を確認し、そこに記載されている社会保険料の金額をチェックします。明細には、どの保険にどれだけの金額が引かれたかが記載されています。 |
| ③人事・給与担当者への問い合わせ |
|---|
| 計算方法を理解した上で、それでも金額がおかしいと感じる場合は、会社の人事部門や給与担当者に問い合わせてください。 |
| ④外部機関への問い合わせ |
|---|
| 会社の説明に納得がいかない場合や、会社が適切に対応してくれないと感じる場合は、最寄りの社会保険事務所や労働基準監督署に問い合わせることも検討してみてください。 |
ほとんどの企業は、賞与・ボーナスの社会保険料は、正しい計算に基づいて算出しているはずです。
目安として、賞与が50万円前後の場合、社会保険料は合計7~8万円前後引かれる傾向なので、そのくらいの金額であれば、間違っていないケースも多いです。
よくある質問
賞与からも社会保険料が引かれる?
賞与からも社会保険料と所得税(源泉徴収税)が引かれます。詳しくはこちらをご覧ください。
賞与から控除される社会保険料の計算方法は?
賞与の金額の千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、健康保険料や厚生年金保険料を計算します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
介護保険制度の概要
日本では急速な高齢化が進み、「介護保険制度」への関心が高まりつつあります。 総務省統計局の資料によれば、2017年9月15日時点で、65歳以上と定義される高齢者の人口は3,514万人で、総人口に占める高齢者人口の割合が27.7%と過去最高と…
詳しくみる建設業で外国人雇用するには?手続きや注意点を徹底解説
建設業で外国人を雇用するには、適切な在留資格の確認と必要な手続きを正しく行うことが重要です。 特定技能や技能実習などの業務内容に応じた在留資格があるか確認し、労働環境を整えることでスムーズな外国人雇用が進められます。本記事では、外国人雇用の…
詳しくみる退職後に雇用保険(基本手当)を受給するための手続きは?必要書類も解説!
会社退職後に失業手当(基本手当)を受け取るには、ハローワークで説明会の出席や失業の認定などの手続きが必要です。 ここでは、離職票などの基本手当を申し込む際の必要書類や、手続きの流れを紹介します。また、基本手当がいくらもらえるのか、計算方法を…
詳しくみる社会保険の電子申請手続き
電子申請とは、これまで紙媒体で行ってきた申請書や届出書の提出を「e-Gov(イーガブ)」という電子申請システムを利用し、インターネットで行う手続きのことです。 社会保険に関する手続き方法は、この電子申請の普及により劇的に変化しました。 電子…
詳しくみる国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要な場合について解説
国民年金第3号被保険者関係届とは、会社員や公務員など会社や組織に所属し厚生年金保険に加入している第2号被保険者が配偶者を扶養に入れる際に提出しなければならない書類です。配偶者の収入増加や離婚などで扶養から外れる際も提出が必要で、提出先は日本…
詳しくみる資格確認書とは?どこでもらえる?送付状のテンプレも
2024年12月2日以降、従来の健康保険証が新規発行されなくなる代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となります。 しかし、何らかの事情でマイナンバーカードを取得・利用できない方のために、医療保険者(協…
詳しくみる