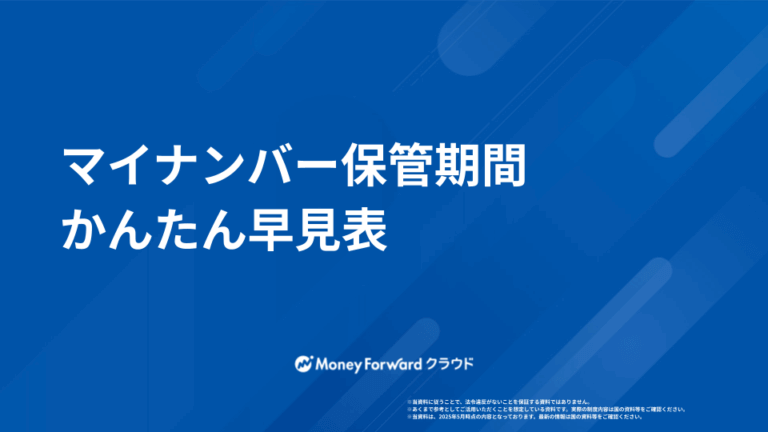- 更新日 : 2025年6月23日
マイナンバーの保管期間に関するまとめ
国税関係帳簿や書類は一定の保管期間が義務付けられています。事業規模や書類の種類にもよりますが、7年の保管期間であれば問題ないと認識されている方が多いことと思います。
ではマイナンバーはどのように保管することが義務付けられているのか、またどのタイミングで廃棄しなければならないのかを詳しくみていきましょう。
特定個人情報の保管期間には保管制限があります
特定個人情報はマイナンバー法で利用目的を明示した上で収集し、必要がある限り保管し続けることができます。個人番号カードの有効期間は10年(※20歳未満については5年)ですが、番号そのものは原則として生涯唯一の番号として取り扱うことになっています。何度も収集する手間を省くために、事務手続きで必要な限り保管し続けることができるとしています。
マイナンバーのガイドライン内では「保管し続けることができる」という表現で、実質的な保管期間を事業者に委ねています。前提として使用しないデータはできるだけはやく廃棄したり削除したりするようにとの保管制限があるからです。
税法上の保管義務は更生の請求手続きや修正申告に準じた期間が設定されています。しかし特定個人情報は証拠証憑としての役割を果たさないため保管する理由がないともいえます。そのため特定個人情報はできるだけ速やかに廃棄するものであるが、保管する必要があれば「保管し続けることができる」と事業者に判断を委ねているのはそのためなのです。
たとえば継続して雇用する従業員のマイナンバーは、源泉徴収税といった税に関する手続きだけでなく、健康保険や雇用保険など社会保険に関しても利用する必要があります。そのため従業員を雇用している限り、保管し続けることができます。
これは休職中の従業員に関しても同様に定義づけることができます。原則として休職は復職を前提としたものですが、休職の内容によっては復職の時期が未定となる場合もあります。復職が未定であったとしても、当該従業員の特定個人情報は引き続き継続雇用の状態であるため、マイナンバー等を保管しておくことによって再度収集する手間を省くことができるのです。また、退職した従業員に対して退職後も支給する給与や賞与がある場合も、源泉徴収票の作成が必要である限り保管し続けることができると解釈することができます。
当該書類に関する所管法令によって一定の保管義務が発生する場合は、その法令に準じる形で保管期間を設けることになります。言い換えれば、一定の保管期間が経った書類に関してはただちに廃棄する必要があるのです。
参考:帳簿書類等の保存期間および保存方法|国税庁HP
| 帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売上金元帳、買掛金台帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など | 確定申告書の提出期限より7年間の保存義務 |
| 書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など | |
参考:給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁HP
| 給与所得者の扶養控除等申告書 従たる給与についての扶養控除等申告書 給与所得者の配偶者特別控除申告書 | その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日から7年間の保存義務 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 退職所得の受給に関する申告書 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 |
なお、
・退職所得の源泉徴収票/特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
といった法定調書は、提出義務があるのみで保管義務はありません。
ただし、これら法定調書を作成する元となる書類(領収書など)に対して、7年間の保存義務が生じます。
参照:
雇用保険法施行規則第143条(書類の保管義務)|e-Gov法令検索
健康保険法施行規則第34条(事業主による書類の保存)|e-Gov法令検索
| 雇用保険被保険者資格取得/喪失届 | 完結の日より4年間の保存義務 |
| 健康保険/厚生年金保険被保険者資格取得/喪失届 健康保険被扶養者(異動)届 健康保険/厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書/終了届 | 完結の日より2年間の保存義務 |
廃棄する方法にはどのような手段がありますか?
個人番号利用事務や個人番号関係事務を行なう必要のなくなった特定個人情報は、できるだけはやく廃棄処分しなくてはなりません。廃棄や削除するために「容易に復元できない手段」で行なうことが重要になります。それではどのような手段が復元不可能な手段となるのでしょうか。
たとえば通知カードや個人情報カードのコピーをとっていた場合は紙媒体で保管していることになります。紙媒体を廃棄するためには焼却や融解が挙げられます。また復元できない程度に細断できるシュレッダーも廃棄手段として有効です。
次にデータで保管している場合を考えてみましょう。特定個人情報データを保存している電子媒体や機器類は、削除専用のソフトウェアを使用することや、物理的に破壊する手段があります。またデータ復元用システムといった専用の装置を用いなければ復元できない場合、容易に復元できない手段だと考えることができます。
さらにマイナンバー制度では廃棄削除するだけでは事足りず、その事実を記録しておく作業も必要となります。廃棄削除に関する内容として、廃棄した特定個人情報の書類名称、部数、担当者名、廃棄手段などを記録します。記録内容にマイナンバーを記載したり転記したりすることのないように注意します。
また取扱件数が多い事業者の場合、委託することも考えられます。廃棄作業を委託した場合、証明書等の発行によって記録とすることが可能となります。
まとめ
マイナンバーの保管期間に対する考え方は、これまでの法令や制度とは圧倒的に異なります。電子帳簿保存法という法律があることからもわかるように、原則として保存したり保管したり、廃棄せずに確認できる状態にしておくことに重点をおいた考え方が主流でした。しかし、マイナンバー制度においては使用しない特定個人情報は廃棄削除することが前提となっており、「使用し続ける期間は保管することができる」という条件付きで保管期間を設定することを事業者が判断できるようになっているのです。
廃棄や削除することを前提に管理するようガイドラインで定められているのも大きな特徴だといえるでしょう。保管期間を長く設定することによって、担当者が入れ替わることも考えられます。適切に管理できなくなってしまったということを未然に防ぐために、定期的に研修したり作業手順を見直したり、継続することが重要となります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業者が行うべきマイナンバー制度への対応
マイナンバー制度の導入に伴い、個人事業主にもその対応が必要になりました。特に個人事業主の場合「給与等の支払者」と「支払を受ける者」のいずれの立場も想定されるため、個人事業主特有の対策が必要です。 個人事業主の2つの立場 多くの法人の場合「給…
詳しくみるマイナンバーの桁数は何桁になるの?
マイナンバーの桁数が12桁なのは、ご存じですか? この数字、実は無作為に選ばれることはありません。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で使用されていた住民票コードが基になっています。 マイナンバー(個人番号)の桁数は12桁 マイナ…
詳しくみるマイナンバーは外国人に対してどのような影響があるか
マイナンバー制度では、日本に住民登録のあるすべての人に個人番号を付番します。それは外国人であっても変わりません。 外国人にもマイナンバー? 外国人であっても、日本に住民登録をした場合、マイナンバーが付番されることになります。 日本に中長期間…
詳しくみるマイナンバーの企業版、法人番号を徹底解説
企業(法人)にも共通番号が付番されます。この番号は法人番号と呼ばれ、様々な面で個人番号(マイナンバー)とは異なる取り扱いを受けます。法人番号は、個人番号(マイナンバー)とどう異なり、どう利用していくことができるのでしょうか?徹底解説します。…
詳しくみるマイナンバー制度における本人確認の意味と本人確認した後の対応
番号法では、マイナンバーを取得するとき、「なりすまし」防止のため、必ず本人確認をすることを事業者に義務づけています。特にマイナンバー導入の初年度、従業員から取得するときなどでは、顔見知りであるからと、本人確認がおろそかになってしまうこともあ…
詳しくみる海外転出や赴任においてマイナンバーカードはどうする?
2015年にマイナンバー法が施行され、市町村から住民票を有するすべての人にマイナンバー(個人番号)が通知されています。 マイナンバーカードについても、ポイント付与のキャンペーンなどの影響もあり、ここにきて取得する方は増えているようです。 と…
詳しくみる