- 更新日 : 2026年1月8日
退職金共済と退職金制度の違いは?中退共の仕組みや退職金制度の選び方を解説【規定テンプレート付】
退職金制度は、従業員の将来の安心を支える大切な仕組みです。制度には「退職金共済」と呼ばれる制度もあります。
とくに中小企業向けの「中小企業退職金共済(中退共)」は、国の助成を活用しながら簡単に導入できる制度として注目されているのが特徴です。
本記事では、退職金共済と一般的な退職金制度の違いや、制度の仕組みについて解説します。
目次
退職金共済と退職金制度の違い
退職金制度は、従業員が退職するときに働いた年数や会社への貢献に応じて、一時金や年金を支給する仕組みです。
一方で、退職金共済は業種や会社の規模に応じて選べる「退職金積立制度」のことを指します。代表的な「中小企業退職金共済(中退共)」は、国からの助成もあるため、中小企業が導入しやすい仕組みです。
退職金共済は退職金制度のひとつですが、共済型の退職金制度として位置づけられています。
退職金制度には「企業年金型」や、保険を活用して退職金を準備する方法もあります。企業は自社の状況に応じて、適している制度を選択可能です。
また、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、74.9%の企業がなんらかの退職金制度を導入しています。制度の形態別の企業割合は以下のとおりです。
- 退職一時金制度のみ:69.0%
- 退職年金制度のみ:9.6%
- 両制度併用:21.4%
参考:令和5年就労条件総合調査
とくに最近は、中小企業退職金共済をベースにしながら、独自の上乗せ制度を設ける企業も増えてきています。このように、安定性と柔軟性を両立させた退職金制度を実現しています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
退職金制度の種別
退職金制度には、4つの主要な形態があります。それぞれの制度には独自の特徴があり、企業は自社の状況に応じて適切な制度を選択可能です。以下で詳しく解説します。
退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員が退職する際に一時金の形で支給される制度のことです。給与や働いた年数などをもとに、会社が独自の計算方法を決められます。法律によって支給しなければいけない決まりはありません。
柔軟に制度を作れる反面、退職金として支払うお金は企業内で確保する必要があります。多くの人が同時期に退職すると、多額の支払いが発生するため、財務負担が重くなるリスクがあるでしょう。
また、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、退職一時金のみを支給している企業の割合は69.0%です。退職給付のなかでも一番多く採用されているため、一般的に知られている退職金は、退職金一時金を指すケースが多いでしょう。
退職金共済制度
退職金共済制度は、在籍中に外部の共済機関に掛金を積み立てて、退職時にまとめて支払われる制度のことです。中小企業向けに設計された制度が多く、掛金の全額が損金算入できるため、税制面でのメリットがあります。また、資金の運用・管理は共済機関が行うため、企業の負担も減らせます。
この制度は、国からの助成を受けられる場合もあり、会社の負担を抑えながら退職金を提供できるのが特徴です。ただし、掛金を減らしたい場合には条件があり、柔軟性がやや制限されます。代表的な例は「中小企業退職金共済制度(中退共)」で、多くの中小企業で利用されています。
確定給付企業年金制度(DB)
確定給付企業年金制度(DB)は、会社があらかじめ約束した年金額を従業員に支給する仕組みです。掛金の運用は会社が一括して行い、運用リスクも会社が負担します。
DBには「規約型」と「基金型」の2種類があります。
| 比較項目 | 規約型確定給付企業年金 | 基金型確定給付企業年金 |
|---|---|---|
| 運用主体 | 会社が生命保険会社・信託銀行などと契約 | 独立した法人(企業年金基金)が運営 |
| 従業員数の要件 | 制限なし | 300人以上(複数企業の合算も可) |
| 設立手続き | 厚生労働大臣の承認が必要 | 厚生労働大臣の認可が必要 |
| 管理・運用 | 生命保険会社・信託銀行などが実施 | 企業年金基金が実施 |
| 特徴 |
|
|
どちらも労使合意のもと、厚生労働大臣の承認や認可を受けて実施します。DBは、従業員にとっては、将来もらえる年金額が決まっているため、安心して働き続けられる制度といえるでしょう。
企業型確定拠出年金制度(DC)
企業型確定拠出年金制度(企業型DC)は、企業が掛金を拠出し、従業員がその資金を運用する年金制度です。運用の結果に応じて将来の年金額が決まるため、従業員が自分の判断で資産運用に携われます。
個人ごとに資産が区分され、転職時には持ち運びも可能です。掛金の上限は、ほかの年金制度への加入状況により月額55,000円または27,500円となります。
また、2022年10月からは原則としてiDeCoとの併用もできるようになり、より柔軟な運用が可能になりました。ただし、掛金の限度額は確定給付企業年金(DB)などの有無によって異なり、上限内で調整が必要です。
企業型DCは柔軟性があり、従業員の高齢期の資産形成を支援する重要な制度です。
退職金共済制度の種類と対象
退職金共済制度には、企業や従業員の特性に応じて選択できる複数の制度があります。ここでは、それぞれの制度の加入対象やメリットなどを解説します。
中小企業退職金共済
中小企業退職金共済制度は、独自の退職金制度をもつことが難しい中小企業向けの国の支援制度です。
中小企業の事業主が中小企業退職金共済事業本部(中退共)と退職金共済契約を結び、従業員の退職時に退職金を支給する仕組みとなっています。
制度に加入できる企業は、業種によって規模の基準が異なり、次の範囲であれば加入可能です。
| 業種 | 条件 |
|---|---|
| 一般業種 | 常用従業員数300人以下 または資本金・出資金3億円以下 |
| 卸売業 | 常用従業員数100人以下 または1億円以下 |
| サービス業 | 常用従業員数100人以下 または5千万円以下 |
| 小売業 | 常用従業員数50人以下 または5千万円以下 |
中小企業退職金共済制度に加入するメリットは、以下のとおりです。
- 新規加入時に従業員ごとに掛金が最大6万円減額される(一部例外あり)
- 掛金は損金または必要経費として全額非課税となる(※1)
- 口座振替による自動納付で手間がかからない
※1:資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用される
一方で、掛金が全額事業主負担となることや、一度導入すると制度変更が難しいといった課題もあります。しかし、国のバックアップがある安全な退職金制度として、従業員の福利厚生充実や長期的な人材確保を目指す中小企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する経営者のための、積立型退職金制度です。2023年3月時点で全国で約162万人が加入しており、将来への備えとして広く活用されています。
加入資格・対象者は、以下のとおりです。
| 業種 | 加入資格・対象者 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合 |
|
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)などを営む場合 |
|
| 企業組合 協業組合 |
|
| 農事組合法人 |
|
| 弁護士法人・税理士法人などの士業法人 |
|
掛金は全額所得控除の対象で節税効果が高く、月額1,000円から70,000円まで500円単位で設定できるのが魅力です。加入後の掛金増減も自由で、契約者は低金利で事業資金の貸付制度も利用できます。
また、共済金の受け取り方は、一括・分割・併用のいずれかを選べます。一括受け取りは退職所得控除、分割受け取りは公的年金等控除の対象です。
一方で、掛金の払い込み期間によって受け取り額が変動するため、長期的な加入を前提となります。また、早期解約時には受け取り額が掛金総額を下回る場合もあります。
このように、小規模企業共済は税制面のメリットが大きい一方、長期的視点が求められる制度です。加入を検討する際は、これらの特徴を理解した上で判断することが重要です。
特定退職金共済
特定退職金共済(特退共)は、商工会議所や地方自治体が運営し、外部組織に運用を委託する退職金制度です。会社の規模に関係なく加入でき、計画的に退職金を積み立てられます。
掛金は月額1,000円から30,000円まで選べて、全額が損金または必要経費として非課税となります。
契約の対象は商工会議所がある地域で事業を営む企業や個人事業主です。満15歳以上70歳未満の従業員なら加入でき、使用人兼務役員も対象になります。ただし、試用期間中や非常勤の従業員は加入するかどうかを選択可能です。
掛金が全額非課税であることや、退職金が従業員に直接支払われるのがメリットです。中退共と異なり、加入期間が短くても退職金が受け取れます。また、過去の勤務期間も通算できるので、長期的な福利厚生に適しています。
ただし、掛金の額が低いと、退職金が元本割れしやすい点がデメリットです。この制度は、中退共と一緒に加入できるため、従業員の福利厚生を充実させたい企業に適しています。
特定業種退職金共済
特定業種退職金共済は、建設業・清酒製造業・林業向けの退職金制度です。働いた日数に応じて掛金を納め、その業界を離れるときに退職金がもらえます。仕事が不安定になりがちな現場で働く人たちの生活を支えるのが目的です。
| 契約対象者 |
|
|---|---|
| 加入対象者 |
|
メリットとして、掛金が全額損金(個人事業主は必要経費)算入可能な点や、業界内での転職時も掛金が通算される点が挙げられます。従業員が業界を引退するまで退職金が積み立てられるため、業界全体で労働者を支える仕組みです。
ただし、中小企業退職金共済と併用して加入できないのがデメリットです。また、業界をやめるまで退職金がもらえないため、転職時の資金としては使えないという制限もあります。
社会福祉施設職員等退職手当共済
社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、社会福祉法人の施設で働く職員のための退職金制度です。2023年4月現在、約88万人が加入しています。
運営は独立行政法人福祉医療機構(WAM)が行い、掛金と国・都道府県の補助金でまかなっています。
加入できるのは、社会福祉施設や特定介護保険施設を経営する社会福祉法人です。施設で働く職員なら、パートの人も一定の条件を満たせば加入できます。
法律にもとづいて退職金がもらえるため、職員の安心感と定着率向上につながります。掛金は全額非課税扱いされるので、経営者に節税効果もあるのが魅力です。
また、退職金は職員に直接支払われるため、経営者の事務負担が少なく済みます。一方で、職員一人あたりの掛金が月額45,500円と高く、補助金が適用されない施設もあるため、財務的な負担が大きいのがデメリットです。
中小企業退職金共済との重複加入ができないため、制度を選ぶ際は慎重に検討する必要があります。
退職金規定の無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、退職金規定の無料テンプレートをご用意しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
中小企業退職金共済の掛金は誰が払う?
中小企業退職金共済(中退共)の掛金は、すべて事業主が負担します。掛金は毎月従業員一人あたり5,000円から30,000円の範囲で設定でき、全額が損金または必要経費として計上可能です。従業員の給与からの天引きや負担を求めることはできません。
法人企業の場合は損金として、個人事業主の場合は必要経費として全額非課税扱いされるため、税負担を抑えられるのがメリットです。
また、加入時には国から一定の助成金が支給されることもあり、会社の経済的な負担を軽くできます。
たとえば、従業員一人あたり月額掛金の1/2(上限5,000円)が、加入後4ヶ月目から1年間助成される仕組みがあります。
このように、中退共は事業主が主導して運用する制度であり、従業員に負担をかけずに退職金制度を導入できるのが魅力です。
中小企業退職金共済と社内の退職金制度を併用できる?
中小企業退職金共済と社内独自の退職金制度は併用できます。そのため、中小企業退職金共済で基本の退職金を運用し、会社の制度で役職や働いた年数に応じた追加の給付を設けるのが一般的です。
また、退職金を複数の場所からもらう場合は、支払う側ごとに必要な手続きや書類を準備する必要があります。
たとえば、退職所得の受給に関する申告書や住民票などを中退共と社内の退職金制度それぞれに提出します。また、退職金をもらう順番も事前に決めておく必要があり、支給額によって税金の取り扱いが変わる場合もあるため注意しましょう。
なお、企業型確定拠出年金(企業型DC)などの制度とも併用できますが、以下の制度は併用ができません。
- 特定業種退職金共済
- 小規模企業共済制度
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
制度を組み合わせる場合は、仕組みや手続きをよく理解して、適切な運用を心がけることが大切です。
中小企業が退職金制度を選ぶポイントは?
中小企業が退職金制度を選ぶ際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 導入や運用にかかる負担
- 退職金額の自由度
- 従業員の運用負担や受け取り時期
退職金制度の設計や管理に手間をかけたくない場合は、簡単に導入できる「中小企業退職金共済(中退共)」がおすすめです。国からの助成を一定期間もらえるため、とくに小規模の事業者には導入しやすい制度です。
また、退職金額の自由度も考慮しましょう。退職金の金額や条件を自由に決めたい場合は、「確定給付企業年金(DB)」や「企業型確定拠出年金(DC)」が適しています。役職や退職理由によって金額を調整できるため、企業の考えに合わせた運用ができます。
次に、従業員の運用負担や受け取り時期にも注目しましょう。「確定給付企業年金(DB)」は退職したときに受け取りが可能で、従業員が自分で運用する必要もありません。そのため、従業員の負担が少なく済みます。
一方、「企業型確定拠出年金(DC)」は運用で得た利益に税金がかからず、運用次第で退職金額が増える可能性があります。投資に興味がある従業員には魅力的ですが、60歳まで受け取れない点には注意が必要です。
会社の規模や目的、従業員の特性に応じた制度選択が、経営の安定化と従業員満足度の向上につながります。
退職金制度を活用して、働きやすい職場を作ろう
本記事では、退職金共済と一般的な退職金制度の違いを解説しました。退職金制度は、企業の規模や業種によってさまざまな選択肢があります。
制度を選ぶ際には、導入・運用の負担、退職金額の自由度、従業員の運用負担や受け取り時期がポイントとなります。自社の状況と従業員のニーズを見極め、長期的な視点で適している制度を選択しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
役職手当とは?決め方や相場、設定時の注意点を解説
役職手当とは、役職に応じて支給される賃金のことです。支給するかどうかは企業が任意に設定でき、残業代が出ない管理職にその代わりとして支給できるというメリットがあります。 設定の際は、…
詳しくみる給与振込同意書とは?書き方・記入例やどこでもらえるかを解説【無料テンプレ付き】
給与振込同意書とは、会社が従業員の銀行口座に給与を振り込む際、従業員がその方法に同意したことを示す書類です。 給与振り込みに関する同意を得ることで、法令遵守やトラブル回避が可能です…
詳しくみる西宮市の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
西宮市は、阪神間に位置し、洗練された住宅地と商業エリアが調和する魅力的な都市です。多くの企業が集まるこの地域では、給与計算の正確性と効率性がビジネス成功の鍵を握っています。 本記事…
詳しくみる【テンプレ付】昇給辞令とは?給与辞令との違いや書き方について解説
昇給辞令とは給与の改定を通知する給与辞令の一種で、昇給時に交付される辞令書です。そもそも辞令とは、会社が従業員に対し人事命令を通知する目的で交付されるもので、代表的なものには採用辞…
詳しくみる割増賃金とは?計算方法や60時間超の割増率、未払い時の対処法までわかりやすく解説
従業員に法定労働時間を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合、企業は通常よりも高い率で計算した割増賃金を支払う必要があります。これは労働基準法で定められた企業の義務であり…
詳しくみる目黒区の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
目黒区は東京の中でも特に洗練された商業地区として知られ、多くのスタートアップやクリエイティブ企業が拠点を構えています。こうしたダイナミックなビジネス環境では、給与計算の正確性とスピ…
詳しくみる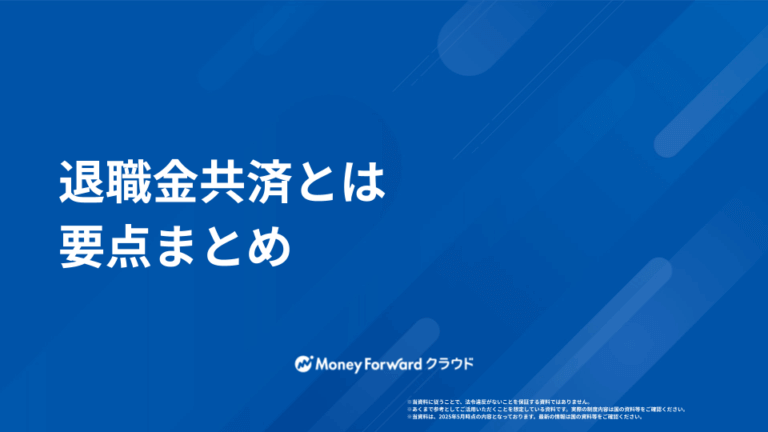

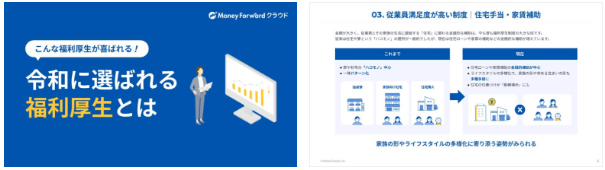
.jpg)
