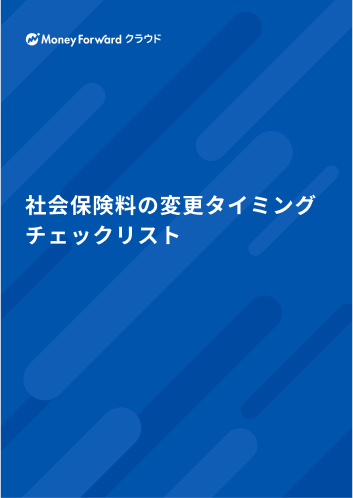- 更新日 : 2025年5月27日
社会保険料の変更に伴う手続きを解説!随時改定の意味など
社会保険料は、月々の給与額ではなく、標準報酬月額をもとに算出されます。毎年1回、7月に算定基礎届を提出することにより決定され、固定的賃金に変動があった場合は月額変更届による随時改定を行います。
今回は、社会保険料の決定方法と変更が必要なタイミングについて解説するとともに、随時改定による変更の手続きについて説明します。
目次
社会保険料が変わるタイミングはいつ?
社会保険料の変更時期は、毎年9月です。変更の手続き自体は、毎年7月に行います。
社会保険料は、毎月の給与ではなく「標準報酬月額」をもとに決定されます。標準報酬月額とは、毎年4月から6月までの3か月間の報酬の総額を、その期間の総月数で割る、いわば「3か月間の平均給与」です。通常、毎年7月に、この標準報酬月額を決定するために必要な「算定基礎届」を年金事務所に提出し、そこで計算された報酬の平均額もとに新たな標準報酬月額が決定され、9月から社会保険料が変更となります。
給与から天引きできる社会保険料は、給与を支払った月の前月分です。たとえば9月分の社会保険料は10月分の給与から天引きすることになります。標準報酬月額の変更により社会保険料が変更されるのは9月ですが、実務的には10月分の給与から変更後の社会保険料を控除することを覚えておきましょう。
企業は、4月から6月までに支払った報酬を所定の方法で計算して算定基礎届に記載し、届け出なくてはいけません。算定基礎届の対象となる従業員は、原則として社会保険に加入するすべての従業員です。この社会保険料変更の手続きを「定時決定」と呼びます。しかし、なかには昇給や昇格などにより標準報酬月額が2等級以上変動するケースもあるでしょう。そうしたタイミングでは、定時決定を待たず「随時改定」により社会保険料の変更を行います。
社会保険料の変更に関わる随時改定とは?
随時改定とは、定時決定の時期を待たずに標準報酬月額を変更させる手続きのことをいいます。その届出を、月額変更届と呼びます。下記に示すすべての条件を満たした場合、随時改定の対象となります。
- 基本給、家族手当、通勤手当など、支給率・支給額が決まった固定的賃金に変動がある
- 支払基礎日数が17日以上ある
- 変動した月から計算した3か月の平均に該当する標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある。
なお、賞与の支給が年に3回以下の場合は、標準報酬月額とは別に、「標準賞与額」として毎月の保険料とは別に計算して納付します。ただし、「年4回以上」支給する賞与は、標準報酬月額の対象に含めて社会保険料を計算しなければいけないため注意が必要です。
賞与の社会保険料計算については、以下の記事も参考にしてください。
随時改定と定時決定の違い
随時改定と定時決定は、上述のように目的・対象・タイミングが異なります。
【目的】
- 定時決定:9月から翌8月まで、1年間の社会保険料を決めるための手続き
- 随時改定:固定的賃金等の上昇に伴う、社会保険料変更のための手続き
【対象】
- 定時決定:社会保険に加入しているすべての従業員
- 随時改定:随時改定の条件に当てはまる従業員
【タイミング】
- 定時決定:毎年7月1日~10日の間に、「算定基礎届」を提出する
- 随時改定:固定的賃金の変動後3か月間の報酬で随時改定の条件に該当するかを判断し、対象となる場合には、「月額変更届」を速やかに提出する
随時改定の対象となる人
随時改定の対象となるのは、先にあげた3つの条件に合致する場合です。以下に、それぞれの条件について詳しく説明します。
- 基本給など、固定的賃金に変動がある
- 支払基礎日数が17日以上ある
- 動した月から計算した3か月の平均に該当する標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある。
固定的賃金の変動とは
随時改定では、標準報酬月額が2級以上変動する場合が対象です。ここでいう「変動」には、以下のケースが含まれます。
- 昇給、降格
- 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
- 時間給などの基礎単価の変更
- 歩合給の単価や歩合率の変更
- 住宅手当や役職手当、通勤手当といった毎月定額となる手当の変更
このとき、変更対象となるのが「固定的賃金」である場合に注意が必要です。たとえば、基本給に変動がなく、残業代が上昇し給与の総額が上がったケースでは、随時改定の対象になりません。残業代とは、稼働実績などによって変動する「非固定的賃金」です。
ほかにも、テレワーク時に支給される「在宅勤務手当」は、パソコン等の実費をカバーする性質のものは固定的賃金の変動とはみなされず、逆に「月額1万円」のように固定で支払われるものは、固定的賃金の変動に含まれるなど、手当の実態によっても違いがあります。
標準報酬月額に2等級以上動く変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当するかどうかも十分に確認しましょう。
参考:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集|日本年金機構
支払基礎日数とは
給与計算の対象となった日数のことをいいます。日給や時給で計算している従業員の場合は、出勤日数を、月給制・週給制で賃金を支払う従業員の場合は暦日数で計算します。
また、パートタイムなどの短時間労働者の支払基礎日数は11日以上となる例外があるため注意しましょう。
短時間労働者とは、以下のすべての要件に該当する労働者です。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
引用:「事業主の皆さまへ 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています」|厚生労働省
2016年10月から厚生年金保険・健康保険の適用拡大が実施され、厚生年金保険の被保険者数が常時 501 人以上いる企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険への加入が義務となりました(特定適用事業所)。また、常時500人以下の企業であっても、労使の合意によって短時間労働者の社会保険への加入を申し出ることで、社会保険へ加入することができます(任意特定適用事業所)。
特定適用事業所や任意特定事業所で勤務する短時間労働者の場合には、支払基礎日数は17以上ではなく11日以上となります。なお、事業所の規模については、2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上に法改正が行われる予定です。
また、パートやアルバイトであっても、1週間の勤務時間と1か月の勤務日数が正社員など通常の従業員の4分の3以上となる短時間労働者の場合には、特定適用事業所や任意特定事業所に関係なく当然に社会保険の被保険者となります。この場合は、原則通り支払基礎日数は17日以上となりますので注意しましょう。
参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 |厚生労働省
8月・9月の随時改定予定者
毎年7月に算定基礎届を提出します。そのとき、7月に随時改定を行うために月額変更届を提出する場合は、算定基礎届の提出する必要はありません。8月・9月にすでに随時改定が予定されている従業員がいる場合、申し出により7月の算定基礎届の提出を省略することが可能です。
参考:8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について|日本年金機構
随時改定の有効期間
随時改定で変更された保険料は、再び随時改定が行われない限り、当年の8月までの各月に適用されます。7月以降に随時改定を行う場合は、翌年8月までその金額が適用されます。
随時改定をしなかった場合はどうなる?
随時改定を行わない場合、正しい額の社会保険料を納めない時期が発生します。過払い・不足の状況となり、精算が必要です。不足分の社会保険料については、延滞料が課される可能性もあります。また、虚偽の随時改定を行った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される恐れがあるので注意しましょう。
参考:健康保険法第208条
社会保険料の変更に伴う手続き
社会保険料の随時改定は、条件に該当する変動があったタイミングで速やかに月額変更届を提出します。原則として届出用紙以外の添付資料は不要です。以下に、手続きの方法を解説します。
前月と今月の固定的賃金に変動があるか確認する
毎月、決まって支給している固定的賃金に変動があるかを確認します。昇給や降格により変動のほか、通勤手当の廃止、在宅勤務手当や駐在手当など新たな手当の支給がないかを確認します。
変動した賃金を支給してから3か月後に標準報酬月額を確認する
固定的賃金に変動があってすぐに随時改定を行うわけではありません。随時改定の条件となるのは、「変動した月から計算した3か月の平均に該当する標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある」場合です。そのため、変動から3か月間の平均額で標準報酬月額を確認し、以前よりも2等級以上の差が発生している場合のみ、月額変更届を作成します。
届出様式に記入する
日本年金機構のウェブサイトより、月額変更届の様式をダウンロードし必要事項を記入します。届出には、対象となる3か月分の支給総額を記入します。このとき、基本給だけでなく通勤手当や残業手当など、固定的賃金と非固定的賃金を含めた総支給額を記入しましょう。
作成した届出書は、郵送、窓口、電子送付の形式で管轄の年金事務所または事務センターに提出します。
参考:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届|日本年金機構(PDF)
P21「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」|日本年金機構
年金事務所から通知書が届く
届出のあと、年金事務所から「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通書」が事業主に届きます。そこに記載された標準報酬月額をもとに、給与から控除する社会保険料を計算しましょう。また、健康保険の保険料は都道府県ごとに異なり、協会けんぽのホームページから保険料額表で確認することができます。健康保険組合や厚生年金基金などに加入している場合には、それぞれの加入している組合や基金などで確認しましょう。
参考:都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
新しい社会保険料を給与計算に適用する
給与計算で新たな社会保険料を適応したのち、給与明細書とともに、社会保険料の等級が変更になった旨を通知します。給与明細書の備考欄に記載するなどの通知方法がよいでしょう。
社会保険の加入条件変更に注意を
現在、社会保険の適用事業所は「厚生年金保険の被保険者数501人以上」の企業となっていますが、年金制度改正法により、2022年10月から段階的に社会保険の適用義務範囲が拡大されます。また、パートやアルバイトなど短時間労働者の加入条件にも変更があり、今後、自社の社会保険加入の対象となる従業員について、見直しが必要です。
社会保険料は、賃金の変動に合わせた適切な額を控除するとともに、社会保険の加入対象について、適切に対応できているか見逃さないでおきましょう。
【社会保険の適用範囲】
- 現在:従業員数501人以上
- 2022年10月1日より:従業員数101人以上
- 2024年10月1日より:従業員数51人以上
【パート・アルバイトの加入条件の変更】
- 労働時間:所定労働時間が20時間以上
- 賃金:月額88,000円以上
- 学生:適用除外
- 勤務時間:継続して1年以上雇用されていること→2022年10月より廃止(雇用の見込みが2か月超に変更)
年金制度改正法の詳細については、以下の記事も参考にしてください。
マネーフォワード クラウド社会保険なら社会保険料の変更もスムーズに
マネーフォワードクラウド給与では、随時改定の機能を使い、対象となる従業員がいるかどうか簡単に確認できます。月々の確定した給与計算内容をもとに算出されるため、随時改定が遅れてしまうといったミスを防ぐことができます。
そのほか、法令改正・増税・社会保険料の料率改定などがあった際には自動でアップデート。従業員はパソコン・スマホから給与明細を確認できるため、ペーパーレス化も即時に実現可能です。
製品の詳しい機能や使い方については、企業担当者さま向けのオンライン個別説明会を行っておりますので、まずは気軽にお問い合わせください。
よくある質問
社会保険料が変わるタイミングはいつですか?
毎月7月の定時決定に必要な算定基礎届を提出することで、その年の9月から翌8月までの社会保険料が決定されます。固定的賃金の変動があった場合には、月額変更届を提出し、随時改定により変更されます。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険料の変更に関わる随時改定とは何ですか?
固定的賃金の変動があった場合に標準報酬月額を変更するための届出です。月額変更届を提出することで、新たな標準報酬月額が決定されます。標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!
社会保険労務士の資格は人気の国家資格の1つです。人気の理由は、企業の人事・総務で労働・社会保険の手続き、就業規則の作成、ハラスメント対策などの実務を行うことも、独立して開業することもできることにあります。 今回は、年金問題、働き方改革、ハラ…
詳しくみる社会保険料の勘定科目は?仕訳方法を解説
社会保険は健康保険や厚生年金保険などからなり、毎月の給与から保険料が源泉徴収され納付されています。これら社会保険料は基本的に労使折半での負担で、会社負担分と従業員負担分をそれぞれ適切な勘定科目で会計処理しなければなりません。当記事では社会保…
詳しくみる労基とは?相談問題やメリット・デメリット、労働基準監督署の役割を解説
労基とは労働基準監督署の略で、全国に321署があります。厚生労働省の第一線機関であり、会社が労働基準法違反をしていないかを監督しています。労働者からの通報先となっているほか、使用者からの相談も受け付けています。使用者は労働条件・労災保険・労…
詳しくみる65歳以上も雇用保険に入れる?失業保険や年金のもらい方、給付金も解説
2017年の雇用保険法の改正により、65歳以上でも雇用保険に入れるようになりました。 法改正までは、65歳以上の方が雇用された際は雇用保険適用外でした、ただし、同じ会社で65歳になる前から継続して働いていた人は「高年齢雇用継続被保険者」とし…
詳しくみる士業の方は注意!社会保険における常時5人以上とは?対応方法を解説
個人の事業所は、従業員が常時5人以上となった場合、一部の業種を除き社会保険の強制適用事業所となります。加入条件を満たす従業員がいる場合には、社会保険の加入手続きが必要です。 2022年10月に適用業種の範囲変更があり、これまで対象外であった…
詳しくみる労働保険の年度更新とは?時期や電子申請・申告書の作成方法、効率化を解説
労災保険や雇用保険の年度更新は、電子申請の導入により、効率的な申告が可能となっています。これにより、平日の日中に労働局や労働基準監督署に出向く必要がなく、休日や夜間でも自宅から申告できるようになりました。 本記事では、労働保険の年度更新につ…
詳しくみる