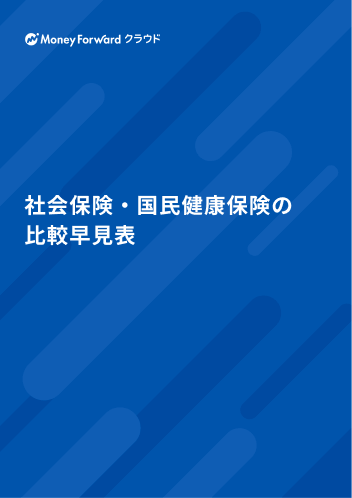- 更新日 : 2025年4月23日
押さえておくべき社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い
自分で起業するという計画を立てたときには、不安もあるでしょうが、ワクワク感も大きいですよね。今は勤めていらっしゃる会社の健康保険に加入されているものと思いますが、退職後の健康保険をどうするか考えていますか?
退職後一定期間は、現在の勤め先の健康保険を続けることも選択肢のひとつですし、新たに国民健康保険に加入することもできます。それぞれで保険料等が異なってきますので、これからその違いについて詳しく見ていきましょう!
目次
社会保険(健康保険)と国民健康保険との違い
社会保険(健康保険)とは、一般的に企業に勤めている方が勤務先を通じて加入する健康保険のことを指します。一方、自営業者の方は、国民健康保険に加入するのが一般的です。それでは、社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いについて具体的に見ていきます。
運営主体
社会保険(健康保険)には、まず全国健康保険協会の運営する「協会けんぽ」があります。ほかにも企業によっては、企業グループで独自に組合管掌健康保険を設け、協会けんぽよりも手厚い福利厚生の提供を行ったり、独自の組合名での保険証の交付を行っています。
対して国民健康保険は、それぞれの市区町村が運営しています。
保険料の違い
社会保険(健康保険)の場合には、今もらっている給与をもとに保険料が算出されます。夫が会社に勤めていて妻が専業主婦というケースでは、夫が保険料を支払うことで、妻や子供は保険料を負担することなく保険証が交付されます。
例えば、東京都で協会けんぽに加入している場合、最低保険料は5,707円/月となります(令和3年3月分より、介護保険料は含まず)。また、所得に応じてアップしていき、136,776円が上限となります。さらに、この金額を会社と従業員で折半することになりますので、負担額はさらに減ることになります。
一方、国民健康保険は前年の所得をもとに保険料の算出が行われます。そのため、会社を辞めて起業し、収入が安定しないうちに国民健康保険への切り替えを行った方には、保険料が大きな負担となることも考えられます。
また、国民健康保険には扶養という考え方がないため、保険の加入者全員に保険料がかかってきます。先ほどの例でいうと、妻や子供に保険を適用するためには、夫の分だけでなく全員分の保険料を支払わなければなりません。国民健康保険の保険料は均等割と所得割という2つで構成されています。例えば東京都の特別区の場合には、多くの地域において均等割が「加入者数×38,800円(令和3年度)」となっており、、これに加えて所得割等も加算されるので、保険料負担が大幅に増えることが考えられます。
保険料で比較すると、ケースバイケースではあるものの、国民健康保険の方が負担が大きくなる傾向にあります。
カバー内容の違い
国民健康保険では、出産手当金や傷病手当金が支給されないということが大きな違いとして挙げられます。社会保険(健康保険)の場合には、上記を含む各種給付金は要件を満たせば全て支給されます。
社会保険(健康保険)から国民健康保険への注意点
ここでは、社会保険(健康保険)から国民健康保険への切り替えにあたって、注意が必要な点について説明します。
退職日の翌日付で社会保険(健康保険)の資格は喪失する
退職の場合、社会保険(健康保険)の資格は退職日の翌日で喪失となります。したがって、月末退職の場合、翌月1日が資格喪失日ということになります。
社会保険料は被保険者資格喪失日の月の前月までが徴収の対象となりますので、3月31日退職の方は被保険者資格喪失日が4月1日となり、社会保険料はその前月の3月分まで発生します。3月30日退職の方は被保険者資格喪失日が3月31日となり、社会保険料はその前月の2月分まで発生する違いがあるので注意が必要です。
保険証を返却する必要がある
退職の際に、勤め先に保険証を返却する必要があります。扶養家族の保険証も発行されている場合は、これらもあわせて返却します。
退職日の翌日からは国民健康保険に加入していることになる
退職日の翌日からは、加入手続きを行っていない場合でも他の公的医療保険の加入者でなければ、国民健康保険に加入しているとみなされます。そのタイミングから保険料の請求が発生することになりますので、退職後は速やかに加入手続きを行いましょう。
迷ったときは「任意継続」という手段も
実は、会社勤めを辞めた方が国民健康保険に加入しない方法もあります。そのためには、現在の勤め先で加入している社会保険(健康保険)の任意継続という制度を利用します。
任意継続は、退職者が希望をすることで退職後2年間は社会保険(健康保険)への加入を継続ができる制度です。任意継続の場合には、それまでのような保険料の会社負担はなくなり全額自己負担となりますが、それ以外の負担をすることなく扶養家族の保険証を用いることができます。
ただし、任意継続を利用するためには、退職後20日以内に手続きしなければならないという点に注意が必要です。また、会社勤めのときと異なり、給与からの天引きにより保険料を支払うわけではないため、自分で納付をする必要があります。場合によっては、1日でも納付が遅れると強制的に退会させられることもありますので、注意しましょう。
国民健康保険へ新たに加入するか、任意継続をするか迷った場合には、任意継続を選択するというのもひとつの手だと考えられます。一旦、国民健康保険に加入すると、任意継続に切り替えることができなくなるためです。
保険料の減免について
経済的な理由により国民健保険料の納付ができない場合には、保険料の軽減・減免(免除)措置というものがあります。自治体ごとに減免基準等は異なりますが、会社を辞め、起業した方は該当するケースがあります。
自治体によっては、所得割が免除となり、また均等割も2割〜7割の減免などとなっていますので、詳細な条件などはお住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
退職時には任意継続と国民保険を比較しよう
社会保険(健康保険)と国民健康保険の違いについてみてきました。
今後独立する予定がある方などは、一度じっくり任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合とシミュレーションしてみてはいかがでしょうか?
ご自身の状況を勘案して、ぜひベストな選択肢を探してみてください。また、社会保険料の計算は自動計算で間違いがなく、料率改定も自動更新の便利な社会保険料計算機能が充実の給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」をぜひお試しください。
よくある質問
社会保険(健康保険)と国民健康保険はどのように違いますか?
それぞれ運営主体が異なりますが、保険料や保険のカバー範囲が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険は住んでいる地域によって保険料が異なるのですか?
社会保険(健康保険)も協会けんぽと独自の組合では保険料が異なるように、市区町村により均等割額、所得割などが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険(健康保険)の任意継続とはなんですか?
任意継続は、退職者の希望により退職後2年間は社会保険(健康保険)への加入を継続できる制度です。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
社会保険の関連記事
新着記事
福利厚生が最低限しかないとどうなる?全くない会社への罰則や自分でできる対策も解説
福利厚生がない、または最低限しかない会社で働くことは、私たちの生活や将来設計に大きな影響を与えます。しかし、実際にどのような影響やリスクがあるのか、具体的に知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、法律上義務付けられている福利厚生…
詳しくみる女性が本当に嬉しい福利厚生ランキング!働きやすい職場への取り組みを解説
近年、多くの企業が女性社員向けの福利厚生を充実させています。これは少子高齢化や働き方改革が進む中で、女性が出産や育児を経ても安心してキャリアを継続できる環境が求められているからです。本記事では、女性向け福利厚生の導入背景や企業にもたらすメリ…
詳しくみる会社からの出産祝い金とは?福利厚生で支給される金額相場やタイミングなどを解説
会社が従業員やその家族の出産をお祝いする「出産祝い金」について、気になっている方も多いのではないでしょうか。出産祝い金は企業独自の福利厚生の一環であり、支給条件や金額は企業ごとに異なります。 この記事では、出産祝い金の仕組みや一般的な相場、…
詳しくみる福利厚生による節税の仕組みとは?経費になる条件や節税効果の高い制度も解説
福利厚生は、従業員の働きやすさや満足度を向上させる制度として広く認識されていますが、実は企業にとって法人税を軽減する「節税対策」としての側面も持っています。特に、法定外福利厚生費の中には、一定の要件を満たすことで損金算入が可能となり、税務上…
詳しくみる福利厚生としてマッサージを導入する方法は?相場や経費の取り扱いも解説
近年、働き方改革や健康経営の推進を背景に、企業が福利厚生としてマッサージサービスを導入するケースが増えています。単なる「癒し」の提供ではなく、従業員の心身の健康維持や生産性の向上、離職率の低下といった効果を期待できるため、注目度が高まってい…
詳しくみる会社は福利厚生で保険を導入すべき?社会保険との違いや種類、メリット、導入方法を解説
企業が福利厚生として導入する保険制度は、従業員の満足度や安心感を高め、企業にとっても人材の定着率向上や優秀な人材確保に効果的な制度です。しかし、「どのような保険を導入すればよいか」「そもそも福利厚生として保険が必要なのか」と疑問を抱える担当…
詳しくみる