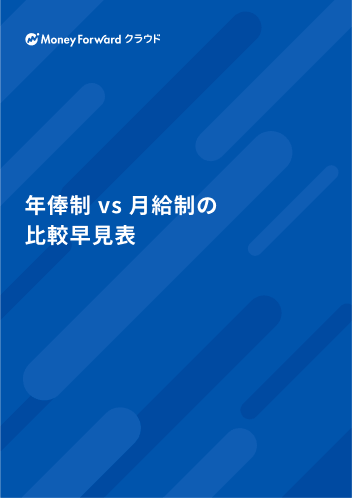- 更新日 : 2025年5月27日
年俸制とは?メリット・デメリットと注意点を解説
年俸制とは、いくつかある給与形態のうち、年間の給与をあらかじめ決めて支給される給与形態を言います。
この年俸制が、月給制や日給制など他の給与形態とどう違うのか、また年俸制のメリット・デメリット、年俸制における注意点について解説しますので、企業との労働契約を考えている方は参考にしてください。
年俸制とは?
年俸制の定義は、「年俸制は本来労働時間に関係なく、労働者の成果・業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度」です。
年俸の額の決め方は、企業と従業員が契約内容や賃金などについて話し合い、最終的に合意することにより、1年を単位にして決定された給与が支給されます。
年俸の主な支払方法としては「毎月年俸の1/12ずつ支給」する方法や「年俸を14分割してそのうちの12回分は毎月の給与として、残りの2回分をボーナスの意味合いで支給」とするケースが多いです。
では、数ある給与形態の中から、なぜ年俸制を採用する企業があるのでしょうか?
年俸制を採用する背景には、年俸制は1年分の給与を事前に把握できるため、企業が経営計画を策定しやすいという点があります。
企業の経営には人件費が重要な要素となっており、その人件費を把握できるということは経営にとってとても大事なことになるのです。
年俸制と月給制はどう違う?
年俸制と月給制はどのような点で違いがあるのでしょうか?
年俸制は1年単位の給与を決定し、その金額を分割して毎月支払う制度です。成果や成績、能力が反映される成果主義を採用している企業で導入されている傾向にあります。
月給制は社員の年齢や勤続年数を考慮して、毎月の基本給やその他の諸手当を決定して毎月支払う給与形態です。
給与が毎月労働者に支払われるという点では、年俸制も月給制も同じですが、年俸制が事前に決めた年単位で給与を決定するのに対して、月給制は月単位で給与を決定するところが違います。
また、年俸制の場合は年間に支払う給与の額が決まっていますが、月給制の場合は毎月の給与が変動するので年間に支払う給与の額が決まっていないという違いもあります。
年俸制と日給制はどう違う?
次に、年俸制と日給制はどのような点で違いがあるのでしょうか?
年俸制については、前項「年俸制と月給制はどう違う?」で述べた通りです。
日給制は1日を単位として給与額を決定し、その額に実際に出勤した日数を掛け算して賃金を支給する形態です。
年俸制では取り決めた年俸額を分割して毎月給与が支払われますが、日給制では1日あたりの給与額が決まっていて、それに実際の勤務日数を乗じて1カ月分の給与を算出しますので算出方法が違います。
また、年俸制の場合は年間に支払う給与が決まっている事に対して、日給制の場合は勤務日数により変動するので年間に支払う給与の額が流動的であるといった違いもあります。
年俸額はどう決まる?
では、年俸額はどのようにして決まるのでしょうか?また、決定した年俸額はどのような形で支払われるのか、それぞれ見ていきましょう。
年俸額の決め方は企業によって異なる
年俸制において、年俸額の決め方は企業によって異なります。社員それぞれの成果や成績、能力などの評価を元に、会社と社員の間で協議を行い、双方の合意に至った場合に翌年の年俸額が決まるのです。
合意に至らない場合には雇用契約が成立しませんので、よく話し合ったうえで決めることになります。
年棒制において給料は1回払い?
年俸制なので、給料は1年に1回、まとめて払えばよいのかと言えば、そうではありません。労働基準法第24条では「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
これは、年俸制だからと言って特別な例外があるわけではなく、年俸制であったとしても、給料は毎月1回以上支払わなければなりません。
年俸制のメリット
ここからは、企業と年俸制で契約することによるメリットについて見ていきましょう。
場合によっては給与の大幅アップを狙える
年俸制の場合、年齢や勤続年数に関係なく個人の能力や成果が評価されれば給与の大幅な増額も期待できます。
また、成果が給与に直結する制度であるため、仕事に対するモチベーションがアップすることも労働者側のメリットになるでしょう。
長期的なライフプラン・ローンや旅行などの予定が立てやすい
年俸制の場合、1年間の給与額があらかじめ決定しており、突然減給されたり、会社の業績によって変動したりすることなどがありません。したがって、自家用車やマイホームの購入時に長期のローンを組む際にも、ある程度ローンの返済計画について事前に計算できる点がメリットと言えるでしょう。
また、上記のような高額な買い物の他にも、結婚・出産・育児や老後など、長期的なライフプランも考えやすくなる点もメリットです。
年俸制のデメリット
次に、企業と年俸制で契約することによるデメリットについて見ていきましょう。
成果によっては給与が下がるケースがある
年俸制の場合、個人の能力や成果で給与が上下しますので、上がることがあれば下がることもあります。
デメリットとしては、成果を出し続けないと給与が下がる可能性があることや、成果を出し続けることがプレッシャーになり、焦りや不安から実力が出せなくなることがあげられます。
成果がすぐに給与に反映されない
年俸制は、最初に決めた年俸額を支払う必要があるため、年度中はその年俸額を変更することは原則としてできません。
たとえ、優れた成果を出したとしても、すぐにその結果が給与に反映されるわけではなく、次の年度まで、その成果が給与に反映されないということも起こり得るのです。
年俸制における注意点
ここでは、企業と年俸制で契約する場合の注意点について見ていきます。
固定残業代の場合、年俸の中に残業代が含まれているケースがある
年俸制であっても、所定労働時間を超えて残業を行った場合には、残業時間に対応した残業代を支払ってもらう必要があります。
ただし、年俸制で固定残業代制度(または、みなし残業時間制)を導入している場合、年俸のうちのいくらが残業代であるか、また、それが何時間分の残業代に相当するかを労働契約書などに明示することなどで、本人の同意を得ていることが必要になります。
従業員本人の同意があれば、取り決めた残業時間を超過しなければ残業代の支払いは発生しないことになります。
みなし残業に関する疑問は、以下の記事も参考にしてください
ボーナスの支払い方に特徴がある
年俸制の場合でもボーナスの有無は企業で規定している就業規則や雇用契約書によります。
ボーナスが支払われる場合、支払方法はいくつかあります。
1つめは、年俸を14分割、16分割などして、そのうちの12回分を給与に、残りの2回分または4回分を賞与として支給する方法です。
2つめは、年俸を12分割して給与として支給し、ボーナス分は別に各従業員の成果に応じて支給する方法です。
上記の2つの支払い方以外にも、企業の業績が良かった場合に「臨時ボーナス」が支給される場合もあります。
欠勤控除は適用される?
年俸制の場合でも、早退・遅刻・欠勤などがあった場合には欠勤控除されます。
ただし、欠勤控除される場合には、就業規則に規定されている必要がありますので注意してください。
年の途中に退職もしくは解雇された場合、給与の支払いはどうなる?
年途中で退職した場合、給与の支払いはどうなるのでしょうか?
年俸制であっても、年途中で退職してしまった場合には、基本的に働いていない期間分の給与は受けることができません。
年俸に賞与が含まれる契約の場合、賞与支給日の前に退職した時は在籍していた期間分の賞与は基本的には支払われます。
ただし、支給日時点で在籍していない従業員には賞与を支払わない旨が賃金規程等や契約書に記されている場合には、支給されない場合がありますので、事前に就業規則、賃金規程、契約書等を確認しておきましょう。
年俸制の場合、各種税金の支払いはどうなる?
年俸制の税金については、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料という社会保険と雇用保険、所得税があります。
年俸制の各種税金の支払い方法については、年俸の支払方法によって変わってきます。
例えば、年俸を12分割して毎月支払う場合と、年俸を14分割や、16分割などして一部を賞与で支払う場合について考えてみましょう。
社会保険料は、計算する基になる金額が給与の場合には「標準報酬月額」、賞与の場合には「標準賞与額」と異なるため、社会保険料は分割した支給の状況によって変わります。雇用保険料は支給額によって変わり、所得税は課税対象額によって変わります。
どのような支給方法が得かはそれぞれ計算してみないとわからないため、「こうすれば得になる」ということはありません。
年俸制のメリット・デメリットを理解したうえで雇用契約を結ぼう
これまで、年俸制のメリット、デメリットや年棒制の注意点について見てきました。
これから、企業との間で年俸制で契約することを検討する場合には、これらのメリット、デメリットや注意点を参考にしながら自分に合った給与形態かどうかを総合的に検討して雇用契約を締結するようにしましょう。
よくある質問
年俸制と月給制の違いについて教えてください
年俸制は、成果主義と結びつけて1年単位の給与を決定し、その金額を分割して毎月支払う給与形態で、月給制は、従業員の年齢や勤続年数を考慮して基本給や手当を決めて毎月支払う給与形態です。詳しくはこちらをご覧ください。
年俸制のメリットについて教えてください
企業と従業員の間で話合いの上で1年間の給与を決めているので、年の途中では突然の減給ができないこと、また収入に関して見ると、自家用車やマイホームの購入など、長期的な計画が立てやすいことがメリットです。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
2025年最新!給与計算におすすめの本13選【初心者・資格勉強にも】
給与計算はミスが許されない重要な業務です。そのため、業務の内容や知識に不安を感じている初心者の方も多いでしょう。給与計算に関する知識や実務を習得するには、本を読むのがおすすめです。本記事では初心者向けや資格取得など、給与計算に関するおすすめ…
詳しくみる給与規程(賃金規程)とは?作成時の規則と手順を解説ーサンプル付
労働者が事業主と労働契約を締結する際、最も重視する労働条件として賃金があります。その事業所で根拠となるのが給与規程(賃金規程)ですが、そもそも作成は法的に義務づけられているのでしょうか。また、どのようなことを記載するのでしょうか。 今回は、…
詳しくみる賞与支払届とは?記入例や手続きの流れをわかりやすく解説
賞与支払届は、従業員の保険料の計算や年金記録を作成するために必要な書類です。 そのため、賞与支給後、期限までに年金事務所へ提出しなければいけません。 そこで本記事では、賞与支払届の作成から提出まで、人事労務担当者がスムーズに手続きを進められ…
詳しくみる定額減税において従業員への案内は必要?テンプレートも紹介
定額減税は、従業員の税負担を軽減するための重要な制度です。しかし、従業員がこの制度を正しく理解し、適切に利用するためには、企業の人事担当者による案内・周知が不可欠です。 本記事では、定額減税における従業員への案内が義務であるかどうか、案内・…
詳しくみる岐阜県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
岐阜県は自動車部品や機械工業が盛んで、製造業を中心に多くの企業が活動しています。また、伝統工芸や観光業も地域経済を支える重要な産業です。こうした多様なビジネス環境では、給与計算の正確性と効率化が企業運営において不可欠ですが、中小企業にとって…
詳しくみる最低賃金とは?制度の概要や種類をわかりやすく解説
労働者に は契約に従って労働する義務はありますが、使用者にも労働の対償として賃金を支払う義務があります。また、賃金には最低の額が定められており、その額を下回ることは許されません。 本記事では、最低賃金についての概要や注意点などについて解説を…
詳しくみる