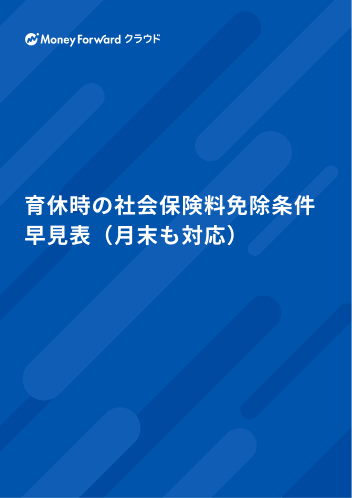- 更新日 : 2025年5月27日
月末時点で育休なら社会保険料が免除?賞与の場合はどうなる?
月末が育休期間に含まれている場合、基本的には当月の社会保険料は免除になります。ただし、育休の開始日と終了日が同月にある場合は、休業期間が14日未満だと社会保険料が免除されないため注意が必要です。
さらに育休中に賞与を受け取る場合、受け取った月の末日を含めて休業期間が1か月以上あれば、賞与にかかる社会保険料も免除されます。
育休により社会保険料が免除になるタイミングについて把握すれば、給与からの控除をおさえて、手取りの金額を増やしたり支出の負担を軽減したりできるでしょう。
目次
育休中の社会保険料の免除の仕組み
育休中は社会保険料が免除されますが、住民税は前年の所得をもとに算出しているため、引き続き支払いが発生する点に注意が必要です。
免除となる社会保険料と、実際に引かれている金額を把握することで、正確に家庭の支出管理ができるでしょう。
また通常であれば、社会保険料が免除される場合は将来受け取れる年金額が減ります。しかし育休の場合は、基本的には将来受け取れる年金額を減額せずに社会保険料の免除が受けられます。
免除となる社会保険料の種類
育児休業中に免除される社会保険料は、主に下記の2つです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
健康保険料は、医療サービスを受けるために支払う保険料であり、主に会社員や公務員が加入する健康保険制度にもとづいています。
厚生年金保険料は、企業に勤務する会社員や公務員が加入する公的年金制度に関連する保険料で、老後の生活を支えるための年金を提供することが目的です。
健康保険料と厚生年金保険料は、育休を取得した月から、終了日の翌日が属する月の前月までの期間にて免除されます。
社会保険料の免除を受けるには、事前に職場へ必要書類の提出が必要です。具体的な手続き方法は職場により異なるため、必ず確認が必要です。
社会保険料はどのくらい引かれているのか
社会保険料は主に健康保険料・厚生年金保険料から構成されており、保険料は標準報酬月額にもとづいて計算され、一般的には労使折半で負担します。
たとえば給料が月20万円の場合、社会保険料は以下のように計算されます。
― 健康保険料:約9,980円
― 厚生年金保険料:約18,300円
合計で、社会保険料は毎月約28,280円程度引かれます。
また給料が月30万円の場合、社会保険料は次のように計算されます。
― 健康保険料:約14,970円
― 厚生年金保険料:約27,450円
合計で、社会保険料は毎月約42,420円程度引かれます。
社会保険料は、毎月職場から配布される給与明細で確認できます。
基本的には給与が増えると社会保険料も増加しますが、具体的な金額は、加入している保険の種類や地域によって異なる場合があるでしょう。
社会保険料が免除されると年金は減る?
厚生年金保険料または国民年金保険料は、毎月支払うことで、老後に年金が受け取れます。
しかし、未納や免除の月があった場合、老後に受け取れる年金額が減額される場合があるため注意が必要です。
育休中には厚生年金保険料または国民年金保険料が免除されますが、育休の場合は免除期間中も、保険料を支払ったものとみなされます。そのため、育休を理由に将来の年金額が減少することはありません。
自営業者の場合も、育休中は国民年金保険料が免除され、免除された期間も保険料を納付したものとして扱われるため、年金受給額が大幅に減少することはありません。
育休中は有給・無給でも社会保険料は免除される?
育休中の社会保険料は、法定下における育休を取得している場合、給与の有無にかかわらず免除されます。
社会保険料の免除は、育休が法的に認められたものである限り適用されます。
たとえば、育児中に就業した場合、職場の事情によるやむを得ない就業であれば、就業した給与分の社会保険料は免除される可能性が高いでしょう。
月の末日が休業期間に含まれており、または育休開始日と終了日が同月の場合で14日以上の休業日がある場合も、社会保険料が免除されます。
しかし、育休の取得前に予定されていた就業である場合は、そもそも育休とみなされない可能性が高いため、社会保険料が免除にならない場合があります。
月末時点で育休期間なら社会保険料が免除?
育休中は、基本的に社会保険料が免除になります。
ただし、育休開始日と終了日、休業日数により社会保険料が免除される月とされない月がある点に注意が必要です。また育休中に賞与を受け取り、賞与の社会保険料を免除してもらうには、賞与を受け取った月の末日を含めて休業期間が1か月以上必要です。
社会保険料が免除になるスケジュールを把握して、計画的に育休を取得しましょう。
育休開始日が月末日の場合
育休の開始日が月末日の場合、その月の社会保険料は免除されます。また、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象となります。
ただし、育休開始日が月末日であっても、以下のような場合には社会保険料が免除されないことがあるため注意が必要です。
- 月末日の1日だけ育休を取得した場合
- 賞与を受け取った月の末日から育休を取得し、育休が1か月未満の場合
※賞与のみ社会保険料が免除にならない
育休開始日が月末日の場合のスケジュール例を3つ紹介します。
【例1】
― 育休開始日:2025年1月31日(末日)
― 育休終了日:2025年3月15日
社会保険料が免除される月:
⇒ 1月分は免除、2月分は免除、3月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
【例2】
― 育休開始日:2025年2月28日(末日)
― 育休終了日:2025年4月10日
社会保険料が免除される月:
⇒ 2月分は免除、3月分は免除、4月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
【例3】
― 育休開始日:2025年3月31日(末日)
― 育休終了日:2025年4月5日
社会保険料が免除される月:
⇒ 3月分は免除、4月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
末日に育休を取得した場合、終了する日により社会保険料が免除される月が異なります。
育休終了日が月末日の場合
育休を取得した月に14日以上の育児休業を取得した場合、その月の社会保険料が免除されます。また、育児休業が月末に終了する場合も、終了日が属する月の保険料が免除されます。
ただし、以下のような場合には社会保険料が免除されないため注意が必要です。
- 同月に取得した育休が14日未満の場合
育休終了日が月末日の場合のスケジュール例を3つ紹介します。
【例1】
― 育休開始日:12月1日
― 育休終了日:12月31日
社会保険料が免除される月:
⇒ 12月分は免除
【例2】
― 育休開始日:12月15日
― 育休終了日:1月31日
社会保険料が免除される月:
⇒ 12月分は免除、1月分は免除
【例3】
― 育休開始日:12月20日
― 育休終了日:12月31日
社会保険料が免除される月:
⇒ 12月分は免除されない(育休の取得日数が14日未満のため)
月の末日に育休を終了する場合は、育休の開始日および同月内で取得する育休の日数に注意が必要です。
育休終了日が月末近い場合
育休が月末近くの場合、育休の開始日によって社会保険料が免除になる月が異なります。下記の場合は、社会保険料が免除にはなりません。
- 同月に取得した育休が14日未満の場合
- 育休の終了日が末日ではない場合
育休終了日が月末近い場合のスケジュール例を3つ紹介します。
【例1】
― 育休開始日:1月1日
― 育休終了日:1月28日
社会保険料が免除される月:
⇒ 1月分は免除
【例2】
― 育休開始日:3月20日
― 育休終了日:3月30日
社会保険料が免除される月:
⇒ 3月分は免除されない(育休の取得日数が14日未満のため)
【例3】
― 育休開始日:4月20日
― 育休終了日:6月27日
社会保険料が免除される月:
⇒ 4月分は免除、5月分は免除、6月分は免除されない(月末が育休に含まれていないため)
末日付近で育休が終了する場合、当月の社会保険料が免除にならないため、可能なら末日を育休の終了日としたほうがよいでしょう。
育休中に月末日のみ就労した場合
育休中における就労については、あらかじめ決まっていた就労であれば、育休の日に当てはまらないとされることがあります。
しかし、職場の事情により、本来であれば育休として休業する予定だったが、就労せざるを得ない場合は育休中と認められる場合が多いでしょう。
育休中に月末日のみ就労した場合のスケジュール例を2つ紹介します。
【例1】
― 育休開始日:1月18日
― 就労日(あらかじめ就労することを決めていた):1月31日
― 育休終了日:3月20日
社会保険料が免除される月:
⇒ 1月分は免除されない(1月31日が育休としてカウントされないため)、2月分は免除、3月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
【例2】
― 育休開始日:1月18日
― 就労日(本来なら休業日の手はずだった):1月31日
― 育休終了日:3月20日
社会保険料が免除される月:
⇒ 1月分は免除、2月分は免除、3月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
就労日が育休として認められるかどうかで、社会保険料が免除になる月が変わるため、就労する場合は注意が必要です。
育休を10日間のみ取得した場合
育休を10日間など短期間のみ取得した場合も、社会保険料が免除になる場合があります。ただし、下記の場合は社会保険料が免除にならない場合があるため注意が必要です。
- 育休開始日と終了日が同月の場合
育休を10日間のみ取得した場合のスケジュール例を3つ紹介します。
【例1】
― 育休開始日:1月3日
― 育休終了日:1月12日
社会保険料が免除される月:
⇒ 1月分は免除されない(育休の取得日数が14日未満のため)
【例2】
― 育休開始日:2月28日
― 育休終了日:3月9日
社会保険料が免除される月:
⇒ 2月分は免除、3月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
【例3】
― 育休開始日:3月22日
― 育休終了日:3月31日
社会保険料が免除される月:
⇒ 3月分は免除されない(月末が休業期間に含まれていないため)
休業期間が10日間といった短期間の場合は、月末を休業期間に含めるかどうかで、社会保険料が免除されるかが異なります。
産後パパ育休の場合
産後パパ育休とは、主に男性が子どもの出生日から8週間以内に取得できる育児休業制度です。産後パパ育休は、父親が出産直後の配偶者と共に育児を行いやすくすることを目的としています。
産後パパ育休を取得した場合も、通常の育休と同様に社会保険料が免除されることがあります。社会保険料が免除される条件は通常の育休と同様で、下記のとおりです。
- 月の末日が育休の休業期間に含まれていること
- 育休の開始日と終了日が同月の場合、休業期間が14日以上あること
産後パパ育休も、取得することで社会保険料が免除される場合があるため、夫婦そろって育休を取得することが望ましいでしょう。
育休中の賞与(ボーナス)にかかる社会保険料免除の要件
育休中に賞与を受け取る場合、下記の条件を満たせば、賞与にかかる社会保険料が免除される場合があります。
- 賞与を受け取った月の末日を含む、連続した1か月を超える育休を取得していること
- 賞与が支給された月の末日が、育休の対象期間に含まれていること
つまり、取得する育休が1か月を超えていることが条件です。
たとえば、10月5日に賞与を受け取った場合、10月の末日が育児休業の期間に含まれており、休業期間が1か月を超えていれば、社会保険料が免除されます。
育休中の賞与にかかる社会保険料の免除は、育休の期間と賞与の支給月の関係が重要です。
育休中に就労した場合は社会保険料が免除される?
一般的に、育休を取得している間は社会保険料が免除される場合がほとんどです。しかし、就労を行った場合、就労内容や就労時間によっては社会保険料が免除になる場合とならない場合があります。
育休中の就労において、社会保険料が免除になる条件は下記のとおりです。
- 同月内で14日以上の育休を取得する場合
- 育休中の就労が、本来予定されていなかった場合
- 就労日の末日が休業期間に含まれている場合
育休中に、就労することは想定されていません。そのため、あらかじめ休業中に就労することがわかっている場合は、育休から復帰したとみなされ、社会保険料が免除にならないことがあります。
あくまで、職場でやむを得ない事情があったために就労した場合に、社会保険料が免除されます。
育休に伴う社会保険料免除の手続きの仕方
育休の取得に伴う社会保険料の免除は、本人が職場へあらかじめ申請する必要があります。
職場から育児休業等取得者申出書を受け取って必要事項を記載し、職場へ提出しましょう。個人事業主や、職場に用紙がない場合は、日本年金機構の公式サイトからダウンロードして記載します。
書類を受け取った事業主は、育児休業等取得者申出書を管轄の年金事務所に提出しましょう。
書類等に不備がなければ、育休の開始日が属する月から、育休が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間において、社会保険料が免除されます。
ただし、月の末日が含まれているか育休を取得した月に14日以上の休業が必要です。
育児休業等取得者申出書の提出は、基本的には事業主が管轄の年金事務所へ提出しますが、職場によっては自身で提出する必要があるでしょう。
法改正【2025年4月~】育休手当の給付額が実質10割に
2025年4月1日から施行される改正雇用保険法により、育児休業給付金の給付額が67%から80%へ引き上げられ、かつ社会保険料が免除されることで、実質10割の支給が実現します。
厳密には、育児休業給付金の67%に加えて、新しく出生後休業支援給付が13%上乗せされる形で給付されます。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付は、2025年4月から施行される新しい支援制度です。
子どもの出生後における生活費の負担軽減および、両親がともに育休を取得しやすくする目的で設けられました。
出生後休業支援給付を受けるには、下記の条件を満たす必要があります。
- 両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得すること
- 男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育休を取得すること
受け取れる出生後休業支援給付の金額は、休業開始前の賃金の13%相当額で、最大28日分が支給されます。
そのため、最大28日間は現行の67%に加えて出生後休業支援給付の13%が上乗せされ、さらに社会保険料が免除および非課税になることで、給付額が実質10割になるのです。
産休・育休に関わる申請書類のテンプレート
産休・育休を取得するには、はじめに職場へ取得する旨を伝えたうえで、産休申請書または育児休業申請書の提出が必要です。
多くの職場では、企業が指定した形式および用紙に必要事項を記載して提出します。
とくに指定がない場合は、Money Forward クラウド給与の公式サイトで公開しているテンプレートに必要事項を記載して、ダウンロード・印刷する方法がおすすめです。
産休申請書テンプレート
産休を取得するためには、職場へ産休申請書を提出します。産休申請書には下記の事項を記載します。
- 所属部署名
- 社員番号
- 氏名
- 出産予定日
- 産休の開始予定日
- 産休の終了予定日
職場によっては、医師または助産師による妊娠証明書の添付が求められることもあるでしょう。
職場に指定の産休申請書がなければ、下記からテンプレートをダウンロードして印刷し、必要事項を記載したうえで職場へ提出しましょう。
育児休業申請書テンプレート
育休を取得するためには、職場へ育児休業申請書を提出します。育児休業申請書には下記の事項を記載します。
- 所属部署名
- 社員番号
- 氏名
- 子の氏名
- 子の生年月日
- 申請書本人と子の続柄
- 育休の開始予定日
- 育休の終了予定日
- 育休中の連絡先
職場に指定の育児休業申請書がなければ、下記からテンプレートをダウンロードして印刷し、必要事項を記載したうえで職場へ提出しましょう。
育休の社会保険料の免除は月末を休業期間に含めるかどうかで異なる
育休中は基本的に社会保険料が免除になります。
ただし、社会保険料が免除になるためには下記の条件が必要です。
- 月の末日が休業期間に含まれている
- 育休開始日と終了日が同月の場合、休業日が14日以上ある
育休中に就労する場合は、就労が本来予定されていたかどうかで休業期間に含まれるかが異なり、社会保険料が免除されない場合があるため注意が必要です。
育休の開始日と終了日に注意して、社会保険料が免除される制度を適切に利用しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働保険とは?労災保険と雇用保険の違いや事業主の加入手続きも解説!
社会保険という用語は広く知られていますが、労働保険という用語はあまり認知されていないのではないでしょうか。 しかし、労働保険は働く労働者にとって不可欠な保険制度です。 本稿では社会保険における労働保険の位置付けと、その種類・内容、加入手続き…
詳しくみる介護保険制度の概要
日本では急速な高齢化が進み、「介護保険制度」への関心が高まりつつあります。 総務省統計局の資料によれば、2017年9月15日時点で、65歳以上と定義される高齢者の人口は3,514万人で、総人口に占める高齢者人口の割合が27.7%と過去最高と…
詳しくみる介護保険料の計算方法は?第1号・第2号被保険者の違いや保険料の取り扱いについて解説
介護保険法では、介護保険被保険者のうち、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳以下の公的医療保険加入者を「第2号被保険者」と定めています。第1号被保険者と第2号被保険者とでは介護保険料の決定方法や納付方法が異なります。 本稿で…
詳しくみる雇用保険とはどんな保険?
雇用保険とはどのような保険でしょうか。「雇用保険とは……」と聞くと、失業した際にお金が給付される失業等給付のことを思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、雇用保険とは、失業保険だけでなく、さまざまな機能があります。今回は、雇用保険の概要につ…
詳しくみる国保計算を基本から理解するための3つのポイント
職場で社会保険に加入していない人や生活保護を受給していない人であれば加入が義務付けられている国民健康保険(以下、国保)。 ここではこの国保の保険料計算(以下、国保計算)の基本と、保険料がどんなもので構成されていて、どうして支払わなくてはなら…
詳しくみる労災がおりるまでの期間の生活費は?傷病手当金や失業手当なども解説
仕事中や通勤中の事故や病気によって労災保険を申請したものの、実際に給付が開始されるまでには一定の時間がかかります。中には数ヶ月かかるケースもあり、その間の生活費に不安を抱える方も少なくありません。 この記事では、労災保険の給付を受け取るまで…
詳しくみる