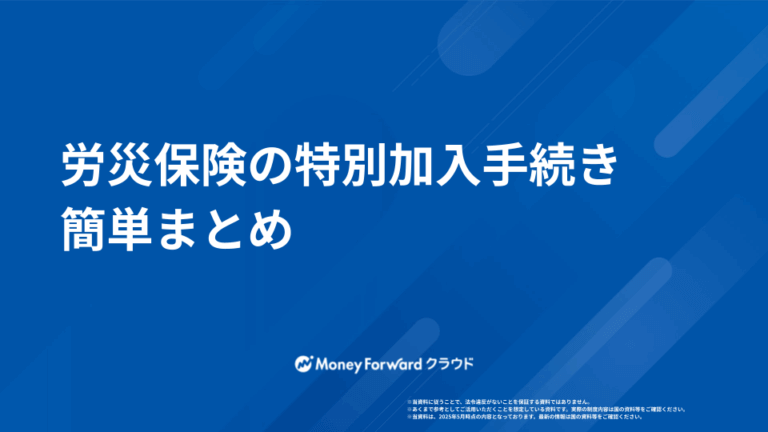- 更新日 : 2025年7月3日
労災保険の特別加入制度とは?対象者や申請についても解説
労災保険制度は、労働によるケガ・病気などから労働者の生活を守るためのものです。
しかし、労災保険は基本的に日本国内で雇用されている労働者のみが対象となるため、労働災害が発生しても労災保険の対象にならないケースも起こり得ます。より多くの労働災害に対処できるように、本来対象外の人でも労災保険に特別加入できる制度が設けられています。
この記事では労災保険の特別加入制度について、概要や対象者、申請手続き方法や注意事項などを紹介します。
目次
労災保険の特別加入制度とは
労災保険とは、労働者が被った労働災害に対して保険給付やサポート事業などを提供する保険の制度を指します。
労災保険が適用される「労働者」とは、基本的に事業主から雇用されている人を指します。しかし、フリーランスや事業主なども状況に応じて労災保険が適用されるケースもあります。「特別加入制度」と呼ばれるもので、主に業務実態や災害発生状況などを鑑みて判断されます。
以下では記事内容の前提として、労災保険の概要について解説します。
労災保険とは
労災保険とは、勤務中・通勤中の労働者が負傷・疾病・死亡などの被害を受けた際に労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度のことです。「労災保険」という言葉は略称で、正式には「労働者災害補償保険」と呼びます。
「労働災害が原因のケガ・病気によって医療機関を利用する」「仕事を休業させられる」「高度な障害が残った」などの事態が起こったことで生じる補償などが該当します。なお、保険給付だけでなく労働者福祉の増進も行われており、労働者がより早く社会復帰できるようなサポート事業も労災保険の一部です。
事業主が労働者を1人でも雇用している場合、労災保険への加入が法的に義務付けられています。加入時に求められる保険料もすべて事業主が負担しなくてはなりません。労働者の雇用形態・勤務日数などに関係なく、雇用しているすべての労働者が対象です。
労災保険の特別加入の対象者は?
労災保険は、基本的に日本国内の労働者を保護するために設けられている制度です。
そのため、本来は労災保険に加入できない立場の人が特別加入するためには、複数設けられている条件のいずれかに該当している必要があります。
基本的にはこの章で紹介する4種類の条件が用いられますが、2021年4月1日の法改正から条件がさらに4種類増えています。「芸能関係作業従事者」「アニメーション制作作業従事者」「柔道整復師」「創業支援等措置に基づき事業を行う方」に該当する場合、別途調べてみましょう。以下では法改正前から設けられていた4条件について解説します。
参考:令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
中小事業主等
労災保険に特別加入できる対象者には「中小事業主等」が含まれます。中小事業主等とは以下の2パターンの条件をともに満たしている人を指します。
- 特定人数以下の労働者を常時使用している事業主
金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下の場合に該当します。その他の業種は300人以下が条件です。 - 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人
事業主の家族従事者はこちらに該当します。その他にも中小事業主が法人その他の団体であった場合、代表者以外の役員が対象です。
労働者を常時雇用している条件は年間100日以上使用していることとされます。通年雇用していない場合でも該当しうるため注意しましょう。また、同じ会社で複数の工場・支店などを有している場合は、各施設で使用している労働者数の合計が用いられます。
一人親方等
単独で事業運営を行う「一人親方」と呼ばれる事業者も、労災保険特別加入の対象に含まれます。一人親方は労働者を使用せず、自身も会社から雇用されていません。あるいは労働者を使用しても年間100日未満に収まり、労働者でなく同居・同一生計の家族のみで働いています。依頼を受ける際は請負契約によって仕事をするケースがほとんどです。
こうした一人親方は事業主に該当しますが、基本的には自身も現場に出て働きます。現場で働く以上、労働災害に遭う可能性が高く、日常の勤務で労働者と同様のリスクを負っている立場です。そのため、本来労災保険に加入できない事業主に該当していても労災保険のサービスが求められます。一人親方に労災保険サービスを提供するために、特別加入制度の利用が認められています。
特定作業従事者
特定作業従事者とは、指定されたさまざまな業務に取り組んでいる人のことです。主に以下の条件にあてはまる人が該当します。
- 特定農作業従事者
一定以上の農産物販売額や農地面積を持っている農業者であり、大型農機具の使用や高所作業、農薬散布などを行う場合に該当します。 - 指定農業機械作業従事者
各種農業機械を使用して耕作・開墾・栽培・採取などの作業を行う農業者が該当します。
機械はトラクター・コンバイン・無人航空機などが対象です。 - 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
国や地方公共団体が実施する訓練作業に従事する人が該当します。
訓練には職場適応訓練と事業主団体等委託訓練が存在します。 - 家内労働者及びその補助者
家内労働者や補助者のうち、特に危険度が高いとされる業務に従事する人が該当します。
プレス機・研削盤・有機溶剤などを用いる業務が含まれます。 - 労働組合等の常勤役員
労働者を常時使用しない労働組合等で、組合の事務所や各種公共施設などでの集会運営・団体交渉など組合活動に必要な作業を行う人が該当します。 - 介護作業従事者及び家事支援従事者
介護作業従事者は介護その他の日常生活における世話や機能訓練、看護などにかかわる作業を行う人です。家事支援従事者は家事の代行・補助を行う人が該当します。
海外派遣者
国内の事業主から海外の事業に労働者・事業主等として派遣されたり、開発途上地域への技術協力事業で派遣されたりする人も労災保険に特別加入できます。単なる留学目的や現地採用などのケースでは該当しません。
労働者として派遣されるケースでは、海外にある支店・工場・現地法人などに労働者として派遣される場合が該当します。事業主等としての派遣は、現地国で使用している労働者の人数が基準になります。労働者数が少ない国であれば、事業主として派遣された際に労災保険への特別加入が可能です。
また、国際協力団体から海外に派遣され、支援活動に従事する人も労災保険特別加入対象に含まれます。開発途上地域への技術協力事業は、JICAのような国際協力団体による事業が該当します。
労災保険の特別加入の申請手続き
労災保険への特別加入を希望する場合、個人ではなく、必ず団体として手続きを行う必要があります。そのため、最初は地域の特別加入団体に申し込みましょう。団体を事業主、申し込んでいる加入希望者を労働者とみなして労災保険適用が行われます。なお、特別加入団体は都道府県労働局長の承認を受けている必要があります。念のため確認しておくと安心です。
その他に、既存の特別加入団体を利用せず、自分で新しく団体を作る方法もあります。特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長に提出して、都道府県労働局長に監督署長経由で申請します。申請書には加入希望者が扱う業務の具体的な内容や業務歴、希望する給付基礎日額などを記入しましょう。申請に対する労働局長からの承認は、申請日の翌日から数えて30日以内かつ申請者が加入を希望する日に行われます。
労災保険の特別加入の注意事項
労災保険への特別加入を希望する際に、条件を満たしていても加入できないケースがあります。大きな原因は加入希望者がすでに労働により病気を患っている場合で、就労でなく療養に専念しなくてはならないと判断されれば労災保険に加入できなくなります。
加入希望者の病気について調べるために、特定業務を一定期間務めていると加入申請時に健康診断の受診が求められます。健康診断の受診が求められる業務内容と期間は、以下のように定められています。
- 粉じん作業を行う業務
3年以上勤務していると該当します。じん肺健康診断が必要です。 - 振動工具を使用する業務
1年以上勤務していると該当します。振動障害健康診断が必要です。 - 鉛業務
6ヶ月以上勤務していると該当します。鉛中毒健康診断が必要です。 - 有機溶剤業務
6ヶ月以上勤務していると該当します。有機溶剤中毒健康診断が必要です。
労災保険への特別加入を積極的に考えよう
労災保険の特別加入制度について、概要や対象者、申請手続き方法や注意事項などを紹介しました。
日本国内で働く労働者を守るための労災保険ですが、必要に応じて柔軟な運用がなされています。加入条件を満たさずとも重要かつリスクがある労働をこなしている人は多くみられるため、特別加入制度はより幅広い人を支えるために有用な制度です。
特別加入するための条件を正確に把握して、労災保険への特別加入を積極的に検討しましょう。業務に安心感が生まれるため、より安全に能率的な業務を行いやすくなります。
よくある質問
労災保険の特別加入制度とは?
労災が起こりうる仕事をしながらも労災保険への加入条件を満たしていない人が、例外的に労災保険への加入を行える制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険特別加入の対象者は?
中小事業主や一人親方、特定作業の従事者や海外派遣者など複数の立場が該当します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
労災保険の関連記事
新着記事
60歳以降の再雇用、給与の目安は?決め方や下がる理由、違法となる場合を解説
60歳以降も働き続ける再雇用制度を利用する方が増えていますが、多くの人が気にするのは、再雇用後の給与ではないでしょうか。定年前よりも減額されることが一般的ですが、どのくらい下がるのか、どんな場合に違法になるのかを理解しておくことは、安心して…
詳しくみる平均賃金の端数処理とは?欠勤や3ヶ月未満の計算方法や具体例を解説
平均賃金における端数処理は、平均賃金の計算時に生じる1銭未満や、手当支給時の1円未満の扱いを定めたものです。この記事では、平均賃金の計算方法や含める賃金の範囲、算定期間の考え方、そして端数処理の具体例までを簡潔に解説しています。 平均賃金の…
詳しくみる不正打刻とは?タイムカードの事例や違法時の処分、対策を解説
不正打刻は労働時間を偽り、賃金や残業代の不当支払いにつながる行為です。放置すれば労働基準監督署の是正勧告や送検、詐欺罪の適用など企業にも従業員にも重大な不利益が生じます。本稿では法的リスク、発覚プロセス、判例、処分方法、そして最新勤怠システ…
詳しくみる定年後の再雇用は嘱託が多い?メリット・デメリット、給与や契約の決め方を解説
定年後の再雇用では、嘱託契約を採用する企業が多く見られます。少子高齢化が進む中、経験豊富な人材を活かす手段として注目されています。この記事では、嘱託という働き方の特徴、メリット・デメリット、給与や契約内容の決め方、企業が留意すべき点をわかり…
詳しくみる従たる給与についての扶養控除等申告書の提出とは?意味や書類の書き方を解説
副業や兼業で複数の勤務先から給与を得ている方にとって、「従(じゅう)たる給与についての扶養控除等申告書」は、所得税の源泉徴収手続きにおいて大きな意味合いを持つ書類です。この申告書の提出状況は、毎月の源泉徴収税額や年末調整、さらには確定申告の…
詳しくみる残業時間の端数処理とは?1分と15分単位の違い、計算例を解説
残業代の計算時に「端数処理」はどのように行えばよいのでしょうか。1分単位で処理すべきか、15分単位でも問題ないのか。 労働基準法では、原則として労働時間は1分単位で計算し、働いた分すべてに賃金を支払うことが求められています。ただし、一定の条…
詳しくみる